【特別企画】
史上初のオンライン大会に挑んだ「第3回全国高校eスポーツ選手権」大会レポート
ユニークな局舎会場、オンライン独自施策、次世代に向けて紡いだ伝統に密着
2021年3月15日 00:00

- 3月13日、14日オンライン開催
第3回目となる全国高校eスポーツ選手権が3月13日、14日の両日、オンラインで開催された。当初は開催自体が危ぶまれた大会だったが、第3回で早くもその伝統が絶えることがないようにと、関係者が力を合わせなんとか開催にこぎ着けた。結果としては、過去最多の出場チームを数え、まったく滞りなく全日程を終えるなど、成功を収めることができたが、この背景にはどのようなドラマがあったのか。本稿では全国高校eスポーツ選手権レポートの締めくくりとして、第3回大会の意義と、今後のeスポーツシーンに与える影響をレポートしたい。個々の試合やチームインタビューについては別記事でまとめているのでそちらを参照いただきたい。
NTTグループとのパートナーシップが実を結んだ“局舎”会場
それにしても第2回が終了した12月の年の瀬に、第3回がこのような事態になると誰が予想できただろうか。全国高校eスポーツ選手権は、既存のスポーツに並ぶ新たな文化事業として100年続く大会を目指して、徐々に参加校を増やしながら成長を持続させる計画で進められている。第3回は最初から文部科学省の後援を受ける形で、飛躍の年とすべく、より多くの高校生が参加できるように競技種目を増やしたり、決勝大会の全国キャラバン構想の一環として開催地を関西にすることなどが検討されていたと聞くが、新型コロナの影響ですべて流れてしまった。
「新しい生活様式」が求められる中、第3回大会の計画を練り直す過程で、大きな援軍になったのがNTTだ。NTTとは、2020年1月のNTTe-sports設立発表以前から交渉をはじめ、全国高校eスポーツ選手権を下支えしている施策であるeスポーツ部支援プログラムにも光回線を組み込むなど、深い協力関係にあったが、第3回大会ではこの深い結びつきをフル活用した。
具体的には、NTTグループが持つ“局舎”を大会会場として採用。筆者が把握している限り、大会がオンラインにならざるを得ないと決まった時点で、会場に局舎を使う構想で動いていた。これにより、スポーツ大会として必要不可欠となるフェアネス(公平性)と、オンライン大会としては最高水準の試合環境の両方を確保することに成功した。
使用した局舎は、MCや実況解説の配信スタジオとして東京を筆頭に、大阪、札幌、釧路の計4カ所。いずれも12月に確定した出場校の位置を踏まえた上でのチョイスであり、新型コロナウイルスの影響で、局舎に応援団を入れたりといったことはできなかったが、オフライン大会のように、すぐ隣にチームメイトがいる環境で試合ができたのはとても良かったと思う。ちなみに、N校が利用した東京会場については、機材の関係からLFSを使っており、会期2日目「リーグ・オブ・レジェンド」部門第1試合のN校同士の対決は、本大会唯一のLANでの試合となっている。
実証したオンライン大会の可能性と、待ち望まれるオフライン大会の復活
そして今回は初のオンライン大会となったが、オンライン開催らしい施策が取り入れられていた。
ひとつは試合前やインターバルの間、選手達のボイスチャットを聞けるようになっていた。しかもチームごとにボイスを左右に分けて定位させ、2つのチームと、実況解説の声が聞き分けられるようにしていたのは良かった。ゲームを先取したチームは勢いづき、緊張もほぐれて会話が弾むが、ゲームを落としたチームは口も重くなる、そういった生々しい雰囲気まで伝わってきた。
とりわけ有効に作用していたのは「LoL」部門だ。試合前のバンピックフェイズを丸ごと聞けるようになっており、限られた時間の中で相手チームと駆け引きを繰り返しながらバンピックを繰り返していく際の独特の緊張感をよく伝えていた。実況解説が喋っていると聞き取りづらい部分もあり、次回はTV放送の副音声のような分離配信や、一部配信で採用されているようなAIによる文字起こしといった工夫にも期待したいところだが、取り組み自体はとても良かったと思う。
その一方で、試合中の鋭いかけ声や緊迫感のあるやりとり、勝利時の雄叫び、こうした選手達の声は一切聞けないようになっており、個人ビューの設定もなかったため、選手個々のプレイ状況を見ることもできなかったのは残念だった。客席もないので歓声も聞こえない。当然、試合後半にかけて徐々に応援のボルテージが上がっていく感覚や、会場の一体感などもなく、運営側も応援コメントを読み上げたり、舞台裏の情報を伝えたりなど工夫はしていたものの、やはりオフライン大会の復活を強く望みたいと思った。
ただ、心配されたオンライン大会にありがちなネットワークエラーによる長期中断や、通信のラグによる大会そのものの質の低下などは、選手側は感じ取っていたかもしれないが、試合を視聴している限りではまったく感じられなかった。これを応用すれば、今後、オフライン大会が復活した際に、地方の局舎を活用することで予選大会もオフライン化できるかもしれない。今回の座組は、eスポーツ大会の新たな可能性を感じさせてくれた。
高校生大会らしい一発勝負のおもしろさと、紡がれる伝統
さて、筆者は今年も2日間通しで観戦していたが、全国高校eスポーツ選手権は、数あるeスポーツイベントの中でも、突出して見応えがある。理由は、やはり出場選手が全員高校生であるというところが大きい。多くても3回しか出場できず、選手の学年が異なる場合、同じチーム構成は今年が最後になる。相変わらず前夜は緊張で一睡も出来なかったり、思うようなパフォーマンスが出せない選手が続出し、易々と不完全さを表すところもいかにも高校生的であり、とりわけ「LoL」部門は準決勝までBO1ということで、一発勝負のドラマ性と、青春らしい切なさがある。そうした命がけの真剣さがスポーツとしての感動を生む。
筆者の手元には第1回大会からの資料が残っているが、3回ともなるとそれがひとつの伝統として紡がれていくことを感じている。もう全日程が終わってしまったので、今更オススメしたところで遅いが、紡がれる伝統に着目しながら観戦すると、応援により一層熱がこもること請け合いだ。
まず「ロケットリーグ」から見ていくと、今大会で台風の目となったのが、2大会連続決勝大会に出場し、見事優勝の栄冠を掴んだN高「NRLG Cats」のtetu選手。スピードフリップと呼ばれる最速移動のテクニックをはじめ、プロレベルの実力を駆使し、他チームを圧倒。第2回大会で一緒に組んだyayo256率いるN高「NRLG Cows」との予選決勝の戦いが事実上の決勝戦と言えるような突出した強さで優勝を収めた。
ただ、tetu選手は最初からスター選手だったわけではなく、第2回大会ではベスト4で敗退している。対戦相手は、第1回優勝、第2回準優勝というずば抜けた成績を残した佐賀県立鹿島高校「OLPiXと愉快な仲間たち」だ。tetu選手はOLPiX選手をライバル視し、第2回敗戦時に彼を超えるべく今後も「ロケットリーグ」を続けることを明言していた。
そのOLPiX選手率いる「OLPiXと愉快な仲間たち」も、第2回大会では、大分県立鶴崎工業高校「雷切」の連携力に敗れており、OLPiX選手としても悔いの残る大会となった。OLPiX選手は現在「ロケットリーグ」のプロゲーマーとして、HANAGUMIのエースとして活躍しているが、おもしろいのは、そのHANAGUMIが公式指導パートナーとしてコーチングを行なっているのが、tetu選手らが所属するN高だということだ。
OLPiX選手が果たせなかった2連覇の夢を、tetu選手らN高が繋いでいく。第3回大会で優勝したN高「NRLG Cats」は、tetu選手以外は1~2年制と若いチームで、校内にもうひとつの「NRLG Cows」もいて戦力は十分。HANAGUMIのコーチングもあり、N高は第4回も引き続き優勝候補筆頭であり続けるだろう。
「リーグ・オブ・レジェンド」もおもしろい。第1回でflaw、赤バフという超高校級プレーヤーが大会を大いに盛り上げてくれたが、彼らが優勝、準優勝という実績を挙げる中、ベスト4止まりで悔し涙を流したのが、当時1年生だったN高「KDG N1」のmarimo選手だ。
そう、本大会でN高「KDG N1」優勝の立役者となった彼は恐るべき事に、3回しかない大会の歴史で、全大会で決勝大会に出場し、第1回:ベスト4、第2回:優勝、第3回:優勝という前人未踏の記録を打ち立てているのだ。その安定感、リーダーシップ、そして実力は大会随一といっても過言ではない。現在既にプロチームDetoNation Focus Meサブメンバーということだが、全国高校eスポーツ選手権が生み出したスター選手として、将来が楽しみな高校生アスリートだ。
もう1人は、同じN高「KDG N1」サポートのshakespeare選手だ。本大会の直前に、OCNのCMで田中みな実さんと共演することが発表されて話題を集めたが、N高の学生というだけでなく、ミスコン2019のファイナリストであり、スターダストプロモーションに所属するモデルであり、「LoL」グランドマスターで、RascalJesterの練習生、GALLERIA SQUADのメンバーと、肩書きに事欠かない。
第2回大会ではサブに回ることもあったが、本大会ではレギュラーとして全試合に出場し、サポーターの役割で勝利に貢献した。本大会はオンラインだったため、試合中の表情見ることは残念ながらできなかったが、その代わりに分かりやすいボイスで大会を盛り上げてくれた。
女性選手という時点ですでに珍しいのに、確かな実力で2連覇にも貢献と、マンガのようなキャラクターだが、こうしたスター選手が出てくるだけで大会は盛り上がる。女性アスリートの伝統はどのような形で受け継がれていくのか。第4回大会にも注目したいところだ。
第1回大会の時点で予期されていたN高全種目完全制覇。優勝を目指すためのノウハウ共有が急務
個人的に、今回も大いに楽しませて貰った全国高校eスポーツ選手権だが、提言らしきものが1つあるとすれば、決勝大会まで出場するような有力校が固定されつつある一方で、過去の決勝大会出場校が出場すらしなくなっている現状があり、参加校を拡げる施策がいよいよ急務だと言うことだ。
第1回大会時点で、N高のような通信制の高校が、オンラインで完結するeスポーツと相性が良いことは明らかだった。今回、2種目で完全制覇を達成したN高を筆頭にルネサンス、クラーク、アートカレッジなど、学校として正規のeスポーツコースや、学校を挙げてeスポーツを支援する体制が整っている高校は、大事な活躍の場として今後も積極的に全国高校eスポーツ選手権に出場するだろう。
しかし、その一方で、第1回「LoL」部門で優勝した東京学芸大付属国際中等教育学校や、同じく第1回、第2回の「ロケリ」部門で優勝した佐賀県立鹿島高校や大分県鶴崎工業高校は第3回に出場すらしていないという現実にも目を向けるべきだ。
これは学校が全日制だからとか、eスポーツ部がないからとかではなく、単純に1人あるいは複数人の生徒によるムーブメントを、学校側が支える体制や、大会運営側としてそれを支援する体制が弱いことが原因だと思われる。せっかく校内に芽吹いたeスポーツの芽を摘んでしまうのはあまりにももったいない。
また、大会がメジャーになるにつれて、2年前のように1人あるいは数人のゲーム好きが仲間を募って出場すれば即結果を出せるような状況ではなくなりつつあるのも事実だ。本大会で決勝大会に出場するような高校は、正規でeスポーツがカリキュラムに組み込まれていたり、プロスポーツ選手のコーチングを受けられたりする環境が整っている。学生たちもそうした環境を求めて、eスポーツに専念するためにわざわざN高に転入するという事例も出てきている。
こうした流れがもし先鋭化すれば、一部のeスポーツに熱心な高校だけが参加する大会になりかねない。文化事業として“全国高校”のタイトルにふさわしい大会にするためにも、大会側や学校側の過去の取り組みを共有し、多くの教員にとって未知の領域である“eスポーツ部”の運営に役立てられるような環境作りが必要なのではないだろうか。
すでに第4回大会も発表された。第4回は、「3月は卒業シーズンで忙しいので困る」という学校側の希望を通す形で再び開催時期を年末に戻す計画となっているが、第3の種目の追加も計画されており、今回以上に慌ただしい進行になることが予想される。学生の教育の一環として全国の高校がこぞって参加したくなるような支援施策、つまり“eスポーツ部支援プログラムのソフトウェア版の整備”に期待したいところだ。
© JHSEF and THE MAINICHI NEWSPAPERS.All rights reserved.










































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)














![オリ特付【02/26発売☆即納可能】【新品】【PS5】伊達鍵は眠らない ‐ From AI:ソムニウムファイル[PS5版]★浅草マッハオリジナル特典アクリルキーホルダー付★ 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/gazou1/4940261521165.jpg?_ex=128x128)

![【新品】【PS5HD】PS5用無線コントローラー ブラック[在庫品] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10870000/10872925.jpg?_ex=128x128)








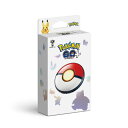

![シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME【通常版】(Blu-ray)【Blu-ray】 [ 庵野秀明 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8634/4988003878634_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ウマ娘 シンデレラグレイ 7【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8146/4907953228146.jpg?_ex=128x128)
![ウマ娘 シンデレラグレイ 5【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8122/4907953228122_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ウマ娘 シンデレラグレイ 6【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8139/4907953228139_1_2.jpg?_ex=128x128)
![『シドニアの騎士 あいつむぐほし』Blu-ray [初回限定版] 【Blu-ray】 [ 逢坂良太 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2373/4988003872373_1_2.jpg?_ex=128x128)

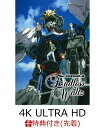
![とんでもスキルで異世界放浪メシ2 第2巻【Blu-ray】 [ 江口連 ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9346/4988111669346_1_5.jpg?_ex=128x128)
![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア【Blu-ray】 [ 古谷徹 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4722/4934569364722.jpg?_ex=128x128)
![忍者と殺し屋のふたりぐらし 第3巻【Blu-ray】 [ ハンバーガー ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8301/4988111668301_1_2.jpg?_ex=128x128)