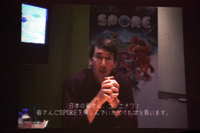|
||||
|
EAJ、Will Wrightのライフワーク「SPORE」発売記念イベントを開催 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
会場:デジタルハリウッド東京本校
エレクトロニック・アーツ株式会社は、9月5日、都内にて、シミュレーションゲーム「SPORE」の発売記念イベントを開催した。
会場には同社関係者に加え、会場となったデジタルハリウッドの学生、そしてスペシャルゲストとして芸能界を代表する“博学王”として知られる唐沢俊一氏と、現役東大大学院生として数々のテレビ番組に出演している“ギャル世代の才女”木村美紀さんが出演し、ふたりの「SPORE」のプレイ体験と、「SPORE」が生まれた歴史背景について熱いトークセッションが繰り広げられた。
「SPORE」は、本日9月5日発売で、価格はオープンプライス。想定価格は7,000円前後。対応OSはWindows XP/Vistaとなっている。
■ 構想8年、E3やGDCの常連作品だった「SPORE」がついに発売!!
我々が初めて「SPORE」について取材したのは2002年3月まで遡る。当時はプロトタイプの制作を進めている段階で、Will Wright氏自ら「『Spore』については、今はまるで宇宙をさまよっているような感じで、岩を目の前にした彫刻家のような気分なのだ(笑)」と回答していることから、「発売は相当先になりそうだ」という印象を持ったことを良く覚えている。しかし、まさかあれから6年半も待たされるとは思わなかった。
もちろん、この6年半の間に、様々なドラマがあった。ハイライトとしては、のちにGDC 2005最大のサプライズ、最良の講演として評されるWill Wright氏の講演「The Future of Content」で、「SPORE」のゲームデザインが初公開されたこと。そして翌年のWill Wright氏のキーノートスピーチ。また、先月のEA Asiaレポートでもお伝えしたように、非ゲーム系のセミナーにも積極的に参加するなどして、自身ライフワークとして位置づけている大作「SPORE」を、ゲーマー層のみならず非ゲーマー層にも広げる活動を続けている。
正直なところ、Will Wright氏は、EAにおいても、米ゲーム界においても大きな存在になりすぎていて、彼が直接ゲームの開発にタッチすることは少なくなっている。2008年8月時点の彼の名刺の肩書きも「Galactic Explorer(宇宙探検家、もちろん冗談である)」で、開発パイプライン上の存在ではない。しかし、「SPORE」は、「Sim City」と同様に彼自身がプロトタイプから作り上げた数少ない作品のひとつであり、そういう意味では、米ゲーム界、そして世界のゲーム界において、極めてエポックメイキングなゲームとなることは間違いない。
ふたりの話は、発売そのものに力点が置かれすぎていて、ゲームの魅力や今後のロードマップなどの紹介については弱かったのが残念だった。ただ、これまでにEAとMaxisが「Sims」フランチャイズで行なってきたビジネスを見る限りでは、「SPORE」においても、これ単体で終わるとは考えられず、キャラクタやビークル、宇宙船などのバリエーションを深めるためのデータ集、そしてストーリー性やゲーム性を拡張する拡張パックの発売は間違いないと予想される。非常に息の長いフランチャイズになると考えておいていいだろう。
ふたりの挨拶に続いて、Wright氏本人からのビデオメッセージが再生された。Wright氏は、「科学とふれあえる機会を作りたかった」と切り出し、ユーザーに向けては「宇宙を見て欲しい」、「生命とは何かということに注目して欲しい」、「(『SPORE』をプレイすることで)世界の見方が変わると思う」と、ゲームクリエイターから1段も2段も高い視点から「SPORE」のユニークなゲーム性をアピールしてくれた。
| 【細胞(水中)ステージ】 | ||
|---|---|---|
 |
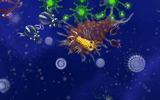 |
 |
| 「SPORE」の最初のステージとなる細胞ステージ。微生物としてタイドプールを駆け回る | ||
| 【クリーチャーステージ】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
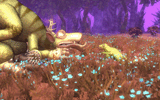 |
| 水中から陸上へ。陸にも外敵がいっぱいだ。細胞ステージで、肉食性と草食性のどちらを選ぶかによってゲーム性が変わってくる。好戦的なら肉食性、友好的なら草食性を選ぶといい | ||
| 【集落ステージ】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 操作対象がひとりから複数に進化する。群れを作り、集団で敵対勢力と立ち向かっていくことになる | ||
| 【文明ステージ】 | ||
|---|---|---|
 |
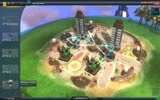 |
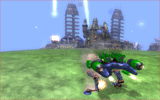 |
| 様々な部族、都市、文化が誕生し、生き残りをかけて他の部族と外交を行なっていく。リアルタイムストラテジー的な要素の強いステージだ | ||
| 【宇宙ステージ】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 最終ステージは宇宙が舞台。宇宙船に乗り込んで異星人との接触やテラフォーミングを計っていく。いわゆる銀河帝国を作ることも可能だ | ||
■ H・G ウェルズ「宇宙戦争」から、水木しげる「宇宙虫」まで
あらゆる“進化娯楽ネタ”が飛び出したトークショウ
 |
| スペシャルゲストとして登壇した唐沢俊一さん(右)と木村美紀さん(左) |
 |
| 秘蔵映像に解説を加える唐沢さん。「SPORE」をプレイして「宇宙虫」を思いつくところが唐沢さんらしいところだ |
 |
| 自分自身が創造したクリーチャー“ポニョ”の容姿を身振り手振りで説明する木村さん |
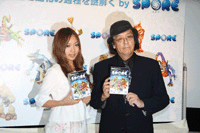 |
| 「SPORE」で作成したキャラクタは、サーバーにアップロードすることも可能。唐沢さんや木村さんが創造したキャラクタに出会えるだろうか!? |
まずふたりの「SPORE」プレイ経験が披露された。唐沢さんは、「実は時間がとれず、宇宙(ステージ)まで行けてないが、細胞から(パーツを)組み合わせて進化させていくという過程がすっごくおもしろくて、いろいろなことを試すうちに進化の袋小路にはまってしまうようなことが多かった」とコメント。木村さんは「すっごくおもしろくてハマってしまった。ここ3日間ぐらい寝るのを惜しんでずっとやってしまって、最後のステージ(宇宙ステージ)まで行きました。独自のキャラクタが作れるので何回やってもおもしろいですね」と嬉しそうに報告し、唐沢さんが真顔で驚くという一幕もあった。
ふたりのトークセッションは、「エンタテインメントとしての進化」と題された唐沢さんによる特別講演のスタイルが取られた。基本的には、木村さんの「SPORE」のインプレッションを語り、それを受けて唐沢さんが、“人類が「SPORE」に至るまでの道のり”を語るという形で進められた。唐沢さんは、「実は“進化”を娯楽にするという試みは古くから行なわれているんですよね」と、唐沢さんらしいユニークなアプローチで、「SPORE」生誕までの歴史を振り返った。
唐沢氏は、“進化”を娯楽にした始まりは、19世紀に書かれたH・G ウェルズの「宇宙戦争」だという。「宇宙戦争」に登場する火星人は、現代にいたるまで宇宙人のイメージのひとつとして知られるようになった、いわゆる“タコ型星人”である。頭脳ばかりが大きく、大気が薄く、重力も少ない火星で活動するために、手足が長細くなっている。唐沢氏によれば、これは未来における人類の進化を予測した姿だという。
同じくH・G ウェルズの作品「タイムマシン」は、「宇宙戦争」と反対に、人類の“退化”を娯楽にしたものだという。この物語では、環境が悪化し、原始人のように退化してしまっている人類が描かれる。唐沢さんは「この頃(19世紀末)から、“進化”というテーマは知的なエンターテインメントとして受け入れられていたのではないか」と結んだ。
続いて、木村さんが「SPORE」の宇宙空間の広さについて、「(銀河系の)全体を見渡すことができるし、星をクローズアップすることもできる。宇宙を支配する神になったような感じ」とコメントすると、すかさず唐沢氏は「実はそれもすでにSFで描かれているんです」と切り返し、エドモンド・ハミルトンの「フェッセンデンの宇宙」を紹介した。
「フェッセンデンの宇宙」は、1937年に発表されたSF小説で、科学者フェッセンデンが実験室内に人工の小宇宙を創造し、さまざまな実験を繰り返すという荒唐無稽な物語。唐沢氏は「『SPORE』をプレイして最初に思い浮かんだのがこの小説。フェッセンデンの実験に魅せられた主人公が夜の街に出て、ふっと夜空を見上げた時に、ふと自分を見つめる大きな目が見える、そんな小説なんです。だから『SPORE』のクリーチャーたちも、ふと自分は誰かに操られているんじゃないかってふっと思うんじゃないかって(笑)」と、縦横無尽の博覧強記ぶりを発揮。これにはさすがに最高学府に籍を置く木村さんもついて行くのがやっとといった感じだった。
続いて唐沢氏は、いかに人類が、“進化をエンタメしてきたか”を秘蔵の資料を使いながら披露してくれた。残念ながらすべてのスライドや映像は撮影禁止だったため、お見せできないのが残念だが、全面カットするのはあまりにもおしいので、唐沢氏が何を見せてくれたのか、以下にまとめておきたい。
・The Ounter Limits(米、1963年)
1960年代の北米SFテレビドラマ。映像では、未来的な科学実験室を舞台に、人間を人工的に進化させる実験が行なわれていた。実験は成功し、ハンサムな主人公は、頭皮が後退した巨頭の未来人になる。
・週刊少年マガジン(日本、1967年刊)
当時の週刊少年マガジンは漫画ばかりではなく記事も多かった。その中の未来人を特集した記事。背丈4メートル、頭皮がなく、手足が細く、歯もない。現代的な価値観で見ると、“むごたらしい姿の化けもの”にしか見えないが、当時はそれこそが素敵な未来だと考えられていたという。唐沢氏は「進化の概念も進化していることがわかる」とまとめた。
・Mars and Beyond(米、1957年)
ディズニーのアニメーション。火星の生態系がストイックに描かれる。常に砂嵐、水はあるがすぐ凍り、地上を蠕動する生物、紙ペラのような薄い飛行生物、マジックハンドのような捕食機能を持つ生物など、奇妙な生態系が描かれる。「弱肉強食の世界という点で『SPORE』と似ているところがある」(唐沢氏)
・宇宙虫(日本、1965年)
今回個人的にもっとも驚いた資料。日本にも「SPORE」的な発想は存在していた!! 1965年発行の「別冊少年キング11月号」の読み切り短編漫画。作家はあの水木しげる氏。主人公“凡太”の爪の中で見たこともない虫がふ化する。両親から虫を飼うことを反対され、凡太は仕方なく、虫をマッチ箱に入れて、近所の池の中央にある島に捨てる。1カ月後、凡太が池に行ってみると、虫たちは弓矢や小舟を使って狩猟を行なっていた。数日後には橋ができ、たたら場まで完成。さらにその1カ月後には、ビルができ、戦艦や空母が島を守っていた。そして原爆実験の成功。最終的にはロケットで自分の故郷へと帰っていった。まさに「SPORE」そのものである。
・ネオファンタジア(イタリア、1976年)
ディズニーアニメ「ファンタジア」のパロディーアニメ。宇宙飛行士がとある星に残した飲みかけのコーラの瓶の中で生物が誕生し、次第に成長して瓶を飛び出していく。軟体生物は、目を手に入れ、口を持ち、手、足そして翼とどんどん成長し、最終的には人類へと成長していく。まさに一個の生物が「SPORE」的発展を遂げるアニメーションだ。
トークショウのまとめとして、唐沢さんは、「“進化”は学術的なものではなく、エンターテインメント、つまり娯楽として楽しんできた歴史が駆け足の紹介でしたがおわかりになったかと思います。“進化娯楽”の頂点にいるのが『SPORE』というゲームだと思います。プレイしながら我々は時代の先端にいることを実感しながら、感性を進化させていってください」と笑顔でコメントした。
木村さんは、「このゲームの魅力は、自分でキャラクタを設定して、名前から手や足も全部自分で決められることです。自分は2本足で、足が10に対して頭が1ぐらいの“ポニョ”を作りました。三角形に足を開くことができて、目がひとつあって、羽根がついていて、手から角が生えていて、いろんなところにいろんなパーツを置くことができるんです。理想的なクリーチャーを作れて凄くおもしろかったです」と、身振り手振りを交えながら興奮気味に一気にまくしたてた。
さらに思い出したように「文明のステージでは都市を造れるんですが、私は“ポニョ御殿”を造ったり、いろんなものを生産できる“ポニョ工場”や娯楽施設なども作りました。名前も自由に付けられて、自分だけの世界を作れるのがおもしろいと思います。ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います」とまとめてくれた。
(c)2008 Electronic Arts Inc. All rights reserved.
□Electronic Arts Japan(日本語)のホームページ
http://www.eajapan.co.jp/
□「SPORE」のページ
http://www.japan.ea.com/spore/
□関連情報
【8月18日】PCゲームファーストインプレッション「SPORE」
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080905/spore.htm
【8月18日】「SPORE」発売直前!! シンガポール訪問中のWill Wright氏インタビュー
「Global Brand Forum」で全産業界に向けて語られたスピーチも併せて紹介
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080818/wr.htm
【8月14日】EA Asia、シンガポールにてプライベートイベントを開催
シンガポール動物園でWill Wright自ら「SPORE」を披露
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080814/eaa_01.htm
【8月14日】EA Asia、アジアに「SPORE」を紹介するプレスイベント開催
Will Wright氏が「SPORE」のルーツを語り、ゲームを実演
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080814/spore1.htm
【2006年3月26日】Will Wright氏キーノート「What's Next in Design」
「SPORE」への熱い想いとゲームリサーチの重要性とは?
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20060326/gdc_will.htm
【2005年3月13日】ウィル・ライト氏が未来構想を語る「The Future of Content」
ライト氏のライフワーク「SPORE」で実演したプロシージャルな世界
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20050313/gdc_will.htm
(2008年9月5日)
[Reported by 中村聖司]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.