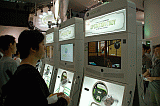|
||||
|
「東京ゲームショウ2006」マイクロソフトブースレポート |
 |
会場:幕張メッセ
入場料:当日1,200円、前売1,000円
小学生以下無料
マイクロソフトブースの目玉は、なんといってもミストウォーカーの坂口博信氏が手がけるXbox 360用RPG「ブルードラゴン」と「ロストオデッセイ」だろう。どちらもクローズドの専用ブースで公開されており、15人単位の総入れ替え制で約15分のプレイ時間が与えられていた。会場と同時に長蛇の列が出来上がる人気ぶりで、待ち時間は常に90分以上。23日、24日の一般公開日は、ビジネスデーをはるかに上回る人が訪れる。並んでいればほぼプレイできるかと思われるが、万全を期したい人は早めに並んだほうがいいだろう。
■ ブルードラゴン、ロストオデッセイ
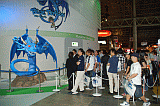 |
ゲームが始まると、主人公の少年「シュウ」が木々が見える開けた場所に立っている。フィールドには、「これぞ鳥山ワールド!」といった強烈な個性を放つモンスターが数匹、ゆっくりと動き回っている。一定の距離まで近づくと発見されるため、モンスターに体当たりされるか、もしくはこちらからXボタンでエンカウントを仕掛けると戦闘画面に突入。このとき、相手から仕掛けられると不意打ちで不利になることがままあり、逆に背後からエンカウントに成功するとバックアタックでこちらが有利に立ち回れるケースが多かった。
戦闘画面はオーソドックスだが、5人の少年少女たちの“影”が他のRPGと一線を画すポイント。防御に回るとダメージを受けるのは本体である少年少女自身だが、ひとたび攻撃に回れば影のドラゴンたちが猛烈な攻撃を仕掛ける。デモプレイ用にあらかじめ「戦士」や「魔法使い」といったイメージの能力が設定されていたが、先日のMedia Briefingで報じているとおり、実際にはプレーヤーが好きなように影を育成することができる。
戦闘シーンで興味深かったのは、一部の特殊な攻撃や魔法などに“タメ”が使われていること。ボタンを押している間だけゲージが伸び、タイミングよくボタンを離すと威力や発動のタイミングが変化するといった具合。これが適度な緊張感もしくはアクセントになっており、先頭が間延びすることなく楽しめた。もちろん、レベルの高い技や魔法を使ったときはド派手なエフェクトが繰り出され、それはもう見ているだけで頬が緩んでくるほどだ。
「ロストオデッセイ」のデモプレイモードは、冒頭シーンからの1種類のみ。先日のMedia Briefingでお知らせしたとおり、鎧を着込んだ大軍勢による激しい激突から一転、魔法によるものか、天に広がった大地から溶岩が降り注ぎ両軍が飲み込まれ灰燼と化していく。Media Briefingではここでデモプレイが終了したが、クローズドブースでは(普通にプレイしていれば)ここから先の展開を体験することが可能。
固まった溶岩の上を歩き回る主人公。犬が鎧を着込んだような敵と散発的なエンカウントを繰り返すと、やがてふたりの友軍に出くわす。地獄絵図と化した戦場で、まさか生き残りがいるとは夢にも思っていなかったようだ。驚きを隠せないふたりを尻目に、眉ひとつ動かさない主人公。その先に待ち受けているものは……。
あくまでも序盤を体験しただけだが、本作のポイントはドラマチックなムービーからシームレスに戦闘や通常パートが挿入されるというインタラクティブな構成にあるように感じられる。そのぶん、人によっては「え、ここで戦闘?」と唐突な印象を受けるかもしれない。戦闘のシステムはきわめてオーソドックスで、斬新さはないが安心してプレイできる。もしかしたら、物語の流れに身を任せるには奇をてらうよりも従来型のシステムのほうがフィットすると判断されたのだろうか。雰囲気によって好き嫌いはわかれそうだが、そのぶんひとたび気に入ったのなら、その人が得られる没入感は他の作品をはるかに上回りそうだ。
■ ロストプラネット エクストリーム コンディション
 |
出展バージョンのマルチプレイモードは、雪原を舞台に4対4で戦う形式。さすがに体験版で慣らしている人が多く、一瞬たりとも気が抜けない戦いが続出。記者は当初「へへっ、こんなのVSに乗ってしまえばこっちのもんさ!」とタカをくくっていたが、スタッフの人に「いや、案外そうでもないんですよ」とたしなめられる。
なぜそのようなアドバイスが与えられたのかは、数秒後に身体で理解することになる。なんと(どうやったのか……)敵チームの誰かが記者のVSに時限爆弾を仕掛けたのだ。異様な雰囲気に気づいて慌ててVSを降りようとすると、飛び降りた直後に時限爆弾が炸裂して記者のキャラクタが死亡。「あー、今のは、あえて降りないほうが正解でしたねぇ」とスタッフの残念そうな声。しかも、VSを撃破されると戦力ゲージが大幅に減る。これは痛い。
「VSは確かに強いんですが、生身の雪賊でも脚部に攻撃を集中されると厳しいですね」とのこと。シングルプレイも重厚で実に歯ごたえがあったが、マルチプレイはそれにカジュアルさが加わるため、よりリピート性が高まるといった雰囲気。マルチプレイは1回ごとの総入れ替え制につき、リベンジしたい気持ちをグッとこらえつつ試遊台をあとにする。仕事じゃなければ、適当に間を置いて再び列の最後尾に並んだであろうことは想像に難くない。
ブース内では2大RPGの勢いに押されているが、試遊が終わったあとの“後ろ髪を引かれる感覚”は(個人的な好みもあるが)記者的には「ロストプラネット」のほうが勝っていた。早く自宅で心置きなく戦いたい。今はもう、それしか言葉が出てこない。
■ DEAD OR ALIVE EXTREME 2
 |
メインはあくまでも「ビーチバレー」だが、ミニゲームには「カメラの操作が可能」という決定的な機能がある。忙しくてそれどころじゃないといったケースもままあるが、余裕があればチョコチョコ動かして美しい肢体をさまざまなアングルから堪能できるというわけだ。プレイ中はもとより、前後に見せるしぐさもファンの心理をくすぐってくれる。
ボタン連打、タイミング重視と極めてシンプルだが、前述の要素がすべてをカバー。先日のMedia Briefingで「スポーツゲーム」として名前があげられた瞬間、会場になんともいえない「……つっこんでいいですか?」といった雰囲気が漂ったことでもわかるとおり、もはやスポーツというタームはオブラートにさえならない。男なら堂々と「こういうの大好きですから!」とパッケージをレジに持っていこう。そういった意味において、本作がファンの期待を裏切ることは絶対にない。
■ Rockstar Games presents Table Tennis
 |
パワー、テクニックなど特徴の異なる選手、コスチューム、会場を選んでゲームスタート。左右のドライブ、カット、スマッシュといったボタンは、一般的な卓球ゲームなら「打つ瞬間に押す」のが通例だが、本作は「あらかじめボタンを押して“タメ”を作っておき、打つ瞬間にボタンを離す」という意表を突くシステムを採用。
最初は「これ、慣れるまで全然試合にならないんじゃないか?」といぶかってしまったが、実際はすぐ順応することができた。というのも、ボタンを押して作るタメは、あくまでも力の入れ具合に作用。とりあえず返してしまいたいときは、押してすぐ離せば、ある程度までキッチリ反応してくれる。このあたりのさじ加減、バランス感覚が、非常にいい具合なのだ。
タメを作って打ち返すということは“読み”が重要になってくる。返してくる角度、相手と自分の位置など、ベストな条件が揃えば全身に電撃が走るような「してやったり!」感が突き抜ける。言葉は悪いが、これはもう麻薬的といってもいい。反射神経だけでは到達できない領域がある。過去、このような卓球ゲームがあっただろうか。
もしブースを訪れることがあれば「へぇ、リアルだねぇ」で素通りするなかれ。卓球ファンはもちろん、スポーツゲームが好きな人は必ず気に入っていただけるはずだ。
□Xbox 360のホームページ
http://www.xbox.com/ja-JP/
□「東京ゲームショウ2006」のページ
http://tgs.cesa.or.jp/
□関連情報
【9月20日】マイクロソフト「Xbox 360メディアブリーフィング」開催
日本向けタイトルを拡充、年内に110タイトルをリリース
http://watch.impress.co.jp/docs/20060920/ms.htm
【9月20日】マイクロソフト、「東京ゲームショウ2006」のXbox 360出展タイトルを発表
http://watch.impress.co.jp/docs/20060920/mstgs.htm
【「Xbox 360」記事リンク集】
http://watch.impress.co.jp/docs/backno/news/x360link.htm
(2006年9月22日)
[Reported by 豊臣和孝]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.