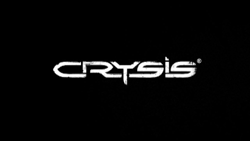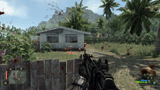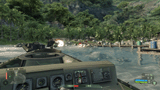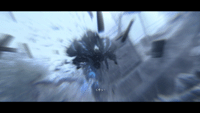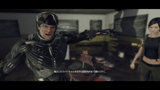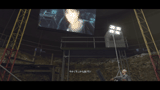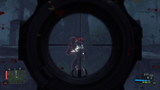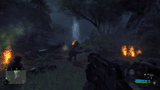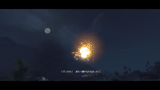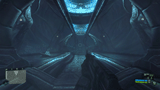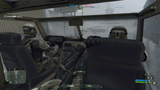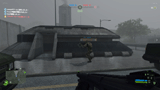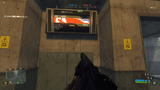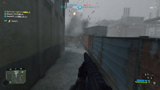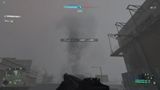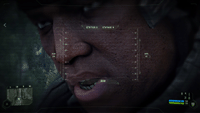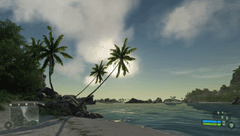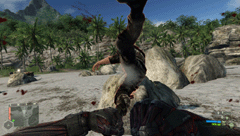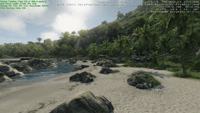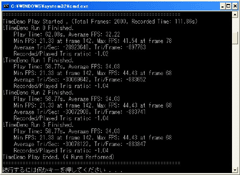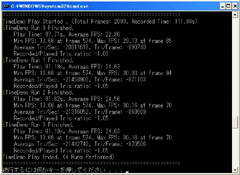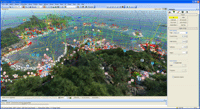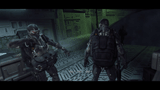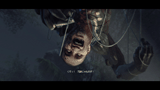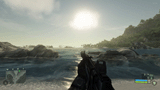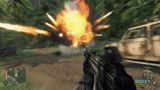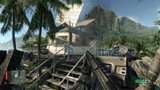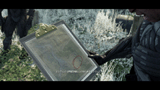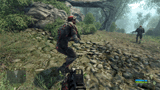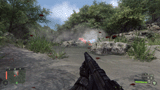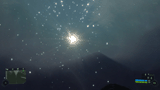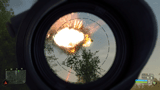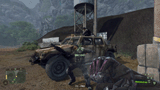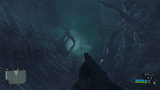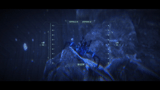|
||||
|
★PCゲームレビュー★
PCゲームには、時代の節目を担うタイトルが存在してきた。リリースから数年間、競合タイトルの評価基準とされてきたビッグタイトルだ。グラフィック面を強く牽引してきたFPSの世界では特にそれが顕著で、古くは「Quake」、「Unreal」などがそれにあたる。いずれもリリース直後は動作が重いと言われながら、新機軸の映像でゲームユーザーを魅了し、ゲームPCの「ハイエンド」を定義する存在として君臨してきた。
「Crysis」は、まさにその役割を果たすタイトルだ。本作最大のウリであるグラフィックスは掛け値なしに美しく、圧倒的な存在感を誇っている。そのため要求するPCスペックも非常に高く、結論から先に書いてしまうと、最高設定では「現行のハイエンドPCですらスペックが足りない」ほどだ。この点が、現行世代のゲーム機基準で構成されることの多いゲームタイトルの中にあって異彩を放つ。本稿では、PCゲームの「次世代」を見事に再定義してくれた本作の魅力をお伝えしたい。 ■ ゲーム界最新最強のグラフィックに酔え! 注目のCryENGINE2.0エンジン初タイトル
まずグラフィックス。室内・屋外両方を高クオリティで描画し、屋外にいたっては島ひとつを一望に納める距離から、草一本のディティールまで描画するという圧倒的なスケーラビリティを誇る。また、リアルタイムに処理されるライティングのおかげで、昼夜の連続的な光源の変化をリアルに再現。リッチなポストエフェクトで、非常に存在感のある絵作りに成功している。 ゲームプレイに変化を加える物理処理も見逃せない。本作に登場する多くの家屋は、爆発物でバラバラに吹き飛ばせる。パーツ単位で物理処理されているから、屋内に潜む敵を、建物もろとも潰してしまうようなゲームプレイが可能になっているのだ。敵の首根っこを掴み投げ飛ばせば、ぶつかったオブジェクトが崩壊すると同時に敵を倒せる。まるでアクション映画のワンシーンのような迫力だ。本作はこうした仕掛けが全編を通して満載されている。
ゲームそのものの構成としては、ストーリーを追うシングルプレイモードと、最大32人で戦うマルチプレイモードを搭載する。シングルプレイでは、本作ならではの自由度の高い行動範囲と戦法の幅によって、リプレイ性の高いゲームを楽しめる。マルチプレイモードでは、戦略的な段階を追って敵基地を壊滅させるという、本作独自の「POWER STRUGGLE」ルールが特徴的だ。次章からはそれぞれのゲームモードについて詳しくご紹介していきたい。
■ リプレイ性抜群のゲーム性に、充実のシナリオ・演出。グラフィック以外も抜かりない手応え
このような設定で始まる本作のシングルプレイは、周囲数十キロメートルの広さを持つ島全域を舞台に展開する。基本的なゲームシステムは標準的なFPSながら、主人公が「ナノスーツ」と呼ばれる強化服を装備している点が特徴的だ。このスーツにより、主人公は一般兵士にない各種の強化能力を使えるのだ。 ・ナノスーツによる強化能力を駆使して戦う面白さ ナノスーツによる強化能力の種類は「マキシマム・アーマー」、「マキシマム・ストレングス」、「マキシマム・スピード」、「クローク」の4種類。「アーマー」は敵の攻撃を吸収し、体力低下を防ぐ。「ストレングス」は筋力を強化し、ジャンプ力、パンチ力を倍増させ、射撃時の反動を抑える。「スピード」はダッシュ時の速度を数倍にする。「クローク」は主人公に光学迷彩を施し、敵の目から姿をくらます。 ナノスーツは常時1種類の能力を発動する代わりに、スーツエネルギーを消費する。頻繁に使うことになる「アーマー」は、敵の射撃を数発受け止めるとエネルギーが切れ、それ以降攻撃を受ければ直接ヘルスにダメージを受けることになる。攻撃を連続で受けてヘルスが0になれば死亡だ。他の能力も同様に、発動するたびにエネルギーを消費していく。エネルギーは一定時間で自動回復するが、エネルギーが切れている間の主人公は一般兵とそう変わらない能力になってしまう。状況にあわせたエネルギーマネジメントが重要だ。 プレイを開始してしばらくは、各種能力の使い勝手を学習する段階になるだろう。最初のうちは「アーマー」に依存して普通の射撃戦になることが多いが、プレイに慣れてくれば各種能力の面白い使い方が見え、他の能力を活用できるようになってくる。そうなれば一気にゲームが面白くなる。 例えば「クローク」で身を隠しながら敵に近づき、「掴む」キーで首根っこを掴んで、「ストレングス」強化に切り替えて他の敵に向けてブン投げるという按配だ。「クローク」しながら敵を一箇所に誘導し、足元に手榴弾を置いて「スピード」強化で急速離脱するのも楽しい。工夫次第で本作の戦闘を多角的に楽しめるようになるだろう。
武器をカスタマイズすることも面白さのひとつだ。主人公の装備する銃器には、種類に応じてサイレンサーやグレネードランチャー、スコープなどの追加パーツを装着することが可能。サイレンサーとスコープを付け、「ストレングス」強化で正確な射撃を遠距離から叩き込むといったプレイは、中盤以降の強力な戦術のひとつだ。物音を立てて敵を1箇所におびき寄せ、ライフルにつけたグレネードランチャーで一網打尽にするのも面白い。
・中盤以降に劇的な展開が。2度目以降のプレイでは選択肢が広がり、楽しみも深まる
「何がどうなってんです? 俺たち死にまくってるじゃないすか!」 このあたりの展開は、ゲーム中各所に挿入されるリアルタイムレンダリングのカットシーンでじっくり描かれていく。カットシーンでは、通常ゲーム画面にさらなるポストエフェクト効果が加えられ、ゲーム画面でありながらプリレンダーのムービーに見えてしまうほどのクオリティで描画される。日本語版における字幕のクオリティも高く、ちょっとしたSF映画としても素晴らしい出来栄えだ。 戦いは、沿岸部での散発的な戦闘から、本格的な襲撃作戦、戦車戦など、バリエーション豊かに進行していく。序盤は北朝鮮軍との戦いが中心で、ひたすら敵の掃討を目指してプレイしていると、やや単調に感じる部分もあるかもしれない。しかし本作では、中盤から終盤に掛けて、ストーリー的にもゲームプレイの変化としても、劇的な展開が待ち受けている。それがどのような内容であるかは実際にプレイしてのお楽しみにしていただきたいが、ラストまでプレイすれば、シングルプレイFPSとして近年稀に見るほどの充実感を得られるだろう。 そうしてクリアした後も、もう一度ゲームを始めてみよう。本作では特に、一度クリアした後、ゲームプレイの特徴を押さえてからのプレイが楽しい。というのも、ナノスーツの能力や武器のカスタマイズをうまく使って、選択肢の豊富な戦いを組み立てることができるからだ。オープンフィールドのマップを採用していることもあり、ルート選択も自由。一度プレイしたシーンでも別の角度からプレイし、新しい戦い方を試してみよう。
物理制御された家屋を破壊しまくって派手なプレイをするもよし、「クローク」でスニーキングアクション的に、最小限の敵だけを倒して先に進むもよし。筆者の場合は「ストレングス」を多用して、物を掴んで投げつけるだけで敵を倒していくという遊びにハマっている。本作はグラフィックだけでなくゲームプレイも「ハイエンド」なのかもしれない。
■ マルチプレイはオリジナルルール「POWR STRUGGLE」がイチオシ
「POWER STRUGGLE」モードは、本作ならではの独自色を出していて面白い。基本的なルールは、2チームに分かれ、マップ上に配置された各種の施設を占領し、エイリアンテクノロジーによる各種の超兵器を開発、それを使って敵基地を完全に破壊する、というものだ。施設の占領システムは「BattleField」に近く、ゲームの勝利目標は「Enemy Territory」に近いが、プレイ感覚は非常に固有のものだ。 マップ上に多数配置されている施設には、バンカー、兵器工場、研究施設、エネルギーサイトなどがある。それぞれに異なる役割を負っており、バンカーは兵士の出撃地点、兵器工場では戦闘車両が作れ、研究施設ではエイリアンテクノロジーに基づく超兵器を製造できる。そのために必要なエネルギーを溜めるため、各地のエネルギーサイトを確保するというわけだ。 シングルプレイモードと同様に、マルチプレイでもプレーヤーは皆ナノスーツに身を包んでいる。このため、高い塀を「ストレングス」モードで飛び越えたり、「クローク」で敵の目をごまかす(うっすら見えるので無防備な場所では自殺行為)ような戦い方が可能だ。武器はシングルプレイ以上に豊富で、基本的な各種銃器類に加えて、エイリアンテクノロジーを使った冷凍光線(直撃すると凍りつき、衝撃で割れる)など個性的な武器が多数登場する。 その中でも最重要の兵器が、ゲームの勝敗を分ける「TAC ランチャー」だ。これはグレネードランチャーのお化けのような個人装備で、弾頭にはなんと戦術核を備える。ひとたび発射すれば、周囲数十メートルのオブジェクトをまとめて粉砕してしまう威力だ。ゲームに勝利するには、この装備、もしくは戦術核弾頭装着型の特殊戦車を使い、敵の基地を壊滅させるというわけ。拮抗したラウンド終盤の攻防戦は、戦術核が各所で炸裂し、「ド派手」という言葉では言い尽くせない惨状を呈する。これまで体験したことのないマルチプレイの風景である。
欠点について指摘すると、本作のマルチプレイはやや複雑なルールを備えていることもあり、戦術理解度の高いプレーヤーが揃わない限り、なかなか勝負がつきにくい傾向がある。現在のところは、プレーヤーの多くがゲームルールの勘所を学んでいる最中のようだ。このあたりのゲーム性も「ハイエンド」と言えるかもしれないが、多くのプレーヤーがルールを理解する頃には非常に面白いゲームが展開されると期待していいだろう。
■ DirectX 9世代最強タイトルの座は確実。DirectX 10タイトルとしてはどうか?
グラフィックスセッティングの最高設定については、DirectX 9とDirectX 10で異なるものになっている。オプションスクリーンで「低」、「中」、「高」、「最高」として用意されている選択肢のうち、DirectX 9バージョンで利用できるのは「高」までだ。「最高」設定を利用するには、基本的にはDirectX 10対応の環境を準備する必要がある。つまり、Windows VistaとDirectX 10対応ビデオカードが必要になる。 「高」と「最高」の2設定の間では多くの違いがあるが、ここでは目に付くポイントを3点取り上げよう。「パララックス・オクルージョン・マッピング」と「ゴッドレイ」効果、「オブジェクト・モーションブラー」効果だ。 地面や壁などのテクスチャには、「高」設定で「パララックス・マッピング」効果が適用されており、テクスチャに立体感を加えている。「最高」設定ではこれに加え、サーフェスの凹凸情報に基づき、光源方向からの遮蔽を考慮した影処理が施される。これによる立体感の向上は劇的で、地面を眺めればその効果が一目瞭然だ。
2番目の「ゴッドレイ」効果は、太陽光線など強い光が空気中の微粒子に反射し、それがオブジェクトに遮られることで「光が漏れ出す」ような映像を実現する。木立の間から太陽を眺めると、美しい光線のほとばしりを見ることができる。3番目の「オブジェクト・モーションブラー」効果は、言わずもがな、オブジェクトに対し運動量ベースのブラーをかける効果だ。それぞれの効果については下のスクリーンショットを検討してみてほしい。
さて、実はここで紹介した効果を含めて、公式にDirectX 10フィーチャーとされている設定は、ゲームの設定ファイルを触ることでDirectX 9環境でも適用することができる。結果的にDirectX 9バージョンでもDirectX 10バージョンと同等の絵を出すことができる。つまり、DirectX 10だから美しい環境が実現されているわけではないのだ。サポート対象外となる行為なのでここで具体的な方法について触れることはしないが、各ファンサイトにて設定の詳細について検証が進められている状況なので、興味のある読者は各サイトを当たってみるとよいだろう。ただし、実行に移す場合は、くれぐれも自己責任で行なって貰いたい。 あえて上記に触れたのは、現在のところDirectX 9バージョンとDirectX 10バージョンで、「最高」設定の絵を出したとき、実はDirectX 9バージョンの方がパフォーマンスが良いからだ。これについては筆者の環境でも同様の傾向を確認できた。この点について現在Electronic Artsでは、DirectX 10バージョンでのパフォーマンスを改善させるパッチを準備中であるのとのことだ。このリリース時期については明らかにされていないが、いずれにしても現時点で結論を出すのは賢明ではなさそうである。 ・最高設定は凄く重い! これがハイエンドPCゲームの新基準になる?
本作のインストールイメージにはベンチマーク用のバッチファイルが搭載されているため、これを使用して平均fpsを計測した。計測したPCはCore2Duo 3.4GHz、GeForce8800GTXシングルという構成で、現状ではややハイエンドに位置する性能。共通の条件は解像度1,360×768ドット、アンチエイリアシング×4とした。DirectX 9バージョンの実行OSはWindows XP 32bit、DirectX 10バージョンはWindows Vista Home Premium 64bit Editionである。
計測した組み合わせは、DirectX 9バージョンにおいては「高」設定と「最高」相当のシェーディング機能をONにした状態の2種。DirectX 10バージョンでは「高」設定と「最高」設定の2種類。なお、今回の計測で試したDirectX 9における「最高」相当の設定と、DirectX 10バージョンでの「最高」設定は完全に同一ではない点にご留意いただきたい。
簡単にまとめると、DirectX 9バージョンで利用可能な「高」設定において、筆者の環境では平均30fpsをやや上回る程度のパフォーマンスである。室内など視界が限定された空間では60fpsに達することもあるが、屋外の複雑なシーンでは20fps以下に落ち込むこともある。なんとか普通のプレイが可能、といった按配だ。 そしてDirectX 10バージョンでの「最高」設定においては、筆者の環境では10~20fps程度となり、プレイに支障が出てしまう。より高い解像度(1,920×1,080ドット)に設定すると、fpsがさらに低下し、低解像度に設定するとやや向上が見られるため、処理能力の不足のバイアスはビデオカードにありそうだ。
感触としては、DirectX 10モードでのフレームレート低下ぶりが著しいことは確かだ。原因は定かではないが、ドライバとの相性、OSの違いなど複数の異なる要因が関わってくるため、簡単には結論づけられない。ここは素直に本作のDirectX 10最適化パッチのリリースを待つことにしたい。 ■ 「激重」動作も、時代の節目を担うタイトルとしての必要悪。そのこだわりを評価したい
まず動作の重さは、純粋にゲームとしてみれば確かに弱点だ。なにしろ、本作の特徴である美しいグラフィックスを堪能したいのであれば、ミドルクラスのPCではまったく力不足であり、最高設定でプレイしたければハードの進化を待つしかないというバランスなのである。 しかし、それこそが本作の持つ良さであるとも言える。動作の重さは、描き出されるグラフィックスクオリティの対価として必要なものだ。PCゲームの歴史において、このような特性を備えてリリースされたゲームはあまたある。「Quake」、「Unreal」といったゲームは、ソフトウェアレンダリング時代の集大成として、当時のPCスペックの限界に挑戦していた。 また、例えば「Operation Flash Point」は、リリース時、最高設定でまともに動かせるPCは存在しなかったが、オープンフィールド系ゲームに新たな基準を打ち立てた功績がある。かつての「Unreal Tournament」シリーズも、リリースされるたびに「ハイエンドPCでも重い」と言われたものだ。しかし、それは常にハードウェアの進化が問題を解決してきた。 本作の立ち位置はまさにそこだ。CryEngine2.0のリリースタイトルとしてこれからのPCゲームに必要な素材をそろえた本作は、ゲームそのものの評価とは別に、今後しばらくはあらゆるゲームタイトルと比較され、また新ハードウェアの検証に使われる「基準」として君臨することになるだろう。 その寿命はどれほどになるだろうか。筆者のPCは、現行世代としては一応「ハイエンド」近くに位置する構成である。ビデオカードを2枚差し以上にし、CPUをクアッドコアにしたところで、性能を倍に引き上げるのが限界だろう。それでも本作の最高設定は40fps以下程度で動作する計算になる。一般的に、ゲームが完全に快適と言えるフレームレートは平均60fps以上、重くなるシーンでも快適にプレイしようと考えれば平均100fps以上は欲しい。となると、本作を完全に快適に動作させるためには、現行世代で望めるハイエンドPCをさらに3倍近く高速化する必要がある。ムーアの法則を無理に適用させるとすると、このパフォーマンスがハイエンドクラスまで降りてくるのに3年ほどの期間が必要な計算になる。
ここで強引に結論づければ、本作は「3年後の標準的な最新ゲーム」に匹敵するグラフィックスクオリティを持つゲームと言えるかもしれない。もちろん、ゲームにまつわる半導体やソフトウェアの進歩は単純に議論できない問題だ。しかし、このような強引な予測をしてしまいたくなるのが、本作のような冒険的PCゲームの隠れた役割であると言いたい。PCゲーマーとして、今そのようなタイトルをプレイできることを素直に喜びたいところだ。
(C) 2007 Crytek GmbH. All Rights Reserved. Crytek, Crysis and CryENGINE are trademarks or registered trademarks of Crytek GmbH in the U.S and/ or other countries. Electronic Arts, EA, and the EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
□エレクトロニック・アーツのホームページ http://www.japan.ea.com/ □「CRYSIS」のページ http://www.japan.ea.com/crysis/ □関連情報 【11月14日】EA、WIN「CRYSIS」北米と欧州で発売 完全日本語版の初回生産分には特典を同梱 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20071114/crysis.htm 【10月29日】EAとNVIDIA、WIN「CRYSIS」体験版を公開 英語版を提供。製品版では日本語化 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20071029/crysis.htm 【9月25日】西川善司の3Dゲームファンのための「東京ゲームショウ2007」 グラフィックス講座 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20070925/tgs3d.htm 【9月21日】マイクロソフトブースレポート「Games for Windows」編 「FS X: 栄光の翼」、「CRYSIS」、「World in Conflict」など、DirectX 10世代タイトルを複数出展 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20070921/tgs_gfw.htm 【8月1日】西川善司の3DゲームファンのためのE3ゲームグラフィックス講座 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20070801/3de3.htm 【7月15日】E3 Media and Business Summit現地レポート EAブースレポート http://game.watch.impress.co.jp/docs/20070715/eab.htm 【3月7日】西川善司の3Dゲームファンのためのグラフィックス講座 ~「CRYTEK CRYENGINE2.0」GDC 2007特別編~ 屋外の自然表現にこだわったリアル系グラフィックスマジックの秘密 http://game.watch.impress.co.jp/docs/20070307/cry2.htm (2007年11月30日) [Reported by 佐藤“KAF”耕司]
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||