
|
||||
|
CESA DEVELOPERS CONFERENCE 2006レポート
カプコン、「大神」プロデューサーとディレクターが語る制作秘話 |
||||||||||||||||||
 |
会場:昭和女子大学
CESA DEVELOPERS CONFERENCE 2006の2日目に、クローバースタジオ株式会社の代表取締役社長で、カプコンから発売された「大神」のプロデューサーを務める稲葉敦志氏と、ディレクターの神谷英樹氏が「プロデューサーvsディレクター ~大神の乱~」というテーマで開発秘話を語った。300人近く収容できる教室いっぱいに受講者が集まる盛況となった。
2人の話から、プロデューサー、ディレクターという仕事の具体的な姿、作品制作への想いが伝わってきた。制作の苦労に関しての部分は、受講者全体から「そうだよね」という共感も強く感じられ、時には受講者から爆笑も飛び出す非常にユニークな講演だった。
■ ディレクターとは、プロデューサーとは? 開発現場でのそれぞれの役割
 |
| クローバースタジオ株式会社の代表取締役社長で、「大神」のプロデューサーを務めた稲葉敦志氏 |
 |
| 「大神」のディレクターの神谷英樹氏。「バイオハザード2」、「デビル メイ クライ」、「ビューティフルジョー」など多くのヒット作を手がける |
講演は稲葉氏がいくつかのテーマを出し、それについて2人で語る、という形式になった。「プロデューサー、ディレクターって何?」、「作品性とメッセージ性」など、いくつかのテーマで見えてくるのは、作品のテイスト、にじみ出てくるものはディレクターが作り出すということ。メッセージとして思うものもあるが、それは作品で語られていく。メッセージやテーマ、テイストを「言葉」にし、どうセールスポイントにしていくかはプロデューサーの仕事だという。
神谷氏は「バイオハザード2」のディレクターを務めたが、ホラーが苦手で、ホラーゲームという視点からは初代「バイオハザード」が持っていたものにはかなわなかった、と語る。その後、神谷氏はPS2向けに「バイオハザード4」と名付けられたタイトルを制作していた。新しいハードで展開する作品として、ホラーではなく、かっこよさを追求した今までにはない方向性を持ったゲームを作っていった。その時、当時プロデューサーを務めていた三上真司氏から呼び出され「これ、もうバイオハザードじゃないだろ」と言われてしまうことに……。その作品は「デビル メイ クライ」として発売されることになった。
その後「ビューティフルジョー」などを手がけた神谷氏がプロデューサーの稲葉氏に提案したのが「大神」だった。その時に神谷氏はひたすら「癒し」というテーマを稲葉氏に言い続けた。神谷氏は長野で山に囲まれて育ち、東京や大阪で生活をしている内に、「大自然」への思いが強くなっていったという。このテーマは稲葉氏を驚かせた。神谷氏の熱意に稲葉氏は応えた。
しかし「ホラー」といったアピールしやすいテーマに比べ、「癒し」や「大自然」といった漠然としたイメージとテーマを、わかりやすくアピールするのには苦労させられたという。ディレクターはゲームの作品性を決定し、ゲームはディレクターの個性が前面に出たものになる。プロデューサーはその作品をどう市場にアピールするのか、どう「売る」のか。作品においてプロデューサーが自由にできる範囲は少ない、また、捏造して、ディレクターの作りたいものと違ったイメージで売ってはいけないと稲葉氏は語る。
また、「大神」が“アート”と海外のメディアに評価されたことも引っかかったという。神谷氏もアートという言葉には少しずれたものを感じた。「僕たちが作っているのは、エンターテイメントだから……」という神谷氏の言葉に、稲葉氏はすかさず「エンターテイメントというのも便利な言葉だよね」というツッコミを入れる。エンターテイメントとアートの違いは、「ユーザーへの視点」だと2人は意見を合わせていった。自分を見て作るものがアートで、ユーザーのことを見て、考えて作るのがエンターテイメントだという。この考えは、次に話されるスタッフ論へとつながっていく。
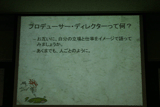 |
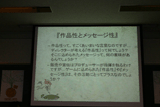 |
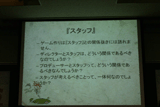 |
| 稲葉氏から提示されるテーマ。いくつかの問いから「大神」の現場風景が明らかになっていく | ||
■ スタッフとスケジュール。ゲーム制作で忘れてはいけないテーマとは
 |
| 夏休みが終わってからじゃないと宿題をやらなかったという神谷氏。「今も変わってないよね」と稲葉氏から厳しいツッコミが |
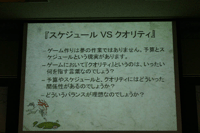 |
| ゲームという「作品」に求められる厳密なスケジュール。物作りと、期限の問題は普遍の、そして避けることのできないテーマだ |
神谷氏も「大変でしたねえ」としみじみと答える。スタッフもそれぞれクリエーターとして主張したいものを持っている。ディレクターが提示するテーマに対して、どう応えるか、時には子供のような反発をお互いがしてしまうこともある。ディレクターはそうしたスタッフを統括する“力強い”存在でなくてはいけない。
「大神」の制作を進行させる上で、神谷氏は「出したアイデアをつぶされてしまう」というスタッフからの声に悩まされた。スタッフが提案する“やりたいこと”を作品の方向性を考えて時には否定しなくてはいけないこともある。このときに大事なことが「ユーザーのために作っているか?」という問いである。プレーヤー、ユーザーにとって良いことなのか、そうでないのか、この価値観を忘れて主張ばかりをくり返してしまうのは、「無意味な反抗」になってしまう。「アートではなくエンターテイメントなんだ」という想いはゲーム作りでは忘れてはいけないことだ、と神谷氏は語る。
プロデューサーである稲葉氏は、「従順でも平均的な能力のスタッフと、暴れ馬だけど能力の高いスタッフ、究極的に選ぶのはどっちか?」という問いを神谷氏に投げかける。神谷氏は少し悩んでから「暴れ馬」のスタッフを選ぶと答えた。神谷氏は、もしディレクターの言うことをすべて忠実に聞いてくれるスタッフがいたとしても、それで面白いゲームを作ることは難しい、と答える。理想はディレクターが投げかけ、提示するものを何倍にして返してくるスタッフだ。
僕が出したアイデアをそのまま作ってくれたとしても、「良くできたね」で終わってしまうが、スタッフの独自の主張をディレクターが提示し、ユーザーのことを考えた上で発展させてくれれば「おお!」となる。ユーザーがゲームをプレイして感動するのと同じような体験ができる。神谷氏は今まで手がけた作品を振り返り、「デビル メイ クライ」ではそういう驚きが最も多かった、と語った。
次に稲葉氏が提示したテーマは「スケジュールと作品のクオリティ」。作品を完成させるためには“締め切り”という考え方が必要不可欠だ。ボリュームやクオリティ、やりたいこと、など、ゲームは作っていかないとわからないことが多いが、その前にある程度のスケジュールを決めておかなくてはならない。 スケジュール終盤になると「これをやってみよう」というディレクターの提案に「スケジュールが……」とスタッフが答えることがある。神谷氏は小さく「いいじゃねえかそんなの」とつぶやくこともあるという。稲葉氏はディレクターとしてはそれはある種健全なこと、だという。スタッフを増やしたい、1人増やすといくらかかるのか、時間進行はどうなるのか、それを管理し、スムーズに進行させることはプロデューサーの役目だ。
どこまで「締め付ける」か、クリエーター達の作品作りを許すか、時にはスタッフ全員をそろえて稲葉氏が「説教」をすることもある。神谷氏は「『大神』はどうしても桜の咲く頃にゲームを出したかった、初めて4月20日は死守しなくちゃいけないな、とスケジュールを意識しましたよ」と語った。
「ゲームは商品であり、そのお金で僕たちは次の作品を作ることができます。ゲームというのはディレクターとプロデューサーのそれぞれが持つ引力の、引き合う真ん中のところで成り立っているものだと思う」という神谷氏のメッセージに、稲葉氏は「僕が考える最高のディレクターはもはや人間かどうかすらもはやわからない“生き物”です。褒め言葉で、突っ走っている人。プロデューサーはそんな危険物を取り扱う人です。どちらも一皮剥くとまともじゃない部分が出てくる人達です。できれば直接話を聞いたりせずに、作品を通して接して欲しいですね」とかなりキツイ冗談の入ったコメントで講演を終えた。
少しスローな雰囲気の、受講者から爆笑も飛び出すユニークな講演だったが、2人の話から「ゲームを作るチーム、商品としてのこだわり」が強く伝わってきた。稲葉氏は時にはフォローし、時にはツッコミで神谷氏から言葉を引き出す。その関係は、プロデューサーとディレクターという仕事を象徴しているように筆者には思えた。すべての仕事に共通するような要素も、ゲームという特別な作品を作り出す環境ならではの話もあり、驚きと納得のある講演だった。
□CESAのホームページ
http://www.cesa.or.jp/
□「CEDEC 2006」のページ
http://cedec.cesa.or.jp/
□カプコンのホームページ
http://www.capcom.co.jp/
□クローバースタジオのホームページ
http://www.cloverstudio.co.jp/
□「大神」のページ
http://www.o-kami.jp/
□関連情報
【4月14日】カプコン、PS2「大神」完成発表会を開催
稲葉氏、神谷氏が難航続きの開発3年間を語る
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20060414/okami.htm
(2006年9月1日)
[Reported by 勝田哲也]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.