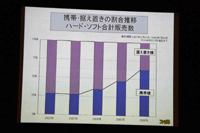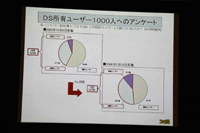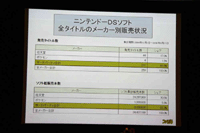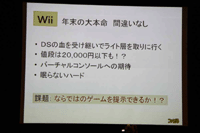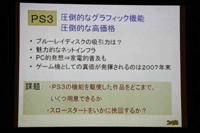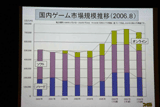|
||||
|
CESA DEVELOPERS CONFERENCE 2006レポート
エンターブレイン浜村氏、次世代のゲーム産業の展望を語る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
会場:昭和女子大学
CEDEC2日目の開幕は、エンターブレイン代表取締役社長の浜村弘一氏から、「ゲーム産業次世代への展望と、そこに求められる開発者の資質」と題した基調講演が行なわれた。浜村氏は、CEDECやAOGCなど国内のゲームカンファレンスの常連スピーカーとしてすっかりお馴染みの存在だが、ファミ通グループ代表としての顔より、ゲームジャーナリストとしての顔を前面に押し出し、早くからオンラインゲーム市場の潜在力の高さやオンラインゲーム市場を抜きにした市場規模の計測の不備をアピールしてきたことで知られる。
今回の基調講演では、ファミ通グループの各種統計データ、アンケートデータを駆使し、次世代機に対する予測、期待を中心に論を進めながら、次世代を担うクリエイターらに対し、オンラインというインフラを一種のプラットフォームとして定義づけ、ゲームプラットフォームの自由化、ビジネスモデルの自由化をアピール。そこに眠る大きなビジネスチャンスを掴む新しいコンテンツの到来を強く希望した。浜村氏らしいデータマイニングの手法をうまく活用した技ありの基調講演だった。
■ 2006年度上期はニンテンドーDSが市場を席巻、キーワードは「パーソナル」
続いて浜村氏は、2006年上期(3月27日~8月27日)のデータを紹介した。上期の時点で約280万本の売り上げを記録し、現在も売り上げを伸ばしつつある「New スーパーマリオブラザーズ」を筆頭にすでに3本ものミリオンセラーが誕生している。下期では「ポケットモンスター」の新作があり、年末には次世代機のリリースが予想されることから、2005年度を大幅に超える数字が出ることを予測した。
浜村氏によれば、ゲーム産業は上期は不作傾向で、基本的に下期偏重型であり、上期にこれだけヒット作が生まれるのは異例のことだという。この上期の売り上げを支えたのがニンテンドーDSだと浜村氏は説明する。リストを見れば一目瞭然だが、2005年の時点で上位10本中7本がDSタイトルで、2006年上期のデータでは実に9本と、ほぼ独占状態にある。ハードの売り上げも1,000万台を突破し、それに後押しされてミリオン達成に掛かる期間も短縮されつつある。さらに、新規ユーザーの購入率も徐々に向上しつつあり、ゲーム業界にとって理想の展開になりつつあることを報告した。
懸念材料として、発売タイトル数のシェアではわずか20%弱の任天堂が、売り上げの約80%を占めていることを挙げた。これは6月に実施された任天堂の経営方針説明会でも同様の質問が出ている。代表取締役社長の岩田聡氏は「ゲームを作るのには時間がかかる。今年の年末までに出てくる“コッテリ型”のゲームの売れ行きを見てから判断して欲しい」と発言している。浜村氏はこの懸念材料については、8月24日に発売されたばかりのニンテンドーDS版「ファイナルファンタジー III」がひとつの判断材料になるという考え方を示した。
エンターブレインのデータによれば、同作はすでに初期出荷の消化率9割を超える50万以上の売り上げを記録しており、ミリオン入りは確実視されるという。つまり、サードパーティーは売れないという唯一のネガティブ要素もこれによって破られたというわけだ。
浜村氏は、DSが市場にもたらしたものとして、家庭用ゲーム機の脇役としての位置づけからの脱却、ライトユーザーまで広がったゲームファン、低予算によるゲーム開発などを挙げ、キーワードは「パーソナル」だとした。ニンテンドーDSでは最初に自分の名前を入力し、ワイヤレスネットワーク機能を使って、簡単に他のユーザーと繋がることができる。
この結果、母と子、カップルといったライト層にまで広がり、ユーザーがユーザーを呼ぶ連鎖が起きているという見方を示し、今後については「2,000万台、3,000万台も不可能ではない」と強気の予測を示した。プレイステーション 2が2,000万台弱であり、仮に2,000万台を達成すれば、家庭用ゲーム機市場における大きなパラダイムシフトになる。今後両ハードがどのように推移していくのか注目されるところだ。
| 【2004年、2005年の国内市場規模比較】 | ||
|---|---|---|
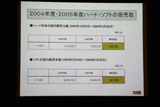 |
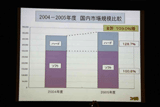 |
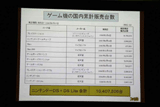 |
| 2005年度は、2004年度と比較してハード、ソフトとも純増。トータルとしては前年比9%成長ということになる右の図は、ゲーム機の累計販売台数を示したものだが、ニューフェイスのニンテンドーDSの勢いが凄い、DS Liteに至ってはわずか半年で400万台を売り上げている | ||
| 【ニンテンドーDSの躍進を示すデータ群】 | ||
|---|---|---|
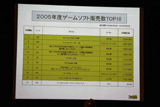 |
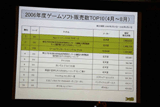 |
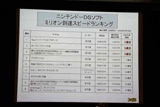 |
| 2005年度、2006年度とも、売り上げ上位はニンテンドーDSがほぼ独占状態にある。「Newスーパーマリオブラザーズ」はわずか2週で100万本を達成。9月にはゲームボーイブランドを代表するヒット作「ポケットモンスター」シリーズ最新作「ダイヤモンド/パール」がDSに登場。この勢いはまだまだ続きそうだ | ||
■ 年末商戦の大本命はWiiと予測、第4の次世代プラットフォームは“オンライン”
トップバッターとして任天堂のWiiを取り上げ、「年末の大本命 間違いなし」といきなり一点掛けの姿勢を明確にした。大本命とする理由として、DSと親和性が高く、またDSの設計哲学も受け継いでいること、20,000円以下と予想される価格的なアドバンテージなどを挙げた。販売台数の見込みは、5年で1,000万台と予測。これは現行機のニンテンドーゲームキューブが400万台弱ということを考えると、かなり高い数値だ。
プロモーションビデオの作り方にも言及し、「映像ではなく、遊んでいる人を映しており、ゲームのおもしろさが伝わりやすく、遊んでみたいと思わせてくれる」とコメント。その一方で、体験型のスポーツゲームについては「やってて疲れる、長時間はキツイかもしれない」、「ゼルダの伝説」については「ターゲットがポインタアクションなので、既存のゲームの文法が身についている人には多少の違和感がある」と一定の注釈を付けた。
その上で浜村氏は、Wiiは「ゲームが初のユーザーにとって楽しいかどうかに傾注したハード」と定義づけ、「既存のゲーム文法を捨てていいのだから、クリエイターにとっては大チャンス。“脳トレ”のような大ヒットの土壌がある」と、参加者に対して発破を掛けた。
対するSCEIのプレイステーション 3に対しては「圧倒的なグラフィックス性能、圧倒的な高価格」と評価し、再三価格の高さを引き合いに出し、初期50万台はすぐ捌けるものの、その後は伸び悩むスロースタートの展開を予測。売り上げ見込みは、5年で1,000万台と、Wiiと同じ数字を挙げた。これはPS2の約半分の数字であり、かなり厳しい評価だ。
標準搭載されるブルーレイディスクについては「プレイステーション 2のDVDのような起爆剤にはならない。むしろPS3がブルーレイを後押しする」と冷静な見方を示し、ネットワークサービスをはじめプラットフォームとしてオープンな姿勢や、HDDをデタッチャブルにするというPC的、家電的な展開に期待を押せた。
肝心のゲームについては、ゲーム機としての真価が発揮されるのは「『ファイナルファンタジー XIII』や『メタルギアソリッド4』といった大型タイトルが登場してくる2007年末頃になる」とし、「その間に値下げもあるだろうし、39,800円ぐらいになれば」とあくまで値下げがメインストリームのプラットフォームになるため必須条件という姿勢を崩さなかった。
ゲーム機として「39,800円、大作待ち」という見方はある意味妥当だが、PS3の能力はゲームだけにとどまらない。浜村氏自身が指摘したように、PC業界や家電業界も巻き込んだ次世代のネットワークコンソールであり、一ゲームメディアだけの視点では「予測不可能」というのが正直なところではないだろうか。
Xbox 360については、「Windows Vistaとの連携により大敗はなくなった」と微妙な評価を下した。Windows Vistaとの連携により、リビング(Xbox 360)と書斎(Windows PC)の両方を狙い、またロイヤリティビジネスから、Xbox Live!を使ったディストリビューションビジネスへと戦場を移しつつあるという観測を示した。課題としては、市場獲得のムラをどうするのか。そのまま日本市場で当てはまる課題である。
さらに浜村氏は、4つめの次世代プラットフォームとして「オンライン」を取り上げた。ネットワーク環境が整っているPCをベースとし、ビジネススキームから完全に1からゲームビジネスを構築できる自由度の高さなどを挙げ、「ハードウェアプラットフォームに縛られる時代は終わった」とした。
具体例として、プラネット高橋兄弟が取り組んでいる「Gプラネット構想」を取り上げ、ビジュアルロビーにぶら下がるコンテンツに、「聞いた話では大物クリエイターが関わっている」と、未発表情報を公開。来るべきソフトウェアプラットフォーム時代に期待感を込めた。
最後に浜村氏は「皆さんに謝らなければならない」と発言して、日本国内ゲーム市場の推移予測の2006年度以降の上方修正データを公開した。ハード、ソフトに関してはDSの誤算分が修正されている印象だが、オンラインも数百億が上積みされている。昨年のCEDECでデータを公開した際には、「見込みが甘い」と叩かれたそうだが、その予測以上に市場が伸びたという。
修正後の2006年度の予測はなんと7,000億超。2005年度の約5,800億円から実に1,200億円ほど増えることになる。次世代機が出揃う今年の年末商戦については、「実は供給が安定してきたDS Liteが一番売れるのではないかという話もある」と表現をぼかしたが、次世代機が売れなければこの見込みは大きく外れることになる。ともあれ、今年の年末はゲーム業界にとっては大きな節目となりそうである。
| 【オンラインゲームに対する期待】 | ||
|---|---|---|
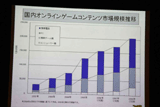 |
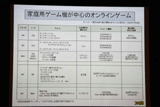 |
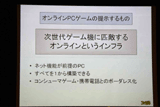 |
| 2004年のアジアオンラインゲームカンファレンスで基調講演を担当した浜村氏は、引き続きオンラインゲーム市場に高い興味を持ち続けている。代表的なタイトルのデータに関しては、統一性がなく曖昧だったが、ビジネススキームを1から自由に組み立てられることをメリットとして着目したのはおもしろい。確かにクリエイターとしては魅力的な要素だろう | ||
| 【クリエイターへのアンケート】 | ||
|---|---|---|
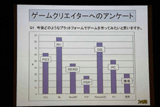 |
 |
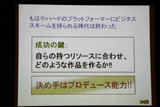 |
| 最後に紹介されたクリエイターアンケートでは、作ってみたいプラットフォームでWiiがトップ、次点でDS、3位がPS3という結果になっている。PCがXbox 360を抜いて4位に浮上しているのもおもしろい | ||
□CESAのホームページ
http://www.cesa.or.jp/
□「CEDEC 2006」の公式ページ
http://cedec.cesa.or.jp/
□関連情報
【2006年8月30日】CESA、「CESA DEVELOPERS CONFERENCE 2006」を開催
過去最多の1,700人強が参加する国内最大のゲームカンファレンス
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20060830/cedec_01.htm
【2005年8月29日】CESA、「CESA DEVELOPERS CONFERENCE 2005」を開催
“次世代”を見据えた意欲的なセッションが目白押し
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20050829/cedec_01.htm
(2006年8月31日)
[Reported by 中村聖司]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.