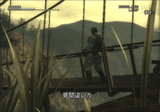| ||||
|
★PS2ゲームレビュー★
シリーズ累計1,460万本を売り上げる人気諜報アクションゲーム「メタルギア ソリッド」シリーズ。その完結編となるタイトルが「METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER(以下、「MGS3」)」だ。今回の作品のメインテーマは“サバイバル”。サバイバル感覚を際立たせるシステムとして、動植物を捕食して食糧とする「FOOD CAPTURE」、重症部位を自ら治療する「CURE」などを導入。「生命活動を維持することの困難さ」を作品世界に盛り込むことで、主人公“スネーク”とプレーヤーとの距離感が一層近づいた作品といえる。
その生命感が一番よく理解できるのがジャングルだろう。たとえば、ジャングルに生い茂る草を踏みつけた足が地面から離れた時、草がゆっくりと元の形に戻っていくというシーンだ。自然界では当然の光景がゲームの中に形成されているというだけで、筆者の心情には日常では決して抱かない感情がこみ上げてきてしまった。この「MGS3」の映像美は、すべてのプレーヤーに体験してほしいと素直に感じた。
■ こんなにも人は面白い動きができるのか……。愛すべき「MGS3」の登場人物たち 「メタルギア ソリッド」シリーズで定評のあるストーリーテリングの巧みさは「MGS3」でも変わらない。冷戦という時代背景の中、軍事任務という流れに絡められた様々な人間関係が交錯する壮大なスケールの人間ドラマ。このストーリーは、病的なまでに上手くまとまっていると思う。シナリオの展開パートと、アクションゲームパートの配分も絶妙で、筆者もつい「もう少しだけ先を……」と止めどころを見失い、SAVEを10時間くらい忘れて夢中になってしまった。
物語の演出に重要な役割を果たしているのが、ゲームの随所で惜しげもなく投入されるリアルタイム描画によるポリゴンデモシーン。リアルタイムデモは、ゲーム中で使用されている背景やキャラクタデータやカメラを元に、リアルタイムにポリゴンデモを作成するというもの。今作は、人物の動きにさらに磨きがかかり、一流俳優の舞台を見ているかのような、それでいて実写では出しにくい計算され尽くしたアクションでポリゴンデモは進行していく。 主人公の“スネーク”は任務に忠実な骨太な兵士である。無線による会話デモからもわかるが、今回の主人公は本当によく喋る。その中のジョークや、任務を完遂しようとする強い覚悟の台詞から、“スネーク”の人物像がプレーヤーにしっかりと伝わってくる。感情移入するために充分な、愛すべき主人公だ。特に筆者が好きなシーンが、ボス戦の後のポリゴンデモ。排除した敵に対し、数秒の余韻を持たせているところだ。生命の終焉という空虚感に触れ、一瞬兵士であることを忘れ呆然とする"スネーク"。だが、すぐに戦士としての本能が主人公を任務に引き戻す……。筆者の私見だが、そんな“スネーク”の情感が見事に表現されているシーンだと思う。 “スネーク”の敵対勢力に属する登場人物も、スネークに匹敵する強烈な個性を放っている。特撮作品で言えば敵組織の悪の幹部、ゲームで言えば中・大ボスに相当する強敵たちで、それぞれが個性的な独創的な攻撃方法でプレーヤーを苦しめる。ボス戦は基本的に1対1のバトル。戦闘前にはポリゴンデモが入り、対決のボルテージをグッと高める。このボス戦の味付けは「MGS3」でも健在だ。くせもの揃いのボス戦がしっかりと描かれているがゆえに、「メタルギア ソリッド」シリーズをプレイしている人も多いのではないだろうか。そんなファンは、今回「MGS3」に大いに期待してほしい。その期待は裏切られることはない。
「MGS1」のFOXHOUND、「MGS2」のデッドセルを超える特殊部隊「コブラ部隊」。スズメ蜂を武器に使う兵士、火炎放射兵士など、その攻撃手段は多彩。コブラ部隊の中でも……というか歴代メタルギアシリーズキャラクタの中でも一、二を争うであろう反則的にブッ飛んだ兵士が「ザ・ソロー」。詳しく書くことはできないが、その初見のインパクトたるや蕎麦屋で蕎麦を注文したら、最高級のステーキを出されたような感覚であった。ぜひ、すこしでも多くの方に「ザ・ソロー」戦を体験してもらいたいものだ。 ■ カムフラージュが影響を及ぼすスニーキングミッション 戦闘の舞台が人工建造物からジャングルへと変わった今作でも、シリーズ特有の「敵に見つからずに潜入する」という大前提は変わらない。敵兵士はスネークを察知すると、頭の上に「!」マークを表示し攻撃を仕掛けてくる。無線で増援を呼ばれてしまうと、とうてい主人公に勝ち目はない。そこで敵から身を隠しつつ進む「スニーキング」を行なう必要がある。 既存シリーズでは「物陰に隠れて、敵をやり過ごす」くらいしかやりようのなかったスニーキングだが、今回は「CAMOUFLAGE」という新たな偽装システムが付加された。サバイバルビュアーを開き、「CAMOUFLAGE」を選ぶとフェイスペイントとユニフォームのパターンが表示される。場面に効果的なフェイスペイントとユニフォームをチョイスすることで、カムフラージュ率がアップし敵の目を欺きやすくなるという仕組みだ。たとえば、暗夜の場面なら、フェイスをblack、ユニフォームもblackというコスチュームにすればよい。
こうしてカムフラージュ率を高めれば、敵の足元近くまで接近しても気付かれない場合がある(ジャングルで確認)。ジャングルというシチュエーションがあってこそだと思うが、スニーキングの緊迫感はCAMOUFLAGEによってさらに昇華されたといえる。反面、この数値に頼りすぎて「おい、なんでカムフラ率80%なのに敵に見つかっとんねん」とドジを踏むシーンもちらほら。それが悔しい。その悔しさをバネに次はもっとうまく隠れてやる、と完璧なかくれんぼに挑戦していく……。その繰り返しで発見されることが減っていくうちに、それが言いようもない快感になってくるから不思議だ。
正直な話、簡易MAPにもなっていたソリトン・レーダーが無くなったのは少々残念。進行ルートを確認するために、読み込みの入るサバイバルビュアーからMAPを選択しなければならないからだ。とはいえ、後述のFOOD CAPTUREなどにはアクティブソナーを、暗闇には暗視ゴーグルをと様々なアイテムを使いわけることで、よりリアルな単独潜入のシチュエーションを楽しめるようになったともいえる。 ■ 近接戦闘術CQCが取り入れられた戦闘シーン
ハンドガンから対空ロケット砲まで、幅広い射撃兵器が用意されているのも「MGS3」の魅力。スニーキングで安全位置を確保し、主観カメラの状態で敵を捕捉、狙撃が成功したときの快感は今作でも健在だ。AK-47などの突撃銃では弾の連続発射が可能なフルオート機能がある。ジャングルの中をフルオートで掃射すれば、気分はまさに映画「ランボー」の世界。通常のステルスミッションでは味わえない。爽快感を堪能することができるだろう。
今作は近接の戦闘にCQC(クロース・クォーターズ・コンバット)というシステムが採用されている。これは接近戦に特化した格闘システムで、前作にも存在した投げや首締めなどの発展形と言っていいだろう。発動はパンチ/キックと同じ○ボタンを使用。CQCを狙うには、ボタン長押しなのでパンチが暴発することはないと思うが。筆者としては、前作のようにパンチが○ボタン、投げが□ボタンと独立していたほうがやりやすかったと感じる。もちろん、CQC方式はレスポンスが悪いわけでも操作が複雑でもないので、小一時間ほどあればマスターできた。ようは慣れの問題だろうか……。 ■ 潜入任務を有利にさせるシステム「FOOD CAPTURE」と「CURE」 筆者の私見になるが、生きるために最良の安定した状態を保つこと、それが今作においてのサバイバルの意味ではないかと考える。この「MGS3」独特のサバイバル感覚が理解できる新システム、「FOOD CAPTURE」と「CURE」について説明したい。 今作では、LIFEゲージの下にスタミナゲージが付加された。このスタミナゲージはいわばスネークの空腹度のようなもので、時間経過で減少していく。スタミナゲージの残量が僅かになると、LIFEの自動回復速度の低下、主観視点時の視界のぶれ、など様々な活動障害を招いてしまう。このスタミナゲージを回復するための手段が「FOOD CAPTURE」だ。これはジャングルや室内に潜む動植物を攻撃し、食料アイテムとして入手するシステム。スタミナゲージの減少がLIFEゲージの減少につながるわけではないので、スタミナゲージがゼロの状態でもプレイは可能だ。
だが、“スネーク”という人間臭いキャラクタに感情移入していると、この「FOOD CAPTURE」に対する重要度がグッと深まってくるはず。中盤のステージで、ジャングルのように動物も少ない室内があった。FOODも底を尽き、スタミナゲージは果てしなくゼロに近い。そんな状態で目の前を一匹のネズミが通った時、筆者は心底「このネズミ、美味そう」と感じた。「FOOD CAPTURE」は人間の持つ生理的要求に直結したシステムなのだ。
捕獲した動植物は、サバイバルビュアーの「FOOD」で食べることができる。食料を食べるごとにスネークが「不味すぎる!」、「もっと食わせろ!」などのボイスで味の評価をする。この大真面目なスネークのリアクションを見たいがために、様々な食材をそろえてしまう自分がモニターの前にいた。中には食べるとコンディションを崩す食料もあるのだが、後述の「CURE」システムで治癒することが可能。
特に面白かったのは洞窟での「FOOD CAPTURE」だった。洞窟内でサーマルゴーグルを装着したところ、パッと地面に無数の明かりが点灯した。カニだった。カニの群れの中にグレネードを放り込むと、一瞬の閃光の後辺りは無害なフードアイテムの山。「これだけあれば、しばらく持つ」とその時は安堵したものだ。数時間後、カニは見事に腐敗し、そのカニを食べたスネークは「腐ってた……(CV.大塚明夫)」と悶絶することになるのだが……。筆者が幼いころ、海でヤドカリをバケツ一杯捕まえてきたら、次の日9割が死滅していたというトラウマが蘇る一瞬であった。 ■ 重症の骨折までも一瞬で治療可能~CURE~ 前作にも存在した、出血や風邪などの主人公の状態異常。今作の主人公はさらに怪我をしやすくなっていて、ダメージを受けた部位に銃弾なら銃創、矢による攻撃なら矢創など様々なタイプの怪我を負ってしまう。怪我状態では、LIFEゲージに赤いゾーンの一部が赤くなり、LIFEの最大値が減少してしまう。それら怪我や病気などを、現地でオペするというシステムが「CURE」だ(怪我を放置しておいても時間はかかるが完治はする)。プレーヤキャラのダメージと回復手段をここまで拡大させ、ひとつのシステムとして確立した面白い試みだ。
サバイバルビュアーからCURE画面に入ると、主人公のレントゲン図のような画面になり、怪我をしている部分が表示される。怪我の箇所の状態のテキストを読解し、薬物治療と外科治療を行なう必要がある。銃創などの外科治療には、サバイバルナイフ、葉巻、軟膏、消毒薬、止血剤、固定具、包帯、縫合セット。風邪などの薬物治療には、血清、胃腸薬、解毒剤、風邪薬を処方する。
こうして書くとCUREの実行は複雑そうだが、怪我の状態に従ってアイテムをポンポンと使用するだけで回復率が上昇。100%になれば全快するというお手軽なシステム。複数の怪我を負っても、慣れれば1分もしないうちに全ての傷を全快できるだろう。アイテムを使用する順番は治療効果に関係がなく、包帯を巻いた後に弾丸をナイフで摘出する、という明らかに間違った順でも効果は変わらない。これには少々の違和感を感じたが、それはプレーヤーへの親切設計ということで納得できた。
じつは別段CUREを使わなくても、スタミナゲージを回復させた状態で放置させておくか、セーブして数時間後に再スタートすることで重症箇所は自然回復できてしまう。これもまた「FOOD CAPTURE」と同じく使用しなくてもよいシステムなのだ。だが、この自然回復というのがやっかいで、話の先に進ませたいという欲求と回復の板ばさみになるのだ。時間の取れないプレーヤーは有効活用すべきシステムだろう。 ■ 「サルゲッチュ」のピポサルが登場するモード「猿蛇合戦」
一通りこのモードを遊んで思うことは……というか、冷静に文章を書いている場合ではなく、今すぐちゃぶ台をひっくり返して「おかしいだろ!」と叫びたくなるほど、この「猿蛇合戦」は奇天烈だ。このモードを遊んで思うこと、それは「このコラボレーション、よく実現して形になったな」……ということ。両タイトルの開発スタッフ全員が一時的に脳が溶ける奇病にでも冒されていたのだろうか……。最高です。 最高傑作のうたい文句は伊達ではなく、射撃、潜入、ドラマ性、その他「メタルギア ソリッド」シリーズ原点の醍醐味が、純度の高い状態で「MGS3」の中に詰まっている。 「メタルギア ソリッド」のファンは安心してほしい、「MGS3」は万雷の拍手を持ってエンディングを迎えることのできる内容に仕上がっているからだ。もちろん、既存のシリーズを一度も遊んだことのないプレーヤーでも、けっして過去シリーズの呪縛に捕らわれずに「MGS3」を楽しむことができるだろう。それほど、何度もやられて達成感を得るというアクションゲームとしての純度も高いのだ。 ただしくれぐれも初心者の方は、「MGS3」の意外性と裏切りに満ちた(ドッキリ、とでも言うべきか……)世界観に注意してほしい。その辺りの演出もすさまじくシリーズ最高傑作設定になっているため、くれぐれもコントローラーを壁に叩き付けないで落ち着いて遊んでいただきたい。
惜しむらくは、「メタルギア ソリッド」シリーズが今作で完結編ということだけであろう。願わくば、「METAL GEAR SOLID 2:SONS OF LIBERTY」に追加要素を加えて発売された「METAL GEAR SOLID 2:SUBSTANCE」のように、「MGS3」のバージョンアップ版がリリースされてほしいものである。
□コナミのホームページ (2004年12月16日) [Reported by 福田柵太郎]
また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp Copyright (c)2004 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|