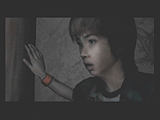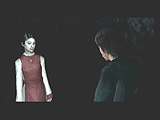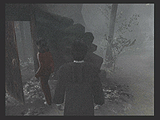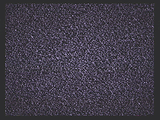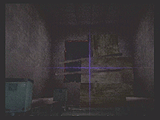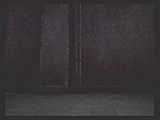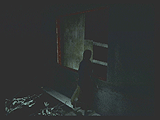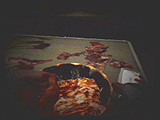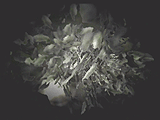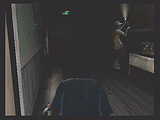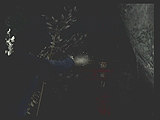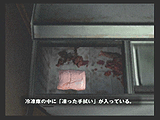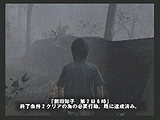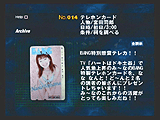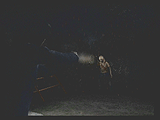| ||||
|
★PS2ゲームレビュー★
あまりにもこわいTVCMのため、放映中止。逆にそれが話題になって高い人気を誇った「SIREN(サイレン)」(以下、「サイレン」)。これまでにもホラーゲームを手がけてきた外山圭一郎氏がディレクタを務めるこの作品は、どのような恐怖を我々に見せてくれるのだろうか。 ■絶望的な状況を描く群像劇 ゲームの舞台は、山の中の小さな農村である羽生蛇村(はにゅうだむら)。ある日の深夜、この村にサイレンが鳴り響き、地震と共に災厄が降りかかる。……どんな災厄だったかは、当事者達にはわからない。ゲームではこの“当事者”達の、必死の生き残り劇を描く。 彼らは、何が起きたか正確には把握できない。わかっていることは、村の様子が一変し、どこもかしこも非常に古く、朽ちた様子になっていることと。水という水がすべてが赤くなっていること。そして、なにより彼らを狙う“屍人”がいる、ということである。 屍人……この名称すら、知らないまま逃げまどっている人間も多い。“生きている”人間を追う存在である。生前の姿を思わせる野良着に、絶対に生きているとは思えない肌の色。知性を感じさせないのろのろした、反復を繰り返す動作と、人間を見つけたときの、動物を思わせる素早さ。人間を冒涜するような恐ろしい雄叫び。 そして何より、屍人達の目から、口から流れる赤い水を見ることで生存者達は悟るのだ。屍人達は、この、雨となって止めどなく落ち、川に満ちている「赤い水」を飲んで、変わり果てた姿になってしまったことを。山奥の村だったはずのこの村が、いまや赤い“海”に覆われていて、屍人達がそこから「帰って」来たことを。 屍人達は、死ぬことはない。棒で叩きのめし、時には拳銃で撃っても、地面にうずくまり、動かなくなるだけ。目を離し、しばらくしてからそこを訪れると、平然と立っている。彼らは決して“生きて”いない、しかし死ぬこともまたないのだ。赤い水が彼らに不死の力を与えている。生存者はそれに気がつく。その証拠に……さっき屍人達に傷つけられた、ぞっとするほど大きな傷が、もう痛まない、何の苦もなく動くことができる。時間はあまりないのかもしれない。彼ら屍人達の列に自分たちが加わるまでの時間は、そう長くないのかもしれない。
彼らのストーリーは非常に断片的なピースとなっていて、プレーヤーはゲームを進めることで様々な人々を操作し、生き延びさせていかねばならない。しかし、ゲームが進むごとに彼らを取り巻く状況は、さらに絶望的になっていく。 ゲームではおおむねの時間軸にはそっているが、微妙に時間が前後したりして、最初はややこしい印象を受ける。しかし、進めていくことで、その無意味に思えたエピソードがかっちりとはまり、大きなうねりになっていく。さまざまな状況で行動を変化させていく登場人物達の行く末も非常に興味が惹かれる。彼らの運命の終端が見たい、というのはこのゲームを進めていく大きな原動力となるだろう。 また、「ゲーム的」なキャラクタの演出も見事だ。このゲームでは「足手まとい」的な役割のキャラクタも多数いて、彼らを連れて屍人のうようよいるフィールドをかけなくてはならない。この時の各キャラクタの演技が非常にいい。謎の美少女、神代美耶子は、不安な気持ちを無理に虚勢を張ってごまかしているところがとてもかわいい。高遠玲子の教え子の小学生・四方田春海は、屍人が近づくとパニックを起こしてうずくまってしまう。 そして……安野依子は、はっきり言って本気でウザかった。「せんせぇ~、何なんですか一体、私たちどうなっちゃうんですかぁ? 助けくるんですか? せんせぇ~」。ああああああ! しらねーよ、こっちが聞きたいよ、つーかもう黙れ! と、本気で殺意がわいてしまう見事な足手まといぶり。被保護者の立場に甘んじて、何もしようとしないばかりか、勝手にパニック起こして逃げて屍人の目の前に飛び出すわ、もうすごいのである。ホラーものでは定番の性格を持ったキャラクタではあるが、この描写はかなり秀逸。キャラクタ性をうまく表現している。 ■相手の視界を“幻視”し、危機を脱する
本作の特徴をなすのが「視界ジャックシステム」である。L2ボタンを押すと、テレビを思わせるホワイトノイズの画面に変わり、スティックを倒すことで色々な映像が現れる。この映像は、屍人もしくは同行者の“視界”である。プレーヤーはこれを使い、さまざまな危機を脱していかねばならない。 よそ見をしているときに後ろを通り抜けたり、敵の針路を読んで、その場所を迂回したりと、プレーヤーキャラクタが見ている光景と見比べながら、あるいは記憶をたどって考え、実行する。ユニークなアイデアをうまくゲーム性に融合させていて、慣れてくるとさらに使い勝手が良くなってくる。 ゲーム性に密着したシステムであり、クリアのためにも必要不可欠なものになっている。あるシナリオでは屍人の隠すものを突き止めたり、またあるシナリオでは屍人の位置をそのジャックで知ることになる。また、行方不明になってしまった同行者の位置を知ることもできるのだ。 視界をジャックしたときのキャラクタ性の描写もまた本作のウリのひとつ。屍人のおぞましい息づかいや、無意味に発せられる声は、のぞき込んでいる自分の正気が侵されていくような感触があって、長時間見ているのは結構苦痛だ。さらに一部のキャラクタは扉をハンマーで叩き続けていたり、無意味な行動をしている感じがより「モンスター」であることを強調している。 警官の屍人はさらに醜悪。どんぶりに盛った赤黒い“何か”を、ずるずるべちゃべちゃと、ずっと食べているのだ。この警官には、物音に反応して違う方向に行くことを確認しなければいけないため、プレーヤーはどうしても見ていなくてはならない。制作者のちょっと意地悪な意志も感じてしまう演出である。 ゲームが進むにつれて、蜘蛛屍人や、犬屍人、さらには羽根屍人といった、さらに人間を冒涜した存在も登場してくる。彼らの視界もまた独特だ。さらにリーダー的な頭脳屍人は、生前を思わせる「声」ももっていて、そのセリフはやはり恐ろしく無意味。甲高い、綺麗な声だったことを思わせる女の人の、調子の外れた狂った忍び笑い。こういった、彼らの運命の残酷さを強調する演出にも力が入っている。 プレーヤーキャラクタはなぜこんな視界ジャックという特殊能力を使えるのか? という疑問には、残酷な種明かしがある。この相手の視界を共有する能力は、屍人たちのコミュニケーション手段なのである。赤い水を体内に取り込んだ者達の、能力なのだ。この事実と、さらに長い時間屍人とも感覚共有をしていかなくてはいけない感触は、キャラクタのみならず、プレーヤーの心さえも赤くて暗い世界に引きずり込んでいきそうな嫌悪感をもたらしていく。
■さまざまな行動が他のキャラクタに影響していく
ゲームの進行は、短いシナリオの連続で構成されている。各シナリオにはクリア条件が提示されており、プレーヤーはそれに会わせてキャラクタを操作していくこととなる。敵は不死であり、プレーヤーキャラクタは一般人のため非力、さらに前述のように連れて歩くキャラクタがいる場合があるので、例え短いシナリオでもクリアをするのは容易ではない。 クリア条件は、そのマップからの脱出以外にも、他のキャラクタに関連するアイテムを見つけたりするものもある。ストーリーを進めていくことで、プレーヤーは俯瞰的に物語を見ることになり、各キャラクタが関係を持っていくことがわかってくる。 シナリオの中には、一見無意味な行動をする「キー」が隠されている。ダストシュートの扉を開けたり、線路を切り替えたり、そのシナリオには何の影響もないが、他のキャラクタによるシナリオで重要な意味を持つ行動だ。意図をしない協力プレイのようで、つながった瞬間は面白い。 各シナリオの関係は、タイムテーブルの画面で確認できる。ゲーム中盤に解放されるシナリオセレクト機能を使うことで、この条件を解放して、次シナリオを出現させ、さらに時間とストーリーが進んでいくという構成だ。 非常にユニークかつ、面白い構成だが、これが「プレイしやすい」のかは、実は少し疑問が残る。あくまで筆者の感想だがこのゲームは非常に難しく、そのシナリオを最低2回はプレイしなくてはならないというのは、どうなのだろうか。斬新で効果的な演出であり、この構成だからこそ出てくる感触は確かにある。しかし、それをデフォルトで「強要」するのは、到達するプレーヤーをさらに少なくしてしまっているとも思えるのだ。 他にも、ゲームの中には「アーカイブ」という情報がちりばめられていて、落ちているノートや、壁の張り紙などをキャラクタが見ることで追加されていく。ゲームの中の秘密を探る重要なものから、お遊び的なモノまでさまざまだが、どれも世界観を補強する、非常にこだわりを感じさせる情報である。この世界にハマったプレーヤーならコンプリートせずにはいられない、収集癖を刺激する仕掛けだ。
■きつすぎるゲームバランス 最後に、このゲームのゲームバランスにふれておきたい。日本では失敗を繰り返すことでイージーモードが追加されるゲームが増え、「クリアは必然」と、なっている作品も多くなってきた。そんななかで、この作品は非常に硬派な難易度を持っていて、そういった意味ではほかのゲームとは一線を画している。 プレーヤーキャラクタが弱い、敵は不死の存在である、絶望的な状況を描きたい……。こういった意図の元、非常に厳しいゲームバランスを持たせたのは、わざとであることは明らかだ。シナリオも意図的に短く切ることで、リトライを繰り返し、何度もキャラクタの死を越えることで進んでいく。このゲームではストーリーの全貌を明らかにできるのは、限られた者であることの証であり、クリアが「報酬」であるゲームバランスは海外のゲームを思わせる。 難易度は制作者の意図したものであることは確かだ。しかし、ゲームをプレイしたときの失敗したときの苛立ち、この作品ではその気持ちが「制作者」に向かってしまいがちな場合が多いのではないだろうか。プレーヤーキャラクタの影に隠れて、屍人との距離がわからないのは? ちょっと微妙な当たり判定は?……重箱の隅的な指摘であるが、プレイを円滑に進むことができなかったプレーヤーは常に自己弁護を計る。本作はプログラム的にも高いレベルと、リアリティーを感じさせる。だからこそ、「できないこと」に、強い不満を感じてしまうのだ。 なによりも、およそ5人に1人の割合で屍人が「銃」を持っているのは、舞台が「日本」であることを考えるとおかしいのではないだろうか。この“銃”がゲームの難易度を跳ね上げているのだ。筆者には、これだけ世界にこだわり、クセは強いが明らかに強い魅力を持つこの作品を生みだしたスタッフが、「隙」を作ってしまったのが信じられない。この設定は、これだけリアルにこだわった世界観の中で「ゲーム」であることを強調してしまっている。 プレーヤーはこの敵が持ってる銃を奪うこともできない。さらに、これらの屍人はまるで捕虜収容所を守る見張りのように、常に臨戦状態で周りを監視してるのである。“志村晃”のシナリオでは、開始1分で射殺されたりする。「ミシシッピー殺人事件」を思い出す人は少ないとは思うが、あれと同じ“制作者の意図した無茶な駆け引き”を現代で体験させるのは、どうなのだろうか? このゲームはその世界観と物語にこだわり、現在の技術ではじめて実現する「恐怖」を表現した非常に優れた「ホラーゲーム」である。もちろん扱っている題材から、プレーヤーを選ぶ作品ではあると思う。しかし、それが理不尽に感じてしまうような難易度でさらに物語を体験できるプレーヤーを狭めていることは、筆者には残念に感じる。 ただし、ゲームとしてはアクションが苦手なユーザーに対してのフォローはできないが、ゲームマスコミやインターネットが積極的にフォローをしてくれている。という点も言及しておこう。提示された情報を頼りに、何度も失敗を繰り返しながら、ゲームを進めていくことは充分可能だ。さまざまな情報はこのゲームが持っている難易度をずいぶん下げてくれる。ゲームを解くことに「努力」できる要素は数多く残されているのである。 なにより、暗闇を怯えながら歩くこの感触は、闇がまだ恐怖の対象であった子供の頃の恐怖をまざまざと思い出させてくれる。この感覚の表現を、本作は他の追随を許さないレベルで再現してくれている。「怖がりたい」プレーヤーは覚悟を決めて挑んでいただきたい。
(C)Sony Computer Entertainment Inc.
□プレイステーションのホームページ (2003年12月5日) [Reported by 勝田哲也]
また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|