
|
||||
|
CEDEC 2008 現地レポートニッチなゲーム作りから、誰でも遊べるカジュアルゲームへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
会場:昭和女子大学
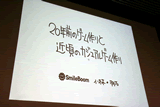 |
| 講演は手書きのスライドで進められた。普段から企画書なども手書きで作ることが多いという |
スマイルブームは札幌のゲーム会社で、今年1月に設立したばかり。エンドユーザーで名前を知っている人はほとんどいないと思われるが、先日「Gamefest Japan 2008」の中で発表された「アクションゲームツクール」の開発を担当している企業である。また小林氏は、PC-8801やX1があった時代からのベテランプログラマで、羽石氏もプランナーとして9年の実績がある。
小林氏と羽石氏は過去、ニッチ市場のゲームファンに向けた、いわゆる「一般受けしないタイトル」を意識的に制作してきた。しかし最近になって、DSでカジュアルなゲームを作ることになり、老若男女を問わず遊べるゲームを制作することになった。このセッションでは、小林氏と羽石氏が以前制作したタイトルがどんなものだったか紹介した後、大きく方向転換したDSタイトルにおける開発の裏話と、そこで学んだカジュアルゲームにおける開発のポイントが語られた。
■ 「変わったこと」を狙い続けた過去のゲーム作り
 |
| スマイルブーム代表取締役の小林貴樹氏。20年以上の経験を持つベテランプログラマで、独創的なタイトルを作ることでも知られている |
このゲームは、ゲーム内に時間の概念があり、時間経過で空腹になって体力の自動回復がなくなったり、夜には店が閉まったりする。また右手と左手という概念があり、右手に持ったものは武器に、左手に持ったものは道具として扱われる。右手にパンを持つと投げてしまったり、左手に武器を持つと道具として何かの効果が発揮されたりもする。
もう1つ特徴的なのが、記憶システム。NPCとの会話の一部を記憶するというものだが、どれを記憶するかはプレーヤーが決められない。時にはどうでもいい記憶で限界まで埋められてしまい、消すには遠くにある教会で懺悔しなければならない。この要素の発案は小林氏。「会社の横にある空き地があって、その間にある塀を逆立ちして乗り越えようとしたが失敗して落ち、突発性健忘症になってその日の記憶がなくなった」という経験から、記憶システムのアイデアができたという。
「何か失敗したらゲームに取り入れれば面白いかもしれない」と小林氏は笑っていたが、当時はゲームの概念も曖昧で、制作における常識というものもなく、自身の体験をゲームに生かしていくのがポイントだったという。
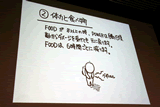 |
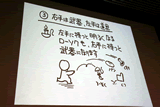 |
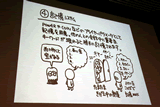 |
| 時間経過がゲームに影響したり、右手・左手の概念を持たせたり、記憶システムを盛り込んだりと、当時としてはユニークな要素を多数詰め込んだゲーム | ||
 |
| スマイルブーム取締役の羽石理奈氏。経済学部の学生の頃、「就職説明会でたまたま近くにあった会社に入ったらゲームを開発していた」という面白い経歴の持ち主 |
このゲームは、双六にミニゲームを入れることで、待ち時間をなくすというのがコンセプト。ある人が双六をやっている間、他の人はミニゲームで対戦していたり、あるいは1人のプレーヤーがボス戦をしているとき、他のプレーヤーがその上で別のミニゲームを遊んで邪魔するといった要素があった。
かなり混沌とした内容で、ミニゲームの企画も180種類ほど出た中から、60種類が実装されている。思いつきで動いているところも多いが、全プレーヤーがパラレルに行動するという仕組みでゲームが成立するかどうかという根本の部分では、実際にボードゲームを買ってきて、コマを無視して独自のルールを作り、参加者全員にゲームボーイをもたせ、「あなたは今ミニゲーム、あなたはボード」という形で検証はしているという。
またこのゲームは、とにかく待たせないことを重視し、ゲーム開始前の名前などの設定画面もパラレルに動作する。4人が同時に設定すると、画面上の情報量もかなり多くなるため、どこまで文字を小さくしてもいいのかを確かめるため、わざわざ古いテレビを持ってきて調整をかけたりもしたという。
いずれにしてもゲームは徹底的にニッチなところを狙ったもの。そういうゲームを作る人たちだということも知られており、「依頼される方からもそれを望まれた」という。またそれだけに、「爆発的に売れる商品になりづらい」ということも自覚はしていたそうだ。
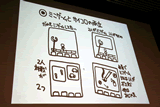 |
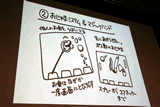 |
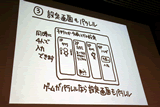 |
| 「ガチャろく」のパラレル動作解説。とにかく休む暇がないほど、いつでも何かやれるというのが特徴のゲーム。「あまり売れなかった」とは言っていたものの、2作目も発売された、コアな人気を持つタイトルである | ||
■ 徹底したニッチ狙いの開発者が、誰でも遊べるカジュアルゲームに初挑戦
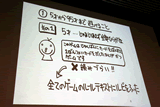 |
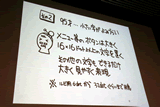 |
| 5歳から95歳まで遊べるゲームに挑戦。当然ながら、それぞれに全く違う問題が存在する |
開発は、DSが発売される少し前に声がかかり、それからずっと制作していたという。小林氏は、「ニッチなところばかり狙っていた会社が作ったので、どんな奇抜なものが作れるかばかり考えていた」という。ところがその企画を出したところ、「そうではなくて、昔からあるようなゲームをDSで作ったらどうなるかを見たい」と言われた。ここから、今までにやったニッチなタイトルとは正反対の、カジュアルタイトルの開発を始めることになる。
まず与えられた指示は、「5歳から95歳まで遊べること」。当時はまだDSの発売前だったので、タッチスクリーンをどう使うかという事例もなかったが、全ての操作をタッチパネルで行なうと決められた。「今までになかったタッチパネルが急についたことで、ボタンとタッチパネルの両方を使いたくなるもの。だがボタンを一切捨てたことが結果としてよかった」と小林氏は振り返った。
羽石氏は「ガチャろく」の開発などに参加はしているが、「何となく入った会社がゲームを作っていた」というほど元々はゲームをやらないそうで、“ゲームの常識”というものがなかった。そのため過去には「ゲームも知らないのに何を言っているんだ」といわれ苦労したことも多かったそうだが、今回のように徹底したカジュアルゲームでは、普段ゲームをしない人も遊べることが前提だったので、羽石氏の視点が逆に役に立つことになったという。小林氏は、「我々がゲームの基本だと思っていたものが、わからないのが当然。20年前から作っていた人間には想像もできない。初めて人の気持ちを考えてゲームを作った」という。
開発の中でも、やはり幅広い年齢層に遊ばせることが課題となった。まず5歳の子供に遊ばせるためには、説明に漢字が入っていては読めないので、全部ひらがなにした。これで何とかなるかと思いきや、大人は読みづらく、子供は読めても結局意味がわからなかった。そこである程度のラインとして、小学3年生くらいまでの漢字を表にして、そこに使われていないものをはずした。また「これを読まないとゲームができない」というところには漢字にルビを振ったり、誰にでもわかる言葉に変えるといった対策もとられた。
次は95歳の対応。こちらは小さな文字が読みづらいという問題がある。文字のサイズを16×16ドットと大きなものにしたところ、DSでは横に16文字しか並ばないが、「それでもいいから大きくしてください」ということに決まったという。ボタンの文字は最低16ドットで、可能ならそれより大きくしたという。
次に、設定画面も変更が必要だった。当初はゲームを短時間で始められるほうがいいと思い、あらゆる設定を1つの画面中に収めた。これを60歳過ぎの方に触ってもらったところ、「名前入力が何の意味がわからない」など、根本的なところから理解してもらえず、ゲームを始めるに至らなかった。「全部のゲームを並べて1画面に納めたほうが早くゲームを始められるが、カジュアルゲームとしては間違えていた」と小林氏は語った。
そこで設定項目を順番に1つずつ表示していく形のメニューが作られた。これは当時売れていた「脳トレ」を参考にしたという。確かにわかりやすくはなったが、全ての設定を順番に入れていくと長すぎた。特にローカルルールなどの設定も詳細にできたため、同じような設問が続いて面倒になってしまった。年配者も今度は迷わずゲームを始められたものの、設定の意味がわからないまま進めたら遊べたという形で、満足な結果ではなかった。
最終的には、ゲーム選択などの基本設定を済ませると、最後にこのゲームで遊ぶかどうかという確認画面を出すようにした。さらにその画面で詳細な設定画面にも行けるようになっており、設定を終えるとまた戻ってくるという形になった。表示の面でも、1つ設定すると左にスクロールして次の画面を表示。戻ると右スクロール、詳細設定は縦スクロールと、スクロールの方向で意味の違いを表現した。
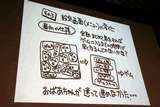 |
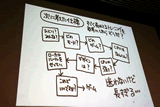 |
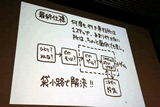 |
| ゲームに至るまでのメニューデザインには苦労の跡が見える。実際に使ってみると、確かに無駄がなく、スクロールにより直感的にメニュー全体をイメージできる | ||
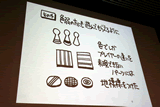 |
| 色弱者でも遊べるよう対策を施している。「だれでも」と銘打つタイトルだけに手抜かりのない仕様だ |
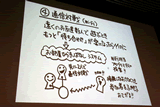 |
| ゲームへの途中参加を可能にした“お部屋ひらきっぱなしシステム”。実現のためのエラー処理も膨大だが、「色々いたずらしてみてください」と自信を見せた小林氏 |
さらに開発が進み、今度はWi-Fi通信対戦に対応することになった。後に別のパッケージとして発売された「Wi-Fi対応 世界のだれでもアソビ大全」である。このゲームでは、42のゲームのうち30以上がWi-Fi対戦に対応している。
当初はWi-Fi対戦をする際、新しい人が参加するためには、一度ゲームを終わらせて接続し直す必要があった。羽石氏はこの点が不便だとは思っていたが、そういうものなのだろうと諦めていたという。しかしあるとき、プログラマから「部屋を開きっぱなしにして、参加者をどんどん追加する形にもできる」と提案された。
システムとしては画期的だったが、これに対応するためには、これまでに制作していた30以上のゲームのデバッグが必要になるため、「作業量を考えると、すぐには決められなかった」という。この点については発注元と相談し、面白そうだということで採用されたという。またこのシステムでは、通信の切断や、DSのフタを閉じた時のスリープでの処理など、ものすごい数のエラー処理が用意され、それによって動作を安定させているという。
■ 誰でも遊べるゲームにするに越したことはない
小林氏はこのプロジェクトから、「奇抜さより安心感と使いやすさを考えるようになった。ノリについてきてくれる人だけ遊べればいいと思っていたが、年配の人でも、だれでも遊べるようにと考えるようになった。ゲームをやったことがない人に直接触ってもらってもらうのがいい。当たり前のことだが今までできなかったと反省している」という。
また長年手がけていた、ニッチな層を狙ったタイトルについては、「昔のように、出せば何でも新しいというジャンルがなく、今は何を出しても昔にかぶるものはある。今後は新しい技術によって、昔のゲームをより面白くする方向に進めばばいいのではないか。ただ新しいルールを生み出していくことがプランナーとしての楽しみなので、今後も続けていきたい」と語った。
最後に小林氏は、「誰でも遊べるゲームにするに越したことはない。基本的に迷わせないことを追求したい。カジュアルじゃないゲームにしても、迷わせないゲームが作れたらプランナーとしては勝ちというところはある」と述べた。
奇抜なゲームには、それが趣向とマッチした人にはとても楽しく感じられるというよさはある。ただ、奇抜と一言で言っても、そのやり方はさまざま。例えば「ガチャろく」では、パラレルに展開するゲームシステムという奇抜さだけでなく、変なコントローラの使い方をするという要素もある。それが「変わったゲームだな」と理解できているうちはいいのだが、「何をさせたいのかわからない」となれば、それはもうゲームとして成立していない。「奇抜なゲーム」だから「理解できる人が少ない」というのはイコールではない、というのが講演内容から感じられた。
現在、スマイルブームが手がけているアクションゲームツクールについて小林氏は、「最近の子供は、大規模なゲームが増えてきたことで、ゲームを作るのが難しいと思っているのではないか。昔のように、ゲームは手軽に作れるんだよ、ということを伝えたい。ゲームを作るのって楽しいなと思えるようなものを作りたい」と語った。果たして誰でもゲームを作れるツールになるのかどうか、こちらの仕上がり具合にも期待したい。
□CEDECのホームページ
http://cedec.cesa.or.jp/
□スマイルブームのホームページ
http://smileboom.com/
□関連情報
【9月4日】マイクロソフト、「Gamefest japan 2008」を開催
遊び、作る楽しみをエンドユーザーに広げていくプラットフォーム戦略が結実
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080904/gf1.htm
【9月4日】エンターブレイン、WIN「アクションゲームツクール」
誰でも手軽にXbox 360用ゲームも作れる「ツクール」シリーズ最新作
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080904/agm.htm
(2008年9月16日)
[Reported by 石田賀津男]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.