
|
||||
|
西川善司のE3ゲームグラフィックス講座(後編) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
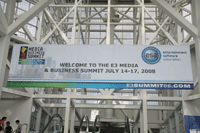 |
会場:Los Angeles Convention Center
今世代の3Dゲームグラフイックスのスタンダード技術は「法線マップによる微細凹凸」、「セルフシャドウ付き動的影生成」、「ハイダイナミックレンジレンダリング」の3要素であり、本連載ではこれらを「今世代の3Dゲームグラフィックス“三種の神器”」と勝手に提唱してきたが、これらの三種の神器のおかげで、今世代の3Dゲームグラフィックスが底上げされことは確か。一部の解像度を上げただけのエセ・ハイデフゲームを除けば、画面の情報量は各段に上がったと思う。
しかし、弊害も出てきている。それは、どれもこれもが、映像的に似通ってきてしまっているという点だ。3Dシューティングタイプのゲームは、なんとなく、みんなUnreal系の「Gears of War」チックな面持ちだし、レーシングゲームはみんな「グランツーリスモ」に見える。美形男女が活躍するRPGはどれも「ファイナルファンタジー」に見えてしまっている。
ここから脱却するには、他が誰もマネできないような独自シェーダ技術を実装するのが直観的な解決方法となるのだろうが、今回のE3では同じ三種の神器をベースとしながらも、背伸びをせずに個性的なビジュアル表現をしてきたタイトルが目に付いた。後編となる今回はこれらを紹介しよう。
■ 「Prince of Persia」
昨年、「アサシンクリード」で一世を風靡したUBI SOFTの今年のイチオシは「Prince of Persia」だ。「また、『Prince of Persia』の続編ですか?」と言われそうだが、今回はサブタイトルをあえて排除した、仕切り直しの完全新作として登場する。
前3作までのプリンスの戦いは3部作でひとまとまりとしており、今回は新シリーズとしてスタートされる。UBI SOFTはこの件について「アラビアンナイトの昔話には色々なお話が綴られるているのと同じく、いろんなプリンスの戦いが『Prince of Persia』として描かれていくものと思って欲しい」と説明している。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
 |
 |
| 新生「Prince of Persia」の主人公は2人。新プリンスとElika | この男女キャラが手と手を取り合って大冒険していく構図はあれを連想させる……!? |
今作ではElikaという女性同伴キャラが登場し、このElikaとプリンスのコンビで決められる連携アクションが新ゲーム要素と訴求される。「Prince of Persia」としては初のオープンフィールドシステムを採用し、謎の古代都市を縦横無尽に駆けめぐることができ、ストーリーもノンリニア進行するとしている。戦闘や移動アクションにおいてもElikaとのコンビネーションを常に意識し、活用しなければならないゲームデザインになっているとのこと。
男女キャラがペアで謎の都市を駆けめぐるというと「ICO」を連想するが、UBI SOFTによれば、「Elikaは映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』のエリザベス・スワンをイメージした」というだけあり、実は見た目よりもかなり強いという設定だ。魔術に長けたElikaは戦闘においてもコンビネーション攻撃を積極発動するし、プリンス1人では到達困難な場所へも身軽さを利用して先陣を切って行ける。Elikaは「ICO」のヨルダよりも大分強い女性として描かれるのだろう。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
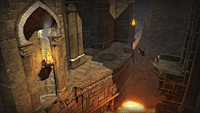 |
 |
| 謎の古代都市で繰り広げられるアクションアドベンチャー | Elikaは魔術を操る。見た目よりも実はやんちゃで強い |
さて、前3作の「Prince of Persia」はゲームとしては良作ではあったが、ベースがプレイステーション 2ということもあって、グラフィックス的な見栄えとしては良くも悪くもPS2レベルであった。
そういった意味では今世代機では初の「Prince of Persia」となる今作は、そのグラフィックスがどうなるのか注目されたわけだが、そのスタイルはかなり意表を突くものであった。
| 【プロモーションムービー】 |
|---|
 |
| [WMV形式: 31.2MB 2分2秒] ZIP圧縮 ※クリックするとダウンロードが始まります |
| その独特なビジュアルとアニメーションにも注目。アニメーションは手付けでモーションキャプチャは用いていないという |
 |
| 動的キャラクタだけに稜線+セルシェーディングが適用されるユニークなビジュアルデザインを採用 |
基本的な使用技術は本連載でいう「今世代の三種の神器」ベース。ライティングはHDRレンダリングベースで、見慣れたわざとらしいブルームもあるし、微細凹凸は法線マップベースだ。影生成はオーソドックスなデプスシャドウ技法をベースに、フィルタ処理をかませた疑似ソフトシャドウを行なったもの。変わったところはない。
やはり一番目を惹くのは、稜線(りょうせん)を意図的に黒色で太くして描くビジュアルスタイルだ。これにより輪郭がサインペンで描かれたようなタッチになる。
さらに観察すると、稜線は動的キャラクタのみに与えられており、その動的キャラクタへのライティングに関しては陰影が「明と暗」ではっきりと出やすいセルシェーディング風になっている事がわかる。
またテクスチャに対して、あえて水彩画やポスターカラーのような彩色で焼き込みの陰影が描かれているのも特徴だ。動的なライティング結果による陰影と、リアルタイム影生成の影とのバランス取りにも人為的な操作が見られ、これもイラスト調とリアル系の中間的な表現の成功に貢献している。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
 |
 |
| 影はリアルタイム生成される。セルフシャドウもあるが、キャラクタに掛かる影は意図的に薄められる調整が入る | リアル系路線100%でいって「アサシンクリード」と似通ってしまうことを避けての決断なのかもしれないが、いずにせよ「新シリーズである」ことの主張は伝わってくる |
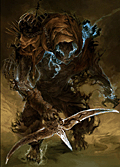 |
| 手描きのコンセプトアートを“そのまま”ゲーム中に動かしたかったというのが、このビジュアルデザインの方向性を決めた |
前3作の開発に際しては様々なコンセプトイラストが起こされ、それらがオフィシャルサイトやマニュアルなどにも掲載・記載されたが、これが予想外に人気を博していたことを知ったチームは「今作ではこのコンセプトイラストをそのまま立体化して動かしてみてはどうか?」という着想にたどり着いたのだという。
そういえばUBI SOFTタイトルで、イラストが3Dで動き出すものといえば「XIII」(サーティーン)があり、ポリゴン数こそ全く違うが、両者は、
・動的キャラクタのみに動的稜線生成する
・陰影が二値的なセルシェーディング風
といった点でよく似ている。
「XIII」のセルシェーディングはポリゴン単位にフラットシェーディングするという単純なものだったが、今作の「Prince of Persia」もよく似ている。また「XIII」では、稜線は、描画モデルとその描画モデルを若干膨らませたモデルを単色の黒色で同時に描いて合成することで生成していた。しかし、この方法では描画モデルの最外殻の稜線しか出せない。今作の「Prince of Persia」ではそうした制限は見られないので、この方法ではなく、今世代らしく、ピクセル単位の法線ベクトルやデプスバッファ中の深度値をキーにして行なうポストプロセス的なメソッドが使われていると推察される。
 |
 |
 |
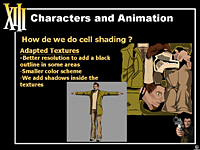 |
| フランスの人気コミックをゲーム化した「XIII」。プログラマブルシェーダを使わないアプローチで実装したという独創的なセルシェーダが当時話題を呼んだ | |
なお今作の「Prince of Persia」のゲームエンジンは、UBI内製の「アサシンクリード」と同じ「Anvil Engine」を採用しているとのこと。
グラフィックス・スペック的な話をすると、PS2から今世代機へベースプラットフォームを移行させたため、主人公のプリンスのポリゴン数だけでも旧PS2 3部作のプリンスの13倍になっているという。UBI SOFTによれば、新プリンスの髪の毛のポリゴン数だけで前作プリンスの全身に相当するという。
キャラクタの陰影は単なる稜線強調+セルシェーダーだけでなく、シワを法線マップで表現していたり、動的影生成、HDRレンダリングといった今世代の三種の神器は一通り組み合わせている。狙ってか偶然なのか、この意外なシェーティング・レシピの組み合わせが独特なイラスト的なビジュアルを作り上げているようだ。
UBI SOFTによれば、キャラクタのド派手なアクションはほぼ全てがアーティストによる手付けモーションであることも宣言されている。モーションキャプチャーは使っていないというのだ。これは意外。ド派手なゲーム中のアクションは敵の位置や動きなどのゲーム展開に動的に対応できるようにプロシージャル制御されるのだ。
少々余談になるが、実は先進的なゲームスタジオでは徐々にモーションキャプチャー離れが始まっている。正確には、モーションキャプチャーで採取したモーションデータの再生だけでキャラクタに“通り一遍”のアクションをさせるだけでは不十分だという判断が広まってきていて、物理シミュレーションやリアルタイムキネマティックスをモーションキャプチャーに融合させていこうという風潮が高まっているのだ。新「Prince of Persia」もこの流れに則ったものになる。
本作のプラットフォームはPS3/Xbox 360/PC。ニンテンドーDS版も出るがこちらは別物。発売時期は2008年末。前3作が全て日本で発売されたことを踏まえれば、今作もきっと日本で発売されることだろう。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| お荷物ではないElika。Elikaの動きはAI制御されるが、プレーヤーの簡単操作でプリンスをその時点で最適な方法で助けてくれる。プリンスにとっては必殺サポート兵器的な位置付け | ||
■ 「Mirror's Edge」~1人称視界から主観視界表現へ
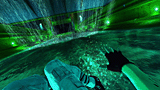 |
| 「Mirror's Edge」は、開発者サイドのこだわりがあって1人称固定宣言がなされた |
時代はプライバシーの消失した当局が完全に情報を統制している近未来。秘密情報は物理的な手渡しで行なうしかスベがなく、そんな世相から当局の管理外に荷物を運搬する運び屋「ランナー」と呼ばれる裏稼業が誕生する。プレーヤーは、法規外の「荷物」を運ぶランナーに扮し、超高層ビルが建ち並ぶ近未来都市の屋上を伝い空中回廊を跳び渡っていくのだが、知らず知らずにこの世界に蠢く陰謀に巻き込まれていくことになる。
シーン内の鏡やガラス窓などを見るとプレーヤーが扮しているヒロイン・キャラクタFaithの姿を見ることはできるが、前述したようにゲームは完全に1人称で進行する。EA担当者によれば「1人称視点にこだわっている。3人称視点モードは絶対に付けない」と言いきるほどなので、日本人が大好きな3人称モードを期待するのは無駄なようだ。
さてプレーヤーは、このFaithになりきって近未来都市の最上階付近を縦横無尽に駆け回り、忍者のように飛びまくり進んでいくことになるが、進行を邪魔する障害物に遭遇しても簡単なアクション操作をすることで、その場において最適なアクションを自動的に繰り出し回避していくことができる。
例えば進行方向に金網があれば、これを素早くよじ登って飛び越えるし、パイプが目の前を横断していればその下を滑りくぐってくれたりする。ジャンプして着地に失敗して落ちそうになっても、掴まるところがあれば、間一髪で掴まってこらえてくれるし、敵にばったり会っても、護身術みたいな拳法を繰り出して敵の銃を自動的に蹴り落としてくれちゃう。絶体絶命の状況においても、簡単なアクション操作だけで、格好いいスーパー・アクションを繰り出していけるカタルシスは、これまでの1人称タイプのゲームにはなかったものだ。
| 【プロモーションムービー】 |
|---|
 |
| [WMV形式: 14.4MB 1分45秒] ZIP圧縮 ※クリックするとダウンロードが始まります |
| リアルとアンリアルの狭間。新世代ゲームグラフィックスとはこういうことだ? |
ゲームプレイを「超高層ビルを跳び渡る」という「落ちたら問答無用で死亡」という即死トラップだらけの舞台設定としただけあって、ゲームシステム側のサポートはかなり手厚いものとなっているわけだが、これが本作のゲーム性設計における「飴と鞭」の使い方の上手さになっている。
実際にプレイしてみると1人称視点固定としながらも、カメラはあまり回転しないことに気がつく。例えば、忍法(?)高速壁歩きをしているときもカメラの天地は回転せず、地面は常に画面下方向にあるような感じで描かれるのだ。このため、現実世界の重力方向とズレが小さいために酔いにくい。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| その状況にあった格好いいアクションを簡単操作で自動的に発動できる | ||
さて、グラフィックスの話に戻すとしよう。この「Mirror's Edge」のグラフィックスも基本的には「三種の神器」ベースで構成されている。微細凹凸や服のシワなどは法線マップで表現され、リアルタイム影生成はデプスシャドウベースのソフトシャドウ、基本レンダリングパスはHDRレンダリングベースといった具合だ。
ヤマカシ系フリーランニングのゲームと言うことで、スピード感を演出するためのモーションブラーの効果的挿入が印象的ではあるが、目に付く奇抜なシェーダーエフェクトはそんなにはない。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
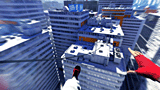 |
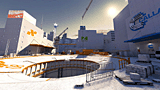 |
| 微細凹凸は法線マップで表現 | 「飛び跳ねて走る」がテーマのゲームなので、モーションブラーは「Mirror's Edge」にとって欠かせない特殊エフェクトとして多用される | 影生成も印象的 |
「Mirror's Edge」の3Dゲームグラフィックスの特徴は、シェーダー技術云々よりもやはり、そのトータルなビジュアルデザインにある。
まず、一見すると無限遠まで描かれているように見えるエピックスケール描画された広大な都市のパノラマビューが素晴らしい。わざとらしいまでの光HDRレンダリングによるのブルーム効果も、「ビルの屋上からの光景」という設定と妙にマッチしている感じがする。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
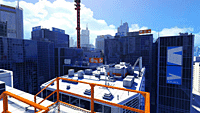 |
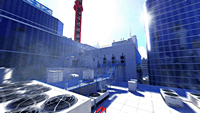 |
| 遥か遠方まで見えるパノラマ屋上ビジュアルは気持ちがいい | わざとらしいまでのHDRレンダリングのライトブルーム効果も、ビルの屋上がテーマの本作では妙にマッチしている? |
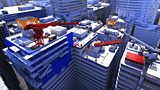 |
| 陰影の出方が妙にフォトリアルなのに、モノトーンに純色アクセントという独特な彩色感 |
妙に陰影がリアルに感じるのは、ビル上の手すり、空調室外機、アンテナなどなど……シーン内の大小全ての凹凸に対して大局的照明を施したような複雑な相互遮蔽陰影が施されているためだ。ビル施設はそれ自体が自己破壊しない静的オブジェクト群であるため、この複雑でリアルな陰影は事前焼き込みの可能性が高いが、いずれにせよ、何らかの「環境遮蔽」表現を実装していると思われる。なお、こうした「環境遮蔽」の陰影についての詳細は後述する。
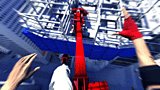 |
| 視界の純色のアクセントペイントはゲームインターフェイスを兼ねている |
さらに注意深くシーンを見ると、モノトーン彩色のビルに赤、緑、青、橙といった純色でアクセント的なペイントが施されていることにも気がつくことだろう。これも「Mirror's Edge」のビジュアルの独創性に大きく貢献している。
これは、実はアーティスティック的な狙いというよりは、ゲーム性の方に深く関わっている。ゲーム画面は1人称視界で描かれるが、さらに言えばゲーム画面は主人公Faithの知覚している主観視界となっているのだ。
具体的に言えば赤はゲーム進行に大きく関わっている構造物であり、例えば逃げ道であったり次のビルへ飛び渡るための重要なポイントだったりするため、プレーヤーは積極的に「赤いもの」にインタラクトする必要がある。橙はよじ登ったり壁走りができる壁に塗られており、敵を出し抜いたり、効率よく逃走するのに使えるエリアという認識になる。
完全リアルビジュアルにしてしまうと、プレーヤーを「どこに行けばいいのかわからない」、「何をすればいいのかわからない」と不安にさせてしまうので、「Mirror's Edge」では、部分的にはリアルを潔く捨て去り、あえてメインビジュアルにゲームインターフェイスとしての“記号”を色彩で表現したというわけだ。
色彩ではリアルを捨てたが、陰影では過剰なまでのリアルを取り込んだことで、偶然か必然か、逆に一種独特なビジュアル世界を表現できたというワケである。いわばリアル3Dゲームグラフィックスと記号系のアンリアルゲームグラフィックスの狭間に独創性を見出した格好だ。
なおEAスタッフによれば、現状公開されているムービーやスクリーンショットの彩色は決定稿ではなく、最終的に微妙な調整が入るとのこと。
「Mirror's Edge」の発売時期は2008年内を予定としているが未定。ただし、PS3、Xbox 360、PCの3プラットフォームで提供される予定。E3のプレゼンではPS3版が用いられていた。
■ 「MADWORLD」~漫画的な白黒グラフィックスに「動き」で彩色するという手法
ゲームは、「オーガナイザー」と呼ばれる国際テロリスト組織が主催する「デスウォッチ」という、互いが殺し合うだけの狂気のサバイバルゲームに参加することになってしまった主人公の視点で描かれる。
「MADWORLD」でゲーム内ゲームとして描かれるデスウォッチは、テレビ番組のように見る者を喜ばせる必要があり、その殺し方が残虐であればあるほど高評価が得られるという仕組み。具体的にはゲーム内に転がっている多様なアイテムや環境オブシェクトを使って、いかに独創性を持って、派手に、残虐に敵を殺せるかを競っていくことになる。まさに狂気の世界「MADWORLD」を描いた作品というわけだ。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 「MADWORLD」は、残虐に派手に殺すほど高評価が得られるという狂気の世界を描いた作品 | ||
ゲームはWii専用として提供され、ヌンチャクとWiiリモコンを使って「殴る」、「蹴る」を超えた「刺す」、「斬る」、「引き裂く」までをバーチャルに体験することになる。
稲葉氏のプレゼンでは、ポール部を折った道路標識を敵の頭部にブチ刺して殴る蹴るのとどめを刺すというアクションや、剣山のようなトゲトゲの突き出た壁に敵をブチ投げて串刺しにするといった見たことのない殺戮表現が披露された。
この過剰なまでの暴力表現がなんとなくギャグのように見えて笑えてしまうのは、「MADWORLD」の表現が完全「白黒」表現のアメコミチックになっているため。アクションの際に発生する衝撃に対しては「ドカ」、「ズガ」に相当する英語表記の擬音語がカラーでオーバーラップ表示されるのも笑いを誘う。ただし、画面に発生する血しぶきや流血表現は赤で描かれるため、それなりにグロテスクな味わいもある。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
 |
 |
| ゲーム世界は白黒表現だが、流血表現はちゃんと“赤い” | 衝撃的なアクションには、擬音語の描き文字がオーバーラップされる |
3Dゲームグラフィックスとしては、基本的には2値的な陰影処理を行なうセルシェーダーベースで描かれる。スクリーンショットでは本当に描き割りの白黒漫画のように見えるが、実際に動いている映像は見る者に独特な手応えを感じさせる。
白黒表現となったことで映像ワンフレーム内の情報量は通常のカラーのゲームグラフィックスと比較すれば激減する。静止状態だと何が描かれているのかわかりにくいくらいだ。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| この画面だけ見ると何が描かれているのかが見えにくいが、動いていると逆に面白い映像効果として見えてくるから不思議 | ||
 |
| 色が付くのは擬音語と血だけ |
モーションブラーはないが、その代わり大きな動きには漫画で言うところの軌跡線や効果線、集中線などで表現されるのも面白い。
Wiiのグラフィックスプロセッサはプログラマブルシェーダーを搭載しなかったため、PS3、Xbox 360、PC以上に各ゲームのビジュアルが似通ってしまっていたが、「MADWORLD」のビジュアルは他のどのWiiタイトルにも似ていない。また、他のタイトルが後からマネしづらいという意味においても「MADWORLD」は唯我独尊的な3Dゲームグラフィックス手法となったといえよう。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
 |
 |
| 派手な動きには効果線や集中線が描き出される。こうした表現の数々もイラスト、漫画的で独特だ | |
残念なのは、これだけの3Dゲームグラフィックスを日本では体験できないかもしれないという点。というのも「MADWORLD」は海外専用タイトルとして開発されているからだ。
もちろん理由は、ゲーム内暴力表現にまつわる問題。この点については稲葉氏も百も承知のようでプレゼン中も「色々な意味で日本での発売は無理だろうと思っています。もともと欧米市場にぶつけるために開発しています」とやや開き直ったコメントを述べていた。なんとか、アーティスティックな部分を強く訴求して、日本での発売をクリアして欲しいところだが……。
■ 影生成の次なるトレンド~環境遮蔽
「三種の神器」で大きな位置を占める動的影生成。これの主流は、いつの間にか「デプスシャドウ技法」となった。この技法では、光源からのシーン内の対象物までの距離をレンダリングして、そのシーン内の遮蔽構造分布図(シャドウマップ)を生成し、実際の各ピクセルのレンダリング時にはこのシャドウマップを参照しながら影か否かを判定していくという流れを取る。自身の影が自分自身にも投射されるセルフシャドウ表現も自ずと出てくれる万能性の高さもあって瞬く間に浸透した。
この技法は、対象シーンの広さとシャドウマップ解像度のバランスに注意しないと影に強いエイリアシング(ジャギー)が出てしまうデリケートな面もあるが、これを回避するための工夫も色々出てきており、今世代は当面、主流となり続けるだろう。
しかしユーザーの目は肥えてくるもので、こうしたリアルタイム生成された影だけでは不自然に見えるようになってきた。HDRレンダリングの浸透で暗部に豊かな階調が現われ、ライトブルームなどのポストプロセスの効果で柔らかい光に満ちあふれたシーンになっているのに、影だけがどうにもキッチリと描き出され過ぎている感があり、ここに違和感を感じるようになってきてしまったのだ。
影の輪郭を柔らかくするソフトシャドウ処理を持ってしても、デプスシャドウ技法などで動的生成された影達は、いかにも「影を生成して投射しております」という風情で、なんというか、後からシーンに貼り付けたような“後付け感”がある。
これは、現実世界に存在する物の陰影が、光源そのものの光だけで生成されているわけではないことにユーザーが無意識に気が付き始めてしまったからだ。
現実世界では光を放つ光源からの直接光だけではなく、その光源に照らされたオブジェクト達もその反射光を発するため、2次光源になりうる。現実世界の屋内であれば天井の蛍光灯は光源だが、蛍光灯に照らされた白い天井や壁の白い壁紙も2次光源としてその部屋の中の物を照らす。影は天井の蛍光灯からの直接光による影が一番強く出るが、そうした壁や天井などの2次光源によって影の色が弱まったりする。3Dゲームグラフィックスで動的生成された影はここまでの表現になっていない。
こうした2次光源以上の複雑な光源に配慮した複雑かつ正確な陰影は「大局照明」(Global Illumination)を行なわなければ出せないため、これを実現するためにはレイトレーシング的なアプローチが必要になってしまう。3Dゲームグラフィックスをリアルタイムレイトレーシングで描画するという話は、未来的な展望としては決して夢物語ではないのだが、少なくとも今は無理だ。
そこで、そうした大局照明っぽい複雑な陰影を出すための疑似手法の研究開発が近年、行なわれてきている。そんな疑似手法で、実際の3Dゲームへの実装が始まったのが「Ambient Occlusion」だ。Ambient Occlusionは直訳すれば「環境遮蔽」となるが、かみ砕いて言えば「環境光から遮蔽された陰影を作り出す」ということを言い表している。
具体的には、これは、直接光以外の2次光源以降の光に対しても配慮したような陰影を擬似的に出すテクニックだ。3Dゲームグラフィックスに用いられる「環境遮蔽」の実装方法としては主に2通りがある。
1つは事前計算した「自己遮蔽項」を用いる方法だ。この方法では3Dモデルを構成する各頂点(テクスチャを用い、処理単位をテクセル単位とすることもある)から、ここが、どの程度他のポリゴンに遮蔽されているかを事前計算しておき、データ化する。具体的には、全天が輝いていたと仮定したとき、各頂点ごとに全方位(実際には4方向、8方向など適当な方向数)をぐるりと見回してそこに、何パーセントの光が到達できるかを計算する。いわば局所的なレイトレーシング的な作業を事前計算しておくというイメージだ。
 |
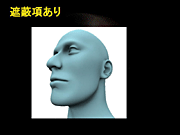 |
| 遮蔽項の有りと無しの比較。鼻の穴や耳の穴の陰影の出方の違いに注目 | |
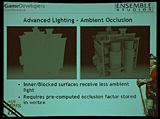 |
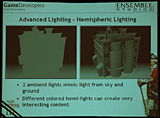 |
 |
| 「AGE OF EMPIRES III」はRTSゲームながら、頂点単位の事前計算の遮蔽項を用いていた | ||
 |
| 「Killzone2」は事前計算の自己遮蔽項をテクセルに格納して、より精度の高い環境遮蔽を実践している |
実際のレンダリング時には、この頂点毎に焼き込んだ自己遮蔽項に配慮して光源処理を行なってやる。演算自体はベクトル積が追加で1個増えるくらいのものなのでそれほど重くはない。こちらの技法を採用した今年のE3出典作としては「Killzone2」(Guerrilla Games)がある。また、早くは「AGE OF EMPIRES III」(Ensemble Studios)が実装した実績がある。
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 「Killzone2」の3Dグラフィックスは、かなり本格的なDeferred Rendering手法を取り入れたことでも注目を集めている。Deferred Renderingについてはまた別の機会に詳しく解説するとしよう。「Killzone2」はPS3専用タイトルとして2009年2月発売予定。日本での発売は未定 | ||
| 【プロモーションムービー】 |
|---|
 |
| [WMV形式: 15.9MB 1分02秒] ZIP圧縮 ※クリックするとダウンロードが始まります |
| オブシェクトとオブシェクトの交叉する接合部分の陰影に注目 |
環境遮蔽のもう1つの実現方法は、ポストプロセスとして実装する「Screen Space Ambient Occlusion」(SSAO)と呼ばれるテクニックになる。これは前出の「自己遮蔽項」を用いたテクニックと違い、事前計算を一切用いないのが特徴だ。なお「Screen Space」とは「画面座標系で処理する」の意味が込められている。
この技法は、「あるピクセルをレンダリングする際、ここがどのくらい周囲に遮蔽されているかを調べていく」ことが基本方針となる。これを調べるには、シーンをレンダリングした後に得られる深度バッファ (Zバッファ) を利用することになる。つまり、この技法を実装するには先にシーンの深度値をレンダリングしておく必要がある。
実際のレンダリング時には、着目しているピクセルを中心に複数の適当な方向 (4方向、8方向など、許容負荷に応じて適当に) に適当な範囲の深度値を深度バッファから読み出して、その地点が周囲からどのくらい遮蔽されているかを調べる。もちろん、局所的な遮蔽しか調べられないがそれで構わない。距離が遠いところの遮蔽物はこちらへの影響は少ないだろうと判断できるためだ。調べた結果、遮蔽されている度合いが高ければそこは暗くなる確率が高いと判断できるので、“陰”として暗く陰影を付けていく。
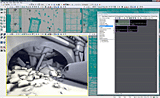 |
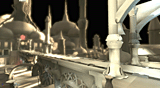 |
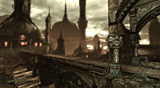 |
| EPIC GAMESは新生「Unreal Engine3.0」を発表。その際にDynamic Ambient Occlusion(=SSAO)がサポートされた | 凹部分の内側や凸部分の外周に柔らかい陰影のグラデーションが出ているところに注目 | このシーンの最終レンダリング結果 |
| 【スクリーンショット】 | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
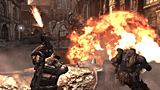 |
 |
 |
| 「Gears of War 2」は2008年11月7日、Xbox 360専用タイトルとして発売予定 | ||
| 【プロモーションムービー】 |
|---|
 |
| [WMV形式: 47.9MB 3分10秒] ZIP圧縮 ※クリックするとダウンロードが始まります |
| ゲームエンジンの進化ぶりだけでなく、ゲームプレイのダイナミズムのグレードアップぶりにも期待がかかる |
この技法は、独CRYTEKが同社のゲームエンジン「CRY ENGINE2.0」に実装したのが最初だとされ、E3出典作ではCRYTEKの最新作「CRYSIS WARHEAD」にて見ることができる。米EPIC GAMESの「Unreal Engine3.0」の最新バージョンにも「Dynamic Ambient Occlusion」という名前で、このSSAOが実装された。これはE3出典タイトルでは「Gears of War 2」で見ることができる。
このような環境遮蔽のテクニックを用いると、柔らかい陰影が的確に出すことができ、直接光だけのリアルタイム影生成だけのときよりもリアリティを増すことができる。
本来の大局照明では、光の出射計算においても2次光源以降についても配慮しなければならない。その意味ではこの方法で増したのは“陰”だけなのだが、最終レンダリング結果は、間接光からの陰影計算を行なったかのような雰囲気がけっこう出てくれる。ここまでの効果があれば疑似手法の結果としては必要十分だといえよう。なお、この2つの手法にはそれぞれ短所と長所がある。
リアルタイム時の負荷は、前者の事前計算した自己遮蔽項を用いた技法の方が低く済む。しかし、シーンが動的に動いた際や、または3Dモデルが変形したり曲がったりする場合には、事前計算した自己遮蔽項は役に立たなくなってしまうという弱点を持つ。つまり、事前計算した自己遮蔽項を、3Dモデルの変形や曲がりに無視して使った場合は、その陰影の出方に不自然さが出ることがあるということだ。
動的なシーンに的確に対応できるという意味では後者のSSAOの方が向いている。いわば毎フレーム、遮蔽構造を再計算するので当たり前といえば当たり前だ。ただし、1ピクセルの陰影計算に反復的にZバッファ参照を行なうことになるためバス消費が高めとなり、レンダリング時の負荷は前者よりも圧倒的に高い。
まとめると、背景オブジェクトや建物などの変形しない静的なオブジェクト主体のゲームでは前者が向いており、動的シーンの占める割合が大きいゲームでは後者が向いているといった傾向はあるかもしれない。
| 【スクリーンショット】 | |
|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
| 元祖SSAO実装エンジン「CRY ENGINE2.0」の最新作品は「CRYSIS WARHEAD」。前作「CRYSIS」の脇役サイコを主人公にした、前作のパラレルストーリーとなる | ||
「三種の神器」の恩恵で底上げされたものの、はからずも「表現としての画一化」が進んでしまった今世代の3Dゲームグラフィックス。このマンネリ化した表現から抜け出ようとして表現自体の独自性を武器にしてきたのが、今回紹介してきたタイトルで言えば「Prince of Persia」、「Mirror's Edge」、「MADWORLD」などになる。これらは無理に中途半端なリアル志向に走らずに、今世代だからできる“新しい味”を作り始めたといったところだろうか。
一方で、3Dゲームグラフィックスのフォトリアリティをさらに極めたいリアル志向勢力は、「三種の神器」にさらに何か新しいテクニックの「隠し味」を加えて、「今世代でできうるリアル」を「濃い口」風味にしようとしている。
熟成期を向かえつつあるDirectX 9/プログラマブルシェーダー3.0からDirectX 10/プログラマブルシェーダー4.0ベースの3Dゲームグラフィックスは、またさらに進化して、我々の目を楽しませてくれることだろう。
□E3 Media and Business Summit(英語)のホームページ
http://www.e3summit08.com/
□「Mirror's Edge」のページ(英語)
http://www.mirrorsedge.com/
□「Killzone」のページ(英語)
http://www.us.playstation.com/PS3/Games/Killzone_2/OGS
□関連情報
【7月31日】西川善司のE3ゲームグラフィックス講座(前編)
物理シミュレーションの活用トレンド「ノンリニア破壊」
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080731/3de3.htm
【2008年7月】「E3 Media and Business Summit 2008」記事リンク集
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080716/e3link.htm
3Dゲームファンのためのグラフィックス講座のバックナンバー
http://game.watch.impress.co.jp/docs/backno/rensai/3dg.htm
(2008年8月5日)
[Reported by トライゼット西川善司]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.