
|
||||
|
Game Developers Conference 2008現地レポートGDCゲームオブザイヤー受賞タイトル「Portal」セッション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
| 会場は超満員。GDCゲームオブザイヤー受賞タイトルのノウハウに多大な関心が集まった |
会場:サンフランシスコ Moscone Convention Center
今回のGDC最大のサプライズは、GDCアワードのゲームオブザイヤーを「Portal」が受賞したことだろう。なにしろ、「BIOSHOCK」や「Call of Duty 4」といったビッグタイトルがノミネートされた中で、「Half-Life 2: The Orange Box」という3本セットの中の、いわばオマケ的な1本が、今シーズン世界最高のゲームだと評されたのである。
弊誌では「Portal」のレビューをお伝えしているので、このタイトルをご存じでない方はぜひご一読いただきたい。このゲームは「Portal Device」という全く新しい仕組みを導入して、FPSが進んできた進化の道筋に風穴を開けた点で、実にイノベーティブだ。そしてステージ全体を流れる独特の雰囲気と、「ただの箱に恋心を抱かせる」ほど洗練された演出によって、鮮烈な印象をプレーヤーの心に焼き付けた。
これらの点が評価され、「Portal」はGDCアワードのゲームオブザイヤーに選ばれたほか、ゲームデザイン部門、イノベーション部門を併せて獲得している。決して「大作」ではなく、また市場的にも大きくは注目されてこななかった作品であるだけに、これは特筆すべき快挙だ。
そしてGDC 2008最終日、開発者自らが「Potral」の秘密を語るセッション「Integrating Narrative and Design: A Portal Post-Mortem」が開催され注目を集めた。今年最高のゲームの秘密を見ようと大勢が集まり、椅子に座れず立ち見、座り見をする聴講者も多数でるほど。間違いなく今年最大級の人気セッションとなった。
■ たった10人の開発チームが最高の栄誉を受けた。ゲームデザインの大切さをクローズアップして振り返る開発秘話
 |
| 「Portal」の開発をおこなったKim Swift氏(写真左)とErik Walpaw氏。セッションはユーモアに溢れ、笑いが絶えなかった |
脚本を担当したWalpaw氏は強烈な個性の持ち主で、説明の都度なにかとジョークをからめて笑いを取る。一言しゃべるごとに会場が笑いに沸く塩梅で、このセッションはお祭り騒ぎ的な様相を呈して大いに盛り上がっていた。
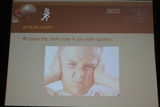 |
| 注意! ネタバレあり。未プレイの方はご退出ください! |
このセッションの主題は、「Portal」における演出とレベルデザインだ。まずKim氏は、セッションを行なう理由として、「小さな開発チーム」、「決定的な商業的成功」を「Portal」が果たしたこと、そして、「全部話したところで後悔することはない」という動機を明かした。これもちょっとしたジョークだろう。
開発規模に関して言うと、ゲームオブザイヤーを受賞したタイトルだけに、どれだけ大規模な開発がおこなわれたかと思ってしまうが、実は「Portal」の開発チームはたったの10人だったという。この作品にはゲーム的な大前提として「Portal Device」(二つの空間を結ぶ携帯型ワープゲート発生装置)という仕組みがあり、基本のゲームプレイはごく初期に完成しうるものだった。10人のスタッフで作りきれる規模のゲームだったのである。
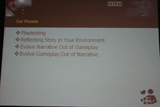 |
| 「Portal」開発の特徴は、プレイテストによってストーリーを洗練させたというプロセスだ |
そこで開発チームはゲームを洗練させるべく、作成、プレイ、評価、改善というプロセスを徹底的に行なった。こういった反復の大切さは他のGDCセッションでも高名なゲームデザイナーが強調していたことだが、「Portal」はゲームの規模が小さいためこのプロセスをダイナミックに行なうことができたようだ。小ささがむしろ利点になっているのである。
全体のレベルデザインを担当したKim氏のアプローチで面白いのは、「Portal」のシナリオに二つの軸が設定されていることだ。それは「ストーリーのストーリー」、「ゲームプレイのストーリー」である。
「ストーリーのストーリー」とは、「Portal」をプレイするとわかるが、舞台となるAperture Science実験施設の置かれた状況自体がひとつのストーリーをなしており、ゲームをプレイすることで、そのストーリーが間接的に明かされるようになっている。プレーヤーは、自己の状況が不明なことに不安を感じ、このストーリーを追うべくプレイへのモチベーションを上げる。
「ゲームプレイのストーリー」というのは、プレーヤーに与えられる「Portal Device」について、その使い方を次第に判明させるために設定された脚本のことである。学ばせるために無機的なチュートリアルをやらせるのではなく、冒頭からゲーム世界に没頭させつつも、要所にプレイ上のポイントを暗示するダイアローグを提示し、違和感を感じさせないまま「Portal」の特殊なプレイを学ばせるというものだ。この二つのストーリー軸が絶妙に絡み合って、「Portal」のキャンペーンモードが実に印象深いものになっているわけだ。
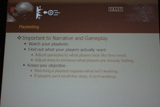 |
| ゲームプレイとストーリーを強調させるために、プレイテストに関する鉄則を設けた |
そのプレイテストにしても、ただ漫然と繰り返すだけでは効果が薄い。「Portal」チームの手法はこうだ。まず、たくさんのプレイテスターを用意する。ゲームをプレイしてもらって、「実際にプレーヤーが望むものを見出し」、「プレーヤーが望む形と思われる方向に調整」、そして「プレーヤーがストーリーについてすでに感じていることをさらに推し進める」というのが方法論だ。
そのときに開発者が持つべき心構えとしては「最初の反応を重視する」ことが重要とされた。良いも悪いも慣れきってしまえば麻痺してしまうからだろう。もし、プレーヤーがストーリーを思い出せないなら、改善の努力は機能していないということだ。これを素直に認めて別のアプローチを試す。開発はこの繰り返しとなる。
■ レベルデザインとストーリーテリングを理想的に融合。遊びの本質を邪魔せずに、深い感情移入を実現する
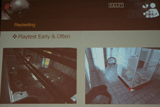 |
| 初期のレベルデザインと現在の対比。開発中にアートスタイルを大幅に変更したというのは「TF2」にも見られた例であり興味深い |
そうしたうえで本格的に開発が進み始めると、今度はストーリーをレベルデザインに反映する部分に注力することになる。ここでの開発思想は、Walpaw氏によると「Eメールやボイスレコーダーを置くのではない限り」(『DOOM3』と『BIOSHOCK』を揶揄している)、「創造的になれ!」ということらしい。
「Portal」チームでは、なるべく自然にゲーム環境になじむ形でストーリー要素を導入することをルールとしていた。そのためにいくつかの手法を試したが、最終的にはゲームの本筋であるテストコースに薄暗い裏部屋を作り、そこに「他の被験者が残したマッドな落書き」を書いておくという現在の形に落ち着けた。
この手法の利点は、速く簡単に作れる上に、十分に効果的であるというところだ。ただし、そういった空間はゲームプレイに影響しないよう、小さく作る。そこをプレーヤーが攻略ゾーンだと勘違いして無駄な時間を過ごさないようにする配慮だ。
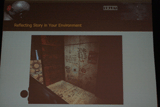 |
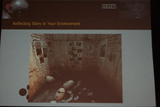 |
| 通常ステージのスキマから入れる裏部屋に、「ストーリーのストーリー」を語る落書きが配置されている。プレーヤーはここで自分の置かれた状況のヒントを得る | |
・ただの箱「荷重コンパニオンキューブ」に深い感情移入
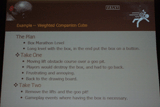 |
| 「荷重コンパニオンキューブ」が登場するステージのデザイン方針。すべて計算づくで作られている |
このステージでは、この箱を使って乗り越えていくパズルが多数でてくる。地面に置いて足場にしたり、ボタンにおいて装置を動かしたりしながら、ステージを少しづつすすんでいき、箱と長い時間を過ごす。その間、プレーヤーの「試験官」であるGLaDoS(施設のマスターコンピュータで、プレーヤーに指示を出したり、皮肉ったり、謎の言動をする存在)が、「おかげで障害を乗り越えましたね。きちんとお礼を言ってください。でも加重コンパニオンキューブはしゃべりませんよ?」、「加重コンパニオンキューブに人格があるとすれば、それは都市伝説です」などと無駄口をたたく。
この脚本とレベルデザインの組み合わせが実に秀逸で、プレーヤーはついに「ああ、実はこの箱ってよく見ると、とてもカワイイな……」などと、箱におかしな感情を抱きはじめてしまうのだ。そしてこのステージの最後には、「箱でボタンを押し、それで開いた炉に箱を投棄、消滅させる」という、血も涙もないパズルが用意されている。プレーヤーは、うっすらと愛情を感じ始めていた「加重コンパニオンキューブ」を自らの手で無慈悲にも破壊するのだ。次のレベルに進むために。これが強烈な記憶となって、プレーヤーの心に残り続け、最終戦への心理的伏線になる。
 |
 |
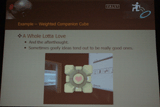 |
| 長い冒険をともにして、ついにプレーヤーは箱に愛を抱く。しかしそれは悲しくも引き裂かれ、ボス戦への複線となるのであった | ||
■ 記憶に残るラストバトル。その実現には多数の紆余曲折があった
 |
| ボス戦がうまくいった理由を分析。この結論に達するまで4回も作り直すハメになったという |
「Portal」チームでは当然そのことを理解しており、ボス戦とそれに続くラストバトルの部分は最大限の力をこめて制作したようだ。それがゲームのラスト部分を4回も作り直したという説明に現われていた。結果として、「Portal」のラストとボスGLaDOSとの戦いは実に印象深く、鮮やかな記憶として残るものとなっている。
Kim氏は、「Portal」のラスト部分がうまくいった理由として、次のポイント挙げた。「前段階にボス戦の戦術トレーニングを配置したこと」、「満足できる内容的ボリュームを用意したこと」、「復讐であること(荷重コンパニオンキューブの件)」がそれである。
トレーニングとは、ボス線に至るラストレベルの途中に設置されている自動ロケットランチャーを使ったパズルのシーンだ。プレーヤーはここでロケットランチャーの照準を誘導し、適切な場所にロケットを命中させてパズルを解く基礎的な法則を理解できる。
Kim氏によると、この部分はレベルデザイン的に余裕のある空間になっていて、プレーヤーのストレスが少ないため、ゆとりをもって学ぶことができるようになっているとのことだ。それを経てだんだんと緊張感が高まり、ボス戦へつながっていく。こういった細かい配慮がうまく機能しているようである。
 |
| 初期のボス戦は難しいだけの無味乾燥としたものだったようだ。幾度も作り直しができたのはゲームの規模が小さいから、といこともある |
そこで次に、激しい戦闘を導入してみた。タレットが大量に登場する広間にボスを設置して、ロケットをポータルで誘導してぶつけるというもの。非常にアクション性が高いものに仕上がり、ハッキリ言ってしまえば「タレットの相手に忙しすぎて、ボス(GLaDOS)について誰も興味を払わなかった」だそうである。これではストーリーがうまく伝わらず、やはりラストが台無しになる。
3番目の挑戦では、致死的な空間がぐんぐん追いかけてくる中、通路を走りながらボスと戦うというものが導入された。これならボスとの戦いに集中できるはず。しかしこれも結果的にはボツとなった。GLaDOSとプレーヤーのコミュニケーションをうまく作りこめず、長い通路のために大量のアートアセットが必要で、ゲーム性が最悪だったから、ということらしい。
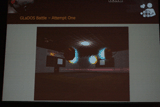 |
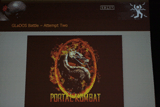 |
 |
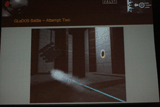 |
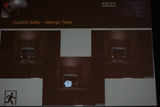 |
 |
| ボス戦の遍歴。現在のGLaDOSの形は最後の最後になって大幅に変更されたようだ | ||
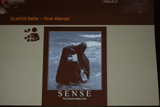 |
| ダメなボス戦を評しての画像。いわく「ナンセンス」。これには大勢の聴講者が爆笑した |
これについてWalpaw氏は、「どんなボス戦がいいかですって? そりゃもう、ストライダーが一杯出て、ジープ乗り回して、ボールぶつけて、アアアアア!!!」と天を仰ぎ、「やってられっか」感を全身で表現。これは「Half-Life 2: Episoce Two」のことを救いようがないほどに批判しているのだが、思いを同じくする聴講者が多いようで会場全体が爆笑に包まれた。
そして現在の「Portal」のボス戦が最終的に構成された。最大のポイントは、ボスであるGLaDOSのデザインを根本から変更したという点だ。複数のモジュールで構成される機械にしたことで、それぞれのモジュールに個性を表すことができるようになった。戦闘自体は簡単に解けるパズルになっているのだが、最初のモジュールが破壊されるイベントを使って、ボス戦に適度な緊張感をもたらすカウントダウンの演出を取り入れた。
カウントダウン自体は非常にゆるやかなものだ。プレーヤーがGLaDOSの無駄口をじっくり聞ける程度に調整し、ドラマをしっかりと伝えることに軸足をおいた。このおかげで、「Portal」のボス戦はプレーヤーの記憶に残る名シーンとなったのである。Kim氏とWalpaw氏は、このことを伝え、講演を締めくくった。
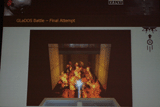 |
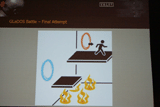 |
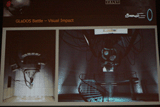 |
| 紆余曲折の結果、「炎の穴」から続くラストシーン及びGLaDOS戦が構成された。その展開は極めてドラマティックで、パズルゲームとしては度外れた感動をプレーヤーに与えてくれる。繰り返し改善するプロセスは大成功を収めたわけだ | ||
■ 長く続いた質問時間には熱烈なファンも登場。GDCの最後を飾る印象的なセッションとなった
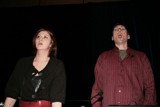 |
| いつまでも続く質問に、Kim氏、Walpaw氏ともに丁寧かつジョークも交えて答えていた |
まず最初の質問は、「『BIOSHOCK』についてどう思いますか?」というもの。GDCアワードの部門賞を分け合ったビッグタイトルだけに、ライバル製品の開発者自ら意見を語ってほしいというのは健全な好奇心といえる。これに答えるにライバルに配慮するかと思いきや、そっけなく「Bad Game. Next Question?」と強烈に切り捨てた。会場がこれにまず爆笑。実は、Valveでは「The Orange Box」の開発中に、「BIOSHOCK」プレイ禁止令が出ていたことがある。そのことで、どうも感情的になっているのかもしれない。この事情を知っている聴講者には、さぞ面白い応答だったろう。
次に「どうしてコンパニオンキューブを殺したんですか。どうして、どうして、どうして!?(Why, why, WHY!?)」と恨み節全開の「箱萌え」的質問が飛び出した。これにはさすがに、Kim氏は「それ、シナリオの説明で言いましたよ」と、Walpaw氏に至っては「そんなこと私も知りませんよ。国家秘密情報局にでも聞いてください」と冷たくあしらってしまった。これにまた爆笑が巻き起こるあたり、このセッション独特の雰囲気がある。
「テストプレイのプレーヤーは頻繁に入れ替えたのですか? どのように確保したのでしょう?」という質問には、「ちょっとそこのキミ、面白いゲームがあるんだけどウチに来てプレイしてみない? なんてできませんよね」と人材確保の難しさを挙げ、そのため「ゲイブ(Valveの創設者)や、その子どもたちにもプレイしてもらってました」と、「Portal」の開発がValve全体を巻き込んで進行した内幕を披露。開発室のムードを感じることができ、非常に興味深かった。
10人のスタッフで開発し、GDCアワードのゲームオブザイヤーを獲得した「Portal」。その開発には、シナリオ、演出と、ゲームプレイを絶妙に融合させる方法論があった。また、その完成度を高めるための徹底した反復作業があった。やっていること自体は極めて王道的な、どこのデベロッパーでもやろうとしていることである。それをどこまで高い次元で行なえるか、それがゲームの完成度を決めるのだろう。
小さいゲームは、改善の反復を行なう上で非常に有利だ。「Portal」の場合、ゲームの最初から最後までをプレイテストするには、8時間もあれば十分だったという。1日1回の通しプレイができる計算だ。大規模なゲームではこうはいかない。
今回のGDCではマイクロソフトから「XNA」をプッシュする「ゲーム民主国家」宣言が出されたこともあり、小規模開発型のゲームというものが今後大きくクローズアップされていく予感がある。「Portal」が今年最高の評価を受けたことは、今後のゲーム業界にとって並々ならぬ意味がありそうだ。
□Game Developers Conference(英語)のホームページ
http://www.gdconf.com/
□Game Developers Conference(日本語)のホームページ
http://japan.gdconf.com/
□関連情報
【2008年】Game Developers Conference 2008 記事リンク集
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20080221/gdclink.htm
【2007年10月26日】PCゲームレビュー「Team Fortress 2」 & 「Portal」
http://watch.impress.co.jp/docs/20071026/orange.htm
(2008年2月25日)
[Reported by 佐藤“KAF”耕司]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.