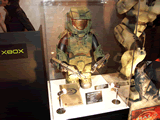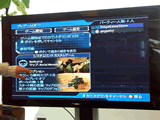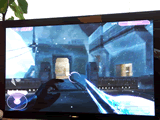| ||||
|
TGS2004ブースレポート ~Xbox編~ その2 |
 |
会場:幕張メッセ
入場料:1,200円(小学生以下無料)
■ マイクロソフトブースでは、4対4のCTFが体験可能
遂に日本でその姿を現した「Halo 2」。24日より開催されている東京ゲームショウ2004のマイクロソフトブースでは、「Halo 2」のプレイアブル出展が実現され、来場者が実際にいち早くプレイできるようになっている。
マイクロソフトブースのメインステージ横に用意された「Halo 2」の試遊コーナーには、全部で8台の試遊台が設置されている。体験できるのは「Halo 2」のマルチプレイモードだ。試遊は8人の入れ替え制となっており、4人ずつの2チームに分かれ、その2チームによる対戦プレイが行なわれる。対戦プレイの内容は、おなじみのマップ「Zanzibar」を舞台に、1旗の旗の攻防を行なう、いわゆる「Capture the Flag」戦だ。1回戦が3分間の時間制限となっており、攻守を入れ替えての全4回戦が楽しめる。
本日はビジネスデーのため、一般来場者は入場できないものの、それでも「Halo 2」の試遊コーナーにはかなりの人が集まっており、常にプレイまでに1時間近い待ち時間が必要なほどであった。それだけ「Halo 2」に対する期待が高いということなのだろう。
実際にプレイしている人たちは、普段から「Halo」などのFPSを楽しんでいるという人がほとんどのようで、誰もがスムーズにプレイを進めていた。ただ、せっかくチーム戦でのCTFが体験できるにもかかわらず、試遊台にはボイスチャット用のヘッドセットが接続されていなかった。CTFはチーム間での作戦が勝敗を大きく左右するため、ヘッドセットで会話しながらプレイできた方がより楽しめるはずで、その点はやや残念。とはいえ、来場者によるにわかチームでのプレイなので、緻密な作戦を立てるのはまず無理だろう。そういう意味では、ヘッドセットがなくても大きな問題はないかもしれない。
今回の試遊機は、Xbox Liveに接続した状態でのマルチプレイが体験できるのではなく、システムリンクによって実現されているそうだ。これなら、ラグの問題は全くない。Xbox Liveに接続した状態でのデモプレイならば、どの程度のラグが発生するかなどといったことも体験できたのだが、そのあたりはまだ最終的な調整中ということで、今回はシステムリンクでの展示となっている。ただ、デモのバージョン自体は最終版にかなり近いものだそうなので、製品版に近い感覚で試遊できるはずだ。
ところで、「Halo 2」の試遊コーナーには、ちょっと見慣れない形のマスターチーフのフィギュアが飾られている。これは、メディコム・トイが制作するオリジナルフィギュア「KUBRICK」の「Halo 2」版というべき、マスターチーフのKUBRICKフィギュアである。展示されているのは、実物大ではなく10倍に拡大したもの。そして、このマスターチーフのKUBRICKフィギュアは、「Halo 2」初回出荷分を購入した人の中から抽選で4,000名にプレゼントされることになっている。初回出荷分の「Halo 2 リミテッド エディション」、「Halo 2 リミテッド エディション Xbox Live同梱版」、そして「Halo 2 通常版」の全てに応募用のシリアルナンバーが同梱されており、そちらを利用して応募する。KUBRICKフィギュアは非常に人気が高く、製品によってはプレミアムが付いて取引されるほど。そのKUBRICKのマスターチーフバージョンもマニアの間で人気となるのは必至なので、ぜひとも手に入れたい一品だ。
■ 非常に細かな部分まで配慮されたマルチプレイモード
東京ゲームショウでの「Halo 2」のプレイアブル出展に備え、開発元のBungie Studiosから開発スタッフが来日している。マイクロソフトブースで開催されたプレス発表会イベントでも登壇した、Bungie Studiosのコンテンツマネージャであるフランク・オコナー氏である。今回、このフランク・オコナー氏に「Halo 2」に関する話を聞く機会を得たので、そこで得た最新情報などを紹介していこう。
まず、多くのユーザーが知りたいと思っているキャンペーンモードに関してだが、残念ながら、やはり今回も全くと言っていいほど教えてもらえなかった。ただ、アフリカのヌーモンバサという都市が今回のキャンペーンモードのカギとなること、また2年前のE3での発表会で流されたムービーの中に登場した宇宙ステーションも実際に登場すること、コブナントが地球を発見したところからストーリーが展開していくことなどが教えてもらえた。とにかく、Bungie Studiosのスタッフは、「Halo 2」の詳細に関してひた隠しにしているが、オコナー氏は「実際にプレイして、その驚きを体験すれば、私たちがなぜ詳細をひた隠しにしてきたのかがわかるはずです」と語っている。全ては11月11日になれば明らかになることだ。
ちなみに、キャンペーンモードのゲームボリュームだが、まだ完全にできあがってはいないが、確実に前作を凌駕したボリュームになるそうだ。難易度が上がり、プレイ時間もかなり長くなりそうである。この要因の1つが、敵のAIの強化だ。今回の敵A.I.は3次元で計算することになっているそうで、上下左右からの攻撃にさらされることもあるようだ。もちろん、AI強化は敵だけでなく、味方の海兵隊員の行動についても同様だ。そのため、前作以上に味方NPCとの行動が重要かつ楽しくなっているはずだ。
また、日本語化に関してだが、メニューの日本語表示はもちろんだが、シングルプレイモードのNPCのボイスも全て日本語に吹き替えられている。北米版とほとんどタイムラグなく日本語版が発売されることは、ファンにとっては非常に嬉しいはず。もちろん、日本語版を利用しても、北米やヨーロッパのプレーヤーとの対戦は全く問題なく楽しめる。その場合でも、日本語版のプレイ画面ではメッセージが日本語で表示される。
次にマルチプレイモードに関してだが、こちらは8月1日に米レドモンドで開催された「Halo 2」体験会でのものよりもさらに進化していた。まず、メニューをちょっと見ただけだが、利用できるマップは10種類以上に増えていた。また、ゲームモードもさらに増えており、その中の「Oddball」を見ることができた。これはマップ上に置かれたガイコツを奪い合い、さらにそのガイコツを保持している時間によってポイントが入っていくというシステムになっている。ガイコツを持っている間は武器が使えない(パンチは可能)ので、敵からは逃げるのが基本。壮絶なガイコツの奪い合いが繰り広げられ、非常に白熱するゲームモードという印象だった。
ゲームルールも細かな部分までカスタマイズ可能となっている。プレイ時間や勝利条件の設定などはもちろんだが、使用できる武器の制限、使用できるビークルの制限なども可能となっており、これによって様々なルールでプレイ可能となるそうだ。
また、マルチプレイモードではヘルスパックは用意されていない。これは、シールドシステムが進化したことにより、必要がなくなったからだそうだ。「Halo 2」のシールドシステムは、前作のものよりも減るスピードが速くなっている。そして、シールドがなくなると、その後1撃で死んでしまう。しかしリチャージのスピードが速くなっているため、攻撃を避けるとすぐにシールドが復活するようになっている。そのため、ヘルスパックが必要なくなったそうだ。ちなみに、シールドの残量は画面左下のレーダーの上に表示される。
マルチプレイ中のボイスチャットに関しては、チーム内でのみコミュニケーションが取れる「チームチャット」という機能が実装される。これはコントローラのあるボタンを押している間は、チームメンバーとだけ会話ができるというもので、これによってチームメンバーとの緻密な連絡を取ったり、作戦を伝えるといったことが可能となる。また、普段は距離に応じて声が届くというシステムを取っているそうだ。例えば、自分の近くにいる人には、敵・味方関係なくしゃべった声が届くことになるそうだ。これはリアルな世界での声の伝わり方を再現したものだそうで、例えば声を潜めて背後から敵に近づき、いきなり声を出して驚かせる、といったこともできるそうだ。
ちなみに、「Halo 2」では二丁拳銃モードが新たに実装されているが、この二丁拳銃を利用した場合のゲームバランスを確保するのが、今回のマルチプレイモードの開発で最も苦心したところだそうだ。例えば、二丁拳銃時には、銃での攻撃時に反動による照準のずれを大きくするといったことが取り入れられている。
このように、「Halo 2」の開発は、マルチプレイモードの開発に終始していると言っても過言ではない力の入れようとなっている。しかし、そのおかげで、「Halo 2」のマルチプレイモードは、これまでのFPSにはない、非常に多彩な楽しみ方ができる、とても遊び甲斐のある内容に仕上がっているのである。
■ コミュニティに配慮した仕組みも導入
「Halo 2」のマルチプレイモードに対する配慮は、これにとどまらない。なんと、プレーヤーのコミュニティに対する配慮まで行なわれているのである。そのなかの1つとして、クランのサポートというものがある。クランとは、ユーザーのコミュニティ組織、いわゆるギルドのようなものだが、「Halo 2」には、クランの活動をサポートする仕組みが導入されているのである。
クランを作成して登録すれば、そのクランに関する様々な情報がBungie StudiosのホームページであるBungie.netで管理される。プレーヤーは好きなクランに加入するのもいいし、友人を集めて新しいクランを作り登録してもいい。1つのクランには、最大100ユーザーが参加可能。Bungie.netでは、クランに参加するユーザーが自分の成績を閲覧したり、クランのメンバーの成績を参照するといったことが可能で、クラン内のランク付けなどにも活用できる。
もちろん、クラン間でのマッチメイキングも可能だ。それも、複数のゲームを同時進行させる形でマッチメイキングすることも可能だそうだ。「Halo 2」では、一度に最大16人でのマルチプレイが可能だが、対戦相手のクランと自分のクランのメンバーが16人以上の場合には、16人ずつの複数のゲームを同時に起動してプレイできるのだ。それにより、16人を超えるクランのメンバーが同時にプレイし、その複数のプレイ結果を集計することによってクラン間の対戦結果を得る、といったこともできるそうだ。
しかも、Bungie.net内にクランの独自ホームページが作られ、様々な活用が可能となる。そこでは、ユーザーがわざわざ統計を取らなくても、実際のプレイデータをBungie Studios側が自動的に集計し、非常に細かな情報として参照できる。例えば、敵を殺した回数などといった基本的な情報は当然として、ビークルを破壊した回数、スナイパーに狙撃された回数、手榴弾でやられた回数といったことなども細かく集計し表示されるそうだ。基本的にはPCから参照することになるそうだが、Xbox上からもその情報の一部を参照できるそうだ。とにかく、クランに関する仕組みはまさに至れり尽くせりといった内容となっている。
クランという組織は、プレーヤーがメーカーとは関係なく、コミュニティの延長線上として独自に組織するようなものだが、そのクランという仕組みをゲームメーカー側がゲーム自体に取り入れ、プレーヤー側に提供するというのは、これまでになかった試みだろう。ある意味Bungie Studiosのチャレンジなのかもしれないが、プレーヤーにとっては非常にありがたい仕組みであると言いえる。
今回、こういったお話を伺っているだけで、身震いするほどわくわくし、一刻も早く「Halo 2」をプレイしたいという感覚になった。前作「Halo」の醍醐味は、キャンペーンモードの重厚なシナリオにあったが、それは「Halo 2」にも受け継がれているはず。事実筆者自身も、「Halo 2」のキャンペーンモードに対してより大きな興味があった。
しかし、今回お話を伺って、マルチプレイモードへの興味が非常に大きくなった。ここまでプレーヤーに配慮したマルチプレイモードが搭載されているゲームは過去になかったと言っても過言ではないだろう。前作でも、熱狂的な「Halo」コミュニティが日本でも生まれたが、「Halo 2」ではそれをはるかに凌駕する、一種のブームと言ってもいいようなコミュニティが誕生する、そういった予感さえする。発売日の11月11日が非常に待ち遠しい。
□東京ゲームショウ2004のホームページ
http://tgs.cesa.or.jp/
□Xboxのホームページ
http://www.xbox.com/ja-jp/
□東京ゲームショウ Xbox情報のページ
http://xboxplaytogether.net/tgs2004/
(2004年9月24日)
[Reported by 平澤寿康]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.
|
|