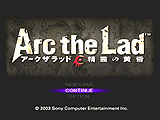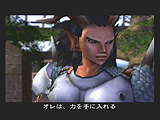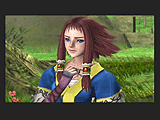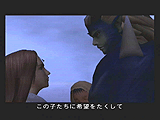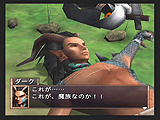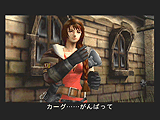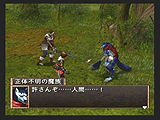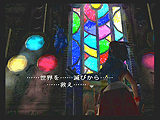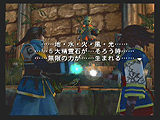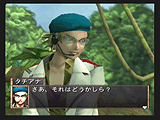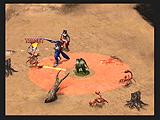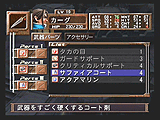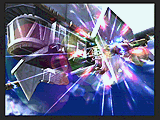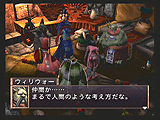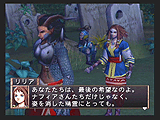| ||||
|
★PS2ゲームレビュー★
ソニー・コンピュータエンタテインメントの看板タイトルのひとつとも言える「アークザラッド」シリーズ。本作「アークザラッド 精霊の黄昏」(以下、「精霊の黄昏」)はそのシリーズ最新作である。「人間」と「魔族」ふたつの種族の対立というテーマを真っ正面からとらえていて、プレーヤーにさまざまな想いを生じさせる作品となっている。 ■ ふたつの種族が対立する世界、ふたりの主人公
人類の文明は進歩し、戦いの歴史は積み重ねられる。さらに長い時がたち、多くの資源を使い果たし、貧困と衰退が人類に影を落とそうとする時代になると人類の前に新たなる脅威が訪れる。モンスターから進化し、高い知能と独自の文化を築き上げた「魔族」である。 衰退を迎える人類と、新しい種である魔族、ふたつの種族はお互いを忌み嫌い、対立を繰り返していく。人類は精霊の力がこもった新しいエネルギー源「精霊石」を発見、過去の文明の遺産をわずかながら蘇らせ、文明と国を維持していった。しかし魔族は既にこの世界の半分を占めるほどの勢力を持ち、彼らもまた魔力の源として精霊石を必要とし、この世界に存在するけっして多くあるとはいえないその資源を人類と争っていた。 人類と魔族の対立。それが本作のテーマである。主人公は魔族の父と人間の母を持つ運命の双子「カーグ」と「ダーク」。彼らはそれぞれ人類と、魔族の未来を想い、世界を揺るがす「大精霊石」に関わる事件に巻き込まれていく。 「精霊の黄昏」は重いテーマを軸に、“飛空挺”や“魔族の文明”といった魅力的な世界観と、個性豊かなキャラクタ達が登場するRPGである。プレーヤーはカーグとダークのふたつの立場から、章で区切られたストーリーを追っていくことになる。特に中盤からはダークとカーグの運命が複雑に絡み合っていくこととなる。ヒロイン「リリア」と出会い、父と母から託された“想い”を彼らがどのように受け止め、結論を出していくか。とてもエンディングが気になるストーリーである。 ■ 答えを探し求めていくふたり ストーリーは序盤から繰り返し魔族と人間の対立が描かれていく。カーグに思いを寄せるポーレットの父ロイドは、後にダークの仲間となるヴォルクに倒されてしまう。しかしその戦いは、魔族との対立で警戒を強めていたという最悪のタイミングで起きた事件だった。ヴォルクはその戦いで妻と子を失い、人間を滅ぼすことを願う存在になっていく。人と魔族は相容れない、争う存在であることを様々なエピソードを交えて強調しつつ描いていく。 ダークとカーグの両親、ウィンドルフとナフィアは種族を超えて愛し合い、ふたりの子をなすが、世界に受け入れられず、離ればなれになってしまう。ナフィアはカーグを連れて生まれ故郷であるユーベルに帰るが、カーグに父親が魔族であることを告げられないまま時を過ごしてしまう。カーグはやがて魔族の脅威に立ち向かう辺境の勇士と成長していく。 ダークは、外見的は人間そのものに見えるカーグとは違い、どこか中途半端な“魔族モドキ”の姿をしている。そのために魔族のテリトリーで暮らす彼は、奇妙な存在として扱われ続け、非常につらい生き方を強要されている。 彼の心には父の遺言である“魔族を救え”という言葉があり、心を許した魔族に裏切られ、“力の強い存在に従う”という魔族そのものの性質に直面した事件をきっかけに、魔族を自分の力に従える事を願うようになる。 このふたりにヒロイン・リリアと、彼女を追う「ディルズバルド軍」、そして“精霊の力”が絡み合っていく。ディルズバルド軍は失われた科学を蘇らせ、強大な軍事力を背景に、各地へ侵攻を開始している。侵攻の目的は、世界のどこかにある5つの「大精霊石」。これをそろえたものは「無限の力」を手にすることができるというのだ。 急速にふくれあがるディルズバルド軍の力。彼らは主人公ふたりの前に立ちふさがる敵として存在を強めていく。その戦いの中でふたりはそれぞれ確かな仲間を得る。 そして大きな流れがやってくる。ダークはディルズバルド軍からリリアを奪還する戦いの中、同じように捕らわれていた母・ナフィアと出会う。しかし、彼女は我が子とほとんど言葉を交わすことができないままダークを庇い、敵の銃弾に命を落としてしまう。ダークとリリアはナフィアの遺言に従い「真実の洞窟」へ赴く。 遅れて到着したカーグは母の死と、そして自分が魔族の血を引く、“人間モドキ”であることを知る。自分に向けられる故郷の人々の激しい嫌悪の感情、仲間さえも魔族の血が目覚めた彼から離れてしまい、彼は傷心のままダークとリリアを追うことになる。 悲しむリリアの前でふたりは激突する。世界が受け入れなかったウィンドルフとナフィアの愛を、ふたりもまた受け入れることができなかった。しかし魔族と人が平和に暮らす奇跡の島の光景が、そしてそれを踏みにじるディルズバルド軍がふたりの心を乱していく。ふたりはまた別れ、仲間と共に魔族と人の両方を脅かす存在であるディルズバルド軍と戦っていく……。 大きなエピソード以外にも、彼らの仲間の話や、世界の描き方など細部まで制作者の思い入れが感じられるのが本作の魅力。街それぞれの特色や、魔族の考察、「仲間」の描き方は好感が持てる。またディルズバルド軍の「暴挙」は、人の元での世界統一という視点でカーグに、力での行ないという視点でダークのある意味の“理想”であるところも興味深い。テーマを元にきちんとエピソードを積み重ねていく感触のある作品である。 ■ オーソドックスながら楽しい戦闘システム 戦闘はターン制で、シミュレーション要素もあるシステム。また、普通のRPGよりイベント要素が強いのも特徴だ。敵の向きも大事な要素になっていて、背後から攻撃すれば、大きなダメージを与えることができる。 人間は“特技”、魔族は“魔力”という特殊能力を持っていて、レベルが上がるごとにいろいろな能力を使うことが可能。カーグとダークはふたつの力を使いこなすことができる。また、キャラクタそれぞれには武器による有効範囲があって、スピード、移動範囲と組み合わせての有効な攻撃を模索する楽しさがある。 攻撃によって経験値が違ってくるので、低いレベルのキャラクタにとどめを刺させるようにするなど、バランスをとることもできる。あえて特定のキャラクタを成長させるのも面白いかもしれない。戦闘開始の際には、キャラクタを不参加にもすることができるので自由な成長が可能だ。 派手なエフェクトとしてはキャラクタ達の“テンションゲージ”が上がった際の“支援攻撃”がかっこいい。非常に攻撃力が高いのも魅力で、序盤の戦闘では特に頼りになる。テンションは特殊能力でも上げられるので、ボス戦にも有効だ。 本作の戦闘は割と「ストーリーメイン」な要素があって、数だけ取り出すと他のRPGより少な目だ。道の障害物をひたすら取り除くように進む戦闘だらけのゲームとはちょっと違ったアプローチである。しかし、もちろん「経験値稼ぎ」も可能で、強いキャラクタを目指すプレーヤーにはそういったプレイも可能になっている。 また「闘技場」という場所も用意されていて、さまざまな特殊ルールでの戦闘を楽しむこともできる。指定された回数を勝ち抜くことで特別なアイテムがもらえ、キャラクタは強力になる。やりこみ要素も、きちんと兼ね備えているのだ。 ■ テーマに正面から取り組んだ意欲作 小説やゲームでは、ハーフエルフやダンピールなど「ふたつの種族の血を引く苦しみ」というものを描いた作品がいくつもあるが、この「精霊の黄昏」の特徴はそういった特別な運命が、カーグとダークたったふたりだけにもたらされていることだろう。世界のどこを旅しても、魔族と人間の子供は存在しない。つまり、本当にこの世界では許されない、すべての生き物が受け入れることができなかった「奇跡」だったのだ。 彼ら自身、自らに流れるもう一方の血を否定しながらも、ウィンドルフとナフィアの「愛」は、確実にこのふたりに受け継がれている。カーグもダークも裏切り者を「生かす」という決断をし、自分のためではなく、本気で「世界のため」に行動していく。特異な愛が産んだ、この特異な主人公の行動に触れ、半ばあきれながらもじょじょに彼らを理解していく仲間達の心情も丁寧に描かれている。 エピソードに関しては最近のRPGに比べると“ちょっとゲームらしすぎる”というものもあるのだが、なによりきちんとひとつのテーマを根底に置き、物語を紡いでいるその姿勢はとても好感が持てる。 魔族の描写は、特に魅力的だ。魔族というのはよくある物語だと、人間の立場からすればいわゆる「悪」を具象化したモノ。筆者としては、お話としては都合がいいが「構成しているものがすべて“悪”という世界って、存在できるの?」という疑問があった。 本作ではここをきちんと考証して描いている。この作品では、魔族はモンスターから進化していく存在であり、ダークの行動に触れ、とまどいながらもさまざまな考えを抱いていく仲間達の描写は、とても面白い。魔族という存在がどう変わっていくのか、そこに対する考察がある。 その代表とも言えるのがデルマだ。自業自得でダークに倒された兄だが、彼女は「強者に従う」という魔族の本能に逆らう。デルマは肉親の情に従って、ダークに惹かれている心をかなぐり捨てて刃を向ける。しかし、それさえもダークは「強い魔族が必要だから」という理由で許し、兄を討ったことを後悔している素振りを見せる。ダークの心に混乱しながらも、だんだんデルマの行動も変化していく。 キャラクタの描写は細かく、プレーヤーはいろいろな思いを抱いていくだろう。テーマにそって描かれる作品ならではの、「考えさせられる」ゲームである。
□ソニー・コンピュータエンタテインメント のホームページ (2003年4月24日) [Reported by 勝田哲也] また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |
|
|