レビュー
「ユミアのアトリエ」レビュー
次世代「アトリエ」シリーズを目指した新作は略式調合やスピーディなバトルなど進化を感じる大作
2025年3月20日 00:00
- 【ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~】
- 3月21日 発売予定
- 価格:
- 9,680円(PS5通常版)
- 8,580円(PS4/Nintendo Switch通常版)
- 13,500円(PS5/Steamプレミアムボックス)
- 12,400円(PS4/Nintendo Switchプレミアムボックス)
- 23,700円(PS5/Steamスペシャルコレクションボックス)
- 22,600円(PS4/Nintendo Switchスペシャルコレクションボックス)
コーエーテクモゲームスより「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」がプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC向けに3月21日に発売される。
本作は、1997年に発売された第1作目「マリーのアトリエ」から続く「アトリエ」シリーズの26作品目だ。今回、一足先にプレイする機会を得られたので、そのレビューをお届けしよう。システムの基本的な部分に関しては先日の台北ゲームショウバージョンで解説しているので、今回は主としてそれ以外を重点的に見ていく。
次世代アトリエは「秘密」シリーズのシステムを継承しつつも、より遊びやすく
1997年に発売された「マリーのアトリエ」に端を発する「アトリエ」シリーズは、現在までに25作品が登場し、累計で700万本以上を売り上げている大ヒットタイトルとなっている。そのシリーズ最新作として発売される「ユミアのアトリエ」では、錬金術が禁忌となった時代が舞台だ。まずは、そのストーリーを見ていこう。
とある大陸に存在し、かつて栄えたアラディス帝国は、錬金術により他国を寄せ付けないほどの発展を遂げる。しかし、突如として発生した謎の天変地異により、滅びの時を迎えたという。それから数百年後、錬金術は“滅亡を招く危険な術”とされ、“悪”であり“禁忌”となった時代。来るものを拒む秘境と化した大陸に一人の錬金術士、ユミア・リースフェルトが足を踏み入れる。3年前、とある事故で母親を亡くしたことをきっかけに、彼女は自らが錬金術士の家系であると知り、同時に多くの疑問を抱く。なぜアラディスは滅びたのか? なぜ錬金術は“禁忌”となったのか? 大陸にすべての真実が眠ると信じて、失われし歴史を追うユミアの旅が今、始まる。
プレーヤーは錬金術士のユミアとして、真実の歴史を追う冒険へと旅立つ。ゲームを始めると、画面に映し出されるのは、おそらくは物語の佳境となるシーン。そこで1人はぐれてしまったユミアを操作していくことで、チュートリアルが進んでいく。
アクションに関しては移動の他、狭い場所はしゃがんだり四つん這いでの通り抜け、最大3段の壁ジャンプ、装備している銃杖を使用してのギミック操作などが用意されており、序盤で一通りの操作が体験できる仕組みだ。戦闘シーンも盛り込まれているが、戦いに関しては後述しよう。
無事に仲間と合流できると、ストーリーの核心に迫ると思われる敵キャラクターが登場し、その後にいよいよ本編スタートとなる。
主人公のユミアは滅びたアラディスを調査する調査団の一員だが、禁忌である錬金術を使える錬金術士のため監視対象ともなっている。そのような理由から、監視役として付いてくる2人のデューラー兄妹とパーティを組み、各所へと出かけていくことになるのだ。
今回はPS5でプレイをしたが、前作以上に登場キャラクターのモデリングが非常に良くできていると感じられた。表情も豊かで感情がしっかりと顔や眼に表れるため、喜怒哀楽といったものも読み取りやすい。そのためか、禁忌の術を扱うユミアに対しイベントにてNPCなどから向けられる視線が、序盤はあまり好意的ではないと感じられ、少々の居づらさを感じてしまうほど。
より手軽に行なえるようになった、フィールドでの採取行動
「アトリエ」シリーズを通しての3本柱となるのが採取・調合・戦闘だが、採取に関して大きくパワーアップしたところは、道具を使っての採取速度が上がったことだろう。
これまでは、手で採る採取に関しては走りながらできるようになっていたものの、杖などの道具を使う場合はいったん立ち止まる必要があった。これが今作では、走りながら銃杖を振って採取でき、走っている状態は維持したまま、採取が終わると再び走り出してくれるようになっている。銃杖を振るといったアクションはカットされないものの、スピーディになったことは確かだ。もちろん、走りながらの採取も非常にスムーズなので、むやみやたらに駆け回って採取しまくってしまう楽しさがあった。
フィールドは、「ライザのアトリエ3」に引き続きオープンフィールドとなっており、探索できる範囲はかなり広大になっている。そのため、ある程度楽に冒険できるようになるファストトラベルやジップラインといったシステムは、今作でも健在だ。ただし、いずれも一度はその場所へと赴いてシステムを起動する必要があるので、それまでは足を使っての地道な移動となる。
とはいえ、それが非常に楽しいのも本作の特徴といえる。戦闘に関してはシンボルエンカウントシステムを採用しているので、敵に触れなければ戦いが始まることはないため、上手に避けさえすれば通行不能な場所以外は探索が可能。もはやシナリオそっちのけで広大なマップ上を駆け巡り、材料を採取しまくったりフィールド上のギミックを動かしてみるなどができてしまうのが、オープンフィールドでプレイできる本作の良いところだろう。
シナリオを進めていけば、各地域の開拓任務が解禁される。これは名前の通り、マップの探索やギミックの開放などをすることで進む任務になっている。開拓には多くの目標が用意されており、それらを達成して開拓率がアップしていくと、開拓クエストが発生することも。クリアすれば、今後にありがたい報酬を受け取ることもできるので、積極的にクリアしていきたい。ここも、順番を問わずに実行したい選択肢から進められるので、マイペースにできるのが良いところだ。
バトルシステムは、これまで以上にアクション要素が強化
戦闘は前作譲りのシームレスバトルとなっているが、もちろん随所に改良が施されている。すぐにわかるのは、戦闘開始までの時間の短さだろう。
敵とエンカウントするとそのまま戦闘シーンへと移行するのだが、以前は最初に武器を構えるなどのポージングタイムの後にバトルスタートとなった。しかし今作ではそれもなくなり、即座にバトルが始まるようになっている。
戦闘終了後も、これまではバトルリザルト画面が表示され、その後に行動が可能になっていた。これも今作ではよりスムーズに変化。戦いが終わるとユミアが靴を直すアクションが入り、その直後から動くことができる。経験値入手の情報は、その後に画面左側に表示されるようになった。
その結果、これまでは戦闘終了後にやや待たされる感があったがそれも無くなり、本当の意味でシームレスバトルになったといえるのだ。レベルアップがあったときは、その演出が入るためこの限りではないが、サクッと始まりサクッと終わるという印象に変わったのは非常に大きい。
バトル全体としては、戦闘の始まりから終わりまでとにかくスピーディの一言。これまでの戦闘は早いものの、その前後のもたつきがちょっと……と感じていた人には、間違いなく朗報だろう。筆者としても、これは諸手を挙げて歓迎した部分だった。
戦闘システム自体は、各キャラクターが持つスキルが○×△□ボタンに割り当てられているので、攻撃時はそれを押すのみと極めてシンプル。攻撃アイテムを装備していれば、R1ボタンを押すたびにスキル攻撃とアイテム攻撃が入れ替わるので、スキル攻撃の回数が尽きたらアイテム攻撃に入れ替え、回復した頃合いを見計らって再び戻すという連携を取ることで、敵に多段攻撃を仕掛けることも可能だ。
敵が赤く光ったら敵の攻撃の合図なので、L2ボタンでガードするか、L2+Lスティックで素早く避けよう。このあたりはアクションゲームを得意とする人なら、ちょっとした敵の行動にも反応して回避できるので、別のゲームを遊んでいるような感覚で楽しめるだろう。
戦闘に関しては、組み込まれているシステムが思ったよりも多く、その説明も序盤に固まっている。適当にプレイしていると、先に紹介されたテクニックを覚えないうちに次の技のチュートリアルが始まってしまい、せっかくのワザも使いこなせない事態に陥ってしまう可能性があると感じた。そうならないために、チュートリアルをある程度こなしたところでヘルプを開き、改めてシステムを見ていくことを勧めたい。レンジ切り替えやジャスト回避など、戦いを優位に進めるシステムが数多く盛り込まれているので、ゆっくりと確実に覚えていきたいところ。
また、展開がスピーディになったことで、気がつけばHPが無くなり戦闘不能に陥っているということが何度もあった。何故だろうと思い途中で自分のプレイを見返してみると、攻撃時の演出が非常に気持ち良すぎるためか、あまり防御せずにアタックばかりを繰り返していたのが原因らしい。
攻撃エフェクトは派手で見栄えも良いため、行動がついそちらばかりに傾いてしまうのだが、防御も重要。今作では攻撃の影に隠れがちな感じがしたので、筆者のようにユミアを戦闘不能にしないよう、しっかりとガードを活用して欲しい。
また、戦闘をせずに遠出することができるため、ろくな準備もせずに遠方まで出かけ、そこで接敵した強敵に負けてしまうということもある。探索は楽しいのだがパーティも鍛える必要があるので、適度に戦うことも忘れずに。
ルールはシンプルで間口は広く、それでいて底知れぬ奥深さを持つ調合システム
そして3本目の柱となる調合に関しては、まったくの新しいシステムが導入された。基本的には、画面に表示されたスロットと呼ばれる場所に、採取した材料を投入していくというシンプルなものだ。このとき、その材料が及ぼす影響範囲が表示されるのだが、これが広いほど結果的には良い仕上がりになるというもの。最初のうちは、スロットに入れる材料選びの時は範囲の広さだけに注目していても問題ない。非常にわかりやすく、シリーズ初心者でも悩まずにできると感じた。
ただし、こだわって調合しようとすると、非常に複雑になっていく。投入する材料の品質や持っている属性、そして影響範囲と、それらを考慮して材料を選ぶ必要があるので、思い通りのアイテムを産み出すには試行錯誤が要求されるのだ。
とはいえ、そんな面倒なことはイヤだという人もいるだろう。そんな時にオススメできるのが、おまかせ材料投入。実行時に、どの要素を重要視するかを選択するだけで、手持ちの材料から目的に合った材料を選んで自動で調合してくれるのだ。しかも、思った以上に賢く作業してくれるので、普通にプレイしていくのであればおまかせ調合1本でも問題ないと思えたほど。もちろん創意工夫して調合すれば、とんでもなく威力のあるアイテムを創れたりはするのだが、難しそうに見える調合の敷居を大幅に下げ、新規ユーザーでも問題なく楽しめるようにしてあるのはグッドだ。
調合先の種類を増やすにはレシピを覚えなければならないが、今作では必要な知識と残響片を集めることでアンロックできるようになっている。必要知識は素材を集めることで、残響片は戦闘に勝利したりフィールドの各所にあるマナ間欠泉などを調べることで手に入る仕組みだ。レシピ増加のためにもフィールドを探索しなければならないというのは、なかなかうまくシステムが組まれているな……と、思わず感心した。
加えて、残響片を揃えられればレシピのレベルアップも可能となっているのも特徴だ。例えばシリーズお馴染みフラムの場合、レシピのLv.1はレシピ習得だが、レベルアップして2になると最初から品質アップの効果が入り、さらにレベルを上げて3にすれば作成される個数が増えるなど、調合しただけで多数のメリットが付属してくる。
これまでは、調合時に材料に工夫を凝らすなどすることで、品質や個数アップといった+αを得ることができた。しかし、本作ではレシピのレベルを上げるだけでそれに近い体験を得られるので、調合であれこれ考えるのは苦手、という人でもプレイしやすくなったといえるだろう。
代わりに、残響片をゲットするためには探索を重ねなければならないため、時間を鬼のように吸い取られるのが怖いところ。もっとも、その間も冒険が進むため苦にならないどころか楽しいので、時間を消費しているという感覚が起きないのが困りものだが(笑)。
今作で非常に便利だと感じたのが、フィールドで行なえる略式調合だ。作れるアイテムは限られているものの、場所を問わずに調合できるというのが優れた点。特に、仕掛を発動させたり敵に撃ち込める通常弾や、非戦闘時にパーティ全員のHPを25%回復させてくれる初級包帯は使用頻度が多いため、これをアトリエに戻り調合していたのでは手間となってしま。しかし略式調合を活用すれば、それらが必要になったときに材料などがあればフィールド上で即座に創り出せるのは、便利この上なし。
ハウジングやスキルツリーなどが用意され、より自由度が向上
「ユミアのアトリエ」で体験できるハウジングは、各所にアトリエの出張所のような拠点を建築できるというもの。方法も簡単で、大規模ランドマークと呼ばれる場所を解放することで得られる専用の空きスペースを確保後に、ハウジングコマンドから建てたい家を選ぶのみ。作成には相応の資材が必要となるが、調合の材料とは別なので、採取しまくっていれば材料には困らないはずだ。ただし、必要量が多いので、探索中こまめに採取するのを忘れないでおきたい。
また、拠点外側に設置する柵や、内部に配置する小道具なども作ることが可能だ。こちらも資材が必要となるが、作成して設置すればインテリアの作成や調合、レシピ想起などができるようになるほか、パーティキャラクターの着替えなどもできるようになる。もちろん壁や床、椅子といったインテリアも作って置けるので、凝り性の人にはたまらないだろう。このインテリアをあっちに置いて、床はこれにして……という作業だけで1日が終わってしまうほどにはハマれるので、注意したい(笑)。
ほかにも、キャラクターを育成するシステムとしてスキルツリーがある。ツリーは採取・調合・戦闘の3種類に分かれており、戦闘などで入手できるスキルポイント(SP)を消費することで、さまざまなメリットを享受することができるようになる。各プレーヤーのプレイスタイルに合わせた柔軟な育成方法が取れるため、好きなように育てられるのが嬉しいところ。筆者は探索メインで進めていたので、採取が有利になるようなスキルを中心にツリーを開放していったが、こういう自由度があるのも良いところだ。
夢中になれるゲームシステムは相変わらずで、どれほど時間が合っても足りないほど
今作も、“あっちも行きたいしこっちも調べたい、アレも調合したいけど例のクエストも気になる、あの敵も倒さないと”といった感じで、とにかくやれることがてんこ盛りに詰め込まれていた。それでいて広大なワールドマップに謎多きストーリーなどといった要素もあり、もはや本シリーズは中堅タイトルではなく、ボリューム的にも大作に上り詰めたと確信したほど。
その分、システム面で覚えることが多くなったため、新規ユーザーは序盤を越えるのが少々苦労するかもしれないと感じた部分もあった。もう少しチュートリアルの密度が薄く広くなれば、特に戦闘システムなどは新たに始めるユーザーも把握しやすくなりそうなので、その辺りは今後に期待したい。
とはいえヘルプが非常に充実しており、分からなくなった時点で随時参照すれば困ることはないはず。今作から入る人は、このヘルプ機能を活用すれば充実したアトリエライフを送れるので、そう問題はないだろう。
キャラクターたちの可愛らしさや筆者にマッチした良きBGM、探索する楽しさに調合の面白さ、そしてストレスの溜まらないスピーディな戦闘に、大ボリュームで抜群のコストパフォーマンスと、JRPGの正統な進化を体験できる「ユミアのアトリエ」。今のRPG好きはもちろん、地道なレベルアップを行う昔ながらのRPGをプレイしてきた人も、間違いなく楽しめるオススメの1本だ。
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※画面はSteam開発中のものです。

























































![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)






![ホリ ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 ミストブラック [NSX-126] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0031/4961818042506.jpg?_ex=128x128)


![任天堂 【Switch2】Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン [BEE-A-JABAB NSW2 ジョイコン2 パ-プルグリ-ン] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0049/4902370553871.jpg?_ex=128x128)






![コナミデジタルエンタテインメント 【PS5】がんばれゴエモン大集合! [ELJM-30911 PS5 ガンバレゴエモン ダイシュウゴウ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0057/4988602179873.jpg?_ex=128x128)


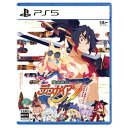
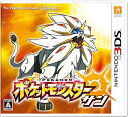

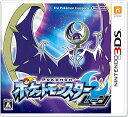





![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア【Blu-ray】 [ 古谷徹 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4722/4934569364722.jpg?_ex=128x128)
![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム0083 -ジオンの残光ー【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4715/4934569364715.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME(通常版)【Blu-ray】/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/634/kixa-952-3.jpg?_ex=128x128)
![あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7808/4580798287808_1_2.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 4(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1352/4534530161352.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 5(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1369/4534530161369.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 7(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1383/4534530161383.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 6(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1376/4534530161376.jpg?_ex=128x128)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0051/4934569370051.jpg?_ex=128x128)