【特別企画】
「エグゼドエグゼス」が稼働40周年! 昆虫型の敵、敵弾、浮遊要塞が次々と迫る名作シューティングをプレイバック
2025年2月8日 00:00
- 【エグゼドエグゼス】
- 1985年2月 稼働開始
カプコンが1985年2月に発売したアーケードゲーム「エグゼドエグゼス」が、2025年2月で稼働40周年を迎えた。
本作は、自機のカーネル号(2Pはサージェント号)を操作し、ショットを撃って敵キャラを倒していく縦スクロールシューティングゲームで、2人同時プレイも可能。操作は8方向レバーで自機の移動、ボタンはショットとクラッシュの2ボタンを使用する。クラッシュは使用回数に制限があるが、画面内の敵弾をすべて消す効果を持つ。敵や敵弾に当たるとミスとなり、自機のストックがゼロになるとゲームオーバーになる。
以下、筆者が今でも大のお気に入りである本作の特徴と、独創的なアイデア、演出の数々を思い付くままに振り返ってみた。
1面から激しい攻撃の連続、巨大浮遊要塞のド迫力に驚愕
筆者が本作に最初に出会ったのは1985年の秋頃、田舎にあった土間を改造(!)したゲームセンターだった。普段、見慣れていたほかの筐体よりモニターのサイズがもひと回り大きい、専用のテーブル筐体で稼働していたこともあり、店に入った瞬間にすぐに目を引かれた。
昆虫をモチーフにした不気味な敵キャラ、まるで本物の金属でできているかのような、リアルに描かれた地上のブロックや砲台などのビジュアルが抜群にカッコよく、当時からシューティングゲームが大好きだった筆者は衝撃を受けた。
だが、100円玉を投入する決断がなかなかできなった。なぜならカッコよさと同時に「すごく難しそう」との印象も持ったからだ。デモ画面をよく見ていると、一番のザコと思われる敵が出現直後に弾を、しかも2発同時に次から次へと撃ってくる。加えて、途中からいかにも強そうな巨大昆虫が出現し、容赦なく複合攻撃を仕掛けてくる様子を見て「あっという間に終わりそうだなあ……」と、まったく自信が持てなかった。
実際に遊んでみると案の定、1面から息を継ぐヒマがないほどの激しい攻撃が繰り返された。デモ画面で見たザコ敵の攻撃は何とかしのいだかと思ったら、今度は画面の下からトンボの編隊がいきなり出現し、しかも弾を時折3発同時に撃ってくるので凄まじい恐怖感に包まれた。
本作を最初に遊んだときに「とにかく腕が疲れる!」との印象も持った。地上のマップに固定された砲台、あるいはレーダーはショットを1発当てただけでは破壊できないものが大半で、前述した巨大昆虫も耐久弾数が10~15発もあるため、連射のスピードと長時間押し続ける持久力が同時に求められた。
自機のショットの射程が短いことにも最初は戸惑った。特に、初期状態では射程が画面の半分少々とかなり短く、たとえ危険だとわかっていても多くの場面で接近戦を強いられる。たまに出現する丸型のPowアイテムを取ると、ショットがパワーアップして射程が長くなる。パワーアップに成功すると派手なジングルが流れることもあり、テンションが大いに上がった。
各ステージの最終地点には、ボスキャラにあたる巨大な浮遊要塞が待ち構えている。最終地点に近付くと不気味なBGMに切り替わり、やがて浮遊要塞が出現する演出もすごい迫力があった。後半のステージでは、浮遊要塞が2回も3回も出現するのが当たり前に。しかも長時間戦っていると画面の下部まで接近してくることもあり、生きた心地がしないほどの恐怖感に何度も包まれた。
とにかく難しかったが、連射をしまくり敵を倒す快感、ビジュアルのカッコよさ、そして独特の澄んだ音色のメインBGMもとても気に入り、本作はしばらくの間、どこのゲーセンでも見掛けたら必ず遊ぶようになった。
お小遣いをシェアして楽しんだ2人同時プレイ。「ネームレジスト」の演出にも大感動
筆者の田舎にあったゲームコーナーでは、100円で2人同時に遊べる料金設定になっていた。当時は2人同時プレイ可能なシューティングゲームが珍しかったこともあり、筆者の友人間ではお小遣いの残高が多いほうが、少ないほうの仲間を誘う形でしばしば遊んでいた。「こないだは、お前におごってやったから、今日はお前がおごれ!」と、ある種の貸し借りをしながら楽しんだことでも本作は思い出深い。
特定の敵キャラを倒すと、野菜や果物などをモチーフにした得点アイテム、フードが随所に出現するのも本作ならではの面白いところ。またPowアイテムを取ると、画面内のすべての敵をフードに変える効果があり、特に巨大昆虫を1万点の高得点がもらえるジャンボイチゴに変身させたときは実に快感だった。
1面の終盤に、1個だけ出現する丸型のPow、あるいは高得点のジャンボイチゴを、どちらが先に取るのかで口論になることもあったが、筆者の友人間では本作を嫌う者は誰もいなかった思う。後に本作がファミコンに移植されると、ゲーム仲間の何人かがファミコン版を発売直後に購入したのが、その何よりの証拠だろう(筆者はお金がなくて買えなかったが……)。
冒頭で説明したように、本作にはピンチ回避の際に役立つ、敵弾を消す効果のあるクラッシュという面白いシステムがある。2人プレイ時は、クラッシュのストックが共用になるため、どこでクラッシュを使うのか、あるいはクラッシュのストックが増える効果を持つアイテム「佐吉」をどっちが取るのかでも、しばしば友人同士で相談、あるいは衝突したこともおぼろげに記憶している(※「佐吉」を取ると5000点のボーナス得点が入るから)。
本作では、ゲームオーバー時の得点が上位5位以内に入るとネームレジストに移行し、自分の名前を書き込むことができる。同じカプコンの「ソンソン」と同様に当時としては珍しい、ひらがなでの入力になっていたが、ある日どこかのゲーセンに出掛けたら100万点を超えるハイスコアを初めて目撃し、「何て上手な人なんだ!」と驚いたのと同時に「つかれた!」と名前に書いてあったので、思わず笑ってしまったことも今なお忘れ難い。
もうひとつ、本作の「ネームレジスト」で衝撃を受けたのが、1000万点達成時の特別な演出だ。本作は自機のストックがゼロになるまでエンドレスで続くが、1000万点に到達すると画面に「おめでとう」と表示されてプレイヤーを祝福する曲が流れ、その場でゲームオーバーになる。さらに「ネームレジスト」に移行すると、通常とは違う特別な曲に変わる、今も昔も珍しいアイデアを導入している。
筆者がこの演出を初めて知ったのは、実はゲーセンではなく、1986年にアルファレコードが発売したゲームミュージックアルバム「カプコンゲームミュージック」だった。本アルバムのカセットテープ版を持っていた友人から借りて聞いてみたら、今までにまったく聞いたことがない、すごくカッコいい曲が流れたのでびっくりした。だが、ライナーノーツが付いていない状態でテープを借りたので、いったいどこの、どんな場面で流れる曲なのか、しばらくの間まったくわからなかった。
それから数年後、どんなきっかけだったのかは忘れたが、未知の曲が1000万点達成時にしか聞けないものだと判明したときには大いに感動した。なお余談になるが、本作の曲は今でも大好きで、「お仕事中BGM」としてたまにではあるが聞いている。
本作はNintendo Switch、プレイステーション 4、Xbox One、Steamで配信中の「カプコンアーケード 2ndスタジアム」にラインナップされているので、今でも手軽に遊べる。
「カプコンアーケード 2ndスタジアム」版は連射ボタンをはじめ、失敗してもやり直せる「巻き戻し」や、ゲームの途中でいつでもプレイデータをセーブできるなど、数々の便利機能を搭載しているのも嬉しい。さらに課金アイテムの「無敵」を購入すれば、自機を無敵状態することも可能なので、1000万点達成の演出を見たことない人は、ぜひ一度ご覧になってはいかがだろうか。
・PS4版「カプコンアーケード 2ndスタジアム」のストアページ
・Xbox版「カプコンアーケード 2ndスタジアム」のストアページ
・Switch版「カプコンアーケード 2ndスタジアム」のストアページ
・Steam版「カプコンアーケード 2ndスタジアム」のストアページ
さらに、本作の開発を手掛けた元カプコンの岡本吉起氏が、自身のYouTubeチャンネルで当時のエピソードを語った動画が公開されているので、興味がある方はこちらも併せてご覧になるといいだろう。
(C)CAPCOM
































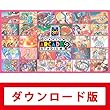








































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)











![スクウェア・エニックス 【PS5】ドラゴンクエストIII そして伝説へ… [ELJM-30512 PS5 ドラゴンクエスト3] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0376/4988601011815.jpg?_ex=128x128)



![PS5 シティーハンター COLLECTOR’S EDITION[サンソフト/クラウディッドレパードエンタテインメント]《発売済・在庫品》 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/482/game-0033624.jpg?_ex=128x128)














![プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第4章(特装限定版)【Blu-ray】 [ 秋谷有紀恵 ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5743/4934569365743.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】ミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾 忍術学園 学園祭【Blu-ray】(舞台写真L判ブロマイド(山田利吉・小松田秀作)) [ (ミュージカル) ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1228/2100014781228.jpg?_ex=128x128)
![舞台『刀剣乱舞』蔵出し映像集 -士伝 真贋見極める眼 篇ー (CD 付き初回限定版)【Blu-ray】 [ 後藤大 ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6112/4988104156112.jpg?_ex=128x128)


![OVA版ロードス島戦記 デジタルリマスターBlu-rayBOX スタンダード エディション【Blu-ray】 [ 草尾毅 ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8407/4988111908407.jpg?_ex=128x128)
![映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち 数量限定豪華版≪とかいを映すうるうるアイズぬいぐるみセット付き≫【Blu-ray】 [ ペンギンボックス ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5935/4935228215935_1_2.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)【Blu-ray】 [ 富野由悠季 ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9963/4934569369963.jpg?_ex=128x128)