インタビュー
「ELDEN RING」フロム宮崎英高氏「今まで通りの作り方をこれからも変えない」
SIE、「PlayStation Partner Awards」メディアインタビューを実施
2022年12月2日 18:00
- 【PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia】
- 12月2日 発表
12月2日にソニー・インタラクティブエンタテインメントより発表された「PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia」。本稿では会場で実施されたメディアインタビューの模様をお伝えする。
インタビューに登壇したのは、フロム・ソフトウェア「ELDEN RING」ディレクターの宮崎英高氏やカプコン「バイオハザード ヴィレッジ」プロデューサーの神田剛氏など、各ヒットタイトルを代表する開発者の面々。ぜひご覧いただきたい。なお「原神」でGRAND AWARDを受賞したHoYoverseはインタビューを辞退している。
フロム・ソフトウェア「ELDEN RING」ディレクターの宮崎英高氏
「ELDEN RING」:GRAND AWARD、USERS’ CHOICE AWARD受賞
――「ELDEN RING」がここまで人気を獲得できた理由は?
宮崎氏:正直、あまり分析できていません。売上が高いのは確かなのですが、なぜかはわかりません。なので、再現しろと言われても困るんです(笑)。ただ感覚としてあるのは、今まで通りの作り方をこれからも変えるつもりはないということです。深く分析して、同じ成功を求めると邪念が生まれそうなので、やめておきたいなと(笑)。ただ今回のようなことはありがたいですし、幸運なことだと感じています。
――世界的な売上が1,000万本を超えて世界的デベロッパーとなりましたが、次の目標はありますか?
宮崎氏:自分たちが世界的デベロッパーとなった実感はありません。今まで通り、我々らしいものを作った結果が「ELDEN RING」です。これからも同じことを続けていきたいですし、より面白い、我々らしいものを作りたいと決意しています。その中でユーザーの皆さんの評価は、そうしたものをバックアップしてくれる環境につながっていくと思います。
――発売後、印象に残っているユーザーからの声はありますか?
宮崎氏:ユーザーからの直接の声はあまり直接は見ないことにしています。というのも、すべてのユーザーの声は聞けませんし、たまたま聞いた意見が自分の中に強く入り込んでしまうと、調整や方針に影響してしまうからです。それが怖いので、直接的な意見を聞かないように注意しています。
ただ皆さんの反応の中では、初めて我々のゲームに触れくださった方が多かったなと。その反応は阿鼻叫喚するようなものが含まれていて、懐かしい気持ちになりました。「ダークソウル」がそうだったんですよね。そういえばそうだったと久しぶりに同じ感覚を味わえて嬉しかったです。初めてやると刺激的なシリーズだと思うのですが、そうした刺激を楽しんでくれる新鮮さや思いを新たに聞くことができて、個人的にも嬉しかったです。
アニプレックス「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」 「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」製作委員会一同
「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」:PARTNER AWARD受賞
――アニメ「鬼滅の刃」のゲーム化で、プレッシャーや大切にした要素はありますか?
製作委員会一同:「鬼滅の刃」は、原作やアニメーション、見ている人が多い作品ということで、そうした人にも楽しんでもらえるように作りました。その上で、ゲームだからこそ実現できる要素として、自らが炭治郎となってストーリーを体験できたり、様々なアクションを自分の操作で体験できたりする部分を意識しました。
また本作で初めてゲームをする方もいることを想定して、誰でも簡単操作で派手なアクションを楽しめるように細かな調整を重ねていきました。
――アニメ「鬼滅の刃」としては初めてのゲーム化ですが、手応えはいかがでしたか。
製作委員会一同:発売するまでは期待と不安がありましたが、結果としては日本の方にも海外の方にも楽しんでいただけました。多くの人に届けることができて、関係各社やプレーヤーのみなさまに感謝したいと思います。
――キャラクターの紹介映像が好評でしたが、力を入れた所はありますか?
製作委員会一同:アニメのゲーム化ということで、キャラクターのアクションの表現をしっかりと伝えられるように意識しました。キャラクターの紹介映像では、アニメにあるカメラワークだけでなく、ゲームならではのカメラワークだったり、アクションの気持ちよさが伝わるようなシーンを入れました。
コナミデジタルエンタテインメント「遊戯王 マスターデュエル」プロデューサーの米山実氏、ディレクターの吉川貴彦氏
「遊戯王 マスターデュエル」:PARTNER AWARD受賞
――「遊戯王 マスターデュエル」はここまでのヒットは想定していたのでしょうか?
米山氏:「遊戯王 マスターデュエル」は対戦者や観客が楽しめる「オンライン遊戯王」として作りました。「遊戯王」ファンを中心に反響をいただいて、その熱量が口コミとなって拡散していきました。そのことで、普段から「遊戯王」に親しんでいない人にも広がっていったのは想定外でしたし、嬉しかったですね。
――本作はマルチプラットフォームで展開しています。これを実現するための苦労などを教えてください。
吉川氏:プラットフォームが様々にあるなかで、異なるUIでも気持ちよく遊べるようにそれぞれを開発してくのは苦労しました。PS5のようなハイスペック機では4Kのグラフィックスや迫力のある映像、演出にこだわりましたし、モバイルなら手軽に遊べるようになど、スペックに合わせて作っていっています。苦労はしましたが、作り込んだことで気持ち良く遊べる環境が整ったのではと思います。
――「遊戯王 マスターデュエル」は今後、「遊戯王」のデジタルゲームとしてどのような立ち位置で展開していくのでしょうか。
吉川氏:「遊戯王 マスターデュエル」は、もともと「遊戯王」のファン向けに作っていたタイトルです。なので引き続き、「遊戯王」が好きな方に向けて、競技性にフォーカスして注力していけたらと考えています。
一方で「遊戯王 デュエルリンクス」というタイトルもあるのですが、こちらは「遊戯王」の世界観が好きな方に向けています。「遊戯王」のデジタルゲームとして、それぞれの強みや特徴を出して「遊戯王」の素晴らしさを届けていきたいと思います。
スクウェア・エニックス「ファイナルファンタジーXIV」リードプロジェクトマネージャーの松澤祥一氏、リードマーケティングプランナーの小野塚由紀氏
「ファイナルファンタジーXIV」:PARTNER AWARD受賞
――「FF14」は2023年で10周年を迎えるが、所感を教えてください。
小野塚氏:「新生エオルゼア」から10周年ということで、私自身は「新生」の直前から関わっていますが、気づけばあっという間の10年でした。このタイトルに関わるチームは停滞しない、チャレンジするという精神があります。自ら目標を作って、そのゴールに向かっていくことを繰り返していくので、10年という時間もあっという間でした。また今後の10年という目標をチームで掲げていますが、その時間もあっという間に経つのではと感じています。
松澤氏:本作はオンラインタイトルで、10年はプレーヤーの皆さんと一緒に歩んできた感覚があります。アップデートを繰り返していろいろなことがありましたが、それもすべてプレーヤーの皆さんのおかげです。今後も、一緒に歩んでいく10年にしたいですね。
――2月には次の10年の施策が発表されたましたが、改めて意気込みをお願いします。
小野塚氏:日々、この先10年、より多くのお客様に楽しんでもらうために開発努力をしています。1人でもパーティーを組んでメインストーリーを進められる新しいシステムだったり、そうしたソロ向けの仕組みなどを作っています。より多くの人に安心して楽しんでもらえるよう展開していきたいので、引き続きよろしくお願いいたします。また無料で遊べるフリートライアルもあるので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
松澤氏:ソロ向けのコンテンツサポートもそうだが、グラフィックスアップデートやPS5への対応もあります。ここから先も、常に攻めるのが大事だと思っています。シナリオは一旦区切りがついていますが、ここから新しい展開を作っていけたら。ぜひ期待してください。
――今後、開発や運営のハードルを乗り越えるのに必要不可欠な要素は何でしょうか?
松澤氏:あったら教えて欲しいですね(笑)。ただ、新しいチャレンジはプレーヤーの皆さんと一緒に楽しんでいけるかどうかかなと。そのつもりで開発していけたらと思います。
バンダイナムコエンターテインメント「機動戦士ガンダム バトルオペレーション2」プロデューサーの倉知洋輝氏
「機動戦士ガンダム バトルオペレーション2」:PARTNER AWARD受賞
――「機動戦士ガンダム バトルオペレーション2」(バトオペ2)にはどんなユーザー層なのでしょうか。
倉知氏:「バトオペ2」の特徴は、グラフィックスの美麗さや重厚な操作感、そしてパイロットとして操作できる面白さにあると思います。なので、モビルスーツを操作したいユーザが多いかなという印象ですね。
また「機動戦士ガンダム」のゲームのなかでも、多人数のチームバトルが特徴なので、対戦好きが多いように見られます。またその影響もあるのか、発話が多いイメージですね。SNSでもトレンドに入るなどの様子を見ていると、コミュニケーションが活発なのかなと思います。
――今年はPS5版の発売がありましたが、PS5だからこそできたことや苦労したことはありますか。
倉知氏:新しいハードだったので、手探りの中で進行しつつ、並行して運営もあったのでその部分は苦労しました。ただそのかいがあって、ロード時間の短縮だったりフレームレートの恒常だったり、パイロット体験を邪魔しないようなものにはできたと思います。
またDualSenseのアダプティブトリガー機能などで、機体の銃を撃ったり兵器を使用していく体感はより強められたかなと。総合すると、没入感を高められたのはPS5版のメリットだったと思います。
――本作は運営型のゲームですが、プレーヤーに継続してもらうために意識したことはありますか。
倉知氏:何よりも飽きが来ないのが重要だと考えたので、週1での機体追加や、月1での調整を入れて、パイロット体験の向上を意識した運営を目指してきました。本作は今年で4周年を迎えましたが、機体は340機ほどになりました。調整が大変になってきたのですが、苦戦しながらも体験向上のために頑張っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
カプコン「バイオハザード ヴィレッジ」プロデューサーの神田剛氏
「バイオハザード ヴィレッジ」:PARTNER AWARD受賞
――先日配信となったDLCの反応やユーザーの声はいかがでしたか。
神田氏:「シャドウズ オブ ローズ」のシナリオに関して、「泣けた」という意見がとても印象的でした。「バイオハザード ヴィレッジ」の本編ではイーサンたち家族のストーリーは完結させるという思いで作ってきて、「シャドウズ オブ ローズ」はそれを追体験する形にしています。
ローズの中の忌まわしき思いを打ち砕くため、ローズが勇気を振り絞って戦いに挑んでいく話です。最後は家族愛につながっていくのですが、そこで感動していただけたと。「バイオで泣くとは思わなかった」というコメントがとても印象的でした。
――PSVR2版が開発中ですが、注目点はありますか。
神田氏:圧倒的な新世代のVR体験と言っても過言ではありません。特に没入感をPSVR2の「バイオハザード ヴィレッジ」で体験してほしいですね。DualSenseとモニターでの操作とはまた違って、PSVR2のコントローラーで動かしたものが、イーサンの動きとなって「ヴィレッジ」の世界のなかで体験できます。
また追加となるアクションとして、銃を扱うものがあります。マガジンを挿入してコッキングまでがアクションできて、二丁拳銃的なアクションも可能です。新しい、没入感あふれる「ヴィレッジ」が体験できるタイトルとして、我々としてもオススメしたいですね。
――「ヴィレッジ」が多くの人にプレイしてもらえたポイントは何ですか?
神田氏:「バイオ7」以降、カプコンの自社エンジン「REエンジン」をベースにシリーズを開発してきました。ホラーを追求する原点回帰を目指してきたなかで、「7」や「ヴィレッジ」、「2」のリメイクとなる「RE:2」なども含めて、コンスタントにシリーズ作を手に取れる頻度を高く開発を進めてきました。プレーヤーの方が飽きずに、次を楽しみにしてもらえるよう、ブランドの価値を高められたと思います。
©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.











































![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)


![任天堂 【Switch2】ドンキーコング バナンザ [BEE-P-AAACA NSW2 ドンキ-コング バナンザ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0495/4902370553413.jpg?_ex=128x128)


![任天堂 【Switch2】マリオカート ワールド [BEE-P-AAAAA NSW2 マリオカ-ト ワ-ルド] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0495/4902370553260.jpg?_ex=128x128)








![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer【2月27日以降出荷分】 [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)




![カプコン 【PS5】バイオハザード レクイエム 通常版【2月28日以降出荷分】 [ELJM-30814 PS5 バイオハザ-ド レクイエム ツウジョウ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0020/4976219137492.jpg?_ex=128x128)


![[Switch] あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス (ダウンロード版) ※2,000ポイントまでご利用可 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/1/802251631_p.jpg?_ex=128x128)


![タイトー イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1 [TAS-G-005 イ-グレットツ-ミニ ア-ケ-ドコレクション1] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0199/4988611224236.jpg?_ex=128x128)



![かたつむりのメモワール【Blu-ray】 [ サラ・スヌーク ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3614/4522178013614.jpg?_ex=128x128)
![おそ松さんスペシャルイベント フェス松さん'18 Blu-ray Disc【Blu-ray】 [ 櫻井孝宏 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2138/4562475292138.jpg?_ex=128x128)
![秒速5センチメートル [ アニメ ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0313/4560107150313.jpg?_ex=128x128)
![銀魂 後祭り2023(仮)【初回仕様限定版】【Blu-ray】 [ 杉田智和 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4409/4534530144409_1_2.jpg?_ex=128x128)
![最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか III(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 鳳ナナ ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1970/4534530161970_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【送料無料】[限定版][先着特典付]アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!- Blu-ray(初回生産限定盤)/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/421/eyxa-14942.jpg?_ex=128x128)
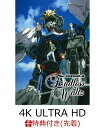
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8899/4580055368899_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 4巻【Blu-ray】 [ 古橋秀之 ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5856/4988104155856.jpg?_ex=128x128)