【特別企画】
「ドラゴンクエスト」36歳の誕生日おめでとう! 当時の思い出を語りつつ、実際に遊んでみた
2022年5月27日 00:00
- 【ドラゴンクエスト】
- 1986年5月27日 発売
本日5月27日は、日本のRPGの中でも代表的な「ドラゴンクエスト」シリーズの第1作目が発売されて36周年を迎える日だ。初代「ドラクエ」の誕生日記念として、筆者と「ドラクエ」シリーズとの出会いについて語っていきたい。当時の時代背景なども加味してご覧頂ければ幸いだ。
中学時代の思い出(黒歴史)
筆者が初めて最初の「ドラクエ」をプレイしたのは、続編の「ドラゴンクエストII(ドラクエII)」が発売してしばらく経ってからの事となる。また、初めて実際にゲームプレイを目にした「ドラクエ」シリーズは「ドラクエII」が最初だ。というのも「ドラクエ」が発売した頃、筆者は中学1年生。その頃の筆者はファミコンよりも8bitパソコン「MSX」のBASICプログラミングでゲームを作るのが楽しかった頃である。
当時の筆者はまだRPGの概念をあまり理解していなかったが、MSX版「ハイドライド」をクリアしていた。また、当時そこそこ流行っていた「ゲームブック」は大好きで、多く所持していた。ゲームブックとは、書籍の中にナンバリングが振られており、文章を読み進めてナンバーが示された場合、指定のナンバーまで読み飛ばしたり、戻ったりすることで、分岐のある物語が楽しめるという書籍だ。これ1冊でゲームが楽しめることもあり、当時は非常に熱中していた。特に当時発売されていた、「アーサー王物語」を題材にした「グレイルクエスト」シリーズは全巻所持しており、これらを熟読するなどファンタジー要素を含むRPGを楽しむ素養はこの辺りから醸成されていたように思う。
初代「ドラクエ」は正直なところ、プレイした時期が遅かったこともあり、自身のプレイで印象に残っている出来事が少ない。後述の友人の1人が、レベル30に到達した「ふっかつのじゅもん」をクラスで誇らしげに自慢していた記憶はあるのだが、当時は「ドラクエ」に興味があまりなかったため、スルーしてしまった。
時が進み、「ドラクエII」の画面を初めて見たのは、「ドラクエII」発売直後の友人宅だ。当時、発売直後の「ドラクエII」を持ちこみ、数人でワイワイ言いながら遊んでいた現場に何故か筆者も呼ばれ、一緒に遊んでいたのだ。ぶっちゃけるとその輪の中には積極的には参加せず、筆者は彼らとは別にマンガを読んで過ごしていた記憶が残っている。一方で、盛り上がっている会話の内容も割と鮮明に記憶している。
特に印象に残っているのは、呪いで犬の姿に変えられてしまった3人目の仲間、ムーンブルクの王女をラーの鏡で人間の姿に戻して仲間に加える、というお馴染みのイベントだ。このからくりが当時の中学生たちはあまり理解できておらず、みんなで「この犬が怪しい」、「何かのアイテムを使えばいいんじゃないか?」、「さっきラーの鏡を使うって言ってなかった?」、「ラーの鏡どこだよ?」、「毒の沼地調べればいいんじゃね?」、「この鏡をどうやって使うんだろう?」といったやり取りでどうにかムーンブルクの王女を人間に戻して仲間にし、大盛り上がりだった。
その後、「ドラクエ」熱が落ち着いたところで、友人から借りて初代「ドラクエ」をプレイした。これまでプレイしてきたアクションゲームとは異なり、のんびりとコマンドを選択するだけで戦闘できる点が非常に新鮮だった印象が残っている。また、洞窟内の音楽が階を下るごとにキーが下がっていく演出が、子供ながらに凝った演出だと感じた。また、竜王の変身も印象的だった。まさか弱々しそうな魔法使いのような姿のボスがウィンドウをはみ出るくらい巨大なドラゴンに変化するなんて、当時としては画期的で、衝撃的な姿だ。
その後は間髪入れずに「ドラクエII」に挑むことになる。こちらも周囲の友人たちがクリアした情報が残っていたことなどもあり、特にハマる要素はなく、クリアできた印象だ。ただし、終盤のロンダルキアの洞窟では、落とし穴エリアを乗り越えるため、マス目に地図を書き、1歩ずつ恐る恐る歩を進めた印象はとても強く残っている。さらに戦闘でボロボロになった状態で洞窟を抜け、ロンダルキアの雪景色に感動するも、ハーゴンの居城に向かう前の戦闘でギガンテスの「つうこんのいちげき」で見事に玉砕した苦々しい記憶は未だに印象的だ。恐らく「ドラクエ」シリーズ屈指の難所だっただろう。
こうして「ドラクエIII」発売前の数か月の間に「I」と「II」をクリアし、「III」発売は近所の電気屋で予約をして発売日当日からプレイすることができた。そう、この段階で筆者は完全に「ドラクエ」シリーズの虜になったのである。「IV」以降の「ドラクエ」は、発売直後にクリアしたタイトルもあれば、後日クリアしたタイトルもあるが、基本的に最新の「XI」まで全てプレイ、クリアしてきた。ちなみに最も音楽が好きなのは「IV」、そして最もプレイが厳しかったのは「VI」だ。
実際にやってみた。ハードな戦闘に四苦八苦! 意外な発見も?
ちょうど手元に環境もあったので、ちょっとファミコン版の「ドラクエ」をプレイしてみた。ふっかつのじゅもんを見ていると書き写しをミスして入力完了後に全否定された時の苦々しい思い出が甦る。
そして王様から目的を語られていざ冒険。この「ドラクエ」の王様の部屋に特に思い出はないが、1つのエピソードを思い出す。前述の通り、「ドラクエ」その物への思い出は薄めの筆者だが、実はマンガの「ドラゴンクエストへの道」は大好きだ。現在絶版の本書は、「ドラクエ」開発当時の裏側を漫画化したもので、その中でこの王様の部屋のエピソードが語られていたのだ。
それは、「ドラクエ」発売前のテストプレイにて、ゲームを全く知らない社員にプレイさせてみたところ、いきなり平原を歩き出し、出現したスライムに倒されてしまったという話。テストプレイ当時は城と街の中間の平原からスタートする作りにしていたが、それでも城や街に入らない人もいることに気がついた当時の中村光一氏は、王様の部屋に閉じ込めて、ここを出るために周囲の人と会話してゲームのルールを理解してもらうというチュートリアルのような仕掛けを思いついたという。本書は他にもこうした開発時のエピソードをユニークに語られており、是非再販してほしい1冊だ。
「ドラクエ」のフィールドコマンドを見ていると、今では見られない「とびら」や「かいだん」、話しかける相手を方向で指定するサブコマンドもあるなど、当時の試行錯誤が感じられる。
フィールドに出て、街でちょっと買い物をしたら、とりあえず何か洞窟に入りたくなったので、北にある「ロトの洞窟」に向かう。入った直後は周囲が何も見えず真っ暗闇だが、たいまつを使用する事で僅かに視野が広がり、かろうじて歩けるようになる。後のシリーズではなくなった灯りのシステムだが、36年経った今見ても、洞窟の臨場感を感じられるいいシステムだと思う。
そして地下2階にあるロトの残した石板を読んでふと思う。宝箱から石板を見つけるものの、この洞窟で得られるのは石板に書かれた情報のみであり、石板もアイテムとしては手元に残らない。ゲーム内の貴重なヒントのみが置かれた洞窟は、攻略情報などもなく、雑誌や書籍、友達同士の情報交換で情報を得ていた時代を象徴するような場所だと感じられた。
そしてせっかくなのであえて素手のまま戦闘に挑み、どうのつるぎ獲得を目指してみることにした。ところが、素手でスライムを攻略するのは非常に厳しい。20ゴールドで購入できる防御アイテム「りゅうのうろこ」のみを装備してスライム相手にレベル上げを試みるが、得られる経験値やゴールドに対して戦闘で消費するHPの割合が高い。そのため、レベル1の状態では宿代すら稼げないうちに宿屋を使用する羽目になり、まさかの赤字スタートとなってしまった。
ステータスはちょっと停止していると自動でウィンドウが表示されるのも、今見直すとなかなか面白い。戦闘して宿を利用するたびゴールドはじわじわと減っていくが、その分経験値は加算されていく。この増減するゴールドや経験値が加算される数字を常時見せることでこちらのモチベーションも高くなる。シンプルながらもうまい仕掛けと感じた。実際、その後のスライム相手の戦闘は苦痛でもあるが、楽しく進められる時間でもあった。そしてレベルアップ! 高揚感のあるこの音源を閃いた故すぎやまこういち氏のセンスも最高だ。
そして素手ながらもHPが増える事で、戦闘回数は増え、宿屋に戻るまでに稼げる経験値もゴールドも増えていき、レベル2にしてようやく宿屋を使っても黒字で全快できるようになった。
今回はどうのつるぎ取得は諦めたが、発売から36年経った今でも十分に遊べてしまうのはそれだけ完成度の高い証だろう。現在ではリメイク版も多く出ており、より遊びやすい作りになっているので、試行錯誤の点も考慮しつつ、プレイして当時を振り返ってみるのも面白そうだ。
この先も色々展開が予定されている「ドラクエ」シリーズだが、本シリーズがすごいのは基本的なコマンドなどはほとんど変わっていないにも関わらず、錬金釜やスキルなど、新たな要素はきっちりと盛り込んでいる点だ。そのため、他のゲームを遊んでいる現役のプレーヤーも楽しく遊べるし、「ドラクエ」シリーズしかプレイした事がない人でも臆せず遊べる。
恐らく「ドラクエ」しかプレイしていない人に最新の「XI」をプレイさせてみてもある程度はプレイできそうな気がする。そのくらい初期のプレイフィールを弄らずに続けてきた結果、他のゲームはやらなくても「ドラクエ」ナンバリングだけはプレイするという層が存在するほど、国民的な人気シリーズとして今なお輝いている理由の1つなのだろう。
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.


































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)



![任天堂 マリオカート ワールド【Switch 2】 BEEPAAAAA [BEEPAAAAA] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_340/4902370553260_1.jpg?_ex=128x128)






![[メール便OK]【新品】【PS5】シティーハンター COLLECTOR’S EDITION [PS5版][在庫品] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10900000/10904478.jpg?_ex=128x128)
![カプコン 【PS5】バイオハザード レクイエム 通常版【2月28日以降出荷分】 [ELJM-30814 PS5 バイオハザ-ド レクイエム ツウジョウ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0020/4976219137492.jpg?_ex=128x128)






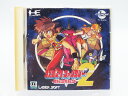



![TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」上巻【Blu-ray】 [ 羊宮妃那 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7436/4562494357436.jpg?_ex=128x128)
![TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」下巻【Blu-ray】 [ 羊宮妃那 ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7443/4562494357443.jpg?_ex=128x128)