先行レビュー
「ELDEN RING NIGHTREIGN」先行体験レポート
新解釈「エルデンリング」! 約40分に濃縮されたRPG体験が魅力的
2025年2月12日 23:00
- 【「ELDEN RING NIGHTREIGN」ネットワークテスト】
- 実施期間:2月14日~2月17日
フロム・ソフトウェアの新作「ELDEN RING NIGHTREIGN(エルデンリング ナイトレイン)」は、短い時間の中にRPGらしい成長要素などを凝縮したハイテンポなゲーム。前作「ELDEN RING(エルデンリング)」が持つボスバトルの緊張感や達成感を残しつつも、新たなゲーム体験ができる。今回はそんな本作について、先行プレビューにて得られた感想をレポートしていく。
本作はゲームデザインを一新したプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション。プレイヤーはオンラインマルチで3人のパーティを編成し、新たなる冒険の地「リムベルト」を探索していく。3日目に出現する強敵を倒すことでクリアとなる本作は、本編「エルデンリング」と全く異なるゲーム体験が特徴的である。
なお、本レポートの内容は、2月14日から抽選で選ばれたプレイヤーを対象に実施するネットワークテストと同じ内容であり、開発中のもの。製品版とは仕様が異なる可能性がある。
「エルデンリング」とは全く異なる体験に。メキメキ成長できるハイテンポなハクスラに進化
今作はフロム・ソフトウェアが得意とする“死にゲー”のエッセンスが鳴りを潜めており、アクションRPGとしてヒロイックな仕上がりに変化していた。限られた時間の中で箱庭型のフィールドマップを素早く探索することを考慮し、装備重量制限・落下ダメージ・レベルアップのパラメータ配分といった要素がオミット。これによって探索が格段にハイテンポになっている。とはいうものの、もちろん同社らしい“達成感”もしっかりと味わえる。
キャラクターの移動アクションについても変化は著しい。ダッシュは霊馬トレントに跨った状態でのスピード感と同じで、高低差に富む断崖絶壁の地形に対してはキャラクター単身でジャンプによる高速壁登りが行なえる。これまで「デモンズソウル」から続いていたようなあらゆる道中のリスクを考慮し、常に万全を期する慎重な歩み方は、少なくともメディアプレビューの体験範囲では意識する必要がなかった。
それほどまでに“スピード感あふれる体験”に舵を切った挑戦的な作風の変化とも言える。シリーズをこれまで遊んできたプレイヤーほど、その変化には新鮮さと驚きが感じられるのではないだろうか。ゲーム全体のスピード感は飛躍的に向上している。
ゲームの基本的なプレイサイクルとしては、リムベルトを探索しながら3日目に出現するボス敵を撃破するというもの。プレイヤーは「円卓」からミッションを選択して他のプレイヤーとオンラインマッチングし、個性豊かなキャラクターたち「夜渡り」を選択してサバイバルすることとなる。
いざミッションが開始するとパーティ編成を組んだプレイヤー3人はリムベルトの地へ送り出される。ゲームが始まればそこからは、常に3人固まって行動しても良いし、全員バラけて各々行動しても良い。自由度の高い雰囲気である。マップを開き「自分はここへ向かう」と、ピン表示で最低限の意思表示をしておくこともできる。
ただし、リムベルトは時間が経過して夜に近づくと、HPを削る雨が降り始めるのでバトルロイヤルゲームの如く、行動可能なエリア範囲が徐々に狭まる。プレイヤー全員が雨に追われボスエリアまで導かれるのだ。なので各プレイヤーは夜に出現するボスとのバトルに備えて、リムベルト中を奔走しながら武器集めやレベリングをサクサクとこなしていく必要がある。こうした流れを1日目、2日目と続けた後、3日目はマップ探索ではなく専用のボスエリアにて、ミッション目標の「夜の王」と戦うのだ。
1ゲームあたり35分〜40分ほどになるが、これは開発チーム内で成長を実感できるよう、試行錯誤の末に導き出されたプレイボリュームなのだという。実際、その時間で「エルデンリング」における成長と攻略の達成感が得られるから、ファストな協力型アクションRPGといった印象を受けた。
なお、1ゲームあたりのクリア時間がまばらなのはボス戦になるとエリア縮小が終わり、倒すまで次の日に移行しないためだ。
舞台となる「リムベルト」は、「ELDEN RING」における「狭間の地」や「影の地」とも異なるフィールドで、マップサイズもゲーム性に合わせたコンパクトなサイズ感。とはいえ、3人で手分けしても1ゲーム中にマップ全体のロケーションを周り切るのは困難だろう。
フィールド内の要所要所に、雑魚敵やらフィールドボスやらが配置されている上、中には洞窟だったり、砦だったりも存在している。ちなみにゲーム開始直後からマップ情報は地図内に全て明記されているので、探索の指標にしやすい。ただし、マップ内はさまざまな突発イベントも発生する。中には“隕石”が降ってくるというものもあるようだ。今回のプレイでは巨大な昆虫たちが大量に密集している悪夢のようなイベントに遭遇した。
こうした地図の情報をもとに、プレイヤーたちは各ロケーションへ向かい、敵を倒したり、宝箱を探したり、ボス敵を討伐しながら、強力な武器やアイテムを集めていく。
フィールドボス、あるいは夜のボスを倒すことができれば、パワーアップ効果か武器を選択式で獲得可能。夜のボスを倒して獲得できるパワーアップは非常に強力な効果が多く、例えば連撃数に応じて体力を回復する、回避行動を取るとその場に落雷が発生する、ダッシュで氷風を巻き起こせるなど、実にさまざまである。
1日目を突破できると、このようなパワーアップ効果を得られる機会があるためか、2日目のフィールド探索はかなり捗った。その分、2日目に登場する夜のボスも強力なので、ペースを上げてガンガン奔走していくことになるワケだ。
大きく前作と異なるところがもう一つ。それは防具と装備重量の概念が存在していないということ。今作では拾える武器や盾に付帯効果が備わっており、レベルアップと両輪で考えられるフィールドにおける主要なパワーアップ要素となっている。魔法と祈祷についてもフィールドで入手する杖や聖印にそれぞれあらかじめ付与されているので、自分で変更はできない。感覚としてはまさしくハック&スラッシュ。敵を倒し、今持っている武器よりもさらに強力なものを求めていくのが成長のポイントだろう。
武器に付いている付帯効果は武器を装備しているだけでキャラクターに反映されるので、それぞれの効果を適応させるためにわざわざ持ち変える必要がない。さらに、弓やクロスボウといった飛び道具の弾数は無制限で、プレイスタイルそのものはかなり柔軟に変化させられる。
ただ、装備重量こそないが装備スロット数は限られてくるので、取捨選択がとても悩ましい。仮に序盤の段階でレア度の高い強力な武器を入手したとしても、その武器をしっかり扱えるようになるまでレベリングする必要もある。ゲーム進行には“成長”が必ず付き物で、いきなり強武器を入手したからといって、一気に強くなれるわけでもない。
レベルアップは本編と同様、各地に点在する祝福でルーンを捧げて行なう。今回のプレビューではレベルの最大値が15までとなっており、レベルが1上がることによる全体的な能力値の上昇には大きな恩恵を感じられた。こうした事情から、道中の敵を積極的に狩りながらルーンはどんどん稼いでいきたいところ。
嬉しいポイントは、ルーンの稼ぎは仲間と共有されるところ。初心者もまずはルーン稼ぎからパーティプレイに貢献しやすいだろう。ただし、ルーンの消費やフィールドで敵や宝箱からドロップアイテムは共有ではない。譲り合うか、早い者勝ちで持っていくかはケースバイケースといったところで、一緒に行動してるとその辺も考慮すべき部分になり得てくる。
また、死亡しても一定時間瀕死状態になり仲間からの救助を受ける余力があるのも嬉しい要素だ。瀕死状態の仲間を攻撃することで、蘇生に必要なゲージを削ることができ、ゲージを削り切るとその場で仲間を復活させられるというシステムである。
一見するとシュールだが、弓やクロスボウ、魔法攻撃などで遠距離から蘇生できる他、広範囲攻撃をすれば敵への攻撃と蘇生を兼ねるなど、バトルのテンポが崩れない上手い落とし所になっていた。
フィールド探索中は瀕死状態から死亡しても復活できるが、その死亡した位置にルーンを落として、さらに最大レベルが1下がるというペナルティが課せられる。もちろん、死亡地点まで戻れば、失ったレベル分のルーンも回収できる。しかし、夜の雨が発生してフィールドが縮小中のタイミングで死亡してしまうと、ルーンの回収はかなり難しい。縮小中のエリア外に出ると、HPがごっそり減り続けていくからだ。
そのため、仲間からの救援を期待できるという意味でも、道中のフィールドボスに共闘できるという意味でも、共に行動するメリットは大きい。なお、夜のボス戦では、復活ができないため、全員が瀕死状態になるとゲームオーバーとなる。
ゲームオーバーでもゲームクリアでも、リザルト画面ではゲーム内通貨と、出撃キャラクターに装備する能力上昇の装備アイテム「遺物」を獲得可能だ。ゲーム中に入手した武器やアイテムは持ち越されないものの、プレイヤーごとに異なる遺物を複数装備して次回のゲームに臨めるので、他のプレイヤーと同じキャラクターであっても、ゲーム中におけるビルドの個性には差が出そうだ。また、外見については各キャラクターに外見を変更するスキンの要素もあるとのことだ。
“夜渡り”たちの個性が光る!今作ならではの「スキル」と「アーツ」による新しいバトル体験
ゲームサイクルやゲーム進行のテンポ感については前述の通り、かなりハイテンポにまとまっている。1ゲーム、40分程度に「エルデンリング」の魅力が形を変えて凝縮されていると言ってもいい。だが、同作と言えば自キャラクターをコツコツと育成し、やがて強力な攻撃手段を得られるようになることも大きな魅力であったと思う。自分なりのプレイスタイルが確立されていき、キャラクターのビルドとプレイヤーのスタイルがシンクロしていく体験は、筆者も気に入っていた。しかしながら今作はエンディングまでに多彩なNPCとの交流を通じて、ナラティブに自キャラクターの旅路と成長に向き合うタイトルではない。
今作のあらかじめ用意されているプレイアブルキャラクターを選んでダンジョン攻略を進めていくという設計は、短く濃縮されたゲーム体験をわかりやすく形にするためにも、ある程度プリセット化せざるを得なかったのではないかと推察できる。が、シリーズプレイヤーによっては、やはりマルチプレイ主体なのだから自キャラクターを持ちたいという声もありそうだ。
しかし、実際にゲームを触れてみると、キャラクター選択制というのが、必ずしもマイナスではないことがすぐに理解できた。誰がどのキャラクターを選んでも、ある程度方向性の決まった役割分担が一貫して行なえるのは大きい。つまるところ“マルチプレイ時のパーティ全員が器用貧乏”といった悲劇は起こり難いのだ。ただし、キャラクター選択制を採用しつつも、同一キャラクターで出撃できるので、メンバー全員が後方から攻撃する「魔女」...という事態にはなり得る。
他にもキャラクター選択制だからこその良さは「スキル」と「アーツ」の存在意義に繋がっている。夜渡りたちは種族も職業も装備も異なるが故に、それぞれが自分だけの特技と言える力を備えている。今回は前衛の「守護者」、遠距離職の「魔女」、バランスの良い「追跡者」、トリッキーで素早い「レディ」を体験できた。
「守護者」は、鷹の亜人種とでも表現すべき風貌のキャラクターでありアーツは人間のキャラクターなら不可能なアクションとなっている。自身の翼で高所まで跳躍したのち、急降下して着地地点の周囲にダメージを与えるといった芸当である。守護者の名に恥じない剛健な守りで戦いに貢献でき、大盾を構えながら防御体制を取る独自のアビリティ「ハイガード」を使用可能だ。
「魔女」は、魔女は初期装備が杖であるため基本的な攻撃はFPを消費しての魔法攻撃に頼りがち。当然、FPの消耗が激しい。本作ではFPをこれまでの聖杯瓶のように回復できないものの、そこはさすが魔女とでも言うべきか、敵に対して魔力を含む何らかの属性ダメージが与えられている場合にスキルを発動すると、その敵から属性に応じた属性痕を回収し、FP回復が自力で行なえる。
属性痕は3つまで回収によって自身にストックでき、最大まで溜まると、やがて属性痕を組み合わせて非常に強力な混成魔法を放つことができる。属性痕の属性が異なるほど強力となり、混成魔法を上手く当てることができると、3日目に登場する夜の王ですらも一気に削り切って倒せてしまった。
「追跡者」は性能バランスや扱いやすさに長けたキャラクター。初期武器は大剣だが、スキルのクローショットが使っていてとにかく便利でカッコイイ。というのも追跡者のスキルはいわゆるフックショットでのワイヤーアクションで、小型の敵は引き寄せることができ、大型の敵や地形に当たった場合は自身をワイヤーで引き寄せ一気に距離を詰められる。動きの大きな大剣が武器なのにスキルのおかげで高い機動力を持ち、チャンスを伺いながら一撃離脱の戦法を得意としている。特定のタイミングでスキルを長押しすることで、大剣を炎でエンチャントし、その後切りかかるといったアクションも確認できた。おまけにアーツは「対象に鉄杭を打ち込んでから爆発させる」というとにかく見映える技である。名称は「襲撃の楔」というらしいが、終始「パイルバンカー」と勝手に呼んでいた。
「レディ」は、素早い身のこなしから繰り出される連続回避が特徴的だ。攻撃と回避のスタミナ消費も少なく、過去作でいうところの技量にパラメータを振ったようなキャラクターである。今回選べた4人の中では群を抜く機動力を誇り、ボス敵や集団を相手取っても回避行動が非常に容易だった。アーツでは自分と周囲の仲間の姿を隠したり、スキルでは直近で敵に与えたダメージをリプレイ再生のようにもう1度与えたりすることができるかなりトリッキーな能力を持つ。アーツもスキルも強力だが狙うタイミングが重要だ。ビジュアル的にもキャラクター人気が出そうなテクニカル志向の人物だった。
このようにキャラクターそれぞれが独自のスキルとアーツを備えているのが、今作におけるプレイアブルキャラクターたちだ。全く異なる強みと独自の能力をそれぞれが持つため、どのキャラクターを使っても自然と役割に由来したゲームプレイを意識できる。本編だとせいぜいボス敵の能力くらいでしか考えられなかった各キャラクターのアクションゲームらしい脚色された能力の数々が、ロールプレイ特有の責任感を上手く濁して調和してくれているかのようだった。
プレイヤーの心は折れづらい新境地へ
キャラクターが持つ強力な個性のおかけで、フィールド探索で発生する雑魚敵との戦闘は、極端に数の差で押し込まれない限り、基本的にはプレイヤーが有利と言えるほどのバランス感だと思える。無論、それはメディアプレビューで体験できた範囲の話でしかなく、製品版ではそうとは限らない。それでも現状明確に述べることができる感想と言えば、“難しすぎてクリアできない”といった極端なゲームバランスではなさそうということだ。初回のゲームプレイでは、キャラクターのスキルとアーツの使い勝手が分からなかったり、夜の雨に飲まれて死亡してしまったりと、初心者らしいシステム理解の浅さから死亡するミスが続いた。
だが、ゲームの基本をある程度抑えてしまうと、マップのどこを目指していくのか、どのフィールドボスを優先的に倒すのかなどなど、セオリーのようなものが早い段階で見えてくる。嬉しいのは、たとえ1日目でゲームオーバーを迎えても、報酬として前述した「遺物」を入手できるということ。その分控え目な性能になるだろうが、装備さえしていれば、次回プレイのときには僅差であっても強くなっているはずである。熟練の夜渡りとマッチングして、協力プレイが良い方向に進んで行けば「前は苦戦したのに割かしアッサリとクリアできてしまった...」なんてことも十分に考えられる。
また、ゲームにある程度慣れてくると、夜を迎えるまでの過程はRPGにおけるレベリング、ハクスラにおける装備掘り周回にも近い心持ちになっていた。レベルを少し上げるだけでもキャラクターはタフに成長していくので、本編では苦戦したその辺の雑魚相手に少々大雑把な戦い方をしても余裕をもって乗り切れる。それでもフィールドボスの中には3人で協力し合わないと倒しづらい敵もいるので、「エルデンリング」が持つボスバトルの緊張感と達成感は失われていないように思えた。ファストな「エルデンリング」として多くの要素が簡略化され、プレイの所感はカジュアルに。それでいてチームメイトと3日目まで生き残り続けていく共闘の体験は濃密だ。
本編ではゲームバランスを考慮して、最低限の制限下におけるフレンドとのマルチプレイが楽しめたが、今作「エルデンリング ナイトレイン」にそういった制限は課されていない。心ゆくまでフレンドたちとワイワイ騒ぎながらリムベルトの地を冒険することができるのだ。ゲームプレイの手触り感がこれだけ手軽なものであるのなら、多くのライトプレイヤーにオススメできる作風だと言える。「エルデンリング」は、プレイヤーの心が折れづらい新境地を迎えたのではないだろうか。
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.
※プレイには開発中のゲームデータを使用しており、製品版の仕様と異なる場合があります。






















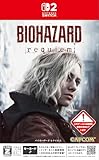








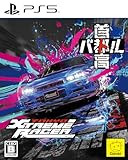











![【Amazon.co.jp限定】劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray【特装版】(早期予約メーカー特典クリアファイル+L判ブロマイド5枚セット付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41N2LB75ruL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![[Switch 2] BIOHAZARD requiem (ダウンロード版) ※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/9/802252599_p.jpg?_ex=128x128)











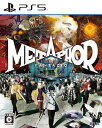



![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS5] Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ) 通常版 SIE(20251002) 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480897.jpg?_ex=128x128)








![任天堂 ニンテンドーサウンドクロック Alarmo [CLO-S-RAAAA アラ-モ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0479/4902370552195.jpg?_ex=128x128)

![六花の勇者3 [Blu-ray] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-sora/cabinet/p05/4988013374683.jpg?_ex=128x128)
![JUNK WORLD(通常版)【Blu-ray】 [ 松岡草子 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1277/4534530161277.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE./アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/689/kixa-35.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】[枚数限定]ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序(EVANGELION:1.11)/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/034/kixa-9.jpg?_ex=128x128)
![メガゾーン23【Blu-ray】 [ 久保田雅人 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4969/4560349034969.jpg?_ex=128x128)
![日々は過ぎれど飯うまし 3(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ team apa ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8536/4534530158536_1_2.jpg?_ex=128x128)
![Aqours Documentary【Blu-ray】 [ Aqours ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0198/4934569370198.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5714/2100014785714_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.3 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4367/2100014774367_1_3.jpg?_ex=128x128)