ニュース
【CEDEC 2018】「FFXV」限界に挑んだ「料理」制作の裏側が明かされる
どアップでも「美味しそう」と思える“3D料理モデル”の作り方
2018年8月25日 00:00
「ファイナルファンタジーXV」で話題になったものの1つに「料理」という要素がある。何が話題になったかと言えば、その3DCGがとにかく高いクオリティだったことだ。体験版の配信直後から「FFXV」は「料理が美味しそう」と話題になり、本編発売後になれば今度は料理をリアルで再現する人が登場して、またそれが話題になったりもした。
CEDEC 2018で実施された「FINAL FANTASY XVにおける料理 限界に挑んだグラフィック表現とその活用法」という講演では、この「料理」制作方法が公開された。登壇したのはLuminous Productions 3Dキャラクターデザイナーの松尾祐樹氏。なぜ「料理」は高品質になり、どうやって実現したのか。その裏側が明かされていった。
プレーヤーキャラクター2.5人分のメモリを料理1つに注ぎ込む!
まず説明されたのは、「FFXV」における「料理」の役割について。ゲームの1日のサイクルの締めとしてキャンプをするとき、プレーヤーが選んだ料理を仲間のイグニスが作ってくれる。システム上は次の戦闘に向けてのステータス上昇の意味もあるが、それ以上に頑張ったプレーヤーに対しての「ご褒美」だと考えられていた。
そのため美味しそうに見せる必要があり、それ故に料理を「超どアップ」で映すことが決まったそうだ。これは生半可なものは作れないと3Dモデラーたちは震え上がったそうだが、その予感どおり、通常の作り方ではアップに耐えられる品質にはならなかったという。
開発チームは様々に料理の品質を上げる検証をしていったが、中でも効果的だったのは「良質な素材を用意すること」、「データの制約を極力なくすこと」、「柔らかさと透明感を出すこと」だとした。
まず「良質な素材を用意すること」について。色々試す中で固まっていったのは、「フォトグラメトリー」を使った撮影だ。フォトグラメトリーとは、撮影素材の周囲を囲むように複数アングルから撮影して、その写真データをもとに3Dモデルを作る仕組みのこと。
体験版の時点では、スマートフォンと無料アプリを使ったフォトグラメトリーでデータを作成していたそうだ。それなりのスキャンデータを取得することはできたが、あまり精密なポリゴンにはならず、「アップに耐えるクオリティ」には届かなかった。そのため、スカルプトの追加、テクスチャの影抜き、色味調整など、ものすごい量の手作業が発生したという。さらに手が加わるごとに不自然さも出てきてしまうため、この方法で品質を上げるのは相当難しいとした。
そこで体験版配信後はスキャンの精度を上げるため、フルサイズの一眼レフカメラや三脚、照明、ターンテーブルなどを用意して、撮影環境を整えることにした。撮影ブースはダンボールと模造紙で手作りしているが、上に乗せたビニール袋で光の具合を調整できるなど、キットで売られているものよりも使いやすいところもあったという。
また運が良かったのが、「料理がすごく好きなアートディレクター」が開発チームにいたこと。松尾氏はさっそくこのアートディレクターを捕まえて、どんどん料理を作ってもらっては撮影していくこととなる。発表スライドを見てもわかるように、撮影が進む度に料理の出来栄えがプロ級になっていったそうだ。
さらに、料理が完成した時点でアートディレクションが終わっているため、撮影後はモデラーが3Dモデルの品質を上げることに専念できる。ほぼ“イグニスの中の人”とも言えるこのアートディレクターのおかげで、一石三鳥くらいの効果はあったのではないか。その結果、肉に振りかけた塩の粒もはっきり見えるような、料理としてもスキャンデータとしても高品質なものができあがった。
そして続いては、「データの制約を極力なくすこと」だ。スキャンデータそのものが高品質なので、そのままCGにすることで可能な限りメモリを使わなく済む。また料理が登場する直前に画面が1度暗転することがわかっていたため、そこで周囲のアセットをすべて消し去ることで、メモリリソースを料理に思いきり使えることが事前に打ち合わせられていた。
実際の料理アセットのスペックは5~15万ポリゴン前後で、テクスチャサイズは4,096×4,096以下、小物と皿は2,046×2,046程度とした。料理によってバラつきはあるものの、トータル使用メモリは100MB以下という制約に決まったという。驚くべきは使用メモリで、「FFXV」におけるプレーヤーキャラクターの開発ルールは1人40MB以下と定められていたそう。つまり、「プレーヤーキャラクター2.5人分のメモリ」を料理1つに当て込んでいる計算となる。この仕様にすることで、デザイナーはかなり余裕を持ってデータ制作ができるようになったそうだ。
アセット作りの際の調整としては、より美味しそうにするために写真よりも照りを出したり、表面を光らせるようにしてシズル感をアップさせた。また「FFXV」開発の終盤ではデザイナーの余裕が出てきたこともあり、一時は「総力を上げて料理を作っていた」こともあったという。たとえばコロッケなら、周囲に粒子をまぶすことで衣のカラッとした感じが出ないか実験してみるなど、どうやったら品質が上がるかの技術検証が積極的に行なわれていた。
最後に、「柔らかさと透明感を出すこと」について。これには、シェーダの仕組みを利用したという。たとえば通常は人間の肌の柔らかさを出すために使われるSSS(表面下散乱)シェーダ。そのままだと赤色が出るシェーダだが、改造して色相を変えられるようにすることで、おにぎりの米粒の柔らかさを出している。
またおにぎりや小籠包は、自己発光させることで透き通る感じを表現した。さらに透明感のある料理には、光の反射を模したマスクテクスチャを当てはめる「ファズ」という機能を使っている。このファズは、いくら、ジャーサラダなどの透過表現に使われたそうだ。
冒頭で述べた通り、こうした開発チームのこだわりがあったからこそ「『FFXV』の料理がすごいらしい」と話題になったわけだが、その反応は日本、海外問わなかったそうだ。「どんなキャラクターが美形か」については各国意見があれど、「料理を美味しそうと思う気持ち」は世界共通らしいと気づいたという。
料理が話題になったことで、カップラーメンとのコラボが実現できたり、スクウェア・エニックスカフェではゲーム内の料理と同じものを出せたり、料理から展開が生まれることもあった。そして何より良かったのは、より多くのユーザーに興味を持ってもらえたことだという。
料理そのものは様々なゲームで見かける要素だが、「FFXV」の場合はデザインチームの粋を集めて全力投球しているところが面白い。きっかけは無茶ぶりのようだが、そこにしっかりクオリティを出して応えてみせる、「FFXV」デザインチームの意地を垣間見た講演だった。































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)



![3goo 【Switch2】GEAR・CLUB UNLIMITED 3 [POT-P-AA3PB NSW2 ギア クラブ アンリミテッド 3] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0045/4589857091714.jpg?_ex=128x128)





![任天堂 【Switch2】マリオテニス フィーバー [BEE-P-AAAEA NSW2 マリオテニス フィ-バ-] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0040/4902370553932.jpg?_ex=128x128)






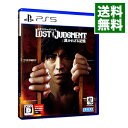
![ソニー・インタラクティブエンタテインメント 【PS5】DualSense(TM)充電スタンド [CFI-ZDS1J PS5 デュアルセンス ジュウデンスタンド] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1456/4948872415064.jpg?_ex=128x128)
![STRASSE フットペダル補強プレート DDPROユーザー必見!CSL Pedalsに対応[ハンコン ストラッセ RCZ01 XZERO SPEED MASTER] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shunte/cabinet/game/str107-00.jpg?_ex=128x128)

![[Switch 2] あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス (ダウンロード版)※480ポイントまでご利用可 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/2/802252532_p.jpg?_ex=128x128)


![【中古】塔の上のラプンツェル MovieNEX [DVDのみ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/issue/cabinet/11599041/11702825/imgrc0099071422.jpg?_ex=128x128)
![劇場版「オーバーロード」聖王国編 通常版【Blu-ray】 [ 丸山くがね ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3726/4935228213726_1_2.jpg?_ex=128x128)
![Aqours Documentary【Blu-ray】 [ Aqours ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0198/4934569370198.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典】最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか III(完全生産限定版)【Blu-ray】(アニメ描きおろしイラスト使用 A5 キャラファイングラフ(スカーレット&ジュリアス)+アクリルスタンド(スカーレット&ジュリアス)) [ 鳳ナナ ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2510/2100014662510_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【先着特典】映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】(描きおろしイラスト使用A4クリアファイル+ボイスドラマつきカレンダーポスター(約A3サイズ)) [ 矢立肇 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4038/2100014784038.jpg?_ex=128x128)
![お気楽領主の楽しい領地防衛~生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に~ Vol.1 【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8216/4582757038216.jpg?_ex=128x128)
![お気楽領主の楽しい領地防衛~生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に~ Vol.2 【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8223/4582757038223.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定グッズ+楽天ブックス限定先着特典】キミとアイドルプリキュア♪感謝祭<アクリルブロック>付版【Blu-ray】(メタリアルグラフ+缶ミラー(5種セット)) [ プリキュア ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5595/2100014825595_1_2.jpg?_ex=128x128)
![『ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~』 Blu-ray(Blu-ray Disc)【Blu-ray】 [ 田村睦心 ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0146/4595559610146.jpg?_ex=128x128)