レビュー
「信長の野望・新生」レビュー
超優秀な武将と戦国の物語を楽しむ
2022年7月14日 00:00
- 【信長の野望・新生】
- ジャンル:歴史シミュレーション
- 発売・開発元:コーエーテクモゲームス
- プラットフォーム:プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC
- CEROレーティング:A(全年齢対象)
- 発売日:7月21日
- 価格:
- パッケージ版 10,780円(税込)
- DL版 10,780円(税込)
- 豪華版(パッケージ版) 16,280円(税込)
- Digital Deluxe Edition 14,080円(税込)
- 【GAMECITY & Amazon.co.jp 限定セット】
- A3複製原画付き限定セットA/B 各38,280円(税込)
- A3複製原画2種付き限定セットC 60,280円(税込)
- 暖簾セット+5,500円(税込)
- 信長愛刀セット+42,900円(税込)
5年ぶりに登場したシリーズ最新作「信長の野望・新生」(以下、新生)。「信長の野望」といえば、自分が戦国時代を駆け抜ける武将になり、自国を開発しながら領土を拡大し、全国統一を目指すシミュレーションゲームだ。今年は作者のシブサワ・コウ氏が最初のゲーム作品「川中島の合戦」をリリースしてから40年ということもあり、そのメモリアルイヤーを飾る作品となっている。
シリーズの16作目となる「新生」では、“自ら考え行動する生きた武将たち”をコンセプトに、家臣たちが自らの判断で行動するのが一番の特徴だ。家臣は与えられた領地を自ら発展させたり、勢力の状況を自ら判断して最善と考える施策を「具申」として提案してきたりする。こうして、君臣一体となって歴史を動かしていくのだ。
本稿では、これらの要素を紹介しつつ、「新生」のレビューをお届けする。
自ら考え行動する生きた武将たち
今回の「新生」では2つの大きなポイントがある。まず1つが「家臣が自ら考えて動く」ということ。もう1つが、全国にある「城」を拠点とした領地は「郡」に分かれており、それぞれに家臣を配置することで領地を発展できるということだ。つまり、登場する約2,200人ものの家臣は自律的に動くため、郡に配置されている家臣へいちいち指示を出さなくても、その能力に応じて最適な動きをしてくれる。「新生」ではこのゲームシステムを踏まえた上で、戦略を決定し、領地を広げていく必要がある。
通常版の場合、プレイできるシナリオは5つある。
・1546年1月 信長元服
・1553年4月 尾張統一
・1560年4月 桶狭間の戦い
・1570年4月 信長包囲網
・1582年5月 夢幻の如く
それぞれのシナリオにより、大名が治める勢力が異なるわけだが、オススメのシナリオはやはり「桶狭間の戦い」だろう。このシナリオの設定だと、全国にはさまざまな戦国大名がいて、小勢力が群雄割拠している状態だ。中には北条家や武田家のように大領地を治める大名もいるが、信長がいる中部や近畿地方は特定の勢力が強いわけではない。このため取ったり取られたりと、ダイナミックな戦国の世を体験できる。
それぞれのシナリオでは、スタートするのにオススメの大名も示されるので、そこから選んでプレイするのでもよいだろう。織田信長や松平元康(徳川家康)、武田信玄といった戦国の有名大名から始めるのもいいし、六角家に代表される弱い小勢力から領地を広げていく楽しみもあるのが、「信長の野望」シリーズのいいところだ。筆者の場合はチュートリアルで示されるように、桶狭間の戦いのシナリオで、織田信長を選んでスタートした。まあ王道である。
なお本作ではチュートリアルが充実しているので、チュートリアルが示すように進めていけば、どのようにプレイしたらよいのかわかるようになっている。「新生」でやるべきことは多いので、1つ1つ覚えていく方がよい。早く遊びたいと気が急く気持ちを抑えて、飛ばさず読んでいくことをオススメする。
まずは自国領土を発展させる
自領にいる配下の武将は「宿老」、「家老」、「部将」、「侍大将」、「足軽大将」、「組頭」という身分に分かれて存在している。先ほども述べた通り、本作では郡に家臣を配置し、領地を発展させていくのだが、郡を治めるためには「足軽大将」以上の身分が必要だ。しかも上のランクの身分に出世するには「勲功」がなければならない。これは、戦で活躍したり、「政策」にある「母衣衆結成」を発令して勲功を高める必要がある。スタート当初は組頭ばかりで知行を与えることができない。
戦によって勢力を広げるためにも、まずは領内を発展させ、自国を豊かにしなければいけない。そのためのコマンドが「内政」だ。内政としては2種類あり、大名が治める「本拠」では「城下施設」による施設建設、「郡開発」による農業地や商業地の開発が可能だ。臣下の領主が治めている「城」では「内政」コマンドで「城下施設」による施設建設、「領内諸策」で「石高増強」、「商業発展」、「修復」が実行できる。
ただし領主の城であれば「知行」により武将を「郡」に割り当てることで、それぞれが適切に発展させてくれる。このため基本的には領主に発展を任せる一方で、急いで施設を整えたり、石高を上げていきたいときは直接指令を出すという形になる。特に石高は、領内に兵士を増やす際に必要となるので、序盤では「石高増強」を積極的に活用したいところだ。
なお武将については「統率」や「武勇」といった能力の他、「人たらし」、「城乗」などの特性がある。城主や領主が優秀であるほど領地が早く発展するので、能力の他に特性にも気を付けて効果の高い武将を配置しよう。
いざ敵の城に攻め込まん
さて、「信長の野望」が楽しいのは何と言っても“戦”だ。敵を攻めて領地を切り取っていくことこそ醍醐味だ。プレイを開始して少したつと何となく領内が整ってきたような気がして、一気に攻めていきたくなるのは当然だろう。しかしその前にやることがあるので、ここははやる気持ちを抑えて進めていこう。
まずは「兵力」と「腰兵糧」の確認だ。兵力は自分の城に何人の兵がいるのかメインマップでも確認できるのでわかりやすいが、腰兵糧については城にカーソルを合わせないとわからない。戦闘が開始されると「腰兵糧」を消費しながら部隊が進んでいくので、こちらもしっかりと確認しておこう。腰兵糧が尽きると部隊の兵士がどんどんと減り、最後には全滅してしまうためだ。
また、敵の城を落とすためには、「出陣」でいきなり攻め込む前に「調略」によって敵の城の勢力をそいでいくのもよい。臣下から敵城への調略を具申されるときもあるので、その際には積極的に調略を使おう。
さて、いよいよ出陣といこう。敵の城に出陣するには以下の方法がある。
・右クリックして表示されるメインメニューから「軍事」-「出陣」により攻め込む城を指定する場合
・攻め込みたい城をクリックして「軍事」-「出陣」で攻め込む場合
上記のいずれを取ってもよいが、メインメニューで「軍事」を選んで表示される「攻略目標」を選び、攻め込みたい城を目標として定めると、必要な兵の数を考慮して出陣する城を選んでくれるので、攻略しやすい。
なお、自分で兵の数を考えることも、自動で勝てる兵力を編成してもらうこともできる。攻略目標を示して戦の準備をすると、腰兵糧もため込むようになるので便利だ。余談だが、攻略目標から敵の城を選んで攻め込む場合、自陣の城の準備が整うとホラ貝の効果音が流れるので、気分も高まる。
なお敵の城を落とす際には、その城にいる城主と共に領主が出陣していくので、先ほどの領内発展とは異なり、今度は「統率」や「武勇」といった能力の高い領主を設定しておき、出陣するとよい。また先ほど述べた武将が持つ特性も重要となるので、こちらも考慮しておきたい。
出陣して敵の城に攻め込む際には、城に属している郡をまず攻めていくことになる。郡を制圧するとそこは自勢力の領地となり、城にたどり着くと攻城戦が開始される。攻城戦では城の耐久が0になると制圧完了だ。
戦場をダイナミックに体験できる「合戦」
「新生」の敵攻略には「合戦」システムが用意されている。これは大名の部隊が戦闘に参加していたり、戦場の近くにいる場合に選べるコマンドだ。
合戦では同時に8部隊が出陣して戦う。それ以上の部隊は控えていて、武将が退却すると戦えるようになっている。なお、武将それぞれが自分で思考して戦うが、部隊をクリックして指示することも可能だ。戦場には「要所」という戦術上の要衝、急所となる「退き口」が存在し、が設けられており、これを攻略することで味方の士気を高めることができるので、積極的に攻略したい。合戦では敵の部隊を全て撃破したり、大名を討ち取れば勝利だが、敵陣地にある「退き口」を全て破壊したり、敵の「総士気」を0にしても勝利となる。
このほか、戦いの中では武将が持っている「戦法」が発動し、敵を攻撃することもある。「戦法」の発動タイミングは自動発動か手動発動か切り替えることができ、発動すると敵をなぎ払うので、「武将情報」で戦法が黄色くなっている武将を積極的に配置したい。
なお合戦は最大16の部隊同士による戦闘が可能で、合戦に勝利すると参戦した部対数によって「威風」が発生し、周辺の国や郡、国衆が寝返ることがある。このため、通常戦闘だけでなく、勝てると思ったら合戦を仕掛けた方が有利になることもある。
こうして敵を攻略していくわけだが、戦いに部隊を割いてしまうと今度は自陣の守りが手薄になることもあり、戦いを仕掛けるのはなかなか難しい。そのためにも「外交」で他勢力と同盟を結んだりして、背後から襲われないようにしていくことが大事だろう。
敵将を配下に置く
戦闘に勝利すると、落とした城に所属している武将を捕らえることができる。捕らえた武将は配下として「登用」できるが、生きたまま野に放つ「全解放」か、「処断」を選べる。能力の高い武将はできれば登用したいものだが、それがかなわない場合は……プレーヤーの心の赴くままに、といったところだろうか。ただし「全解放」すると、別の城を落としたときに登場することもあり、その時にはすんなりと登用できる場合もある。
領地が増えてきたら軍団を結成
今作では大名が直轄統治できる城の範囲に限界があるため、ある程度領地が増えてきたら部下に委任しなければならなくなる。「新生」も同様で、「軍団」を結成して「軍団長」を決め、領地の発展を委任することになる。軍団長に任命できるのは家老と宿老の身分を持つ者だけだが、ある程度版図が広がっているのであれば、戦闘や「母衣衆結成」を通じて「勲功」を稼いで身分が上がっているので、任命できる武将もそれなりに増える。それほど気にする必要はないだろう。
なお軍団長のいる城の位置によって所属できる城の範囲が決まる。城主は「制度改新」をLV.3にしないと配置換えができないので、序盤では軍団長になれるような武将をうまく配置する必要があるだろう。
軍団に対しては全てを委任する「委任攻略」のほか、落とすべき城を指示する「城攻略」、自軍の軍団を支援する「軍団支援」の方針を立てて指示できる。
自然災害が発生することも
「新生」ではこうした合戦以外にも台風や凶作などの自然災害が起こることもある。これらが起きると兵糧の収量が減るばかりでなく、一揆が発生することもあるので早めに対処したい。
史実イベントを堪能する
「新生」では条件がそろうと史実イベントが発生する。テキストで語られる場合もあるが、「川中島の戦い」や「長篠の戦い」といった史実でも重要なイベントはムービーが流れるようになっている。
なお、デフォルトの状態だとプレーヤー大名以外の武将は史実に基づいて死んでいく。有能な人材がいなくなった敵陣地は攻め時なので、こうしたイベントを利用してもよいだろう。なお信長でプレイした筆者の場合、ゆっくりとプレイしていたせいもあるが、木下秀長や丹羽長秀、柴田勝家などといった名将が信長よりも先に死んでいくのがなんとも言えなかった……。
そして天下統一へ
こうして戦いつつ天下をうかがうことになるのだが、その道のりは正直遠い。この記事を書くためにそれなりの時間はいただいたのだが、試行錯誤を繰り返した結果、信長プレイでの指標として示される“東海統一”までなんとか持っていったところだ。本作では以下のエンディングが用意されている。
1.地方統一エンディング
2.三職推任エンディング
3.従属統一エンディング
4.全国統一エンディング
進むべき道としては上から順番、ということになるが、東北や九州の大名から始めた場合は「三職推任」まで行くのが大変かもしれない。信長プレイで当初、いきなり畿内を制圧してみたがエンディングとはならなかったので、地方統一から順序を踏んでいく必要があるようだ。そのあたりはちょっと戸惑った。
こうしてなんとかエンディングまで見たのだが、やはり「信長の野望」は面白い。武将が自律的に動いてくれることもあって、領内の発展がかなりやりやすくなったと感じた。プレイ中は領地のほとんどを軍団長に割り振って任せてしまい、ある程度兵力もたまって発展したところで軍団を解散し、目標とする敵に攻め込む、といったプレイで進めていたが、制圧したい地方に兵力を集中させることができ、撃破するのが容易だった気がする。これであればどの大名の領地に攻め入るか考えやすく、ゲームを進めやすく感じた。
こういうシミュレーションゲームの場合、やれることが多くなって細かい指示ができるのもよいが、あまりにも煩雑になると面倒になり、進めるのが難しくなるものだ。しかし「新生」ではそのあたりのバランスがほどよくなっており、自分で指示をして発展させるのもいいし、筆者のプレイのように軍団長任せで進めていくこともできる。いずれにしても敵に戦を仕掛けて領地を分捕っていくことに「信長の野望」シリーズの面白さはあると思う。シリーズを通してプレイしている人だけでなく、かつてプレイしていた人にもオススメしたいタイトルだ。
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.



































![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)
![NXS-P-ALZLB 任天堂 Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Switch2 ソフト] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premoa/cabinet/pics/1025/4902370553574.jpg?_ex=128x128)

![BEE-P-AAAEA マリオテニス フィーバー 任天堂 [Nintendo Switch2 ソフト] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premoa/cabinet/pics/1124/4902370553932.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch2】Nintendo Switch 2 Proコントローラー [BEE-A-FSSKA NSW2 Proコントローラー] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0039/4902370552843.jpg?_ex=128x128)





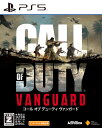

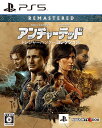


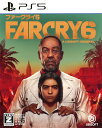







![【中古】【Blu−ray】アナと雪の女王 MovieNEX (Blu−ray+DVD) [デジタルコピーコード使用・付属保証なし] / クリス・バック【監督】 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/renet20/cabinet/item_photo/001199/2/0011992679.jpg?_ex=128x128)
![ミュージカル「忍たま乱太郎」五年生単独ライブ【Blu-ray】 [ (ミュージカル) ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4851/4550621524851.gif?_ex=128x128)
![『葬送のフリーレン』Season 2 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】 [ 山田鐘人 ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5481/4988104155481_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく!」2026 RE:boot(完全生産限定版)【Blu-ray】(ロゴ入りラバーコインケース) [ 守乃まも ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8542/2100014818542.jpg?_ex=128x128)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)【Blu-ray】 [ 富野由悠季 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9963/4934569369963.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】天使のたまご 4Kリマスター (4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc) (特装限定版)【4K ULTRA HD】(A5キャラファイングラフ(シリアルナンバー入り)) [ 押井守 ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7459/2100014787459.jpg?_ex=128x128)
![ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 4th Live Dream ~Bloom, The Dream Believers~ Blu-ray Memorial BOX【Blu-ray】 [ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8755/4540774808755.gif?_ex=128x128)
![ミュージカル『刀剣乱舞』 目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭【Blu-ray】 [ ミュージカル『刀剣乱舞』 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1650/4571603151650_1_2.gif?_ex=128x128)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025【Blu-ray】 [ (趣味/教養) ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8986/4524135238986_3.jpg?_ex=128x128)