【特別企画】
6月6日は「テトリス」の日! 「テトリス」誕生から40年。昔も今も変わらない、その夢中になるシリーズ作品を振り返る
2024年6月6日 00:00
- 【テトリス】
- 1984年6月6日 誕生
今や「テトリス」といえば、世界の誰もが知るゲームの1本なのは間違いないだろう。基本的なルールは非常にシンプルで、画面の上から下へ向かって落ちてくる、4つの四角いブロック(ミノ)で構成されたテトリミノと呼ばれる物体を、左右移動と回転で操作。このブロックが綺麗に横一列に並ぶと、そのラインは消去されて上からブロックが詰まるというもの。しかし、その簡単さとは裏腹に、一度ハマってしまうと易々とは抜け出せない中毒性を持つ、実は恐ろしい(笑)ゲームなのだ。
そんな「テトリス」が産み出されたのは、40年前の1984年6月6日のこと。ロシアの科学者(当時)アレクセイ・パジトノフ氏により、ソビエト連邦領内向けのコンピュータ・エレクトロニカ60向けに誕生した「テトリス」は、今のように派手なグラフィックは使っておらず(使えず)、アスキーキャラクターで画面が構成されていた。もちろん、現代とも違って音楽もなければモノクロ画面なので色もついていないが、それでもパジトノフ氏は夢中になって遊んだそうだ。
日本でのブームをもたらした、最初期の「テトリス」とは
そんなオリジナル版が登場した後、紆余曲折を経て「テトリス」は西側諸国へも広まっていき、日本では1988年のパソコン版やアーケード版、そして翌年のゲームボーイ版などで人々へと浸透していくことになる。最初期に、いわゆる「テトリスにハマった」という人は、このどれかを遊んでいたのではないだろうか。ここで、それら初期3タイトルを簡単に振り返ってみよう。
1998年11月18日に、国内で最初にBPSから発売されたパソコン版は、テンキーの4と6でテトリミノの左右移動を行なうのだが、回転は5キー、そして落下がスペースキーとなっており、操作性としては良い部類ではなかった。それでも、当時発売されていた主要パソコンのほとんどでプレイできたことから、この操作方法が身についている人もいるかもしれない。用意されていたのは、25ライン消すとクリアとなるモードのみだったため、後のアーケード版やゲームボーイ版のように延々とプレイすることはできなかった。
続いて1988年12月上旬にセガからデビューしたのは、ゲームセンター版。いわゆる「セガテトリス」と呼ばれるもので、レバーを下に入れる操作でテトリミノが徐々に落下していったり、着地後もすぐには硬直せず、“遊び”の時間が設けられたことで非常にプレイしやすくなっている。スコアは999999点、ラインは999、レベルは99でカウンターストップ(それ以上数値が増えない)状態になるため、当時はそれを目指して数多くのプレイヤーがコインを投入していた。今でも、全国各地のさまざまなロケーションに置かれているため、一度は目にしたことがあるだろう。
そして1989年6月14日に任天堂から登場したのが、「テトリス」史上初となる対戦を盛り込んだゲームボーイ版だ。本体2台とカートリッジが2本必要にはなるが、通信ケーブルで接続することで対戦プレイを楽しむことができる。2列消せば1段、3列消せば2段、そして4列消せば4段、相手のブロックを押し上げることができるので、溜めて一気に消すかコツコツと攻めるか、プレイヤーに合わせた戦い方が選べた。当時、友人や兄弟などと対戦しまくったという人も多いのではないだろうか。もちろん1人プレイも可能で、その場合はパソコン版のように25ライン消すとクリアになるモード(B-TYPE)と、アーケード版のように持久戦タイプのモード(A-TYPE)から選ぶことができた。
ライセンス問題などがあったものの、1990年以降も「テトリス」はカジュアルゲームの中心として世界中で人気を博していくことに
こうして1990年代に入ると、その人気を受けてコンソール機ではほぼ毎年のように新たな「テトリス」が発売されるようになっていく。あまりにも数が多く、それらを羅列するのは本記事の趣旨では無いため割愛するが、それに輪をかけて似たようなルールを採用した、いわゆる落ちモノゲームも大量に登場する。結果的に「テトリス」は落ちゲーという新たなジャンルを産み出すのだが、自身はライセンス問題で一時期迷走することとなるのだった。だがそれも、1996年にザ・テトリス・カンパニーが設立され、同社が版権管理などを行なうようになったことで解消されることになる。
また、「テトリス」は長年さまざまなメーカーから発売されてきたため、基本的なルール以外に関しては多数の差違が存在していた。「テトリス」公式サイトにある“テトリスの歴史”ページを見ると、ザ・テトリス・カンパニーが設立されたのと同じ1996年に「テトリスの一貫性と品質基準を確立するため、テトリスガイドラインが作成された」とある。
このガイドラインを初めて採用した2002年発売の「テトリスワールド」以降、ガイドラインに沿った「テトリス」が登場することとなり、ある程度ルールの一貫性が保たれるようになるのだった。このガイドラインではさまざまなルールが決められたが、システム的に大きく進化したのが“ホールド”や“最低2つ先まで見える“Next”などだろう。
「ホールド」は、落下中のテトリミノが硬直する前にホールドボタンを押すことで、それを一時的にストックしておくことができる機能。例えば、I型テトリミノをホールドしておき、4列消しを狙えるタイミングで現在のブロックと入れ替えたり、置く場所が無いピースが出現した時にホールドしてピンチを脱するなど、このおかげで戦略のバリエーションが大幅に増えることとなった。
次に出現するテトリミノが分かる「Next」も、最低で2つ以上表示されるようになり、タイトルによっては6つ先まで見ることができるため、脳内での事前シミュレーションが捗ることに。上級者にとっては、嬉しいガイドラインといえるだろう。以下では、そんな時代に登場した数多くの作品のうち、特徴的なタイトルを見ていこう。
まずは、1988年にアリカが開発しカプコンからアーケード版としてリリースされた「テトリス ザ・グランドマスター」。この作品は、ゲームが進行するとテトリミノが画面に現れた次の瞬間に、落下地点に存在するというルールを取り入れたことで話題になった。また、ゲームクリアという概念も導入され、レベル999のクリアを目指してラインを消していくほか、段位も表示されるようになっている。なお、ザ・テトリス・カンパニーにより、同作のプレイステーション版の発売が幻となった事件があったことを記憶している人もいるかもしれない。
2000年にプレイステーション版としてアリカから発売されたのは、「テトリス with カードキャプターさくら エターナルハート」。タイトルにあるように、「テトリス」+「カードキャプターさくら」なのだが、アニメ製作スタッフ描き下ろしグラフィックスが100枚以上収録されているということで、「テトリス」とは関係なく買った人もいたのではないだろうか。
ご多分に漏れず筆者もその一人で、それらイラストを見たいがためにプレイを繰り返したもの。ゲームシステム的には、「テトリス ザ・グランドマスター」の続編となる「テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター2」で導入される先行回転システムなどが入っていたりした。
21世紀に入り携帯電話が普及すると「テトリス」人気の高さから、それらで動く「テトリス」も数多く配信された。なかでも、ジー・モードは多数の作品を積極的に世に送り出し、当時の電車内では同社の「テトリス」をプレイする人を大勢見かけた。2004年には、他のプレイヤーと疑似対戦が楽しめる「テトリスバトル」といった作品も携帯電話向けに登場している。
“大人気間違いなしなので、モバイル端末でも「テトリス」を配信する”という流れは、携帯電話がスマートフォンに取って代わられた現在でも続いている。例えば、2006年にエレクトロニック・アーツが配信したiPod用の「テトリス」はApple Storeのダウンロード数1位になったほか、2013年にiOSやAndroid向けにリリースした「Tetris Blitz」もランキング上位に入るなど、いつの時代になっても世界中で大ヒットを記録した。
そんな中で、2005年にアリカが制作しタイトーから販売されたアーケード向け新作の「テトリス ザ・グランドマスター3 -Terror Instinct-」では、ガイドラインにあった新たな操作方法の「ホールド」が導入された。また、従来と同じクラシックルールと、ザ・テトリス・カンパニーが策定した「テトリス」ガイドラインに沿ったルールを選択することができたほか、プレイステーション版「テトリス with カードキャプターさくら エターナルハート」のシステムをベースにしたSAKURAモードを収録するなどしている。
新たなプラットフォームが登場すれば、それに対応した「テトリス」が発売されるのも自然な流れのようで、2004年に任天堂からリリースされた新ハード「ニンテンドーDS」向けとして、2006年には新作として任天堂から「テトリスDS」が誕生している。本作は、ソフトが1本あれば同時に2人から10人までのプレイが可能なマルチプレイモード、そしてニンテンドーWi-Fiコネクションを利用して離れた相手との対戦ができるWi-Fiモードが楽しめた。「テトリス」公式サイトの、「テトリス」の歴史ページに掲載された情報では、全世界で200万本以上を販売したとのことで、またも大きなブームを巻き起こしたのは間違いないだろう。
こういった流れはPCでもあり、2007年くらいからガンホー・モードが、Windowsプラットフォーム向けとしてオンラインでプレイできる「テトリスオンライン」を運営。基本プレイ料金無料で多人数対戦型「テトリス」が楽しめたり、対CPU戦をプレイすることなどができた。開発を担当していたのは、テトリスオンライン・ジャパンだ。
そして2014年、同じ落ちモノパズルゲームである「ぷよぷよ」とコラボレーションした「ぷよぷよテトリス」がセガから誕生する。どちらのルールでも遊ぶことができるだけでなく、互いに異なるルールでの対戦や、両方のルールを混在させたモードも収録。本作は、ニンテンドー3DSやWii U、PS3、PSVita、さらにはPS4やXbox One、Nintendo Switchと幅広い機種で発売され、大ヒットを記録した。「テトリス」公式サイトの「テトリス」の歴史ページでは発売が2017年になっているが、これはおそらくNintendo Switch版が発売されたタイミングかと思われる。
2018年になると、「Rez」や「ルミネス」といったタイトルで知られる水口哲也氏がプロデューサーを務めた作品「テトリス エフェクト」がEnhance Gamesより登場する。さまざまな操作に合わせてBGMや背景の演出などがシンクロして表示されるため、一種のトリップ状態に入りながらのプレイが楽しめる異色「テトリス」となっているのだ。また、各種VR機器にも対応しており、それらを装着してプレイすれば半端ない没入感を体験することができる。
システムとしては新たにZONEモードが用意され、このモード中は揃えたラインがストックされていき、時間経過か上まで積み上がると一気に消えて高得点が得られる仕組み。数多くのゲーム賞にノミネートされ、受賞もしている。本作は後にアップデートされ、マルチプレイが追加された「テトリス エフェクト コネクテッド」もリリースされた。
マルチプレイの究極とも言える作品が、任天堂より2019年にNintendo Switch向けとして発売された「TETRIS 99」だろう。プレイヤーの画面が中央に、それ以外の98人分が周囲に表示されるフィールドでバトルロイヤルを繰り広げ、最後の1人になるべく生き残りを目指す。
複数ラインか連続消しをすることでライバルプレイヤーのラインをせり上げる攻撃を行なえるのだが、その相手を自身で選択できるだけでなく、あらかじめ決められた作戦を4種類の中から選んでおけば自動でアタックすることも可能だ。
最後にラインを送り他プレイヤーをゲームオーバーにすると、K.O.したということでK.O.バッヂをゲットできると共に、相手が持つバッヂも総取りできる。バッヂは他のプレイヤーにも可視化されるので、数多く持つと狙われやすくなるため、各プレイヤーごとの作戦が問われるのだ。
なおゲームでは無いが、2023年にはApple TV+にて映画「テトリス」が配信されている。「テトリス」というゲームは当時のソビエト連邦で誕生したことも影響し、権利関係が複雑になっているのは有名な話だ。この映画では、その一端を垣間見られるので、興味を持ったならぜひチェックしてみてほしい。
そんな本作の主人公はヘンク・ロジャースだが、それなりの年齢になっている人には「『ブラックオニキス』などで有名なBPSにいた人物」と言えば“ああ、あの人!”と、分かってもらえるのではないだろうか。
ベースシステムはそのままに、まだまだ進化を続けていきそうな「テトリス」シリーズ
「テトリス」シリーズ40年分の歴史を駆け足で見ていったのだが、これ以外にもユーザーが見よう見まねで移植して狭いコミュニティで遊ばれていたバージョンや、キーホルダーの大きさでプレイできるハードなど、すべて挙げるのは難しいほどに豊富なバリエーションがある。公式サイトでは、2015年5月時点で215種類の公式種類がリリースされていると書かれているが、この10年間でその数は更に増えていることは想像に難くない。
歴史に登場してから40年もの間、世界中のユーザーに愛され続けてきた「テトリス」という作品は、これからも陳腐化することなく新作が発売されることだろう。
TETRIS tm
tm and (C) 1987, AcademySoft-Elorg. All rights Reserved. Tetris licensed to Andromeda Software Ltd.; sublicensed to Mirrorsoft Ltd., Sphere Inc. and Bullet-Proof Software Inc.
(C) 1988, Sphere Inc. All Rights Reserved.
(C) 1988, Bullet-Proof Software Inc. All Rights Reserved.
Original concept by Alexey Pazhitnov.
Original design and program by Vadim Gerasimov.
TM and (C)1987, Academy Soft-Elorg. All Rights Reserved. Tetris licensed to Andromeda Software Ltd., and sublicenced to Mirrorsoft Ltd. and Sphere, Inc.
(C)1988 Tengen[Atari Games], All rights reserved. Original concept, design and program by Alexey Pazhitnov and Vadim Gerasimov, respectively. Adapted by (C)SEGA
TM AND (C)1987 ELORG,TETRIS LICENSED TO BULLET-PLOOF SOFTWARE AND SUB-LICENSED TO NINTENDO.
(C)1989 BULLET-PROOF SOFTWARE.
(C)1989 Nintendo
ALL RIGHTS RESERVED.
ORIGINAL CONCEPT, DESIGN AND PROGRAM BY ALEXEY PAZHITNOV.
Tetris (R) & (C) 1985~2022 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
All Rights Reserved. Sub-licensed to HAMSTER Co.
TGM Series Developed by ARIKA CO., LTD.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
Tetris (R) ; (C) Elorg 1987
Tetris Logo by Roger Dean ; (C) The Tetris Company 1997 All Rights Reserved
Original Concept & Design by Alexey Pajitnov
Tetris (R) licensed to The Tetris Company and sublicensed to Arika Co., Ltd.
Cardcaptor Sakura characters, scenes, storyline, animation, art, sound, music (C) CLAMP・講談社・NEP21
Manual and Packaging (C) 2000 Arika Co., Ltd.
Tetris(R); (C)Elorg 1987. Classic Tetris; (C)Elorg 1998,2000
Tetris Logo by Roger Dean; (C)The Tetris Company 1997
All Rights Reserved
Tetris(R); (C)Elorg 1987
Tetris The Grand Master 3TM; (C)Elorg 2005
Tetris Logo by Roger Dean; (C)The Tetris Company 1997 All Rights Reserved
Original Concept & Design by Alexey Pajitonov Tetris(R) and Tetris The Grand Master 3TM licensed to The Tetris Campany and sublicensed to Arika Co.Ltd.
Tetris (R) & (C) 1985~2006 Elorg, a Tetris Holding Company. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey Pajitnov. Logo Design by Roger Dean. ALL Rights Reserved. Certain new game elements developed by Nintendo, and any characters, sounds and video games originally owned by Nintendo: (C) 2006 Nintendo.
(C) 2007 Tetrisonline Japan Inc. All Rights Reserved.
Tetris (R) & (C) 1985-2007 Tetris Holding,LLC.
Licensed to The Tetris Company.
Game Design by Alexey Pajitnov.
Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(c)GungHo Mode, Inc. All Rights Reserved.
(C) SEGA
Tetris (R) & (C) 1985〜2014 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey Pajitnov. Original Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Sega Corporation.
(C)Tetris(R)& (C)1985~2018 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Tetris Effect produced and published by Enhance, Inc. Developed by Resonair and Monstars Inc. All Rights Reserved. The “PS” Family logo and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Unreal, Unreal Engine and the circle-U logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.
(C)Tetris (R) & (C) 1985〜2019 Tetris Holding.
Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris
Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.
Licensed to The Tetris Company.
Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean.
All Rights Reserved.
Sub-licensed to Nintendo.
Certain new content developed by Nintendo, and any characters, sounds
and video games originally owned by Nintendo: (C) 2019 Nintendo.


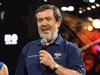
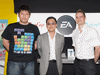




















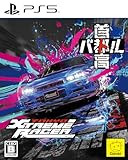











![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)
![NXS-P-ALZLB 任天堂 Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Switch2 ソフト] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premoa/cabinet/pics/1025/4902370553574.jpg?_ex=128x128)
![カプコン 【Switch2】バイオハザード レクイエム 通常版 [POT-P-AA2PA NSW2 バイオハザ-ド レクイエム ツウジョウ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0020/4976219137485.jpg?_ex=128x128)


![[Switch 2] ドラゴンクエストVII Reimagined (ダウンロード版) ※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/8/802252598_p.jpg?_ex=128x128)



![任天堂 【Switch2】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション [BEE-A-FSSKD NSW2 Proコントローラー バイオハザ-ド レクイエム エディション] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0049/4902370553802.jpg?_ex=128x128)












![任天堂 Nintendo Switch Proコントローラー [HAC-A-FSSKA NSWProコントローラー] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1949/4902370535730.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】 [ 芥見下々 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5733/4988104155733_1_4.jpg?_ex=128x128)
![Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2052/4534530162052_1_2.jpg?_ex=128x128)
![シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME【通常版】(Blu-ray)【Blu-ray】 [ 庵野秀明 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8634/4988003878634_1_2.jpg?_ex=128x128)
![「多聞くん今どっち!?」1【Blu-ray】 [ 師走ゆき ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4399/4988003894399.jpg?_ex=128x128)
![マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)(特装限定版)【4K ULTRA HD】 [ 山崎たくみ ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0268/4934569800268.jpg?_ex=128x128)

![【あみあみ限定特典】【特典】BD 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版 (Blu-ray Disc)[ハピネット]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2024/092/med-dvd2-56041.jpg?_ex=128x128)
![THE IDOLM@STER SideM 8th STAGE ~ALL H@NDS TOGETHER~ LIVE Blu-ray【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7239/4540774807239.gif?_ex=128x128)
![Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony - Superbloom - BOX盤【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5605/4573687025605.jpg?_ex=128x128)
![巨神ゴーグ Blu-ray BOX【Blu-ray】 [ 安彦良和 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7374/4582575387374.jpg?_ex=128x128)