ニュース
“カワイイ”が正義! 「ミリシタ」におけるキャラクター量産の取り組みとクオリティアップへの道とは
2020年9月4日 00:00

- 【CEDEC 2020】
- 9月2日〜9月4日 開催
6月29日にサービス開始から3周年を迎えた「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(以下、ミリシタ)。本作に登場する52人のアイドルたちが着用できる衣装数は2,000着を超え、衣装一覧に表示がないものも含めると約3,000着に及ぶ。また、2019年度の追加衣装数は1,501着。月平均で約125着というかなりハイペースな追加数になっている。
そんな「ミリシタ」だが、なぜこれだけの衣装数が用意できたのか。CEDEC 2020では、バンダイナムコスタジオ 第3スタジオ第7プロダクション3Dキャラクターパート リードアーティストの阿部貴之氏により、「ミリシタ」における衣装モデルのワークフローとキャラクターモデルの仕様、これまでにチームが取り組んできた事例について紹介された。
モデル1体は3〜5週間ほどで完成。衣装モデルのワークフローとキャラクターモデルの仕様について
まず「ミリシタ」チームの体制は、チーム全体が100名以上で成り立っており、その約3分の1がビジュアルアーティストにあたる。ビジュアルアーティストの体制は、カードイラストや衣装デザイン、3Dキャラクター、2D背景、3D背景、UI、カメラ、アニメーション、エフェクト・TAとなっている。通称キャラ班と呼ばれている3Dキャラクターの人数は上から3番目だ。
そして、衣装モデルのワークフローだが、基本的には、実装の約半年前に企画から次のSSR衣装やテーマが決まり、衣装デザインのチームに降りてくるのだという。そして、キャラ班が着手しはじめるのは実装3カ月から4カ月前になる。モデル1体完成するのには、3から5週ほど掛かるという目安だ。なお、キャラ班の作業環境は、ツールはMayaやPhotoshopを使い、ゲームエンジンはUnityとなっている。
次に、キャラクターモデルの仕様だが、家庭用「アイドルマスター」からの仕様が継承されている部分もあり、シリーズ伝統のソウルシステムが導入されている。
ソウルシステムは、パラメーターの入力のみで各アイドルの身長や体型へ自動変換してくれる仕組みだ。これにより、モデラーが体型の違いを考えることなくモデリングに集中できたり、共通衣装でバグが発生しても、1つの3Dデータを修正するだけで全員分のバグ対応が可能になる。そのほか、共通衣装なので差別化を図るために、アイドルごとに決まっているカラーが、リボンなどのワンポイントに自動で反映される仕組みも使われている。
なお、SSR衣装など特定のキャラクターしか着ない衣装に関しては、実機側の処理負荷に繋がってしまうため、ソウルシステムはカットしているとのこと。
また「ミリシタ」では、家庭用の仕組みをすべて入れるとフレーム落ちが発生していたため、ほとんどの衣装分だけ独立した頭データが存在している。
とにかく“カワイイ”が正義! 迷ったら“カワイイ”かどうかで判断
では、これだけの衣装数をどのようにしてクオリティ管理しているのか。まず、モデルのチェック体制だが、造形はリーダーがチェックし、骨の挙動はサブリーダーがチェックするようにし、監修は分散して行なっている。これは、ボトルネックにならないよう注意しているのと、次期のリーダーを育てるためでもある。
モデル作成時やチェック時に、クオリティに迷った場合は“カワイイ”かどうかで判断する。バランスは? 衣装のシルエットは? アクセサリーは? 服のシワは? 影は? とにかくカワイイものになっているのかどうかが判断基準になっているという。明確な判断基準を設けることで、方向性の迷いが生じにくくなるのだろう。
さらに「ミリシタ」では、「最高確認会」という会議が行なわれている。「最高確認会」では、MVに関わる各セクションの作業担当者が集まって気さくに意見を言い合いながら、最終的に自分たちの作業がどうアウトプットされているのかを確認している。これはMVのクオリティアップになるほか、チームのモチベーションアップにも繋がっている。
また、新規スタッフが「アイドルマスター」のリアルLiveに1度は参加するという取り組みも行なっている。ユーザーの反応を直接感じることで仕事への責任感が生まれ、モチベーションアップに繋がり、ひいては、それがクオリティアップに繋がっているのだという。
アイドルの可愛さを阻害している症状はバグ
運営型のタイトルでは、家庭用タイトルと違い、バグ対応とモデル量産、新規仕様実装を同時にこなさなければならない。そうすると、衣装や曲数、仕様が増えていくので、それに伴いバグの確率が増えていく。何か対策を打たなければ、バグ対応だけで3Dキャラクターチームの工数を使い切ってしまうことになる。
そこで考えたのは、バグ報告の質を上げるということ。テスターチームと話し合い、ビジュアル系バグに関しては、「アイドルの可愛さを阻害している症状はバグ」という基準で報告の要否を決めるようにした。
また、テスト工数を下げる取り組みとして、体型変更後も揺れ骨の挙動が変わらない仕組みに変更。テスターは最低でも3キャラ分のチェックが必要であったが、これにより1キャラのみの挙動を確認すればいいことになった。
1つ決めると52倍に……。新規仕様や仕様変更の決め方
「ミリシタ」では、52人のアイドルがメインとなるゲームであるため、1つの仕様を決めるだけで、作業量が52倍になって返ってくる。もし、1つの追加仕様が決まり、1キャラ1時間の作業が発生した場合は52時間、労働時間は原則8時間なので6.5日の作業時間が必要になる。
なので、安直に仕様を決めることはNG。コストは低く、効果は最大限を狙うのが大事になる。
企画から追加仕様の目的をヒアリングし、ソウルシステムのように効率のいいワークフローを考えてからGOサインを出す。必ずコストのことを意識して仕様をフローに落とし込むわけだ。
では、「マスターランク5」の仕様はどう決めたのか。まず、「マスターランク5」を追加した目的は、初期SSRに新しい輝きを届けたいという点と、3年目に突入するにあたって新しい要素でユーザーに喜んでほしいという点の2点。実装までの期間は約3カ月程度だったが、モデルはノーマル衣装のものと同じで、テクスチャーの切り替えで表現するというアナザー衣装の仕組みを利用すれば間に合うのではないかと考えたという。
しかしアナザー衣装は、ユーザーが「マスターランク4にしたい」と思わせる配色を意識しており、他アイドルのアナザー衣装と配色が被らない様に配慮されているため、アナザー2衣装もその仕様で続けるのは難しい。そこでアナザー2衣装では、配色のテーマをしっかりと決めようという話に。多くの人が好みやすい配色で、シックで高級感のある衣装で統一した。
ただ、これだけでは、アナザー衣装との差別化が弱いのではないかという話になったことから、ティアラを乗せる案が生まれたという。頭アクセサリーを色替えにした場合は、この先ずっとテクスチャーの作業が発生してしまうが、ティアラの仕様であれば、最初に52×3種の頭データを用意できればいいので、トータルの作業量はこちらのほうが低い。結果、短い期間でも新施策を実現できた。
また、リザルト画面のキャラクターを2Dから3Dへと仕様変更したこともある。そもそも2Dにしていたのは、リリース当初の平均的な端末スペックの問題であるが、2D画像の作成にはレタッチ作業などを行なっていたため、作業量が肥大化しつつあったのだ。
そこで各所へ相談したところ、プロデューサーから「今なら端末のスペックも上がってきているので3D化するのもいいのでは?」という声があがり、3Dリザルト画面へと仕様が変更されることになったという。
3Dになったことで、開発側も作業が楽になるだけでなく、ユーザー側にもメリットが生まれた。阿部氏は、理想の仕様変更はユーザーと開発チームの双方が幸せになることだとしている。
ほかにも、Tシャツの形状であればシステム化することでスピーディに実装することができるのではないか、ということで「Tシャツクール」というツールも開発された。
最初の設計が全て! 運営での心構えは?
阿部氏は、最初の設計がチームのフットワークを決めてしまうといっても過言ではないという。運営中に設計の根本を変えることは不可能であるため、最初の設計が全てになる。
また、運営は「マラソン」という言葉を使っており、長く、極力遠くまで走れるようなペースでスケジュールをたてることが重要だとしている。しかし、作業が流動的かつ突発的に発生するので、スケジュールは常に変動する。スケジュールは、今どれだけの作業を差し込めるかを把握するためのものだ。
そこから、現在のルールが最適とは限らないので、効率化は常に考える。スケジュールに沿って少しでも運営がうまく行かなくなってきたら、何かしら対処が必要なサイン。対応が遅れると負のスパイラルに発展していく可能性がある。
ただし、過度な働き方は人が辞めていく原因になる。人を補充しても教育コストが掛かるため、緊急事態を除き、自己犠牲的な働き方はタブーだ。ユーザーを大切にしつつも、チームや自分たちのことを大切にすることが重要であるとした。
©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



















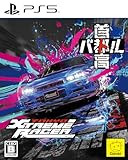










![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)















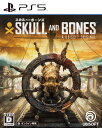













![瑠璃の宝石 4(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 渋谷圭一郎 ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0027/4534530160027_1_2.jpg?_ex=128x128)
![とんでもスキルで異世界放浪メシ 第1巻【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5906/4562494355906_1_2.jpg?_ex=128x128)
![とんでもスキルで異世界放浪メシ 第3巻【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5920/4562494355920_1_2.jpg?_ex=128x128)
![とんでもスキルで異世界放浪メシ 第2巻【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5913/4562494355913_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定グッズ+楽天ブックス限定先着特典】キミとアイドルプリキュア♪感謝祭(通常版)【Blu-ray】(メタリアルグラフ+缶ミラー(5種セット)) [ プリキュア ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5601/2100014825601_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 4th Live Dream ~Bloom, The Dream Believers~ Blu-ray Memorial BOX【Blu-ray】 [ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8755/4540774808755.gif?_ex=128x128)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025【Blu-ray】 [ (趣味/教養) ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8986/4524135238986_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定配送パック】【楽天ブックス限定先着特典】映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」Blu-ray(Deluxe版)【Blu-ray】(クリアしおり6種セット) [ ヒプノシスマイクーDivision Rap Battle- ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3208/2100014783208.jpg?_ex=128x128)