ニュース
Google Playインディーズゲームセッションレポート「生きろ!マンボウ!」の製作者が語るインディーゲームの「今」
2018年4月6日 22:31
「Indie Games Festival 2018」の開催を控え、「Google Playインディーズゲームセッション」がGoogle社内で4月6日に行なわれた。
「Indie Games Festival」はインディーゲームの周知、業界の発展を目指して開催されるもので、4月28日に開催される「Indie Games Festival 2018」は日本で開催されるインディーズのモバイルゲーム開発者を対象にしたコンテスト。日本での開催は今回が初となる。
「Indie Games Festival 2018」では募集されたゲームの中から4月10日にトップ20のゲームを選び、28日に行なわれるイベントでトップ3を決定する。会場ではトップ20に選ばれたゲームを展示し、実機でゲームを遊ぶことも可能とのこと。審査員の他に、一般参加者も審査に参加することができる。
今回のセッションでは、「はねろ!コイキング」や「生きろ!マンボウ!」などを開発し、「Indie Games Festival 2018」審査員の1人でもあるSELECT BUTTONのCEO、中畑虎也氏が登壇。審査員としての立場からコンテストの意義や審査のポイント、開発者としてインディーゲームの動向についてそれぞれ語ってくれた。
審査員として、日本と韓国のゲーム開発事情を比較
中畑氏はまず、韓国で行なわれた「Indie Games Festival 2016」で自身が審査員を務めた体験を踏まえ、韓国のゲームと日本のインディーゲームの違いや審査における評価基準などについて語った。
韓国のゲームはハイクオリティなものが多く、3Dを用いていたり、リアルタイムでオンラインプレイできるものなど比較的プレイ時間が長くなるものが多いとのこと。一方で日本のゲームは短時間でのプレイを何度も繰り返すものが主流だ。尖ったユニークなアイデアを生かした、1発狙いといってもいいゲームが多いという。この違いはターゲットとする市場が異なるために生じているようだ。
韓国のゲームは、どうやって海外でヒットするかを考える必要がある。一方で日本のゲーム会社は、日本で売れるだけで十分な収益が得られるので、国内市場だけを見据えればいいのだ。「韓国では開発者がスターみたいに扱われる」と中畑氏。それだけ、ゲーム業界の中で対外志向が強いことの表れだろう。
続いて、審査の中身やポイントについては、ゲームを評価することの難しさについて踏まえつつ「審査項目に沿って審査するが、ユニークさや尖っているかに注目する」とのこと。中畑氏が審査の対象となる開発者に求めることは、プレゼンの見せ方だ。韓国では開発者による8分間のプレゼンを行なったが、プレゼンの内容によってゲームの面白さが伝わるかどうかが決まってしまう。
中には、プレゼンの内容さえ良ければ点数が上がったかもしれない……と思うようなゲームもあったようだ。中畑氏はプレゼンターにアドバイスとして「プレゼンターは動画等で分かりやすくまとめてもらえれば審査しやすいです」と語った。ビジネスの商談でもゲームのコンテストでも、プレゼンが重要なのは変わらない。
また、今回のコンテストの意義についても言及された。インディーズのゲームは目の前でユーザーに触ってもらえる機会が少ないので、開発者にとって良い機会になる。また、アワードを取ることができれば、ユーザー獲得の大きな機会にもなる。特にGoogle主催のコンテストだけあって、露出度も高いのは最大の魅力だとのこと。また、大手と違って小規模・少人数なインディーズの開発者は孤独だという。コンテストなどの場所で仲間ができれば、モチベーションの向上に繋がるのもこうしたイベントの意義だとした。
ゲーム開発者として見るインディーゲーム事情
続いてはゲーム開発者としての話題に。インディーゲームについて開発者として意識していることやマネタイズ等、話題は多岐に渡った。
まず、ディベロッパーとしてどのようなことを考えてゲームを作っているのか? という質問に対して「丸みと尖り」というワードで説明。「尖り」とは突拍子もない、見たことがないゲーム性のこと。これがないと皆の目に留まることがないため、インディーゲームにとっては重要な要素だ。
たとえば、「生きろ!マンボウ」ではマンボウが簡単に死ぬ。この突拍子のなさが尖っている部分であり、ユーザーに「どんなゲームなんだ?」と興味を抱かせる。しかし、ただ尖っているだけではユーザーは離れていってしまい、一瞬で消費されてしまうだけになる。そこで「丸み」が必要になる。丸みとはゲームに対する親近感を抱かせる部分。プレイしやすさやUIの取っつきやすさががこれにあたり、ゲームへの定着に寄与するとのことだ。
「東アジアや北米といった海外市場も狙ってゲームを作るんです」と中畑氏。ゲームで得られる売り上げの7割近くが海外からのものだという。とはいえ、海外市場を狙ってデザインを欧米の物に寄せても欧米の人が描いたものには勝つことができない。だからこそ、UI等を練り上げ、文字を読まなくてもプレイできるゲームを製作するそうだ。
Google Playの五十嵐氏によると欧米の方が「芸術としてのゲーム」という考え方が強く、新しさや切り口をインディーに期待されているという空気があるとのこと。「尖った」ゲームが求められる市場だからこそ、より一層「丸み」も求められる。UIを広く受け入れられるものにしたからこそ、国内・海外問わずにSELECT BUTTONのゲームは成功できたのだろう。
また、記者に「これが凄い」と思ったインディータイトルを訊ねられ、中畑氏は「『どうぶつタワーバトル』は凄いゲームですよね。なんで思いつかなかったんだろう」と答えた。文字を使わなくても動画を見ればゲームのプレイ方法が簡単にわかり、手軽にプレイできる。老若男女がプレイできるカジュアルさがを凄いと感じたとのことだ。
続いて、インディーゲームのマネタイズに話が及んだ。面白いインディーゲームは尖った他にないようなゲームが多い一方、ロングスパンで遊ばれるものは少ないためにマネタイズが難しい。中畑氏はマネタイズに関して「如何に爆発的にダウンロードして貰うか」を重視していると語った。インディーゲームはソーシャルゲームと異なり、運営コストが低いため手がかからない。だからこそ、爆発的にダウンロードをしてもらって、その中で広告による収益をだしていくのだ。
爆発的なダウンロードを獲得するために重要なのがSNSの存在だ。「SNSでバズるかは、1番考えていますね。企画書の段階で、バズらないと思ったら落とすこともあります」と中畑氏。また、最近ではインディーゲームも広告を出向してユーザーを引き寄せようとするように変化してきたとのことで、インディーゲームの宣伝の方法は今後変わっていくのかもしれない。
一方で、爆発的なダウンロード数を稼いでもある程度ユーザーが定着しなければ意味はないだろう。中畑氏曰く「ダウンロードされた後も、30日は遊んでもらえるゲームを作る」とのこと。そのため、「生きろ!マンボウ」のような継続性の高い育成型シミュレーションゲームを製作するのだそうだ。
ゲームのタイプは短時間で終わり、何度も繰り返して遊ぶアーケードタイプのものと、それより少しプレイ時間の長いシミュレーションゲームに分けることができる。丁度前者が「どうぶつタワーバトル」、後者が「生きろ!マンボウ」にあたる形で、アーケードタイプのゲームも人気はあるが、東アジアではシミュレーションゲームも強いのだという。
Indie Games Festival 2018について
また、今回GoogleからIndie Games Festival 2018に関する情報も提供された。集英社の協力のもと少年ジャンプ+賞が制定。この賞は集英社が独自に行なうもので、集英社審査員により、ファイナリスト、Top20の中から1名の受賞者が選出される。受賞者は連載作品のゲーム化ライセンスとそれに伴う制作費(最大1000万円まで)が少年ジャンプ+より提供される。また、ゲーム配信の際には、少年ジャンプ+から全面バックアップまでつく、開発者にとって非常に魅力的な賞だ。
また、28日に行なわれるファイナルイベントでの審査方についても改めて提示された。ファイナルまで残り、展示されたトップ20のゲームの中からトップ10が一般参加者と審査員の投票により選ばれる。トップ10に選ばれたゲームはそれぞれ10分弱のプレゼンをする機会が与えられ、一般参加者と審査員による採点によりトップ 3が選ばれる。参加者は4月15日まで受け付けるとのこと。当日は2時半からトップ10の審査が開始される予定となっている。
インディーゲームは大手ディベロッパーが作るゲームに比べ画期的で、新しいと感じるゲームが多く、可能性に満ち溢れている市場だ。インディーゲームに日が当たることはゲーム業界全体にいい影響をもたらすのではないだろうか? 日本開催ということもあり、Indie Games Festival 2018以後のインディーゲームの動向には期待がかかる。




















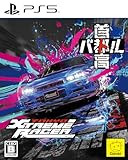










![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)

![AZLA FitSense for SWITCH 2(TM) アナログスティックカバー [AZL-FITSENSE-NS2-GR]【送料無料】【ゆうパケット対応】【3月6日発売 発売日以降お届け】 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akiba-eshop/cabinet/item15/8809825495419-5.jpg?_ex=128x128)



![[switch2対応!! 安心の国内メーカー] Switch Switch2 コントローラー 有機ELモデル Lite スイッチ2 スイッチ ワイヤレス プロコン プロコントローラー switchコントローラ プロコンswitch プロコン2 ワイヤレスコントローラー ジョイコン 連射機能 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/habit-onlinestore/cabinet/imgrc0108532336.jpg?_ex=128x128)









![ソニー・インタラクティブエンタテインメント スティックモジュール(DualSense Edge(TM) ワイヤレスコントローラー用) [CFI-ZSM1G PS5 デュアルセンスエッジ スティックモジュール] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0075/4948872415729.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【新品】【PS5】三國志8 REMAKE[PS5版][在庫品] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10790000/10795051.jpg?_ex=128x128)


![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)






![[Switch] イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード (ダウンロード版)※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/6/802252526_p.jpg?_ex=128x128)

![『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』(通常版) 【Blu-ray】 [ サンエックス ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7545/4571614677545.jpg?_ex=128x128)
![銀魂 後祭り2023(仮)【初回仕様限定版】【Blu-ray】 [ 杉田智和 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4409/4534530144409_1_2.jpg?_ex=128x128)
![音楽朗読劇READING HIGH第3回公演 「Chevre Note」~Story from Jeanne d'Arc~【Blu-ray】 [ 中村悠一 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6116/4534530116116.jpg?_ex=128x128)
![ルパン三世 カリオストロの城 【4K ULTRA HD】 [ 山田康雄 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7311/4988021717311_20.jpg?_ex=128x128)
![キミとアイドルプリキュア♪感謝祭(通常版)【Blu-ray】 [ プリキュア ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0758/4535506020758_1_2.jpg?_ex=128x128)
![劇団「忍たま乱太郎」 忍たま長屋物語【Blu-ray】 [ (趣味/教養) ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0611/4550621580611.jpg?_ex=128x128)
![ミュージカル「Fate/Zero」 ~A Hero of Justice~(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ TYPE-MOON ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0782/4534530160782.jpg?_ex=128x128)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0051/4934569370051.jpg?_ex=128x128)
