【特別企画】
アーケードゲーム「ツインビー」が稼働40周年! 野菜、台所用品、文房具が敵キャラに! 個性あふれる名作シューティングをプレイバック
2025年2月14日 00:00
- 【ツインビー】
- 1985年2月 稼働開始
KONAMIが1985年2月に発売したアーケードゲーム「ツインビー」が、今月2025年2月で稼働40周年を迎えた(※)。
本作は、自機のツインビー(2Pはウインビー)を操作して空中、地上用の2種類のショットで敵キャラを倒していく縦スクロールシューティングゲームで、2人同時プレイも可能。各ステージの最後に出現するボスキャラを倒すとステージクリアとなり、ツインビーのストックがゼロになるとゲームオーバーになる。
以下、筆者が最初に出会った頃の記憶を元に、個性あふれる本作の魅力を改めて振り返っていこう。
※:本作の発売日は1985年3月5日の記録もあるが、ゲームマシン刊「アーケードTVゲームリスト」などには2月の記載があるため、本作を2月の発売として執筆させていただいた。
独特のパワーアップシステムに悪戦苦闘
筆者が当時住んでいた地元には、ド田舎ゆえ新製品を入荷するゲーセンは1軒もなく、数か月に一度のペースで遠征していた町のゲーセンにも、本作は1985年の時点でどこにも置いていなかった。
本作の名前を筆者が初めて目にしたのは、稼働を開始してからしばらく経った1985年の12月頃、ゲームセンターではなくファミコン専門誌、確か「ファミコンマガジン(ファミマガ)」であった。友人が持っていた、本誌の「ファミコンで出してほしいアーケードゲームTOP10」と題した記事を読んでいたら「ツインビー」という名前が目に付いた。画面写真が掲載されていなかったので、どんなゲームなのかは全然わからなかったが「ベスト10に入るぐらいだから、きっと面白いゲームなんだろう」と想像していた。
その後、各専門誌で本作のファミコン版の情報が掲載され、テレビCMも流れるようになると「面白そうだな」と興味が大いにわいた。1986年1月にファミコン版が発売されると、すぐに友人が購入したので筆者も早速遊ばせてもらった。明るいビジュアル、敵も味方もコミカルなデザインのキャラクター、軽快なBGMのどれをとっても素晴らしくてすぐに気に入ったが、ツインビーをパワーアップさせるのがすごく難しい印象も率直に受けた。
ツインビーをパワーアップさせるためには、特定の雲を撃って黄色のベルを出現させ、さらにショットを数発撃ち込み、ベルの色を白(ツイン砲)、青(スピードアップ)、分身(緑。ファミコン版は点滅)、バリア(赤)に変化させてから取る必要がある。ベルは放っておくと、すぐに画面下に落下して消えてしまうこともあり、敵と戦いつつベルを狙い撃つのが難しく、なかなか思うようにパワーアップができなかった。
どうにかこうにか、ベルの色を変えられて「ヨッシャ!」と思った直後、勢い余って撃ったショットがベルに当たり、元の黄色に戻してしまうことは日常茶飯事。ベルに夢中になるあまり、タケノコなど地上の敵が撃った弾を見落としたり、時にはいっしょに遊んでいた友人が色を変えたベルをうっかり取って怒られたりしたことも、今となっては楽しい思い出だ。
苦労の末に、ツインビーが強化されるベルを取ったときには派手がファンファーレが流れ、「超」がつくほどノリノリのBGMに変化する演出も最高に気持ち良かった。パワーアップ後のBGMが素晴らしかったことも、筆者が本作を気に入る大きな要因だったように思う。
コミカルなデザインの敵キャラたちのインパクトも忘れられない。1面はイチゴやピーマン、枝豆などの野菜、果物がモチーフで、2面は包丁、ドンブリなどの台所用品、3面はタコやゾウなどの動物、4面はハサミ、スタンプなどの文房具、そして5面はヒマワリ、バラ、電球、ヒューズなどの植物と電気用品をキャラクター化した敵が登場し、見た目にも実に楽しかった。
ツインビーの腕に敵の攻撃が命中すると片腕がなくなり、地上用ショットを放つスピードが落ちてしまう。もう片方の腕も破壊されると地上用ショットが撃てなくなるが、直後に「ピーポーピーポー……」のサイレン音とともに出現する救急車と合体すると、両腕が復活するシステムも、良い意味でとてもおかしかった。
2人同時プレイ中は、ツインビーとウインビーが縦または横に合体すると特殊なショットが撃てる。特に、横並びで合体すると撃てる「ファイヤー攻撃」はとても強力だが、お互いの息がなかなか合わず、こちらも実戦で使いこなすのはかなり難しかった記憶している。
各ステージの最終地点には、巨大なボスキャラが出現する。1面のボス、オニオンヘッド将軍は、本体の周囲を回転するコロンのスピードがメチャクチャ速いのでびっくりした。2~4面のボスも、巨体でありながら動きがとても機敏で、特に4面に出現するクローテバイス将軍の、左右に高速で移動するスピードには面食らった。ラスボスにあたる5面ボス、スパイス大王の体当たりと、スピンの複合攻撃にもさんざん苦しめられた記憶がある。
対ボス戦のBGMは2種類あり、いずれもシンプルながら恐怖感を大いに煽る素晴らしい曲ですぐに気に入った。さらにボス戦でミスをすると、いかにもプレイヤー側がピンチに陥った気になってしまうBGMに変化する。筆者は当時小学生であったが「曲も凝ってるなあ……」と、うなされたことを今でもよく覚えている。
元祖アーケード版との邂逅。「本物」の迫力と演出に感動
1986年の秋か冬のあるとき、当時仲良くなったばかりのゲーム仲間から「アーケード版の『ツインビー』を遊んだ」との話を聞かされた。
本作をどこで遊んだのかを聞いてみたら、それまで筆者がまったく存在を知らなかった、デパート内のゲームコーナーだったとのこと。しかも、その友人は初プレイで1周クリア(※5面のボス、スパイス大王を撃破)したという。根っからの負けず嫌いであった筆者は、後でお小遣いがたまったら、絶対にそのゲームコーナーに遠征するぞと心に決めた。
初プレイでどこまで進んだのかは忘れてしまったが、ファミコン版よりもさらに美しいビジュアルに加え、今まで見たことがない敵が次々と現われ、同じ敵でも出現、行動パターンがまったく違うのでびっくりした。例えば3面には、ショットで破壊できない金棒が大量に出現し、ちょっとでも操作を誤るとバリアを削られてしまう。地上物にも、弾を撃つときには顔を出すが、普段は地面に潜っていて発見しにくい、モグラなどのいやらしい敵が出現する。
空中の一部の敵は、編隊を全滅させるごとに1000点のボーナスが入る仕掛けがあり、多少危ない場面でも毎回ボーナスを狙いたくなってしまう。対ボス戦の最中でも、地上物がどんどん出現して弾を撃ってくるなど「ファミコン版より難しいな……」との印象を受けた。
地上物を破壊した際に、たまに出現するベルを取ると、ファミコン版と同じく空中ショットが3連射になる効果(※ファミコン版はベルではなく、スーパーキャンディーが出現)が、2個目以降のベルを取ると、ファミコン版には登場しない野球ボールが出てくる効果が得られる。ボールはしばらくの間、画面内を高速で飛び回り、触れた敵を次々となぎ倒してくれるのも、これまた快感だった。
結局、その日はスパイス大王を倒すどころか、5面に進むことすらできず本当に悔しかったが、ファミコン版とはまったく異なる体験できてとても嬉しかった。しばらく後になって、分身とバリアを同時に装備できることに偶然気が付くと、それまでのベストスコアは数十万点だったのが一気に200万点まで伸び、先に1周クリアした友人のスコアを超えた思い出も今なお忘れ難い。
ゲームコーナーで、元祖アーケード版のBGMと、ファミコン版では再現されなかったボイスを初めて聞けたときも嬉しかった。
筆者はアーケード版を遊ぶ前に、本作の曲が収録されたアルファレコードのアルバム「コナミゲームミュージックVOL.1」(のカセットテープ版)を友人から借りていたので曲自体は知っていたが、筐体から流れる言わば「原曲」の迫力は、ラジカセとは比較にならないほど凄かった。またファミコン版には存在しない、上位5位以内のスコアを獲得したうえでゲームオーバーになると聞くことができる「ネームレジスト」(名前書き)時の曲も実にカッコよかった。
これはずっと後になって知ったことだが、本作は後に「グラディウス」などにも使用された、コナミのオリジナルシステム基板「バブルシステム」の対応第1弾タイトルである。当時はアーケード用基板のほうが、家庭用よりも同時発色や表示できるキャラの数など、あらゆる面で性能が優れているのが当たり前だった。さらに本基板には、音源がPSGを2チャンネルに加え、ボイスチップとカスタムチップを1チャンネルずつ搭載していたので「ナルホド、だからアーケード版は絵も曲も音色もカッコよくて、しかもボイスの流せるのか!」と、子供心に関心した(つもりになっていた)。
本作はNintendo Switch、プレイステーション 4、Xbox One、SteamでKONAMIが配信中の「アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション」に収録されている。また、Nintendo Switchとプレイステーション 4ではハムスターのアーケードアーカイブス版も配信されている。まだ遊んだことがない人も、本作独特のパワーアップシステムやビジュアル、BGMの素晴らしさをぜひ体験していただきたい。
・Switch版「アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション」のストアページ
・PS4版「アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション」のストアページ
・Xbox One版「アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション」のストアページ
・Steam版「アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション」のストアページ
・Switch版「アーケードアーカイブス ツインビー」のストアページ
・PS4版「アーケードアーカイブス ツインビー」のストアページ
(C)Konami Digital Entertainment





























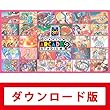





























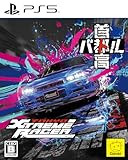










![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)











![【中古】[PS5] DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス ストランディング2: オン ザ ビーチ) 通常版 SIE(20250626) 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480854.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS5] アストロボット(ASTRO BOT) ソニー・インタラクティブエンタテインメント (20240906) 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480649.jpg?_ex=128x128)

![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)



![カプコン 【PS5】バイオハザード レクイエム 通常版【2月28日以降出荷分】 [ELJM-30814 PS5 バイオハザ-ド レクイエム ツウジョウ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0020/4976219137492.jpg?_ex=128x128)









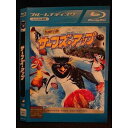


![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)
![アイカツ!×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9421/4580055369421_1_3.jpg?_ex=128x128)
