【特別企画】
大橋編集長勇退記念SP「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」レポート
「ゼビウス」攻略本著者がゼビウス全16エリアクリアに挑戦! 「PasocomMini PC-8801mkⅡSR」も発売決定
2024年5月22日 18:43
- 【ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII】
- 5月18日開催
- 会場:大田区民ホール・アプリコ
2024年5月18日、東京・蒲田の大田区民ホール・アプリコの大ホールで、「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンIII」(以下AABM3)が開催された。
AABMは、その名の通り、電波新聞社から1982年~2003年まで発刊されていたホビーユーザー向けPC雑誌「マイコンBASICマガジン」(通称「ベーマガ」)の読者向けトークイベント。2015年に第1回、2018年に第2回が開催され、今回が6年振り、3回目の開催となる。今回はマイコンBASICマガジンの初代編集長の大橋太郎氏の電波新聞社勇退を記念して開催されたもので、大橋編集長への感謝を伝えるために過去最高の1,300人を超える参加者が集まり、とても盛り上がった。
筆者も、中高生のときにマイコンBASICマガジンを愛読しており、派生して発刊された「ALL ABOUT NAMCO」などの書籍も結構買った覚えがある。自作ゲームも数回投稿したが、本誌への掲載はかなわなかったものの、1987年にマイコンBASICマガジンのスペシャル版として刊行された「PC-8801・PC-8001 プログラム大全集」に筆者が移植したPC-8001mkⅡ用ゲームが掲載され、嬉しかった覚えがある。
AABM3は全3部構成で、13時~18時30分まで開催される予定だったが、トークが盛り上がり過ぎて時間がオーバーし、結局すべてのプログラムが終了したのは19時30分を過ぎるというとても長いイベントとなった。また、トークイベントだけでなく、貴重な資料が展示されたギャラリーコーナーや、オリジナルグッズなどが販売された物販コーナーもあり、特に物販コーナーは12時の開場直後から長蛇の列ができ、トークイベント終了もグッズを買い求める参加者で一杯であった。
ここでは、6時間半を超えたイベントの中でも特に面白かった部分をレポートしていきたい。
X68000版「ボスコニアン」誕生秘話が明らかに!第1部「実録マイコンソフト」
開場は12時だったが、12時前の時点で外にはかなりの行列ができていた。全席指定のイベントなのだが、物販目当てで少しでも早く入場したいという参加者が多かったのであろう。物販コーナーは予想通り、開場と同時に多数参加者が詰めかけ、長蛇の列ができた。イベント開始前に、さくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕氏からのお祝い動画が流された。その動画の中で田中氏は、「小学校の頃からベーマガの読者で、私の小学校、中学校、青春時代はずっとベーマガと一緒でした。この度は改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。これからの活躍に期待しています」とコメントした。
司会進行を務める元ベーマガライターの山下章氏が登場すると、会場から大きな拍手が巻き起こった。山下氏は、過去2回のAABMでも司会進行を務めており(もっと前のベーマガ現役時代も山下氏はよくイベントの司会などを担当していた)、司会はお手の物だ。山下氏が、第2回のイベントに来てくれた人は手を上げて下さいといったところ、7割くらいの人が手を上げ、やはり毎回参加している熱心な読者が多いことがわかった。
続いて、電波新聞社社長の平山勉氏が来場者への挨拶を行ない、「このイベントは、山下さんを始めとする関係者の方々が作り上げたイベントで、参加者の皆様の参加があってこそのイベントだと思っていますので、皆様と一緒に楽しんでいければと思っています。本日は大橋編集長勇退記念ということですが、大橋編集長は結構色々喋っちゃう人なので、そこが唯一の不安です。話しちゃいけないことは皆さんの胸の中にしまっていただいて、最後まで楽しんでいってください」と語った。
第1部のテーマは「実録マイコンソフト」で、元マイコンソフトウェア開発室課長だった大橋太郎氏をはじめ、なにわこと藤岡忠氏、X68000版ファンタジーゾーンディレクターの土田康司氏、YK-2こと古代祐三氏、Yu-Youこと永田英哉氏が登壇した。
まず大橋氏が、マイコンソフトウェアができた経緯について、「当時の副社長がとにかくゲームソフトを作れと、私は何もゲームが分からないので、まず最初にゲームセンターに行ってゲームが上手な人を探すというのがスタートでした」と語りはじめた。以下、第1部のトークの主な内容をまとめておきたい。
マイコンソフトウェアの代表作といえば、やはり「ゼビウス」の移植だが、社内に「ゼビウス」をクリアできる人が誰もいなかったため、ナムコのゼビウス開発者の遠藤さんにゼビウスをクリアできる人を2人紹介してもらったのだという。その1人が大堀さんだ。当時大堀さんは高校生で、しかもかなり校則が厳しい私立高校に通っていたため、ゲームセンターで会うことはできず、大堀さんの帰り道に待ち伏せしてコンタクトしたという。X1版「ゼビウス」をまず開発していたのだが、開発途中のバージョンを遠藤さんに見せたところ、「これじゃはっきり言ってゴミだ」ととても厳しい評価をもらい、徹底的にプログラムを作り直した。「1ヶ月死に物狂いで頑張って、なんとかこれならいいと言っていただきました」(藤岡氏)
マイコンルームでベーマガに投稿されたプログラムをチェックしていたところ、2度大事件があった。その1つが、松島徹氏が14歳の時に投稿したPC-6001用の「ゼビウス」だ。スペックの低いPC-6001で、ゼビウスをできる限り再現していた。「マイコンルームのほうから、課長、大変だ。アンドアジェネシスがPC-6001で動いてる!」と叫び声が聞こえたそうだ。これは市販すべきだということで、すぐ親御さんのところにいき、契約を結び、「タイニーゼビウス」として発売されることになった。松島氏はまごうことなき天才であり、それを発掘したのがベーマガなのだ。
もう1つの大事件は、当時高校生だった古代祐三氏が編集部に持ち込んだ「ドルアーガの塔」のゲームミュージックプログラムである。「PC-8801mkⅡSR用のプログラムなのですが、当時僕はPC-8801mkⅡSRを持っていなかったので、持っている友人の家に毎日寄ってプログラミングしてたんですよ。ビデオゲーム大全集みたいなのの募集があって、そこに投稿しようと思っていたんですが、締め切りが過ぎちゃってたので、学校帰りに公衆電話から編集部に電話して、今からこれを持っていっていいですかと」(古代氏) その古代氏のゲームミュージックプログラムの完成度の高さにも、マイコンルーム一同が驚いたという。
マイコンソフトと言えば、やはりX68000抜きに語ることはできない。X68000全盛期に、マイコンソフトは次々とX68000版ゲームソフトを開発していた。それぞれのソフトごとに語りたいエピソードがある。「源平討魔伝」では、音声の品質がオリジナルよりよくなっているのだが、一つだけ元の音質で入ってる台詞がある。また、「ドラゴンスピリット」では、X68000のスプライト数がギリギリで、なんとかスプライトをやり繰りして実現した。当時は移植といってもアルゴリズムをそのままもらえるわけではなく、もらったとしてもアーケードとは縦横比が違ったりするので、基本は目で見た動きを再現する、ゲーム性を再現することに注力した。
マイコンソフトから1988年に発売されたX68000版「ボスコニアン」だが、なぜこのタイミングで急にX68000にボスコニアンが登場したのか不思議に思ったことはないだろうか。実はこのとき、マイコンソフトでは次に発売するX68000版ソフトとして「アフターバーナーⅡ」を開発していたのだ。開発者は、あの「タイニーゼビウス」を開発した天才、松島氏だ。ある日、アフターバーナーⅡの進捗を見せてくれということで、松島氏から渡されたフロッピーを起動したら、なんとアフターバーナーⅡではなくボスコニアンが起動した。それを見て、藤岡氏はがっかりして片膝をついてしまったそうだ。その後、藤岡氏が大橋氏にその件を相談に行き、もう作っちゃってるのであれば製品にして売ろうということになったそうだ。X68000版「ボスコニアン」は、オリジナルの「ボスコニアン」を単に移植しただけではなく、グラフィックやBGMが大きく強化されている。その楽曲を作曲したのが、Yu-Youこと永田英哉氏とYK-2こと古代祐三氏である。また「ボスコニアン」は、X68000用市販ゲームで初めてADPCMのサンプリング音声とFM音源が同期演奏された作品でもある。
最後にマイコンソフトについて、大橋氏は次のように振り返った。「私は本当は嫌だったんですよ。だってもう既に中年でしたし、ゲームはもう一段落したと思っていたんです。そこでなぜ私がゲームをさらに発表しなくちゃいけないのかというのが不安だったんですが、実際はテレビの番組を超える新しい文化だと言うことに、多分一番最初に気付いた中年だったんじゃないかなと思います」(大橋氏)
最初のサプライズは「PasocomMini PC-8801mkⅡSR」の発表
AABM3は全3部構成だが、各パートの最後にサプライズタイムがあり、ビッグニュースが公開されるという流れになっていた。第1部のサプライズタイムのゲストとして、元ハル研究所の三津原敏氏と電波新聞社の大上友也氏が登場。
三津原氏は、運んできたPC-8801mkⅡSRの箱から何かを取り出そうとしている。箱から出てきたのは、手のひらサイズのミニチュアPC「PasocomMini PC-8801mkⅡSR」であった。8ビット時代のPCをミニチュア化した「PasocomMini」シリーズは、元々ハル研究所が開発・販売しており、過去に「PasocomMini PC-8001」と「PasocomMini MZ-80C」の2製品が販売されていた。「PasocomMini」シリーズは、Raspberry Pi Zeroなどのシングルボードコンピューターに、それぞれのPCのエミュレーターとゲームソフトなどを搭載したものであり、「PasocomMini PC-8001」には全部で21種類のゲームがバンドルされていた(追加分も含む)。
今回、ハル研究所の熱い思いを電波新聞社が受け継ぐ形になり、「PasocomMini PC-8801mkⅡSR」の電波新聞社からの発売が決定した。内蔵ゲームソフトや価格などの詳細については、2024年8月8日に発表されるとのことだ。PC-8801mkⅡSRは、FM音源を搭載し、ゲームにおける表現力が大きく向上した名機であり、「テクザー」や「シルフィード」などの人気ゲームが多数開発された。8月8日の詳細発表に期待したい。










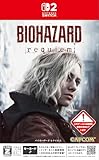








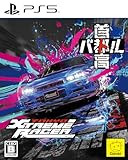











![【Amazon.co.jp限定】劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray【特装版】(早期予約メーカー特典クリアファイル+L判ブロマイド5枚セット付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41N2LB75ruL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)



![[代引決済不可][ニンテンドースイッチ2ソフト] バイオハザード レクイエム 通常版 [POT-P-AA2PA] *数量限定特典付 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/outletplaza/cabinet/261/4976219137485.jpg?_ex=128x128)
![I/Oデータ 【Switch2】microSD Express カード Switch2対応512GB [HNMSD-EX512G] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0008/4957180186269.jpg?_ex=128x128)

![【あみあみ限定版】【特典】白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition 限定版 あみあみパック[インティ・クリエイツ]《07月予約》 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/pb/2026/091/game-0033977.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【新品】【NS2】バイオハザード レクイエム[Switch2版][在庫品] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10890000/10898741.jpg?_ex=128x128)


![Cygames 【Joshinオリジナル特典付】【PS5】GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok [ELJM-30907 PS5 グランブル-ファンタジ- リリンク エンドレスラグナロク] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0057/4570142016499.jpg?_ex=128x128)

![Kepler Interactive 【PS5】Clair Obscur: Expedition 33 [ELJM-30644 PS5 クレ-ル オブスキュ-ル エクスペディション 33] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0463/4974365838577.jpg?_ex=128x128)
![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)



![Pearl Abyss 【Joshinオリジナル特典付】【PS5】紅の砂漠 通常版 [ELJM-30776 PS5 クレナイノサバク ツウジョウ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0046/4580717790976.jpg?_ex=128x128)





![[Switch] あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス (ダウンロード版) ※2,000ポイントまでご利用可 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/1/802251631_p.jpg?_ex=128x128)

![[Switch] Nintendo Switch Online + 追加パック個人プラン12か月(365日間)利用券 (ダウンロード版) ※1,000ポイントまでご利用可 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/3/802252363_p.jpg?_ex=128x128)
![任天堂 ニンテンドーサウンドクロック Alarmo [CLO-S-RAAAA アラ-モ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0479/4902370552195.jpg?_ex=128x128)
![シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME【通常版】(Blu-ray)【Blu-ray】 [ 庵野秀明 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8634/4988003878634_1_2.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 3(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1345/4534530161345_1_2.jpg?_ex=128x128)
![グノーシア 4(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ petit depotto ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1352/4534530161352.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5714/2100014785714_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5【Blu-ray】 [ 西崎義展 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9383/4934569369383_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】[先着特典付]新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/251/bcqa-0025a.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】22/7 計算外 season1 4 (初回仕様限定版) 【Blu-ray】(22/7 キャスト撮り下ろしブロマイド (椎名桜月)) [ 7/22 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5498/2100014595498.jpg?_ex=128x128)
![魔都精兵のスレイブ2 Vol.2【Blu-ray】 [ タカヒロ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4273/4524135284273.jpg?_ex=128x128)