【特別企画】
Razerの最新ワイヤレスゲーミングマウス「Viper V3 Pro」4月26日発売決定!
プロトver.は「VALORANT」大会使用で優勝実績あり!使い心地を実際に体験
2024年4月24日 11:00
- 【Viper V3 Pro】
- 4月26日 発売予定
- 価格:26,480円
Razerは、ワイヤレスゲーミングマウス「VIPER」シリーズの最新モデル「Viper V3 Pro」を4月26日より発売する。価格は26,480円で、本体カラーはブラックとホワイトの2色が展開される。
「VIPER」シリーズはオーソドックスな形状のワイヤレスゲーミングマウス。最新モデルの「Viper V3 Pro」では他シリーズなどで採用された新技術を踏襲しつつ、形状が更に洗練され、持ちやすさと機能性を両立させている。
今回はメディア向けの内覧会にて事前に触れる機会を得たので、実際に操作した感触や製品の詳細について紹介していきたい。
プロトタイプを使ったZENKEN氏が世界大会で優勝の実績も!
Razerの「Viper V3 Pro」は同社が数多く発売するマウス製品の中でもオーソドックスな形状をベースとしたゲーミングワイヤレスマウスの最新モデル。
搭載する光学センサーは自社開発の「Razer FOCUS PRO 35K オプティカルセンサー」で、今回のセンサーは第2世代となる最新バージョンを採用。感度は最大35,000DPIだが、1DPI単位での調整が行なえる。最大速度は750IPS、最大加速度は70Gで、トラッキングの解像精度は99.8%を誇る。また、様々なマウスマットに互換性があり、4mm以上の厚さのクリアガラスでトラッキングが行なえるとしている。
同社ワイヤレスマウス製品では2023年から採用する8Kワイヤレスポーリングレートにも対応。より滑らかなトラッキングにより、ワイヤレス製品のクリック遅延を最小化しており、信頼性と安定性を向上している。マウススイッチには第3世代RAZERオプティカルマウススイッチを採用。90ミリオン(9,000万)クリックの耐久性があるとしている。
形状については、マウス後部が従来より高めに設計されており、手のひらを被せる形で使用するつかみ持ち時の安定性が高まっている。また、ボタンの隙間に指が挟まる事象を防ぐため、クリックボタンの外の部分に段差を設けた。加えて、サイドボタンの位置を変更したほか、2個のサイドボタンの間に僅かな隙間を儲けるデザインにしたことで、利便性が向上している。
本製品の特徴の1つが軽さで、本体重量は54g(White Editionは55g)となっており、前モデルのV2と比べて軽量化に成功している。軽量化については機械的な再設計によるものとしているほか、素材の厳選などにより、一般的には重くなると言われているポストコンシューマーリサイクル材料を使用していながらも軽量化を実現したという。
また、バッテリー駆動時間は1,000Hzポーリングレート使用時の駆動時間は最大95時間で、8Kポーリングレート使用時は17時間。さらに、 AIを活かした「インテリジェントAI機能」により、スマートトラッキング、非対称カットオフ、モーションシンクなどの機能も備えている。
本製品は試作の段階から多くのプロゲーマーたちの手によってテストされ、多くのフィードバックを得て完成度を高めた経緯がある。具体的には、2023年10月以降、5つのメジャートーナメントにおいて45人以上のプロプレーヤーによってテストされており、それらのフィードバックが詰まっているという。
アメリカ・ロサンゼルスに本拠を置くeスポーツチーム・Sentinels所属のプロプレーヤー、ZEKKEN氏は3月にスペイン・マドリードで行なわれた「VALORANT」の世界大会「VCT 2024 Masters Madrid」に北米代表として出場し、見事にチーム優勝を勝ち取った。この時、実際に試合で使用していたのが、何を隠そう開発中の「Viper V3 Pro」のプロトタイプバージョンだったとしており、発売前から世界大会優勝の実績を持ったゲーミングマウスと言えるだろう。
従来よりオーソドックスなデザイン、形状に原点回帰
今回は実際に「Viper V3 Pro」と「Viper V2 Pro」の2台を比較しながら試した上で、改めて本製品の使い心地についてチェックしてみた。
先ずは外観からチェックしていこう。「Viper V3 Pro」の形状は「Viper V2 Pro」と比較すると、つかみ持ちの際に更に安定した収まり心地となっている。「Viper V2 Pro」を持つと手のひらの部分に若干の隙間を感じるのだが、この隙間が「Viper V3 Pro」だとすっぽり収まる。また、つまみ持ちの場合であっても軽量化が功を奏するため、スムーズなマウス操作が期待できそうだ。
「Viper V3 Pro」の表面には滑らかなコーティングが施されている。一方で「Viper V2 Pro」はザラザラとした触感のコーティングになっており、これについてはどちらも一長一短あり、好みの問題と言えるだろう。ただ、プロゲーマーたちからのフィードバックの結果がこのコーティングという点を考えると、長時間の利用には滑らかなコーティングの方が向いているのかもしれない。
マウス底面部に張り付けられているソールについても形状が変更されており、「Viper V3 Pro」ではその面積がかなり増加していた。ただし、実際に比べてみてもソールの違いがどのくらい操作に影響を与えるかまでは判断できなかったが、よりスムーズなスワイプ操作の実現に寄与しているのは間違いないだろう。
| 仕様 | Viper V3 Pro | Viper V2 Pro |
|---|---|---|
| 外型設計 | 左右対称の右利き用 | 左右対称の右利き用 |
| 接続仕様 | Razer HyperSpeed Wireless/有線 | Razer HyperSpeed Wireless/有線 - Speedflex ケーブル |
| バッテリー持続時間 | 1000Hzで最大95時間 | 1000Hzで最大90時間 |
| センサー | 第2世代 Focus Pro 35K オプティカルセンサー | FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー |
| 最大感度 (DPI) | 35000 | 30000 |
| 最快速度 (IPS) | 750 | 750 |
| 最快加速度 (G) | 70 | 70 |
| プログラム可能なボタン | 6 | 6 |
| スイッチのタイプ | 第3世代オプティカルマウススイッチ | 第3世代オプティカルマウススイッチ |
| スイッチのライフサイクル | クリック回数9000万回 | クリック回数9000万回 |
| オンボードメモリプロファイル | 1 | 1 |
| 滑鼠腳 | 100% PTFE | 100% PTFE |
| ケーブル | USB Type-A to C ケーブル | Razer Speedflex USB Type-C ケーブル |
| 概算サイズ | 長さ:127.1mm 幅:63.9mm 高さ:39.9mm | 長さ:126.5mm 幅:66.2mm 高さ:37.8mm |
| 概算重量 | 54g(White Editionは55g) | 58g |
ソフトウェアの機能において、個人的にユニークに感じたのは、旧バージョンなど設定済みのマウスがある場合に、本製品とそれを並べて動かすことで、現在使用しているマウスの感度設定を自動で本製品の設定に移行できる「感度マッチャーキャリブレーション」の機能だ。しかも対象のマウスは同社製品ではなくても、この機能を使う事で、同じ感度設定にしてくれるので、スムーズに移行が可能となっている。
実際にエイミングの練習ソフト「Aimlabs」を使用して、2台のマウスによる操作をチェックしてみた。練習ソフトのスコアだけ見ると「Viper V3 Pro」を使った方が「Viper V2 Pro」より、命中精度もエイムの速度も上となったが、どちらかというとこれはソフトに対する慣れの要素の方が大きいので、あまり当てにはならない。
実際の操作感で言うと、終始安定して操作できたのは「Viper V3 Pro」だった。これは筆者がつかみ持ちで利用していた事もあるが、狙ったポイントにスムーズに移動でき、止めるべきポイントで的確に止まったような感触が味わえた。ただし、筆者はここ数年マウスをほぼ使用していないため、この感想は参考程度に考えてみて貰えれば幸いだ。
本製品については筆者の感想より何よりも実際に世界大会で使用され優勝実績があるというのが大きな説得力になると思うが、「VALORANT」のようなゲームにおいてほんの少しの差が勝敗をわけるという場合には、やはり様々なフィードバックを受けて開発された新モデルというのはとてもオススメできる。ゲーミングマウス購入を検討している方はこの機会にぜひ試していただきたい。
なお、本日の情報解禁と同時に本製品の予約受付も開始されているので、取り扱いストアをチェックしてみてほしい。
(C)2024 Razer Inc. All rights reserved.





















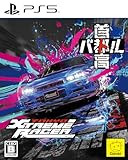











![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)


![[Switch 2] ぽこ あ ポケモン (ダウンロード版)※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/0/802252610_p.jpg?_ex=128x128)





![[未使用]【switch2】Nintendo Switch 2 日本語・国内専用 本体 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/treasure-eight/cabinet/product/game-hard/12888180/imgrc0107636148.jpg?_ex=128x128)

![[メール便OK]【新品】【PS5】ソニックフロンティア[PS5版][お取寄せ品] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10630000/10632153.jpg?_ex=128x128)





![【特典】PS5 ソニック × シャドウ ジェネレーションズ:コレクターズエディション[セガ]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2024/232/game-0030772.jpg?_ex=128x128)
![スクウェア・エニックス 【PS5】STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN(ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン) [ELJM-30103 PS5 ストレンジャーオブパラダイス ファイナルファンタジーオリジン] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0052/4988601011082.jpg?_ex=128x128)




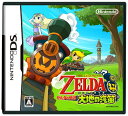

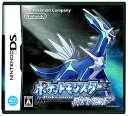






![【中古】 劇場版名探偵コナン ゼロの執行人 通常盤 Blu-ray Blu-ray / ビーイング [Blu-ray]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/12062936/dvcojc6uqkl4leur.jpg?_ex=128x128)
![【中古】【Blu−ray】ライオン・キング MovieNEX (Blu−ray+DVD) リーフレット付 [デジタルコピー付属なし] / ロジャー・アラーズ【監督】 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/renet20/cabinet/item_photo/001301/6/0013016830.jpg?_ex=128x128)
![【中古】 劇場版 名探偵コナン緋色の弾丸 通常盤 BD Blu-ray Blu-ray / ビーイング [Blu-ray]【ネコポス発送】 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo/cabinet/no_image.jpg?_ex=128x128)
![TVアニメ「羅小黒戦記」2(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 花澤香菜 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2175/4534530162175_1_2.jpg?_ex=128x128)
![『葬送のフリーレン』Season 2 Vol.3 初回生産限定版【Blu-ray】 [ 山田鐘人 ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5504/4988104155504.jpg?_ex=128x128)
![『葬送のフリーレン』Season 2 Vol.2 初回生産限定版【Blu-ray】 [ 山田鐘人 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5498/4988104155498.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)
![僕とロボコ ロボコンプリートブルーレイボックス【Blu-ray】 [ 宮崎周平 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2137/4907953222137_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】[限定版][先着特典付]アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!- Blu-ray(初回生産限定盤)/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/421/eyxa-14942.jpg?_ex=128x128)