インタビュー
”トレボー”ことロバート・ウッドヘッド氏らに聞く「ウィザードリィ」の今昔
リメイク版「ウィザードリィ:狂王の試練場」いよいよ日本語版リリース!
2024年5月23日 00:00
- 【ウィザードリィ:狂王の試練場】
- 5月23日 発売予定
- 5月24日午前1時 日本語アップデート予定(Steam版)
現在、Steamにてアーリーアクセスが実施されている、Apple II版の初代「ウィザードリィ」をリメイクした「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord(ウィザードリィ:狂王の試練場)」。そのプレイステーション 5/4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch版が5月23日よりDigital Eclipseから配信されることが発表されている。また、発売に合わせて現在英語版のみのPC(Steam)版にも日本語アップデートが適用される。
リメイク版「ウィザードリィ:狂王の試練場」の大元となった「Wizardry : PROVING GROUNDS OF THE MAD OVERLORD」は、1981年にアップルコンピュータ(現アップル)から発売された、パーソナルコンピュータApple II用タイトルとしてリリースされたRPG初期の作品だ。目的は、3Dのワイヤーフレームで表示されるダンジョン内を探索し、狂王トレボーの命令のもと、地下10階に潜む大魔導師ワードナが持つ魔除けを取り戻すこと。
しかし、魔除けを取り戻したから終わりというわけではない。むしろここからが本番で、永遠に続けられるとも思えるキャラクターのレベルアップ、そしてダンジョンの奥深くで見つける宝箱の中にしか存在しない超強力なレアアイテムを求め、大勢のプレーヤーがその魅力に取り憑かれた歴史に残る名作だ。
リメイク版では、グラフィックスが現代風にリファインされただけでなく、オートマッピングといった機能も備えている。しかし、設定次第では当時のままに戻すこともできるため、どのようなユーザーでも好みの環境でプレイできるようになっているのが特徴だ。
今回、リメイク版「ウィザードリィ:狂王の試練場」リリースに合わせて、開発スタジオであるDigital Eclipseからプロデューサーのジャスティン・ベイリー氏と、リメイク版のアドバイザーを務めた初代「ウィザードリィ」作者のひとりであるロバート・ウッドヘッド氏が来日した。幸いにしてインタビューを行なう機会を得たので、リメイク版だけでなく初代にまつわるいくつかの疑問もぶつけてみたところ、興味深い答えが返ってきたので、ここで紹介しよう。
「ウィザードリィ:狂王の試練場」を現代でも遊びやすく!
――最初に、今回の来日の目的を教えてください
ベイリー氏:私はDigital Eclipseというゲーム開発スタジオに所属していますが、目標・やろうとしていることが、ゲーマーの間で有名なフランチャイズを現代のユーザーに届けることなんです。それだけではなくコアユーザーや過去のユーザー、その当時に有名ゲームを遊べた方々が満足できるように、または新規ユーザーでも楽しめるように当時のゲームを新規でリメイクしたりしてユーザーに届けています。
その中には、例えば前年は「Street Fighter 30th Anniversary Collection」や、「ATARI 50:THE ANNIVERSARY CELEBRATION」「MEGA MAN LEGACY COLLECTION」などがあるのですが、中でも特に愛されていて現代のユーザーに届けたいと思っていたのが「ウィザードリィ」というクラシックシリーズなんです。リマスターに関わって数年間ぐらい経過して、もう間もなくリリースとなります。
――今回のリメイク作品について、話を聞いた時はどう思いましたか? 率直な感想をおしえてください。
ウッドヘッド氏:一番最初の印象としては、「cool!」でした。実際に見て触れたところ品質が高く、デザインも面白いことをしようとしているなというのがわかりました。この40年間に渡って現代化されており、昔に愛された作品としてはとても衝撃的でした。
――元になったシリーズ1作目「Wizardry : PROVING GROUNDS OF THE MAD OVERLORD」は、アメリカでも未だに人気作なのでしょうか?
ウッドヘッド氏:その認識です。ただし、ここ数年間はPCで遊べるような環境がなく、特に現代のPCでプレイすることができませんでした。つまりそれまで初代「ウィザードリィ」は“RPGの歴史の一部として大事な立場の作品”ということでした。今回の「ウィザードリィ:狂王の試練場」は、新しいプレーヤーや新しいゲーマーに、本当に大昔のRPGとは? 当時はどんな感じだったのか? を味わう機会を提供しているのです。
――今回の「ウィザードリィ:狂王の試練場」に、ウッドヘッドさんはどの程度関わっているのでしょうか。
ウッドヘッド氏:基本的には、必要に応じてフィードバックする程度ですが、ゲームを見るたびに良くやってくれているなと思っていました。
――リメイクに際して大変だったのは、どんなところでしたか。
ベイリー氏:特別難しいところはなかったかなと思います。今⽇は、まだ話していないチャレンジとして興味深かったことをお伝えしたいと思います。オリジナルのゲームには、たくさんの罠があります。暗闇のダークゾーンや上に乗ると床が回転するスピナー、そしてテレポートなどです。悩んだのは、オリジナルのゲーム感覚を損なわない形でオートマッピングを追加する方法でした。現代風にリメイクするにはオートマッピングという機能が必要だと思ったのですが、その方法として昔のプレイ感覚と現代のプレイ感覚、両方を満足させないといけないという意識がありました。
私たちがやりたかったことのひとつは、たとえオートマッピングがあったとしても、ダークゾーンやスピナー、テレポートといったエリアにプレーヤーが行くと、オートマッピングを信頼できないナビゲータのようにすることです。そこで、Steam版のアーリーアクセスにて一度実装してみたのですが、ユーザーからは「オートマッピングが正確に働いておらず微妙だ」と言われてしまいました。制作側としては、当時のミステリアスな感覚が失われないよう意図的に実装したものなのですが……。
それで、どうすればオリジナルに忠実でありながら、現代のゲーマーにアピールできるのか? それを何度も何度も考え直しました。最終的には一定のエリア、自分から6マスくらいまでの範囲しか表示しないようにして、そのエリア内の様子はわかるけれど、その外に関しては確認できないように調整しました。マップを表示出来る「DUMAPIC」の呪文を使うとより正確に表示されるようにして、この問題を解決としました。
――当初の実装のままでも、面白そうなシステムでしたね。
ベイリー氏:確かに、当初の方が面白かったところもあったのではないかと思ったりします。実際、例えばFacebookグループなどでユーザーの声を聞くと、グラフィックスを現代化したことに対して一部のユーザーからは「何故このグラフィックスを変える必要があるのか、そのままで良かったのではないか」などの批判の声も上がってきました。
つまり、全員を満足させるのはやはり難しいということです。そのために、オプション画面ではかなり細かい設定項目を設けているのですが、デフォルトのセットは現代のゲーマーが望むものに合わせてあります。それらをオフにすれば、オートマッピングなども全部切ることができるので、本当に当時そのままという遊び方をすることもできます。右下のライングラフィックスも、メイン画面と同じ大きさにして遊ぶことが可能なので、このような部分も含めてできるだけ多くのユーザーが望むような環境に仕上がっていると思っています。
――PS4版をプレイしましたが、全体的に昔と比べて物凄く親切になってることに驚きました。特にキャラクターメイキング後、ヒットポイントが8ではないことにビックリしました。この辺りは色々と考えて現代に合わせたのでしょうか。
ベイリー氏:そのあたりは議論を重ねました。関連の話としては、熱心な開発スタッフのおかげで良いクオリティに仕上がっていると言うことです。皆「ウィザードリィ」の大ファンということで、ロバート・ウッドヘッドさんが開発スタジオに来た時は色々聞いて欲しかったのに、スタッフ陣は「神(=ウッドヘッドさん)が目の前に歩いてきて、緊張してあまり聞けなかった」という事態になりました(笑)。
ともかく、全員がプロジェクトに対する情熱を持っているので良い作りになっているんです。ただ、昔のゲームは周回プレイのことがあまり考えられていません。もっとも、あの時点では周回プレイという意識は、ゲームデザイン面においてはありませんでした。さらに、ゲームのやりやすさ、遊びやすさというところでの入口を広げるため、マニュアル不要にしました。例えばキャラメイクの画面では、マニュアルに書いてあるようなことをすぐ横に表示しています。すべての必要情報が、ゲーム画面の中に揃えているということが重要なポイントです。
マニュアルが必要ない作りにしている一面としては、元のゲームがかなり複雑だったためです。プレーヤーにはあまり見えていませんが、実は内部の挙動を見ると各行動ごとに複雑な処理が成されています。例えば、ダンジョン内を1マス歩くというアクションに対して、実は裏でサイコロを振っているような感じの処理が行なわれているのです。そこで出目に応じて敵とエンカウントしたりという事象が一定確率で発生しますが、それはプレーヤーには見えていませんでした。今回のリメイク版では、キャラクター画面の中にはパラメータの発生確率など、そういった数値がすべて揃えてあります。今まではユーザーに伝わらなかったり、伝え方もなかったのですが、「ウィザードリィ:狂王の試練場」は現代のゲームなので、それらの情報がプレーヤーにも伝わりやすい環境を作り、各種インフォメーションも表示するようにしています。
――プレイ中、右下に表示される画面はApple II版でした。日本人プレーヤーに馴染みのある国内PC版や、またはコンソール機版の画面を表示するようなアップデートは、行なわれる可能性はあるでしょうか。
ベイリー氏:現在のところ予定はないですが、プレーヤーの方々からのフィードバックには常に耳を傾けるように心がけています。本作を初めてプレイした方は日本人に関わらず、PCから始まったユーザーもいればコンソール機から始まった人もいるので、ユーザーが懐かしいと思う時代が人によって異なります。なので今回はゲームの機能としては、どの時代の人間なのかにかかわらず、本当に自分の思い出のままでプレイできるというオプション環境を提供しました。懐かしく感じてもらって楽しくプレイできるように、ということにしています。
――少々気が早いお話ですが、1作目のリメイクは現段階でも高い評価を受けています。今後2作目、3作目と続く可能性はあるのでしょうか?
ベイリー氏:今現在は、「ウィザードリィ:狂王の試練場」に集中しています。もちろん、すごく期待されているのは知っていますが、今年は「Wizardry : PROVING GROUNDS OF THE MAD OVERLORD」43年目でもありますし、「ウィザードリィ」シリーズのお祝いとして本作をリリースしたいということです。将来に関しては、本作を出してから検討します。
ウッドヘッド氏「RPGは全てチェインメイルのようなもの」
――ウッドヘッドさんが来日した貴重なタイミングに伺いたいのですが、初代「ウィザードリィ」をなぜRPGとして作ろうと思ったのか、という根本的なことを教えてください。
ウッドヘッド氏:実は、本当にわからないんです。特に深い理由はなかったと思いますが、その当時はRPGが一番面白いものになるんじゃないかなという考えはあったと思います。
ベイリー氏:この当時、RPGというジャンルはありました?
ウッドヘッド氏:テーブルトークRPG、「ダンジョンズ&ドラゴンズ」だったり、他の作品もありましたよ。ともかく深く考えずに、RPGが一番面白く楽しい、かつ楽しく作れるものになるんじゃないかと考えました。
――当時、RPG以外のジャンルのゲームは遊んでいましたか?
ウッドヘッド氏:はい、もちろん。PLATO(世界初の汎用コンピュータ支援教育システム。いわゆるCAI。アクティビジョンの「上海」の元となった「Mahjong solitaire」など、いくつかのゲームもあった)システムだったり、アーケードゲームから移植されたApple IIのゲームなどをたくさん遊んでいました。でも、プログラミングの方に興味があり、ゲームを遊ぶよりもゲームの蓋を開けて“どうしてこのゲームがこんな動きするのか”という方に魅力を感じていて、そちらに集中し始めました。
――日本で「ウィザードリィ」が発売された時は、国内では既にBPSの「ブラックオニキス」やT&E SOFTの「ハイドライド」といったRPGが登場していました。そのあたりのタイトルについては、知っていましたか?
ウッドヘッド氏:知っていましたが、 私が彼らのことを知ったのは「ウィザードリィ」が発売された後です。覚えておいてほしいのは、当時はインターネットもなく情報の流れが遅かったということです。コンピュータ雑誌も創刊されたばかりでした。僕は田舎にいたので、いろいろなことが真空地帯で起こっていて、他の人たちが何をやっているのかを知るのは、かなり後になってからでした。
プログラミングの勉強も同じで、今ならプログラミングの問題があれば、その解決方法を知るためにインターネットを使えば無限のリソースがあります。プログラマーが何か問題を抱えていても、ネットを検索すれば解決策が出てくる。しかし「ウィザードリィ」のプログラムを書いていたときは、教科書のようなものしかなかったのです。だからこのときは、いわゆる“車輪の再発明”をし続けていました。「ウィザードリィ」の開発では、何度かそういうことがありました。自分で凄い名案が浮かんだとか、凄くいいことを思いついたと思ったら、実はみんな同じことやっていたと。あの当時は情報、リソースが少なかったので、仕方の無かったことでした。
――「ブラックオニキス」といえば、一時期「ウィザードリィ」とデータ交換できるという話題が日本では流行ったのですが、ご存知ですか?
ウッドヘッド氏:「ブラックオニキス」だったかはよく覚えていないのですが、「ウィザードリィ」が流行った頃から、別のゲームに「ウィザードリィ」のデータをインポートできるというのがありましたので、そういったタイトルはある程度把握しています。
――日本では特に人気がある「ウィザードリィ」シリーズですが、国内では今年が1作目発売から40年近くとなります。この間、ウィザードリィが日本のRPGに与えた影響は計り知れませんが、その辺りについてはどう思いますか。
ウッドヘッド氏:自分のやったことが影響力を持ち続けているという事実に、とても光栄で謙虚な気持ちです。でも僕は、RPGはすべてチェインメイル(鎖帷子・くさりかたびら)のようなものであり、「ウィザードリィ」はそのチェインメイルの中の小さな繋がりに過ぎないと思っています。
「ウィザードリィ」が「ダンジョンズ&ドラゴンズ」やテーブルゲームなどと、そしてアメリカでも日本でも「ウィザードリィ」以降のすべてのゲームと繋がっている。RPGというジャンルの中心にある、リンクのひとつであるのは素晴らしいことかもしれません。「ウィザードリィ」が、多くの人の心の中にあるのは嬉しいことですが、しかしそれを強調するあまり、同時期に登場した他のゲームや、「ウィザードリィ」の後に登場した他のゲームに十分な評価が与えられないのではないかとも思い、それは良くないことだと思うこともあります。
なぜかというと、それでは本当に「ウィザードリィ」だけが特別で、それより前に存在したゲーム、その後に生まれたゲームが特別ではないということになってしまうからです。全てが繋がったチェインメイルであり、全てが特別な存在であることを意識するべきではないかと思います。
――日本には今でも1作目のファンが大勢います。それについてはどう思いますか?
ウッドヘッド氏:私のように年を取ってるんじゃないの?(笑)。冗談はともかく真面目に答えると、今でもこのゲームに思い出があるというのは素晴らしいことです。この「ウィザードリィ」をプレイし、そして本作をゲーム界の永遠の一部にしてくれた人々には、温かい気持ちしかありません。
――「ウィザードリィ」のゲームシステムがあの形になったのは、どういった経緯があったのでしょうか。
ウッドヘッド氏:各時代のゲームはその当時のパソコンおよびそのツールに依存するものです。例えば、「ウィザードリィ」のゲームループはシンプルでしたが、時代が経つごとにゲームループがより複雑になってきています。それはハードウェアスペックなどの影響が大きいということですね。
例を挙げると、「ウィザードリィ」シリーズは3D形式でゲームを表現しようとしていましたが、堀井雄二さんが作った「ドラゴンクエスト」シリーズは上から見る視点になっています。それは何故かと言うと、恐らく当時の日本のコンピューターがタイルグラフィックスの表現が得意な作りになってるからではないかと思います。つまり時代ごとのハードウェアのスペック及び、その得意とするところがゲームデザインとして大きな影響を与えたと言うことですね。
1980年代、1990年代、2000年代と各時代を渡って見ていくと、グラフィックスはどんどん良くなっていく。つまり、それはマシンスペックが良くなっていってるということです。逆に、「ウィザードリィ」当時のPCはあの程度のスペックしかなかったので、あれぐらいの描画でした。現代のグラフィックススペックが当時あれば、もっと見た目が現代的なゲームになっていたのではないかなと思います。総じて、ハードがゲームの表現に影響を及ぼすことが大きいですね。
――ウッドヘッドさんに関して、日本のファンの多くに”初期「ウィザードリィ」シリーズを作った人”という認識はあるかと思いますが、その後に何をしたのかを知っている人は多くありません。ここで、“「ウィザードリィ」のその後”を教えてもらえますか。
ウッドヘッド氏:「ウィザードリィ」シリーズの後、MMOゲーム制作のために来日しました。しかし、ちょうどバブル時代が終わりゲーム資金が途絶えてしまい、結局実現できませんでした。でも、週末には楽しいプロジェクトもありました。それはアニメの字幕をつけ、アメリカで公開するというもので、すぐにフルタイムの仕事になりました。30年以上やり続けたことによって、文字通り何百本もの作品をリリースしてきています。
――日本のアニメ作品に、字幕を付ける仕事をしていたんですね。
ウッドヘッド氏:人生における多くのことと同じように、小さな偶然やいろいろなことが重なり、そのような機会に恵まれました。きっかけは、「ウィザードリィ IV」の作者であり友人のロー・アダムスが、元々日本のアニメファンだったことです。1980年代当時、アメリカでは日本のアニメは売られていませんでした。その頃、彼と私は映像の上にグラフィックスを載せることができるコンピュータボードで遊んでいたんです。
すると彼は、そのシステムを使って画面上に字幕をつけられないかと私に尋ねてきました。私がイエスと答えると、日本のアニメに英語の字幕をつけて流すことができるよね、という話になりました。当時は半分遊びでしたが、私たちは実際にライセンスを取得し販売しようという、若気の至りなアイデアを思いつきます。結果的に、そのプロジェクトは大成功しました。その後、他に同じような会社が続々と増えていき、今ではアニメは世界中に広がっています。
――好きな日本のゲームは、何かありますか?
ウッドヘッド氏:実は、そんなにゲーマーではありません。色々な趣味がありますが、特にプログラムに関連してたまたま興味の出たゲームがあれば、しばらくはそれを集中してプレイすることもあります。でも、遊びきったり飽きると、1年あるいは2年と、ゲームを遊ばないこともよくあります。逆に、自分の趣味だったりプログラミングなど、そういったことに時間をかけています。2人の息子は、日本のゲームが大好きですね。ひとりは「ファイナルファンタジーXIV」の北米一のギルドのメンバーになっていて、もうひとりは「ペルソナ」シリーズが大好きでJRPGをたくさん遊んでいます。
――今回のリリースによって、日本の新人プレーヤーだけでなく老練プレーヤーも遊ぶと思います。そんな彼らに向けてコメントをお願いします。
ベイリー氏:新規ユーザ-、老練プレーヤー、そのどちらも満足できるような環境を整えたと思います。アドバイスの視点からいうのであれば、育てているパーティメンバーを、あまり大切にしすぎないことですね。
――ありがとうございました。
(C)2024 DIGITAL ECLIPSE ENTERTAINMENT PARTNERS, CO. ALL RIGHTS RESERVED.
Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd.
Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C)(1981-2024) by FRPG Corporation. All rights Reserved.
Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation.
Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.
・(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
・“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
・Microsoft、Xbox One および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)





![[Switch 2] ぷよぷよ テトリス 2S (ダウンロード版) ※4,800ポイントまでご利用可 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/5/802252395_p.jpg?_ex=128x128)









![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer【2月27日以降出荷分】 [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)


![STRASSE レーシングコックピット[RCZ01専用] シングルモニターベース単品 TV台 グランツーリスモに最適![モニターフレーム ハンコン設置台 コクピット] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shunte/cabinet/game/cockpit-tv-00.jpg?_ex=128x128)

![レトロゲームキーホルダー 単品販売 カラー全6種 (赤・青・黄・緑・黒・白) ※色指定可 レトロゲーム 雑貨 [ 新品 ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/12601355/imgrc0332773756.jpg?_ex=128x128)
![レトロミニゲームキーホルダー 単品販売 カラー全6種 (赤・青・黄・緑・黒・白) ※色指定可 レトロゲーム 雑貨 [ 新品 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/10977376/imgrc0283096077.jpg?_ex=128x128)

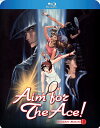

![銀河特急 ミルキー☆サブウェイ(特装限定版)【Blu-ray】 [ 寺澤百花 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0211/4934569370211.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】22/7 計算外 season1 5 (初回仕様限定版) 【Blu-ray】(22/7 キャスト撮り下ろしブロマイド (椎名桜月)) [ 7/22 ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5504/2100014595504_1_2.jpg?_ex=128x128)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8899/4580055368899_1_3.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.3 (特装限定版)<最終巻>【Blu-ray】 [ 富野由悠季 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9970/4934569369970.jpg?_ex=128x128)


![【楽天ブックス限定全巻購入特典】鎧真伝サムライトルーパーBlu-ray BOX 第1巻【Blu-ray】(A4クリアファイル+アクリルスタンド2個セット(上杉魁人&石田紫音)) [ (V.A.) ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7566/2100014777566_1_2.jpg?_ex=128x128)