【特別企画】
コロプラ馬場会長が仕掛ける“遊んで稼ぐ”ゲーム「Brilliantcrypto」配信開始! 最速体験会をレポート
2024年6月17日 17:00
プレイヤーが採掘した宝石はNFTとして保証
ブロックチェーンゲームの「Brilliantcrypto」では、同社が鉱山を提供してプレイヤーが採掘を行いトークンと宝石を手に入れることができる。実際の鉱山を掘っても作業料はもらえても宝石自体をもらえることはないが、本作では自分で掘り出した宝石も手に入れることができる。こうしてゲームに参加することで、新たなデジタルの宝石を作っていくというのも狙いのひとつとなっている。
実際にゲームを遊んでみるとわかるが、デジタルとはいっても宝石はそう簡単には手に入れることはできない。そのため手に入れた宝石は、本物のような感覚が得られるのである。手に入れたデジタルの宝石は、NFTという形で電子的にも保証される。そして、それを欲しいと思う人が出てくることで経済圏が生まれるのだ。
ちなみに同社はサービスの提供者だが、鉱山にどんな宝石が埋まっているのかはわからないように作られている。たとえ無理矢理出したとしても、ニセモノだとわかる特殊なアルゴリズムが採用されているのだ。ユーザーが掘り出した宝石が本物であるということを証明するために、様々なコストを使って研究・開発が行われているのだ。
日本で正式リリースされるまでの間に、様々な取り組みも行ってきた。そのひとつが本格的なメタバース展開をしていくための最初の候補として、ロッテグループが展開するメタバース「CALIVERSE」とMOU(正式合意前段階の合意文章)を締結している。また、世界初のデジタル宝石ファンドも設立している。これは初期に採掘される宝石を購入するファンドで、NFT宝石の価値を作りあげていくために立ち上げられたものだ。
法律が改正されたことで日本で会社を作ることができた
馬場氏によるプロジェクトの概要が紹介されたあと、コインチェック 副社長執行役員の井坂友之氏をゲストに交えて、トークセッションが行われた。最初に選ばれたテーマは「暗号資産市場の現在と未来」だ。そもそも今回のプロジェクトの最大の課題だったのは、日本で実現できるのか? ということであった。
このようなサービスを提供する場合、海外で会社を作ることが多い。それは、トークンを発行して値が付いてしまうと、そのほとんどを会社が所有していることから莫大な額になり、そこに課税される可能性があるからだ。馬場氏によると、ちょうど同社が始めるタイミングで法律の改正されるという話ができたのだという。そのため、開発を日本で行い、改正されたときにそのまま進めていくという形で進めていった。
法律が改正されたタイミングもよく、とんでもない額の課税をされることもなく事業を日本で行えるようになったのだ。
一方、IEOをするために協力したコインチェックの井坂氏は、その話を最初に聞いたときにすごくチャレンジだと思ったと、素直な感想を述べていた。チャレンジングなものをクリアしていくには、トップの強い意志や、税制と法制、ゲームに関する理解など、難易度の高いものが要求される。しかし、馬場氏からは「なんとしてもやるんです」と言われ、その強い意志と覚悟があるのならばということで、きっちりとやることになったと当時を振り返っていた。
「歩いて稼ぐのは俺の分野だ!」と思い会社として研究・開発をスタート
続いて選ばれたトークのテーマは「ブロックチェーンとPlay to Earnに取り組もうと思ったきっかけは?」だ。馬場氏は、ビットコインが出始めたときに、「なんだこれは?」と思ったという。自身は元々エンジニア出身だったこともあり、技術書を読んで「とんでもないことを考えている。はたしてこれはWorkするのか」と思ったのが最初だった。当初はビットコインはそれほど値が付かず、「まぁ、そうなるよね」と思っていたところ、あれよあれよという間に価値が付いていったのだ。
しかし、事業者として取り組むには法令などがクリア出来ない部分もあり、難易度は高かった。そうしたときに登場したのが、「CryptoKitties」という、イーサリアムを基盤にしたオンラインゲームだ。悪ノリのプロジェクトではあったのだが、そこに火が付いてよくわからないネコのNFTに高値が付くということがあった。実際に値がついたことから、これはゲームになるという直感があったものの、そのときもさすがに会社としてやるのはどうかと考えた。
それから時が流れ、歩いて稼ぐ「STEPN」というゲームが登場した。そのときに、「いやいや、歩いて稼ぐのは俺の分野だろう」と馬場氏は思ったという。コロプラは、元々位置ゲーの「コロニーな生活」の人気に火が付いたことから生まれた企業であったからだ。その状況を見た瞬間に、馬場氏はこれはもう捨てておけないと思ったと当時を振り返る。
この「遊んで稼ぐ」という分野に関して、ユーザーの引きはすごい。ゲームは楽しむためのものだが、そこから経済的価値が生まれるのは全ゲーマーの憧れではないかと考えたのだ。さすがに会社としても研究・開発しないわけにはいかなくなったのである。
その後、「STEPN」のほうは失墜してしまう。これは当然のことだが、価値の再生産ができていなかったからだ。歩くことは自分の価値だが、他人のための価値にはなっていないため、先食いしているような構造になっていたのである。その当時出ていたPlay to Earn的なゲームは、ほとんどその道をたどっていた。
そこで、我々がやるのであれば、そうではないものを作ろうと考えた。どんなものがいいか考えたところ、元々宝石を掘りたいと思っていたアイデアが融合してブロックチェーンゲームの「Brilliantcrypto」が生まれている。
コロプラは創業から5000億円のゲームアイテムを売ってきた
デジタルの宝石は、本物の宝石のように価値が付くのか? というところも気になるところだ。これについて馬場氏は、価値があると思ってもらえると考えている。コロプラでは、創業してからこれまで5000億円ものゲームアイテムを売ってきた。これらは元々価値はなく、単にサーバ上のデータベースの値を変えているだけに過ぎない。それでもなぜ売れるかというと、そこに価値を感じているからだ。ゲームを遊んでいてたまにしか出ないアイテムには、価値を感じ愛着も感じるのである。
馬場氏が学生時代のときに、MMORPGが流行っていた。そのゲームの世界では、1000匹倒してやっと手に入るレアアイテムがあった。アイテムとしては文字の色が異なる程度だったのだが、そこにものすごい価値を感じたのだ。そうしたアイテムは、実際にゲーム外でも売買が行われており、数万円の値が付けられていた。それが原初体験としてあり、ゲームにはそうした力があると思ったのだ。
「Brilliantcrypto」は、楽しく掘ることができるものの、実際にやってみるとかなり大変な作業であることがわかる。ひと山をひとりで掘ると、平均12~3時間ほど掛かってしまう。採掘できる宝石は、最大5個程度しか手に入れることができず、出てくる宝石もほとんどの場合はそれほど大きくないものばかりだ。そのため、ゲームを遊ぶ人が増えるほど宝石にも価値が出てくるのだ。
参加者が増えるほど、普段ゲームをあまりやらない人たちにも価値が伝わっていくようになる。価値が伝わることでニーズが高まり、実際に売買されるようになると考えているのだ。そして、これらはビットコインもたどってきた同じ道でもある。
「Brilliantcrypto」には不思議な中毒性がある
というわけで、今回の体験会で久々に「Brilliantcrypto」を遊ぶことができたのだが、本作をゲームとして見たときの魅力は、不思議な中毒性だ。単純に山を掘っていくという作業は、どちらかというと労働に近いものがある。それでも不思議なのは、プレイしているとどんどん続けてしまいたくなるということ。
馬場氏が言うには、“ぷちぷち”に近い感覚だという。たしかに、勝った負けたといって遊ぶゲームも楽しいのだが、ひとりで黙々と山を掘るというのはぷちぷちを潰していきたくなるような感覚に近いというのも頷ける。
いよいよサービスが開始された「Brilliantcrypto」。これをきっかけにお金を稼ぐというのもいいかもしれないが、単純にゲームとしても楽しいので、興味がある方はぜひとも挑戦してみてほしい。
































![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1 (特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51-w6XyYNtL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】『葬送のフリーレン』Season 2 Vol.1 初回生産限定版 (Amazon限定:描き下ろしフラップポーチ付き、Amazon限定全巻購入特典:描き下ろし全巻収納BOX引き換えシリアルコード付き、全巻購入メーカー特典:箔押しトランプ付き) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/41AAnMAwElL._SL160_.jpg)
付き [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51p3oabQuCL._SL160_.jpg)








![スクウェア・エニックス 【Switch2】ドラゴンクエストVII Reimagined [POT-P-AASVA NSW2 ドラゴンクエスト 7 リイマジンド] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0037/4988601012089.jpg?_ex=128x128)
![マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用][ラッピング不可] R-LOGI 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/sokutei/cabinet/rank/imgrc0098105601.jpg?_ex=128x128)




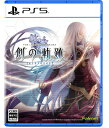
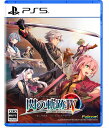
![[新価格版]ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1648/4988601011648_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【新品】【PS5HD】ファイティングコマンダーOCTA for PlayStation5/ PlayStation4/ PC[在庫品] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10600000/10601613.jpg?_ex=128x128)
![元気 【特典付】 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)












![ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー【Blu-ray】 [ アーロン・ホーヴァス ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2023/4550510102023.jpg?_ex=128x128)
![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア【Blu-ray】 [ 古谷徹 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4722/4934569364722.jpg?_ex=128x128)
![【特典】機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(Blu-ray通常版)【Blu-ray】(L判イラストシート(4枚セット)) [ 小野賢章 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6399/4934569366399_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【特典】機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(4K ULTRA HD Blu-ray)【4K ULTRA HD】(L判イラストシート(4枚セット)) [ 小野賢章 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0138/4934569800138_1_2.jpg?_ex=128x128)
![銀河特急 ミルキー☆サブウェイ(特装限定版)【Blu-ray】 [ 亀山陽平 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0211/4934569370211.jpg?_ex=128x128)
![あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7808/4580798287808_1_2.jpg?_ex=128x128)
![『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I=We’re IDOL PRECURE』Blu-ray通常版【Blu-ray】 [ プリキュア ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0734/4535506020734.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-【Blu-ray】(A4サイズクリアファイル(『Eden』絵柄使用予定)) [ (V.A.) ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1329/2100014381329_1_2.jpg?_ex=128x128)
![新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX【4K ULTRA HD】 [ 矢立肇 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0251/4934569800251.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】[限定版][先着特典付]アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!- Blu-ray(初回生産限定盤)/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/421/eyxa-14942.jpg?_ex=128x128)