【特別企画】
アイドル育成×デッキ構築型ローグライク!? 「学園アイドルマスター」にハマる理由を「Slay the Spire」との比較で考察
「1日外出録ハンチョウ」でも紹介された“沼”のようなゲーム性を継承
2024年5月24日 11:05
- 【学園アイドルマスター】
- 5月16日 リリース
- 基本無料(アイテム課金制)
バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS用アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター(学マス)」を5月16日にリリースした。本作は「アイドルマスター」シリーズの最新作にあたり、初星学園アイドル科の生徒をスカウトし、立派なアイドルへと育てていくゲームとなっている。
とくに今注目を集めているのは、そのゲーム部分の戦略性の高さ。いわば「デッキ構築型ローグライクアイドルゲーム」とでも言うべき仕組みになっており、デッキ構築型ローグライクの金字塔として知られる“スレスパ”こと「Slay the Spire(スレイ ザ スパイア)」を連想させるという呼び声も高い。実際にSNS上では、多くのゲーマーたちが夢中になっている姿が見受けられる。
では「学園アイドルマスター」のゲーム部分は、どんなところが面白いのだろうか。「Slay the Spire」と比較する形で、その魅力について紹介していこう。
奥が深いデッキ構築にハマる「Slay the Spire」
「Slay the Spire」は2019年に正式リリースされ、いまだに多くの熱狂的なファンから愛されているインディーゲームだ。「カイジ」シリーズのスピンオフコミック「1日外出録ハンチョウ」にて、“時間を忘れてハマってしまうゲーム”として作中に登場していたことも記憶に新しい。
ゲームの内容としては、内部構造がランダムに生成される「塔」(ダンジョン)に挑戦し、その最深部を目指していくというもので、道中には強力なモンスターとの戦いが待ち受けている。戦闘はターン制となっており、プレーヤーは独自に構築したデッキをもとに、さまざまなカードを使って敵を倒していく。
カードの種類は相手にダメージを与える「アタック」、特殊効果をもたらす「スキル」、場に残って効果を発揮し続ける「パワー」などに分かれており、それぞれカードごとに多彩な効果をもつ。ただしカードを使うためには「エナジー」を消費する必要があり、その数は1ターンごとに限られている。制限されたリソースのなかで、いかにしてカードの効果を組み合わせ、シナジーやコンボを生み出すのか……というところが、プレーヤーの腕の見せ所だ。
何より面白いのは、カード単体の効果だけで戦うとほぼ確実にゲームオーバーを迎えてしまうこと。ボスはもちろん道中の雑魚に至るまで、敵のステータスが異様に高いため、カードの効果を組み合わせて効率的にダメージを出さなければ生き残ることは難しい。またダメージを与えるだけでなく、自分が受けるダメージを減らす「ブロック」によって防御を行なったり、戦闘を優位に進めるためにバフ・デバフを仕掛けたりと、しっかり戦略を練る必要がある。
とくに重要なのがバフ・デバフの使い道だ。たとえば攻撃に関連するものだと、与えるダメージが増えるバフの「筋力」や、受けるダメージが50%増加するデバフの「弱体」などが存在しており、その数値をコントロールすることでダメージ量が大きく変わってくる。
その一方、もっと絡め手的な戦い方もあり、本来防御のために積み重ねる「ブロック」を攻撃のために転用する戦法や、「毒」によってじわじわとダメージを与える戦法など、その可能性は無限大だ。
なお、キャラクターごとに使用できるカードの種類が異なっているのも特徴で、たとえば鉄仮面のアイアンクラッドは「筋力」や「ブロック」の積み重ねで戦うパワータイプ、女殺し屋のサイレントは「毒」や「ナイフ」などのテクニカルな運用を求められるタイプとなっている。
そして本作のもう1つの醍醐味としては、“デッキ構築”の奥深さがある。まずプレーヤーは各キャラクターの基本デッキを持った状態から始め、戦闘や探索によって新たなカードを増やしたり、「焚き火」によってカードをアップグレードしていく。
むやみにカードを増やせばいいわけでもなく、デッキの枚数が多いと必要なカードを適切なタイミングで引けない“手札事故”が起きやすくなる。自分が目指す戦法に合ったカードを厳選していかなくてはならない。時にはショップやイベントなどでデッキから不要なカードを除去することも必要になるだろう。
そのほか、さまざまな効果を発揮する「レリック」や、戦闘時に使用できる「ポーション」といったアイテムも存在しており、ダンジョンに潜るたびに探索の面白さを味わえる。
「学園アイドルマスター」の“スレスパ”的要素
こうしてまとめてみると、「Slay the Spire」のゲームシステムはアイドル育成シミュレーションとは無縁に見えるかもしれない。しかし「学園アイドルマスター」は、かなりデッキ構築型ローグライクを意識したゲーム性になっている。
本作の育成モードでは、プレーヤーが初星学園の生徒をプロデュースし、定期公演「初(はじめ)」に出場させることを目指していく。そのためには地道なレッスンによってパラメータを高めた上で、中間試験と最終試験に合格しなければならない。
たとえるなら、このレッスンはダンジョンの道中に出てくる雑魚モンスター、試験はボスモンスターに相当する。どういうことかというと、レッスンと試験ではアイドルのパフォーマンスとして、“スレスパ的”なカードバトルが行なわれるのだ。
パフォーマンスはターン制となっており、山札から引いてきたスキルカードを使い、パラメータを高めていくことが目的。スキルカードにはパラメータ上昇効果のほか、特殊効果や消費体力なども設定されている。
モンスターを倒す代わりに良いパフォーマンスを披露することが目標となっていて、パラメータの上昇は「Slay the Spire」でいう敵への攻撃、消費体力を軽減する「元気」は「ブロック」と対応している。さらにスキルカードの効果として、パラメータの上昇値を上げる「集中」や「好調」などのバフが存在するのだが、それぞれ「筋力」、「弱体」とほぼ同じ効果だ。
そのほか「元気」の増加量を底上げする「やる気」は「敏捷性」、ターン終了時にパラメータを上昇させる「好印象」は「毒」に対応している。
そして本作もカード単体の効果だけでは攻略が難しい難易度となっており、いろいろなシナジーやコンボを模索することが必要不可欠。たとえば「好印象」や「元気」を溜めた上で、その数値の一定割合分ダメージを与えるスキルカードを使った戦法などがある。これは「Slay the Spire」でいう「毒」デッキや、「バリケード」や「ボディスラム」を使った戦法に近い。
さらに本作にはデッキ構築要素もあり、レッスンやイベントの報酬としてスキルカードを選択して獲得できるほか、「相談」にて必要ないカードをデッキから削除したり、スキルカード自体を強化したりすることもできる。ほかにも「レリック」に相当する「Pアイテム」、「ポーション」に相当する「ドリンク」なども揃っているため、「Slay the Spire」のプレーヤーにとってはお馴染みのシステムと言えるだろう。
選択したキャラクター(プロデュースカード)によって、デッキのタイプが分かれているのも共通点。パラメータを稼ぎやすいデッキの作り方がそれぞれ異なるので、各々の特性をよく理解してからデッキ構築に挑もう。
ちなみに「Slay the Spire」ではゲームを開始すると、巨大なクジラのような見た目の「ネオー」というキャラクターが姿を現し、プレーヤーを導いてくれる。それに対して「学園アイドルマスター」では、あさり先生という人物がアドバイザーを務めているのだが、彼女の苗字は「根緒」(ねお)。これはたんなる偶然なのか、オマージュなのか……。
アイドル育成ゲームのまだ見ぬ景色へ
多くの面で「Slay the Spire」にインスパイアされていると思われる「学園アイドルマスター」だが、もちろん独自の魅力が多数あることも間違いない。
まず、本作は「手軽にプレイできる」という点が大きな違いだと感じる。「Slay the Spire」はダンジョンが3層+αの構成になっており、バトルの数も多いため、プレイのスピードによって変動するが1周分のプレイで1時間前後はかかるものと思われる。それに対して「学園アイドルマスター」の1周にかかるプレイ時間は、大体20~30分以内だ。
編成することでさまざまなバフを得られるサポートカードなど、育成の難易度を下げてくれる要素もいろいろと用意されており、コアなゲーマーに愛されるデッキ構築型ローグライクがカジュアルなゲーム性へと再構築されている。
さらに踏み込んだ部分で言うと、アイドル育成ゲームにデッキ構築型ローグライクを組み合わせることによって生まれる相乗効果も挙げられるだろう。本作は周回前提の作りとなっていて、プロデューサーのレベルに応じたスキルカードの解放や、アイドルの親密度、サポートカードの強化といった要素があり、何度も育成に挑戦することで“もっと上”を目指せるようになっていく。まるでアイドルやプロデューサー自身の成長がゲームシステムに組み込まれているような感覚で、「Slay the Spire」とはまた違ったやり込みの楽しさを感じられる。
また「学園アイドルマスター」の登場人物はいずれもアイドル志望の学生で、その才能はまだまだ発展途上。完璧なパフォーマンスを魅せることの難しさをひしひしと実感させられる……という意味で、一筋縄ではクリアできないゲーム性が上手く噛み合っている印象だ。
アイドル育成ゲームとしてのオリジナリティも群を抜いており、育成の仕上がりに応じて“歌や踊りが未熟なライブパフォーマンス”が映し出されることなど、いろいろな工夫に驚かされる。そこにデッキ構築型ローグライクという全く別のジャンルのエッセンスが加わっていることが、本作ならではの面白さにつながっているのではないだろうか。
ゲーム部分以外にも、アイドルたちのキャラクター性やシナリオの完成度などには目を見張るものがある。「アイマス」シリーズに触れたことがない人でも楽しめる作りとなっているので、ぜひ一度プレイしてみてほしい。
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2019 MegaCrit, LLC.

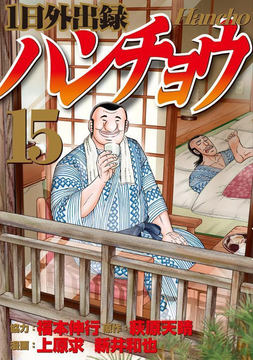












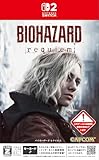









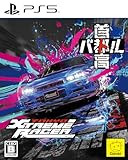










![【Amazon.co.jp限定】劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray【特装版】(早期予約メーカー特典クリアファイル+L判ブロマイド5枚セット付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41N2LB75ruL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)


![ポケモン 【Switch2】ぽこ あ ポケモン [POT-P-AAB5A NSW2 ポコ ア ポケモン] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4521329460420.jpg?_ex=128x128)






![[Switch 2] ぽこ あ ポケモン (ダウンロード版)※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/0/802252610_p.jpg?_ex=128x128)




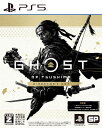


![【新品】【PS5HD】PS5用無線コントローラー ブラック[在庫品] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10870000/10872925.jpg?_ex=128x128)





![【中古】[ACC][PCE] ターボパッド for PCエンジン mini コナミライセンス商品 HORI(HTG-003)(20200319) 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1202/3/cg12023897.jpg?_ex=128x128)

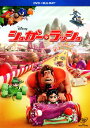

![【中古】【未使用品】塔の上のラプンツェル MovieNEX [DVDのみ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/issue/cabinet/11599041/imgrc0098643361.jpg?_ex=128x128)


![Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2052/4534530162052_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【中古】約束のネバーランド 完全生産限定版 Blu-ray 全3巻セット 約ネバ[10] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/otakarasouko/cabinet/_586/1240010406097_1.jpg?_ex=128x128)
![「多聞くん今どっち!?」1【Blu-ray】 [ 師走ゆき ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4399/4988003894399.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-(4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-ray)【4K ULTRA HD】 [ 矢立肇 ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0213/4934569800213.jpg?_ex=128x128)
![舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折ー【Blu-ray】 [ 三浦涼介 ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4682/4988104154682.jpg?_ex=128x128)