【特別企画】
“敵をなぎ倒す爽快感”をお手軽に得られるタイトー「ハレーズコメット」が稼働開始から38周年!
38年後にはハレー彗星が再び地球に最接近
2024年1月27日 00:00
- 【ハレーズコメット】
- 1986年1月 稼働開始
1986年1月に全国各地のゲームセンターで稼働を開始したタイトーの「ハレーズコメット」が2024年1月に38周年を迎えた。
本作は「ハレーズコメット(=ハレー彗星)」が迫り来るなか、自機を操作し、彗星から現れる敵を倒して太陽系内にある9つの惑星(当時は冥王星も惑星だった)と太陽を救うというシューティングゲームだ。宇宙を旅する彗星はかなりの数があるが、なぜそれらの中からゲームの題材としてハレー彗星が選ばれたのかといえば、約76年という公転周期(天体が太陽を中心とした軌道上を一周するのにかかる時間)を持ち、長らく人類に目撃されてきた知名度の高さと、本作がリリースされた1986年に地球に最接近すると話題になったからだ。
過去に観測されたときは、そのタイミングで災厄などが起きていたこともあり、凶兆の印とも捉えられていたためか、ハレー彗星に限らず彗星全般が、本作だけでなくアニメなどでも悪役として描かれていることも多い。そんな彗星をモチーフにした本作が、稼働を開始してから38周年を迎える。この“38”という数字は、実はしっかりとした意味を持つのだ。
「ハレーズコメット」のモチーフになったハレー彗星。約76年周期の折り返し地点を2023年12月に通過!
夜、外を歩いている時に空を見上げると、目に飛び込んでくるのは多数の星が瞬く広大な宇宙だ。そんな宇宙は私たちにゲームの舞台だけでなく、さまざまな天体ショーをプレゼントしてくれる。人類が体験できる天文関連のイベントには有名な日食や月食があるが、それ以外にも多数の流れ星が見られる流星群や、新たな惑星の発見などが挙げられる。
なかでも、長い尾を引く姿が時代ごとにさまざまな受け止められ方をした彗星の飛来は、天体ショーの中でも花形の一つといえるだろう。
別名“ほうき星”とも呼ばれる彗星は、遠方から飛来して二度と姿を見せないものと、太陽を周期的に回るなどのパターンに分かれる。そのうち突出した知名度を持つのが、約76年という公転周期を持ち、何度も人々の前にその姿を見せつけてきた「ハレー彗星」だ。
前回地球に最接近したのは1986年のことで、このときの人類は科学の目を総動員して彗星の正体に挑んだが、それまではハレー彗星というと、厄災をもたらすものとも言われてきた。1910年の最接近時には地球から空気が無くなるなどの噂が立ち、この世の終わりだと人生を投げ捨てて大騒ぎする人や、空気を確保するためにゴムチューブを買い占めるものなど、さまざまなパニックも発生している。結果的には何も起きず、彗星の飛来は吉凶なにももたらさないものだというのが分かったことで、1986年の最接近時には人々は冷静な目でハレー彗星を観測できるようになったとの話もあるようだ。
そんなハレー彗星は細長い楕円軌道を描きながら太陽の周りを公転しているのだが、近日点は太陽付近、そして遠日点は海王星の公転軌道付近。この遠日点を通過したのが、本稿の1カ月ほど前となる2023年12月の事だ。前回のハレー彗星最接近時には、近日点はニュースなどでも読み上げられたためメジャーになった感があるが、遠日点はマイナーなのでピンとこない人もいるかもしれない。
例えるのであれば、長距離マラソンでいうところの折り返し地点だ。そこを通過し、いよいよ往路から復路へと入ったということで、ハレー彗星の遠日点通過は地味なイベントではあるが、天体ファンでなくとも派手に盛り上がりたいものだ。
しかし、ハレー彗星に限らず、正体が分からなかった時代の彗星は災いをもたらすものとして人々に恐れられていたのは前述したとおり。そのため、時として彗星は悪役として取り上げられることもあった。特に有名な作品と言えば、1978年に公開され2017年にはリメイクもされたアニメ映画「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」だろう。巨大な彗星に擬態した白色彗星帝国が地球を破壊すべく進撃してくる様は今考えると、人々が彗星に対して昔から持っていた恐怖心を表したように思えたものだ。
ハレー彗星との果てしない戦いが描かれるゲームとして登場した「ハレーズコメット」
そして、彗星が悪役として活躍するのはアーケードゲームにも存在する。1986年春に地球への最接近を果たすハレー彗星を題材として、同年1月にアーケードゲームとしてタイトーよりリリースされた「ハレーズコメット」だ。本作が稼働を開始したこの時期は、ハレー彗星が地球の公転周期上まで辿り着いており、近日点までもう少しというタイミングだったことで非常にタイムリーな作品といえた。
ストーリー自体は取り立てて用意されていないものの、彗星が厄災をもたらすという部分を取り上げて「地球を破壊すべく迫って来るハレー彗星と、そこから襲ってくる敵を、自機を操作し撃退せよ」となっている。ある意味「さらば宇宙戦艦ヤマト」を、アーケードゲーム化したものといえなくもないだろう。プレーヤーは、マイシップ1機だけで強大な敵に立ち向かっていくこととなるのだ。
基本システムは非常にシンプルで、操作するコントローラは8方向レバーとショット、そしてボムボタンのみ。ステージは地球から始まり金星→水星→……と、各惑星がそれぞれ舞台になっており、各ステージは3つのエリアで構成されている。
1つ目のエリアの最後には耐久力のあるボスが登場するが、これを破壊できればクリアとなる。2つ目のエリアのラストでは、ついに彗星に到達するも表面の一部が開いて攻撃を仕掛けてくるのだ。敵弾を避けながらハッチをすべて壊せれば、彗星表面が開き3つ目のエリアへと突入する。
彗星内部では、電磁バリアや一瞬姿を隠してプレイヤーを惑わす敵などを破壊しつつ、最終地点にたどり着ければスクロールが停止。敵砲台が大量に出現するので、それらをすべて撃破できれば1ステージクリアとなり、その惑星は救われたことになる。そしてマイシップは、次の惑星を救うべく感動の余韻なく旅立つことに。これを10惑星分繰り返し、すべてを助けることができれば1周目クリアだ。その後、難易度が上昇した2周目がスタートする。
宇宙空間では毎回固定された場所に登場する隕石や敵を、彗星内部であればフタをされた障害物や内部に配置された敵を倒すと、それぞれパワーアップアイテムが出現することがある。自機のショットは3種類あり、パワーアップを取るごとにそれぞれがより太く大きくなっていく。すべてのパワーアップは併用が可能なので、見つけ次第片っ端から回収していくのがベストだ。
ただし、パワーアップアイテムは出現から一定時間が経過すると、自動的に左右どちらかの画面外に向かい“スーッ”と移動するのだが、その際に自機の位置とは反対方向へと動くようになっている。このため、慌ててパワーアップアイテムを追いかけて画面端へと移動すると、そのタイミングで敵に体当たりしたり被弾するということがよくあるのだ。「ハレーズコメット」は、“欲張ってはいけない”ということを教えてくれるゲームなのかもしれない。
このほかにも、パワーアップアイテムの代わりにボールアイテムと呼ばれるアイテムが出現することもある。種類は4つあり、そのどれもが回収することで大きなメリットを得られるのだ。特に、ショットのすべてがフルパワーアップするオレンジのボールは、取ってしまえばそれ以降はパワーアップアイテムを追いかけなくても良く、敵弾の回避に専念できるようになる優れ物。早ければステージ1のエリア2で出現するので、そのときは是が非でも回収したい。
画面右下に書かれたパーセンテージ表示は、プレイヤーが救うべき各惑星のダメージ率となっている。これは、破壊できる敵や敵弾を逃すことで増え、被弾率100%になるとその惑星は破壊されてしまい、残機があってもゲームオーバーになってしまう。当時は地球や太陽が破壊されるならわかるが、冥王星が破壊されたくらいでゲームオーバーはちょっと……と思ったものだが、実際は惑星が一つ無くなってしまえば太陽系の重力バランスが崩れるわけで、そうなれば何が起きるかはわからない。そこまで考えれば、ゲーム終了も酷いことではない。
ちなみに、本作をリリースしたタイトーの代表作「スペースインベーダー」は、残機がどれだけあっても敵を全滅させることができなければ、インベーダーに侵略されてゲームオーバーの憂き目に遭う。「ハレーズコメット」はもしかすると、そういった部分で「スペースインベーダー」をお手本にしているのかもしれない。
各惑星の被弾率は、プレイが続く限り減少することはない。「ハレーズコメット」は、ステージ10をクリアすると再びステージ1に戻る周回プレイとなっているが、被弾率はそのまま持ち越される。つまり、あまりにも敵を逃がしすぎる攻略方法を採っていると、のちのち自分で自分の首を絞めることになってしまうのだ。
ただし、筆者のように“どんなゲームでも1周クリアすれば満足”というプレーヤーであれば1周クリアにのみ専念して、倒すと弾をばらまくような危険な敵を撃たずに敢えて逃がすのも攻略方法の一つ。連射できるからといって、何もすべてを撃ちまくり自らの身を危険にさらす必要は無いのだ。
思った以上にトリッキーな動きをする敵も、チョイチョイと出てくる。パワーアップしていない初期状態の自機では、撃ち逃してしまうだけならまだしも、その動きに惑わされて体当たりしてしまうこともしばしば。この挙動は、日本物産がリリースした「ムーンクレスタ」や「テラクレスタ」に登場する敵に似ている部分があるように感じる人もいたのではないだろうか。
当時のゲームセンターでは、連射は基本的に自分の手で行った!?
「ハレーズコメット」は他の人のプレイを見ていると、自機をパワーアップさせてしまったあとは前方から現れる敵を出現した瞬間に破壊しまくる、爽快感たっぷりのゲームに思えるかもしれない。
しかし、本作がアーケードゲームとしてデビューした1986年は、ゲームセンターはまだまだ手動での連射がメイン。一部のゲームがディップスイッチを設定することで連射になったり、筐体に独自に連射装置を付けていたゲームセンターもあったものの、ほとんどのタイトルは自らの手でショットボタンを連打する必要があった。そのため、当時はプレイ後に腕が疲れまくったのをよく覚えている。
ボタンを連打するゲームの中でも有名な作品といえば、本作より少し前となる1983年から84年にかけて登場した、コナミ(当時)の『ハイパーオリンピック』だろう。このタイトルではボタンを連打することが重要だったが、大勢のプレイヤーがそれに挑んだ結果として出された答えが、ガチャガチャの大きなカプセルでボタンを擦ったり、簡単に折れてしまうプラスチック製ではなく鉄製の定規を使ってのボタン連打(ボタンなどにダメージを与えるのでNG行為)というアクションだった。
特に、鉄定規での連射を行えば簡単に目を見張るような記録を出せたものの、定規の鋭角になった部分で手を切り血まみれでのハイスコアになることも日常茶飯事。置いてある場所もゲームセンターというよりは駄菓子屋のほうが多かったため、鉄定規を弾いている音を聞きつけた“駄菓子屋のオバチャン”が、使っていた人を怒りながら追いかけ回すという光景を何度か見たものだ。追いかけられていたのは小中学生だったが、その駄菓子屋に行かないとゲームを遊ぶ場所が減るわけで、結局は謝りその後も同じ駄菓子屋に通うことになるのだが……。
この鉄定規を使った方法は、「ハイパーオリンピック」がRUNボタンとJUMPボタンのみという操作だから使えたわけで、レバーも操作しなければならない「ハレーズコメット」では無理ということになる。そこで、当時はいくつかの連打方法が編み出されていた。
代表的なのは、青筋を立てながら人差し指や中指で必死に連打するシンプルな方法。だが、他にも腕をけいれんさせ、その振動を指に伝えてボタンを叩く“痙攣打ち”、1つのボタンをピアノの鍵盤を弾くように人差し指と中指で交互に連打する“ピアノ打ち”、そして人差し指・中指・薬指などの爪を使ってボタンを擦る“擦り打ち”といった方法が有名だろう。この時代はほとんどのゲームがショットを連射しないことには話にならなかったため、連射テクニックは必要不可欠なものだったのだ。
「ハレーズコメット」ももちろん例外ではなく、ステージ1のエリア1から、全機破壊するとボーナス得点が入る代わりに個体の耐久度が高い編隊が登場する。他のゲームならいざ知らず、本作ではショットボタンを必死に連打して倒さなければ惑星ダメージになり、ゲームオーバーが近づいてしまう。そんな敵がほぼ毎エリアごとに登場するのだから、腕の体力が持つはずもなし。今でこそ、連射があるので気軽に遊べるが、一度くらいは手動での連射プレイを体験して、当時のゲームセンター気分を味わってみて欲しい。
連射装置が用意されている今の時代では、このあたりの敵に関してはずいぶんと楽になったが、一度ミスしてしまうとリカバリが難しいのは当時と変わらず。被弾してしまえば自機が初期状態に戻ってしまうため、貧弱な装備で改めてパワーアップを集めていかなければならなくなる。エリア1ならまだしも、先に進んでしまえば筆者ほどの腕では復活は不可能。どれだけ残機があろうとも、捨てゲー(残りのプレイを諦めて席を立つ)以外に道はナシだ。そういった部分もまた「ハレーズコメット」の特徴ではないだろうか。
そんな本作の楽曲は全体的に透明感があり、いつまでも耳に残る名曲が揃っていた。特に各エリアの最終戦で奏でられるBGMは、透き通った感じを残しつつも徐々に盛り上がっていき、当時はこれを聞くと妙に闘争心に火がついたものだ。これらの曲を手がけたのは、“OGR”こと小倉久佳氏だ。他にも「ダライアス」シリーズや「ニンジャウォーリアーズ」などでも活躍しており、どれもこれも名曲ばかりだ。氏のファンならば、「ハレーズコメット」をプレイしない理由はないだろう。
敵を片っ端からなぎ倒す爽快感が特徴の「ハレーズコメット」をプレイしながら、2061年に再びハレー彗星を迎えよう!
スーパーレーザー、ダブルビーム、スーパーボールを取ってしまえば、出現と同時に敵を破壊できるようになり、サクッと爽快感を得られるのが特徴の「ハレーズコメット」。もちろん、先に進めばシビアな弾避けも要求されるのでそれなりの腕が求められるが、序盤ならシューティングゲームをかじった程度の人でも楽しめるだろう。
その元ネタとなったハレー彗星が遠日点を通過し、再び近日点を目指し始めた2024年。1986年のハレー彗星最接近時にリアルタイムで本作をプレイしていた人は、次に最も地球に近づく2061年に再度、その姿を拝めるかどうかは分からない。
そんな今だからこそ、38年ぶりに往路を終えて復路に入ったハレー彗星を思い起こしながら「ハレーズコメット」を遊びつつ、当時を懐かしむのもいいだろう。一生懸命指と手を動かして本作をプレイすれば身体と脳が活性化され、ひょっとすると無事に2061年を迎えられる……かもしれない。
(C)TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.































![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)



![任天堂 マリオカート ワールド【Switch 2】 BEEPAAAAA [BEEPAAAAA] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_340/4902370553260_1.jpg?_ex=128x128)






![[メール便OK]【新品】【PS5】シティーハンター COLLECTOR’S EDITION [PS5版][在庫品] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10900000/10904478.jpg?_ex=128x128)
![カプコン 【PS5】バイオハザード レクイエム 通常版【2月28日以降出荷分】 [ELJM-30814 PS5 バイオハザ-ド レクイエム ツウジョウ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0020/4976219137492.jpg?_ex=128x128)






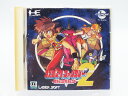



![TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」上巻【Blu-ray】 [ 羊宮妃那 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7436/4562494357436.jpg?_ex=128x128)
![TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」下巻【Blu-ray】 [ 羊宮妃那 ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7443/4562494357443.jpg?_ex=128x128)