【特別企画】
「俺の屍を越えてゆけ」25周年。生きる、死ぬ、託す――
世代交代を繰り返し、呪われた一族の悲願を成就する異色の純和風RPGを振り返る
2024年6月17日 00:00
- 【俺の屍を越えてゆけ】
- 1999年6月17日 発売
1999年6月17日に「俺の屍を越えてゆけ(以下「俺屍」)」 が発売されて、本日で25周年を迎える。初代プレイステーションで発売された本作は、後に2007年2月22日にゲームアーカイブスでのダウンロード版、そして2011年11月10日にはPSPでリメイク版が発売されている。そして2024年4月16日からは、PS5/PS4にて待望の移植版の販売が始まった。
「俺屍」は当時としては珍しい、平安時代を舞台にした純和風RPGだ。日本人プレーヤーにとってはなじみ深い世界設定でありながら、本作はストーリー、システムともに非常にクセが強い作品として知られている。言い換れば、ある意味合わない人にまったく合わないがハマる人にはとことんハマるといった、プレイする人を選ぶタイプの作品だ。
ゲームデザインは桝田省治、開発はアルファ・システム。この両者の名を聞いてピンと来た人もいるだろう。そう、あの「天外魔境II 卍MARU」や「リンダキューブ」などを手掛けた両者だ。これだけで、本作がもうケレン味たっぷりの異色な作品だということがわかるだろう。
本記事では発売25周年を記念し、改めて「俺屍」のどこが異色であったか、そしてどこが魅力的だったのかを筆者独自の視点で振り返ってみたい。なお、発売よりすでに四半世紀が経過していることを鑑み、記事内では本作の重大なネタバレについて触れている部分がある。現在プレイ中、もしくは今後本作をプレイする予定の人にとっては大変に興を削ぐ内容となっているため、そういった人は必ず先に本作をクリアしてから、改めて本記事を読む事を強く推奨させていただく。
キャラ愛を真っ向から否定する、連綿と続く呪われた血脈の“一族史”を描いた異色作
RPGとはある意味、プレーヤーの思い入れを最も反映しやすいジャンルのゲームだと言えるだろう。このキャラは剣でしか戦わない、このキャラは打たれ弱いけど魔法で一網打尽に出来るようにしよう……などと、ある種のこだわりを持ってプレイしたことのある人は多いはずだ。
だが、本作「俺屍」は、そのようなキャラクターへの愛情、思い入れを真っ向から否定する。より正確に言うなら、そのようなキャラ愛は本作の特異なシステムによって早々にへし折られ、決して長続きしない。なぜなら主人公一族である本作のプレーヤーキャラは、ゲーム内の期間で長くとも2年を経たずして、あっさりと死んでしまうからだ。
本作「俺屍」では、通常のRPGのように特定のキャラクターをゲームクリアまで一貫して操作し、育成するということは出来ない。2年にも満たない命を受け継いでいき、世代交代しながら一族の悲願達成を目指していく。つまり本作では同じキャラクターをずっと育成するのではなく、一族全体の力を底上げしていくことが目標となる。
世代交代を描いたRPG作品では「ファンタシースターⅢ」や「ロマンシング サ・ガ」シリーズなどがあるが、これらの世代交代はストーリー進行の過程で特定のイベントとして行われる。だが「俺屍」では、例え攻略途中であっても、寿命が来たら否応なくゲームから脱落し、もうプレイヤーキャラとして操作することは出来なくなる。「ウィザードリィ」シリーズなどのロスト状態になる、と考えれば理解しやすいだろう。
短い時間を精一杯生き、子を残し、悲願を一族に託して死んでいく。「俺屍」は世代交代を繰り返し、一族がそのような宿業を背負う原因となった仇敵・朱点童子を倒すという悲願達成を目指すゲームなのである。
京の都を荒らす朱点童子に挑むひと組の夫婦。しかし2人は倒れ、赤子は呪いをかけられてしまい……
ひとりの天女が
人の男に恋をした。
それがすべての始まりだった。
平安時代、朱点童子を頭目とする鬼たちの襲撃によって京の都は荒廃し、壊滅の一途をたどっていた。時の帝は勇士を集い、朱点の棲む大江山へ何度も討伐に向かわせるが、悉く道半ばで力尽き、生きて帰った者は1人としていなかった。
そして何度目かの討伐の末、源太とお輪というひと組の夫婦がついに朱点の居城・朱点閣へとたどり着くことに成功した。しかし朱点の卑劣な罠によって源太は討ち死にし、お輪も朱点の手中に落ちた我が子の命を救う代わりに、囚われの身となってしまう。
命を救うと約束した朱点は言葉通りに赤子を解放したが、その際に2つの呪いをかけてしまう。その2つの呪いこそが、“短命の呪い”と“種絶の呪い”だ。朱点は約束通り、赤子の命そのものは助けた。しかしその子がやがて成長し、将来の禍根とならぬように予め呪いをかけておいたのだ。
今日でこそ、このような悲惨な背景を持った主人公のRPGは有り触れてきてはいるが、25年前の当時ではRPGといえば「ヒーローの物語」だった。常人よりはるかに高い資質を持った英雄またはその末裔、もしくはこれから英雄になる者の“英雄譚”がほとんどで、本作のように多大な足かせを持つ主人公や、いわゆる“復讐譚”などは非常に珍しかった。
しかし、捨てる神あれば拾う神あり。彼らの顛末を見守っていた天界の神々が憐れに思い、手を差し伸べてきたのだ。お輪と源太の子である赤子は成長して一族の初代当主となり、人ならぬ神と交わることで子を生す。こうして交神によって一族の命脈を保ちつつ、両親の敵である朱点童子を討伐し呪いを解くことを悲願に、いつ果てるとも知れない戦いに身を投じることになるのだった。
世代交代を繰り返して一族を強くしていき、憎き朱点童子を討つために生き長らえよ
こうして主人公一族の未来に、なんとか命運が開かれることとなった。最初の交神の儀で生まれた子はすぐ成人し、初代当主とその子ども、親子2人でゲームがスタートする。こうして交神によって一族の数を増やしつつ、京の町にある一族の屋敷と迷宮を行き来して一族を強化し、朱点童子討伐を目指すのが本作の目的だ。屋敷での各種コマンドは実行するとひと月経過し、また迷宮に遠征した場合は現地で一定の時間が経過すると屋敷へ帰還し、ひと月が経過したことになる。
また本作には「あっさり」、「しっかり」、「じっくり」、「どっぷり」の4つのゲームモードがある。これは単純な難易度ではなく、主に迷宮内での時間経過に関わってくる要素だ。“あっさり”では敵から戦勝点(いわゆる経験値)や所持金を多く貰えるが、迷宮内の時間経過が早くなる。逆に“どっぷり”では得られる戦勝点が低くなり、敵の体力も増加するが、かなり長い間迷宮内に留まることが出来る。これらはゲーム開始時に選択したらクリアまでそのモードのままというわけではなく、いつでも任意に切り替えが可能だ。
つまり、いわゆる経験値稼ぎをするときは“あっさり”にし、迷宮の奥にいるボス目指して突き進む場合などは“どっぷり”にして滞在時間を増やす、といったように目的によってモードを使い分けることが可能となっている。
本作に不慣れなうちは、迷宮に遠征してもすぐ京へ帰還することになるかと思う。また敵もすぐ逃げ出してしまい、思うように戦勝点と奉納点を稼げないかも知れない。だがイツ花や黄川人の話を聞きつつ試行錯誤をしていくうちに、だんだん勝手が分かってくるはずだ。
そしてようやく「俺屍」のシステムを理解し始めた頃、唐突に別れがやって来る。
悲しみを乗り越え、悲願を子どもたちに託し……ついに初代当主、死す!
「当主様に残された時間は、もうわずかしかありません……最後に、新当主ご指名の任、立派に果たされますようお願い申し上げます」
普段とは打って変わって厳しい表情と口調のイツ花がやって来て、初代当主にこう告げる。とうとう、“短命の呪い”による寿命が来てしまったのだ。ようやく、これから、という文字通りの絶妙なタイミングを見計らったかのようなこの別れ。……実に、実にこの「俺屍」というゲームは意地が悪い。
一族が寿命を迎えれば否応なく死去し、ゲームから脱落していくしかない。一族のひとりひとりへどんなに感情移入しようと、それこそ我が子のように可愛がろうと、せいぜいが2年も保たずに皆あっさりと逝ってしまう。このゲームは“キャラクター”を愛でるゲームではない。主人公一族全員を慈しみ、次世代へと受け継ぎながら育てていくゲームだと、改めて思い知ることだろう。
そして、初代当主の最期の言葉 「子供たちよ……俺の屍を越えてゆけッ」
……筆者はこの言葉を聞いたときに、ようやく「俺屍」という作品を真に理解できたのだと思う。そして、すべてのゲームの中でもトップ10に入るくらいにハマったのも、この瞬間からだったのではないだろうか。
筆者の場合、ここで2つの目標を立てた。1つは一族全員の血を決して絶やさないこと、もう1つは全ての神と交神することだ。前者の血を絶やさないということは、生まれてきた子供たち全員が交神し、必ず子どもを残すということだ。本作は素質のない子どもは放置し、よい血筋だけを残していく、といった攻略法がよく語られている。
ゲームの趣旨を考えれば、競馬での競走馬育成のような良い血統のみ受け継いでいくのが恐らく正解なのだろう。だが自分は、例えどんな資質の子であろうとも必ず血筋を残し、絶体に断絶させないという誓いを立てた。一族の血脈を途絶えさせ、一部の優秀な者のみで悲願を達成したとして、それになんの意味があるだろうか。必ず全員で悲願を遂げる、そのことに意味があるとそう思ったのである。
ただ、この目標が実はとてつもなく険しい道のりだということを、後に思い知ることになるのだが……。それは後で述べることにする。
二代目当主のもと、悲願達成に奮起する一族。しかし問題も課題も山積みで……
初代当主逝去のあとは、二代目当主のもとで改めて一族強化に臨むことになる。迷宮の遠征でも最初のうちはほとんど奥の方へは行けず、中ボスにたどり着くことさえ難しいかも知れない。本作では一度死んでしまった者は二度と復活できない(※)ので、とにかく戦闘不能にならないように、とくに序盤は迷宮の入口で戦闘を重ね、いきなり奥へ進むことは絶体に避けるべきだ。
(※)親のキャラクターよりも先に子が死亡してしまった場合、“反魂の儀”が発生する可能性がある。子を復活させられるが親が肩代わりとなって死亡し、復活した子の髪や目、肌の色が親のものへと変化する。ただし当主のみ、直系の子が死亡しても“反魂の儀”は発生しない
一族は、生まれた際に8つの中から職業を選択できる。親と同じ職業だと奥義を継承させることが出来るが、別の職業でもとくに問題はないため、自分の好きに決めてしまっていいだろう。ただし初期に選択できるのは剣士・薙刀士・弓使いの3つのみで、残りの職業は敵から指南書を入手しなければならない。
こうして迷宮と屋敷を往復しつつ、戦勝点や奉納点を稼いで一族を強化していくことになる。こう書くとやや単調なゲーム性の作品だと思うかも知れない。だが、これ以外にも本作にはさまざまな要素があり、プレイを飽きさせない工夫が随所に盛り込まれている。
たとえば本作での戦闘による戦利品は、戦闘画面下に表示された3つのスロットの出目によって決定されるのだが、これがなかなか楽しい。スロットの回転によって未入手のものが確認出来るし、狙ったアイテムが出目になったりならなかったりで、戦闘ごとに一喜一憂できるのだ。また同じアイテムが3つ揃えばボーナスとして戦勝点2倍、本来ハズレの出目である★が3つ揃えば戦勝点3倍となる。今風にいうなら、ソシャゲのガチャを戦闘ごとに回す感覚だろうか。
ただし、大将格の鬼がまれに戦利品を持って戦闘から逃亡してしまうこともある。そうなると一切戦利品を得られなくなるので、欲しいアイテムが出目に出た場合は、率先して大将を倒す必要がある。
そしてまれに戦利品スロットに“朱ノ首輪”というアイテムが混じっていることがある。前述の通り天界の神々は大半が行方不明になっているが、この朱ノ首輪を持っている鬼は朱点童子によって鬼へと姿を変えられた神である。神としての姿を取り戻させ、天界へ帰還させるためには朱ノ首輪を入手しなければいけないのだが、それぞれ異なる条件を満たさないと出目に止まることがなく、入手することが出来ない。
“朱ノ首輪”の入手条件、つまり神々の解放条件はさまざまで、ある鬼を一定数倒す、ある術を会得した者が出撃隊にいるなどの比較的簡単なものから、特定の神の子どもがいる、特定の武器や防具を装備した者がいる、兄弟(親が同じ)で出撃するなど見つけ出すのに苦労するものまで多種多様だ。本作発売当時は、ネット上で神々の解放条件の情報が盛んにやりとりされていたのをよく覚えている。
一族の育成以外にも、屋敷の増築や町の復興などやるべき事は意外と多い。筆者の場合は前述のようにすべての神と交神することを目標にしていたことから、下位の神から順番に交神していったために一向に強い一族が生まれず、迷宮探索も遅々として進まなかった。だがそんなある日、交神の儀でなんと……!
双子が生まれた! 家族が増えて賑やかになったよ! しかしそれが地獄の始まりだった……?
交神の儀で、なんと双子の赤ちゃんが生まれたのだ。まさか双子が生まれることがあるとは思ってもいなかったので、この時は素直に嬉しかった。職業も親と同じ槍使いにし、常に親子一緒に出撃させて、“三本鎗”などど称して遊んでいたものだ。まさに「家族が増えたよ、やったね!」状態である。ところが、だ……。
交神の儀をする時期になって、困ったことになった。前述の通り自分はすべての一族の血を絶やさないと決めていたため、この時点では4つの家系を維持し、一族1人につき子どもも1人、というようにして家系を維持していた。だが双子が生まれたおかげで、家系を5つに増やさなければならなくなったのだ。これは単純な負担の増加で、双子の誕生によってより多くの奉納点を稼がないと、交神することすらままならなくなってしまったのだ。
下位から順番に交神しているのでなかなか強い子が生まれない→奉納点が稼げない→そこに双子が生まれて血筋が増える、という悪循環にハマってしまったわけだ。しかも、その後も双子は2組、3組と生まれてきた。まさに泣きっ面に蜂である。ゲーム後半は、また双子が生まれてきたらどうしようとビクビクしながら交神していたものである。余談だが、続編の「俺屍2」では三つ子も生まれる可能性がある。ホントに勘弁して頂きたい……。
それにしても……冒頭でさんざんキャラクターへの愛を否定する作品だと書いておいて何だが、なんだかんだ言って生まれてくる一族の子は可愛いものである。親である一族や交神相手の神の面影をよく残した顔の子が生まれたときなど、まるで我が子が生まれたときのように嬉しくなってしまう。きっと、「目元はあなたにそっくりだわ」、「髪の色は君と同じだね」などと、わりとよくある会話を交神した2人(1人と1柱だが)も交わしているんだろうな……、なんて妄想が捗るのである。
思えば不死の存在である神々は、それゆえ子どもを設ける必要もない。一族との交神の儀は、もしかすると神々にとっても存外の喜びであったのかも知れない。
神々の中には、動物や妖怪のような異形の外見の者もいる。そういった神と交神した場合、角や牙が生えている子どもが生まれて来ることがある。また一族の子どもたちはだいたいが整った顔立ちだが、まれにナマズのようなギャグ調の顔の子が生まれてきたりもする。そういった人とはかけ離れた容姿の子が生まれたとしても、我が一族の子と思えば一層愛着がわくというものだ。そういう子に限って優秀な素質を持って生まれ、奥義(※)を編み出したりするのもまた楽しい。
(※)ステータスが一定値を越えたときに習得する必殺技。奥義は職業ごとに異なり、効果もさまざまだが、発動には健康度を消費するので注意が必要。また各奥義は最初に編み出した一族の名前が加えられる(疾風剣○○など)。奥義は一族に代々受け継がれていくので、変な名前を付けた者が奥義を編み出すとあとで後悔するハメになる
そんなわけで一族の強化は牛の歩みとなり、世代交代と年代だけが進んでいった。筆者の場合、最終的に最上位の神と交神して本作をクリアしたときには、なんと1800年代まで時代が進んでしまっていた。一時は現代を追い越してしまうのではないか、と危惧したくらいだ。つまり、筆者の「俺屍」は少なくとも平安時代が1800年代までは続いたことになる。なんとも驚くべき事である。
神にも鬼にも事情あり? 困難を乗り越え、長年の仇敵朱点童子をついに討伐! しかし……!?
京の都周辺にはいくつかの迷宮があり、戦勝点や奉納点は迷宮内の雑魚鬼で稼ぐことになる。迷宮内はいくつかのエリアに分かれており、奥へと進むほど強敵が出現する。また、一部は1年のうち一定の期間しか出現しない迷宮もある。
そして迷宮内にはボスとなる鬼が何体か存在し、倒すと奉納点を大量に入手できる。黄川人の説明やボスたちのセリフからして、どうもこのボスたちは何かしらの理由によって鬼と化した、天界の神々らしいのだが……。
他にも、ひょんなことから強運に恵まれ富くじで大もうけするが、亭主が浮気相手と金を持ち逃げし、世を儚んだで鳥居で首を吊り鬼となった鳥居千万宮のボス・九尾吊りお紺(クビツリオコン)や、飢えと寒さに苦しむ人間たちに、火と風の使い方を教えた罪によって九重楼に幽閉された太刀風五郎・雷電五郎(タチカゼゴロウ・ライデンゴロウ)など、何らかの事情がありそうなボスは多い。
このようなボスや黄川人の会話からすると、どうやら天界でなにか大きな騒動が起こったらしく、多くの神々が地に堕とされ鬼となったらしい。果たして天界では何が起こったのだろうか?
こうして一族は強い神々と交神して世代交代を繰り返しつつ、力を蓄えていった。そしてついに京の果て、すやり霞の向こうにそびえる大江山へと攻め入る。苦難の末、とうとう一族の敵である鬼の総大将、朱点童子と相対することになったのだが……。
「たとえ鬼でもなあ! 一度生まれりゃ、命はてめェのもんだ。そっちの勝手な都合で死ねるかよ!」
朱点童子は一族の額に光る印を見て、かつて自分が呪いをかけた赤子の子孫だと気付いたようだ。そしてなぜか激怒し、一族へと襲いかかってくる。一体、何が朱点の逆鱗に触れたのだろうか……?
激闘の末、とうとう一族は仇敵・朱点童子を討ち取ることに成功する。だが次の瞬間、倒したはずの朱点が起き上がり、口をダラリと開けてコミカルな音楽とともにヒョコヒョコと踊り出す。そして朱点の口をこじ開け、中から現れたのは――
【閲覧注意】以下重大なネタバレが含まれます【閲覧注意】
……まるで服を脱ぎ捨てるように、朱点の内部から現れたのは――実体を持った全裸の黄川人だった。朱点から解放されたことで、一族に礼を言う黄川人。そして彼は、おのれの身の上話を語り出す。
かつて大江山には、小さな都があった。黄川人は姉とともに皇子として大切に育てられていたが、ある日、帝が差し向けた軍勢が京の都から大江山へと侵攻する。父は女に化けた賊に後ろから切られ、母は我が子である姉弟を助けるために自らの身を差し出した。そして父と母を失い、姉も殺されて独りとなった黄川人は放浪の末、神々によって封印される。こうして黄川人は実体を失い、鬼の体内に封印されていたのだ。
一族に呪いをかけ、このような宿業を負わせ続けた張本人。それこそが黄川人だったのである。そして黄川人は帝と京の都に住む人々、一族に改めて復讐を誓い、姿を眩ましてしまう。
屋敷に戻ってみると、朱点討伐の際に多くの神が解放され戻ってきたことで、天界では飲めや歌えの大騒ぎとなっていた。一方地上では、京の都の周囲に強大な鬼たちが棲まう新たな迷宮がいくつも出現していた。……つまり、ある意味「俺屍」はここからが本番なのである。
新たに出現した迷宮を訪れると、なぜか以前と同様に黄川人が一族の前に現れ、迷宮について話を聞かせてくれる、しかしこれまでとは違い、神々の間で起こった事について、かなり核心的な内容となっている。こうして一族は物語の裏でいったい何が起こっていたのかを、おぼろげながら知ることになる。
……ひとりの天女が、人の男に恋をした。それがすべての始まりだった。男と天女は姉と弟、2人の子を設けた。神と人との間に生まれた子は、時として神よりも強大な力を持って生まれてくることがある。そしてこの姉弟は、まさしく強大な力を持って生まれた子――“朱点童子”だったのである。朱点とは大江山に住む鬼のことではなく、“神と人との間に生まれた、強大な力を持った子”の事だったのだ。
2人の朱点童子が生まれたことにより、天界は大きく揺れ動いた。元々天界では人間界に介入することを禁忌としていたが、2人を天界の主導者に据えようとする革新派の神々と、それを良しとしない保守派とに分断された。革新派は大江山に小さな都を築き、2人を祭り上げた。しかし保守派は時の帝を操り、姉弟討伐のために大江山へ軍勢を差し向けたのだ。
黄川人は信者たちによってなんとか逃げ延び、鳥居千万宮で捨て子となった。それを拾ったのが、子が出来ずお百度参りをしていた人間の女性・お紺である。彼女の金運は、朱点童子である黄川人がもたらした力だったのだ。一方、母親である天女・片羽ノお業は禁忌を破ったことにより天界にも戻れず、見世物として人の間を転々としていた。そして死んだ姉の魂は当時の最高神であった太照天夕子によって天界へと運ばれ、新たな最高神・太照天昼子となったのだ。
忘我流水道に流れ着いた黄川人は、氷ノ皇子に拾われて育つ。天界第2位だった彼から乳ならぬ血を与えられ、身体が芯から冷え氷より冷たくなるほど血を吸い尽くした結果、黄川人は皇子からさらなる力を得てしまう。そして敦賀ノ真名姫と出会い、彼女の境遇――喰えば不死となる人魚を求めた人間たちに遭わされた悲惨な過去――を知り、ついに黄川人は人間と天界の神々に復讐を誓うようになる。
天界の神々は多大な犠牲を払いながらも、なんとか黄川人を鬼の身体に封印することに成功した。だが封印することは出来ても黄川人を滅ぼすことまでは敵わかった。そこで神々のある計画の元、ひとりの天女に白羽の矢が立つ。
それが片羽ノお輪――片羽ノお業の双子の姉であり、初代当主の母親である。お輪は妹同様に人との間に子を設けるため、地上に降り立った。そして人間である源太との間に初代当主が生まれたのだ。天界の神々はこの“3人目の朱点童子”を以て黄川人を滅ぼそうと企んだのである。
これこそが、この物語の真相だったのだ。なぜ鬼の朱点童子を討伐したときに、多くの神々が解放され天界の神々が祝い騒ぐ一方で、黄川人の封印が解けたことに誰1人警戒を示さなかったか。つまりは黄川人の復活も、神々の計画に織り込み済みだったからである。
こうして一族は事の真相に迫りつつ、黄川人が待ち受ける地獄の底へ向かうことになる。
すべての恩讐を乗り越え、悲願を果たした主人公一族。しかしPSP版ではさらなる試練が待ち受ける……?
限界までおのれを鍛え、最後の迷宮“地獄巡り”の奥へと向かう主人公一族。そこで待ち受けていたのは、黄川人1人ではなかった。なんと初代当主の母、お輪が囚われていたのである。ここでの会話とイベントムービーはかなり精神的にキツいものがあるので、可能ならば自身の目で確かめてほしい。過去に「リンダキューブ」をプレイした人であれば、最終ボスの造形を見て悪夢のシナリオAのトラウマを呼び起こされるかも知れない、とだけ言っておくに留めたい。
長い戦いの末、ついに黄川人は倒れた。すべての怒りと恨みを浄化され、黄川人はお輪とともに天界へ還っていった。一族の悲願も果たし、いずれは呪いも解けることだろう。めでたしめでたし……、とはならない。PSP版では、エンディングのあとさらなる試練が一族に待ち受けているのである。
スタッフロールのあと、PSP版では黄川人と天界最高位の女神、太照天昼子の二柱から話が聞ける。昼子からは「すべてを水に流していただけけますか?」と問われ、黄川人からは「この茶番の黒幕が誰なのか、さすがに気づいてるんだろ?」と問われる。そして黄川人の問いに肯定すると、“裏京都”と呼ばれるモードに突入することになる。
この裏京都は、言ってみればクリア後のやり込み要素のようなものだ。大江山では裏京都のラスボス、太照天昼子と戦えるようになっている。この太照天昼子戦は比喩や慣用的な表現ではなく、文字通りの意味での“ケタ違いの強さ”なので、挑む場合は覚悟してほしい。
またこの裏京都は単なるやり込み要素と言うだけではなく、物語の真の核心に迫る手掛かりを得られるようにもなっている。
【閲覧注意】以下重大なネタバレが含まれます【閲覧注意】
首尾よく太照天昼子を倒すことが出来ると、彼女は「すべてを水に流していただけけますか?」と再び問いかけてくる。いったい彼女は、何を水に流してほしいのだろうか?
たしかに主人公一族は、神々の計画のもと人間である源太と神であるお輪との間に生まれた。そして“種絶の呪い”によって神と交神し子孫を残すしかなくなり、結果として代々“朱点童子”として生まれることになった。
ここで1つ疑問が残る。大江山で鬼の朱点童子を討伐したとき、どうやら彼は神々の計画に気付き、そして激怒した。なぜ彼は激怒したのだろうか?
「君たちがあの鬼にかけられたのは、短命の呪い。でも、暖かい家族がいる」
大江山に初めて討伐に向かったときの、黄川人の台詞である。ここで黄川人は“短命の呪い”だけに言及し、“種絶の呪い”には触れていない。そして、朱点童子が初代当主である赤子に呪いをかけたときの台詞はこうだ。
「せいぜい父ちゃん、母ちゃんの分まで長生きしな」
もちろんこれは、自らが掛けた呪いを皮肉った言葉である。だが、ここでも朱点童子は黄川人同様“種絶の呪い”については触れていない。そしてこのシーンの映像をよく思い返してほしい。このとき朱点は赤子に、呪いを“1つしか掛けていない”のだ。つまり、赤子は朱点童子に“短命の呪い”しか掛けられていなかった可能性がある。
では、いったい誰が赤子に“種絶の呪い”を掛けたのだろうか? なぜ、朱点童子は激怒したのか?
そもそも“種絶の呪い”を掛けられた者は交神の儀によって子を設けるしかなく、結果的に子どもは“朱点童子”として生まれてくる。鬼の朱点童子が赤子の命を救うという約束を守りつつも将来の禍根を断つべく“短命の呪い”を掛けるのは、当然納得がいく。だが“種絶の呪い”まで掛けてしまうと、赤子の子孫が“朱点童子”として自分の前に立ちふさがるかもしれないのだ。そのような可能性が生じることを、わざわざ自らするだろうか?
鬼の朱点童子が激怒したのは、目の前に立ちふさがる一族がすべて“朱点童子”だと気付いたからだろう。そして“朱点童子”を生み出すためには交神の儀をする必要があり、そのために一族に“種絶の呪い”を掛ける必要があったのが誰であるのかを悟ったのだろう。自分が“種絶の呪い”を掛けていないのならば、当然このことまで考えが及ぶはずだ。だから一族に“種絶の呪い”を掛け、自分を滅ぼそうとした黒幕に激怒したのである。天界はまたもや禁忌を破り、自分を滅ぼすために人間界に介入したのか、と。
“種絶の呪い”によって行われるようになった交神の儀は、一族の血が絶えることを神々が憐れんだからではない。鬼の朱点童子と黄川人を倒すため、より強力な“朱点童子”を生み出すことこそが目的だったのだ。
以上のことと、昼子の「すべてを水に流していただけけますか?」という言葉。いったい誰が一族に“種絶の呪い”を掛けたのか、想像がつくのではないだろうか。
もちろんこのことは作中では具体的に描写されてはいない。いうなれば状況証拠による推察でしかない。しかしよくよく考えてみれば、主人公一族は壮絶な“姉弟喧嘩”に巻き込まれただけの存在だったのではないだろうか。黄川人の言う通り、この黒幕にビンタの一発もくれてやりたい気分だが、エンディングテーマ「雄叫び」を聴いているうちに、そんなモヤモヤした気持ちもなんだか吹き飛んでしまった。なんだかんだで、本作は筆者にとって生涯のうちベスト10には入る名作だったと、25年経った今に改めて思う。
本作は、筆者同様根強いファンが多い作品だ。冒頭で述べた通り、この4月からはPS4およびPS5でもPSP版のプレイが可能になっている。この機会にぜひプレイして、多くの人に新たな一族史を紡いでほしいものである。
(C)2011 Sony Interactive Entertainment Inc. 俺の屍を越えてゆけ is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※ゲーム画面はPSP版のものです




















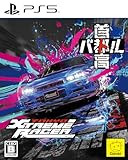











![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)








![WB Games 【Switch2】ホグワーツ・レガシー [POT-P-AAFQA NSW2 ホグワ-ツレガシ-] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0498/4974365870676.jpg?_ex=128x128)


![STRASSE RCZ01用連結強化プレート 単品 ベースフレーム固定[ハンコン ストラッセ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shunte/cabinet/game/str153-00.jpg?_ex=128x128)

![THQ Nordic Japan 【PS5】REANIMAL(リアニマル) 通常版 [ELJM-30779 PS5 リアニマル ツウジョウ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0031/4571574970403.jpg?_ex=128x128)







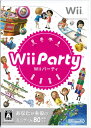






![[Switch] Nintendo Switch Online + 追加パック個人プラン12か月(365日間)利用券 (ダウンロード版) ※1,000ポイントまでご利用可 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/3/802252363_p.jpg?_ex=128x128)

![ペルセポリス 4Kレストア【Blu-ray】 [ マルジャン・サトラピ ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)
![Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ (アニメーション) ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2052/4534530162052_1_2.jpg?_ex=128x128)
![映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」Blu-ray(通常版)【Blu-ray】 [ EVIL LINE RECORDS ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4771/4988003894771.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組)(特装限定版)【4K ULTRA HD】 [ 古谷徹 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0114/4934569800114.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典】グノーシア 3(完全生産限定版)【Blu-ray】(キービジュアルB2タペストリー+公式ミニキャラアクリルキーホルダー(SQ&ジナ)) [ petit depotto ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2236/2100014672236_1_2.jpg?_ex=128x128)

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8899/4580055368899_1_3.jpg?_ex=128x128)
![劇場アニメ『ひゃくえむ。』(特装版)【Blu-ray】 [ 魚豊 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6610/4524135296610_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ゾイドワイルド Vol.2 [Blu-ray] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/424/tbr-28342d.jpg?_ex=128x128)