【特別企画】
DualSense Edgeで死にゲー「Wo Long」を試す
どちらも発売直前! 背面ボタン活用で“より快適な”死にゲーに
2023年1月23日 23:00
- 【DualSense Edge ワイヤレスコントローラー】
- 1月26日 発売予定
- 価格:29,980円
- 【Wo Long: Fallen Dynasty】
- 2023年3月3日 発売予定
- 価格:8,580円より
ソニー・インタラクティブエンタテインメントより1月26日に発売となるプレイステーション 5用DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(DualSense Edge)。今回、発売前となるDualSense Edgeを使用して、さらに3月3日発売予定のダーク三國アクションRPG「Wo Long: Fallen Dynasty」をプレイできたので、その模様をお伝えしたい。
なおDualSense Edgeのより詳細な設定方法や使い心地や、他タイトルにおける使用感などは別途ご紹介しているので、合わせてご覧いただきたい。
“いかに攻め続けるか”が大事な死にゲー「Wo Long」
本題に入る前に、まず「Wo Long: Fallen Dynasty」の特徴を改めてご紹介しておきたい。
本作はコーエーテクモゲームスのTeam NINJAが開発するダーク三國アクションRPG。近年のTeam NINJAといえば「仁王」シリーズが記憶に新しく、その流れを考慮すると、「Wo Long: Fallen Dynasty」は「仁王」シリーズに次ぐコーエーテクモゲームスの新たな死にゲータイトルと言える。
ジャンル名に「三國」と入っているように、本作は後漢末期の「三国志」を舞台としている。そのためアクションは中国武術がベースとなり、また登場キャラクターには劉備、曹操、孫堅といった三国志おなじみの面々が揃う。「仁王」シリーズと同じ“死にゲー”の括りではありながら、「Wo Long」らしい独自のシステムとアクションが特徴だ。
ポイントとなるのは、プレーヤーと敵の両方に設定されている「氣勢(きせい)」ゲージの存在。攻撃を仕掛けるほど「氣勢」は高まるが、防御や回避などの守勢に回るほど「氣勢」は削がれていくというものだ。
攻撃を連続で放って自らの「氣勢」を高めつつ、相手の「氣勢」を最大まで削れば行動不能に追い込んで、強力な必殺技「絶脈」を繰り出せる。戦闘ではこうしたプレイが理想的だが、当然相手も攻撃してくるし、往々にして強い。攻撃一辺倒では手痛い返り討ちにあって、逆にこちらの「氣勢」が最大まで減って行動不能に陥ってしまったりする。
つまり、本作では防御や回避、被ダメージは最低限にしつつ、「いかに攻め続けるか」が攻略では不可欠となっている。戦闘アクションには、敵の攻撃に合わせてタイミングよく発動して攻撃を受け流せる「化勁(かけい)」や、溜めた「氣勢」を使って放つことができる技「武技」などがある。これらを駆使し、強力な敵をねじ込むようにして攻略していく体験が「Wo Long」ならではの醍醐味だ。
DualSense Edgeのカスタマイズで“ヒリつく”アクションがより快適に
今回のデモでは、チュートリアルステージにて本作のシステムを一通りプレイした後、巨大な猪の姿をした妖魔「封豨(ほうき)」と対戦できた。
「封豨」は容貌そのまま圧の強い敵で、突進や踏みつけ、また覆いかぶさってくるような体当たり系の攻撃を繰り出してくる。一発一発の攻撃が重いので、十分に距離を取り、攻撃は「化勁」でしっかり受け流していかないと防戦一方になってしまう。
ただし、ある攻撃に化勁を決めることで、大幅に封豨の氣勢を削ることができ、成功すれば一気に攻撃と「絶脈」を叩き込むチャンスになる。化勁を外すとただ大ダメージを食らうばかりなのでまさに諸刃の剣だが、根気よく、大胆にプレイしていく本作の軸の部分をまさに体験できる敵と言える。
ではそんな封豨との対戦にDualSense Edgeがどう活用できたかというと、特に背面ボタンはかなり役立った。筆者がかなりしっくり来たのは、背面ボタンに「道具の使用」にあたる十字ボタンの“上”を設定したことだ。
デモ版では体力回復アイテムが使用でき、これによって減った体力を全快に近くまで回復できた。特に本作は「死にゲー」なので、体力が残り少なくなったら敵との間やタイミングを見ながらしっかりと回復する必要がある。
本作では左スティックで移動をするが、回復用の上ボタンを使用するには、一旦左スティックから親指を離さなければならない。つまり上ボタンを使う際は足を止めざるを得ないので危険極まりないのだが、背面ボタンに設定していればそのリスクが減る。
本作は、敵をロックオンして視点をある程度固定できるため、カメラ操作の右スティックを離すことはそれほど気にならない。そこで右スティックのフォローはあえて捨て、道具を切り替える左右ボタンも背面ボタンに割り当てることで「いかなる時も左スティックを離さない」設定が実現できる。実際には、背面左に「上ボタン」、背面右に「右ボタン」を割り当てて封豨と戦い抜いていった
なおDualSense Edgeの背面ボタンパーツは長短(レバー型、ハーフドーム型)の2種類があり、筆者は指の引っ掛かり的に短(ハーフドーム型)が使いやすかった。どちらが使いやすいかは好みが分かれるところなので、これは実際に試すほうが早いだろう。
他にも、素早いアクションのためにトリガーボタンの深さは3段階でもっとも浅く設定したり、右スティックボタンのキャップは高めの「ハイドーム」にして指の引っ掛かりやすくしたり、いろいろ試すことで「死にゲー」のプレイをできる限り快適にできた。
DualSense Edgeの場合は、ボタン機能の入れ替えがコントローラー側の設定でできるので、突き詰めればもっと快適な設定も見つかるかと思う。「Wo Long」の発売も楽しみだし、細かいところに手が届くDualSense Edgeのカスタマイズ性は、一度触れたらなかなか忘れられない魅力がある。まだ入手が確定してない方も、今後再販や抽選の可能性は十分にあるので、ぜひチャンスを狙っていただきたい。
©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.



















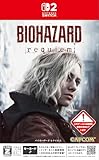









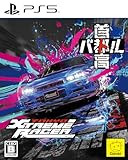










![【Amazon.co.jp限定】劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray【特装版】(早期予約メーカー特典クリアファイル+L判ブロマイド5枚セット付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41N2LB75ruL._SL160_.jpg)
![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)




![インティ・クリエイツ 【特典付】【Switch2】白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション 通常版 [NXS-P-BUVEB NSW2 シロキコウテツノイクス 1+2 ツウジョウ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0064/4582173563569.jpg?_ex=128x128)

![スクウェア・エニックス 【Switch2】オクトパストラベラー0 [POT-P-AAW2A NSW2 オクトパストラベラ-0] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0003/4988601012058.jpg?_ex=128x128)


![スクウェア・エニックス 【Switch2】ドラゴンクエストVII Reimagined [POT-P-AASVA NSW2 ドラゴンクエスト 7 リイマジンド] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0037/4988601012089.jpg?_ex=128x128)




![ハピネット 【PS5】ポピープレイタイム トリプルパック [ELJM-30713 PS5 ポピ-プレイタイム トリプルパック] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0525/4907953564930.jpg?_ex=128x128)


![ソニー・インタラクティブエンタテインメント 【PS5】Stellar Blade (ステラーブレイド) [ECJS-00034 PS5 ステラ-ブレイド] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0174/4948872016858.jpg?_ex=128x128)

![インティ・クリエイツ 【特典付】【PS5】白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション 限定版 [INTI-0040 PS5 シロキコウテツノイクス 1+2 ゲンテイ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0064/4582173563743.jpg?_ex=128x128)
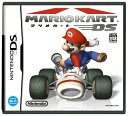



![任天堂 ニンテンドーサウンドクロック Alarmo [CLO-S-RAAAA アラ-モ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0479/4902370552195.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(Blu-ray通常版)【Blu-ray】 [ 小野賢章 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6399/4934569366399_1_2.jpg?_ex=128x128)

![トリツカレ男 豪華版【Blu-ray】 [ いしいしんじ ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5649/4907953235649.jpg?_ex=128x128)
![『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I=We’re IDOL PRECURE』Blu-ray通常版【Blu-ray】 [ プリキュア ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0734/4535506020734.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5714/2100014785714_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.3 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4367/2100014774367_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.2 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4350/2100014774350_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.4 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4374/2100014774374_1_3.jpg?_ex=128x128)

