ニュース
「CryEngine」のVRデモの“立体感”の秘密とは
Crytekのサウンドクリエーターが教えるVRサウンドの作り方
(2016/3/21 09:10)
GDC2日目の19日、Crytekのサウンドクリエーター、Simon Pressey氏とFlorian Fusslin氏は、「Virtual Reality and Real Audio」と題して、VRにおけるリアルなサウンドについての講演を行なった。
メインにセッションを進めたPressey氏は、サウンドクリエーターとして20年以上のサウンド製作キャリアを持つ。映画やコマーシャルのポストプロダクションを経て、2000年以降はゲームの音作りに携わるようになり、UBI Montreal、Bioware Edmonton、SCEE、Crytekと渡り歩いてきた歴戦の強者だ。
一方のFusslin氏は、Crytek一筋10年のキャリアで、「Crysis」シリーズ、「Ryse: Son of Rome」、「Warface」に加え、「CryEngine」の技術デモのサウンドを作成している。いわば同社のエースサウンドクリエーターだ。
技術的な面で「CryEngine」は、Simple DirectMedia Layer(SDL)に加え、CRI、FMOD、Wwiseと各種サウンドミドルウェアをサポートし、ランタイムで動的にミドルウェアを切り替え可能というユニークな機能を持っている。自前のサウンドライブラリを組み込むことも可能だ。
同日リリースされた「CryEngine V」ではFMOD Studioをサポートしていることから、推奨サウンドミドルウェアはFMOD Studioということになるだろうが、サウンドクリエーターの使用経験や必要な機能、データの取り回しの利便性、ライセンス料などを勘案して、自由に選択できるものと考えていいだろう。
本セッションは、VRコンテンツに対して、こういったミドルウェアのそれぞれの機能をどう使ってどういう音を出すといった技術的側面からのアプローチではなく、あくまで楽曲や効果音を作る者として、VRゲームならこういったことを意識して音作りをする、といったものであった。VRコンテンツの体験中は、ついつい我を忘れてしまうが、これからVRコンテンツを体験するときには、本セッションの内容を思い出して、今後は音の方にも意識を向けながら体感すると、また新たな発見があるように感じられた。
Pressey氏たちがVRの音作りにおいて常に意識しているのは、音源の分離と没入感である。また、音のダイナミクスとラウドネスにも気を配る。また、通常のゲームや映像などでは、音源が空間上に実際に存在するものから来る音も、ドラマやシーンの内容を暗示したりプレーヤーのムードを盛り上げたりするための実際のは存在しない音も、当たり前に両方必要になるが、VRの場合これをどうするか、ということもポイントとなる。
Pressey氏はこれらを同社の技術デモ「Back to Dinosaur Island」を例に解説していった。Pressey氏によると、そもそもサウンドはごまかしが効かず、絵よりも変化の周期が激しく、リアルな音でないと嘘っぽく聞こえてしまうのだという。人は自分の頭の位置は常に理解しているものだが、日常ではそれほど意識しない。ところがVRとなると、仮想世界に実際に肉体はないにも関わらず、自分の頭の位置に意識がいってしまう。VRでは、確かに、そこに存在するという実感がより必要になるのだ。さらにVRの音は、VR世界のストーリーとアクションの両面をトータルに盛り上げる役目も負っている。
「Back to Dinosaur Island」の音は、トンボ、恐竜、恐竜の卵などの物理的な物体との接触、没入感、空間の奥行感、アクション、位置取りと、VR空間内で実感するすべての事象に気を配って作られている。具体的なコントロールは、音の発生源に、それぞれに発生源を意味するデータを埋め込み、ダイナミックに移動するオブジェクトの場合は発生源のデータが追従し、さらに発生源の接触を監視することで実現している。
音のダイナミックレンジは広ければ広いほどよく、Pressey氏によると、普通の人は盛り上がりのピークには大げさな大音量を好むそうだ。ヘッドフォン環境で広いダイナミックレンジは可能で必須の事項だ。他にも聴き疲れの提言を考慮したり、さらに臨場感を高めるためにキャラクターボイスやワールドの環境音に加えたり音効で補うこと考えなければならない。ここまでは、既存の立体音響と同様で、まぁそうですよね、といった内容だ。
一方、VR固有の特性として、人はVR環境下ではBGMが流れるといった演出はなかなか受け入れられないのだという。あまり意識したことはなかったが、言われてみればなるほど納得の話だ。これはスクリーンとの距離感やインタラクションの有無、頻度が大きく関係しているように思える。映画やカットシーン、RPGなどのイベントのように、プレーヤー自身が落ち着いて物語に感情移入しているシチュエーションでは、BGMの効果は高く、感情移入を高めるのに役立つ。ところがVR体験では、どこから誰が鳴らしている音なのかよくわからず興ざめだということだろう。
Pressey氏は、どうしても楽曲とともに映画的なシーンをやりたいなら、映画的なビジュアルを用意すべきで、ドラマのアクセントになるような、ごく短い小節のものにすべきだとしていた。Presseyのこの指摘を聞いて、ゲーム内の自分のキャラクターがポータブルプレーヤーのヘッドフォンを装着したり、カーステレオをオンにするといった演出があれば、受け入れられるかもしれないと思えた。とはいえ、BGMを派手にやると空間内の音源と喧嘩してしまい、没入感を阻害する。やはりBGMを鳴らすには十分な工夫が必要になりそうだ。
人間が無意識に、周囲の音を選択的に聞いていることもVRゲームに反映させなければならない。ただ単純に自分の位置と音の発生源との距離をみて、漫然とボリュームを上げ下げする作りではリアリティは感じない。人が気をとられる音とガヤといった区別が必要で、最も接近してしているもの、最も騒がしく音を立てているもの、プレイ状況で重要なもの、巨大な移動物体、2,000~4,000Hz帯の音などに音のフォーカスを当てて、メリハリを利かせるべきだとしていた。
Pressey氏の長年のゲームサウンド開発の経験から来る言は示唆に富んでいた。VRになったからといって、音作りが何もかも劇的に変化したということではない。サウンドの方が、5.1chサラウンドや2chのヘッドフォンでも擬似的にサラウンドを実現する仕組みが存在しゲームサウンドの臨場感に一役買ってきたという経緯があり、ずいぶん先行しているからだ。
プレーヤーが360度、自由に頭の向きを変えることができるという特性が加わったものの、向きの変化に対応して音の定位をコントロールするのは、エンジンのサウンドシステムの仕事でコンテンツ製作上は、従来の立体音響の延長線上にある。
VR HMDでは、その特性から否応なしに視覚的に高い没入感が得られる。その没入感と喧嘩しないで相乗効果をもたらすキモは、Pressey氏のいうように、ただ単純に現実に近づけていけばそれでいいというものではなく、リアルを超えたところにあるリアルを創造して、音にメリハリを持たせることが、プレーヤーにとって違和感がなく自然に体感させることにつながると言えるだろう。






























![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51OfQn3c5vL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1 (特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51-w6XyYNtL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】アイカツ!×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!- Blu-ray(特典:ビジュアルシート+メーカー特典:パスチャーム) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51MrfY-rIuL._SL160_.jpg)
付き [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51p3oabQuCL._SL160_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】『葬送のフリーレン』Season 2 Vol.1 初回生産限定版 (Amazon限定:描き下ろしフラップポーチ付き、Amazon限定全巻購入特典:描き下ろし全巻収納BOX引き換えシリアルコード付き、全巻購入メーカー特典:箔押しトランプ付き) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/41AAnMAwElL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)




![【送料無料】任天堂 Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)マリオカート ワールド セット[BEE-S-KB6PA]【新品・国内正規品】【返品不可商品】ニンテンドースイッチ2 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/digimart-shop/cabinet/kaden/kd0387_01.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch2】ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition [NXS-P-AAAAH NSW2 ゼルダノデンセツ ブレス オブ ザ ワイルド] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0495/4902370553291.jpg?_ex=128x128)










![ソニー [PS5]DualSense デュアルセンス ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー 純正品 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hikaritv/cabinet/plala/201/01233/2010123386_k.jpg?_ex=128x128)












![【中古】【箱説あり】【動作未確認】ニューコードレスパッドセット (ホワイト)[HSS-0116]<レトロゲーム>(代引き不可)6597 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/wondergoo/cabinet/hobbytenpo164/659720250521104_1.jpg?_ex=128x128)
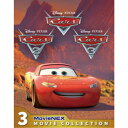
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典+他】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX+他) [ 芥見下々 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4343/2100014774343_1_3.jpg?_ex=128x128)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0051/4934569370051.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】[限定版][先着W特典付]映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』 (特装限定版)【Blu-ray】/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/051/bcxa-2005.jpg?_ex=128x128)

![【先着特典】映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】(描きおろしイラスト使用A4クリアファイル+ボイスドラマつきカレンダーポスター(約A3サイズ)) [ 矢立肇 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4038/2100014784038.jpg?_ex=128x128)

![メダリスト Season2 vol.1【Blu-ray】 [ つるまいかだ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0120/4988111670120.jpg?_ex=128x128)
![メダリスト Season2 vol.2【Blu-ray】 [ つるまいかだ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0137/4988111670137.jpg?_ex=128x128)
![パーフェクトブルー 4K REMASTER EDITION/ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray(豪華版) [Ultra HD Blu-ray] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mifsoft/cabinet/046/vpxv-75204.jpg?_ex=128x128)