【特別企画】
「PSO2:NGS ver.2」、ゲーム内カードゲーム「ラインストライク」が7月実装! 目まぐるしく変化する戦況、相手との読み合いがアツいカードバトルを体験
2024年6月28日 17:00
- 【ラインストライク】
- 7月 配信予定
セガは現在配信中のプレイステーション 4/Nintendo Switch/PC用オンラインRPG「PSO2 ニュージェネシス ver.2」(以下NGS)において、7月の大型アップデートで新要素「ラインストライク」を追加する。
「ラインストライク」は、自分が所持するカードを使って、プレーヤー同士で対戦することができるゲーム内の対戦型カードゲーム。15枚のカードを使用し、3つのラインにカードを出していき、各ラインの戦力値を競い合う。カードには「PSO2」のキャラクターやエネミーが描かれており、コレクター心もくすぐられるカードゲームだ。
今回、「ラインストライク」の本実装を前に、先行体験させていただいた。今回はNPCと対戦する「対NPCバトル」を体験できたので、「ラインストライク」の魅力をお伝えしたい。
「PSO2」のキャラクターがカードに! 短い時間でサクッと楽しめる
「ラインストライク」は、「PSO2」で登場したキャラクターやエネミーたちが描かれているカードを使って対戦するカードゲームだ。カードのイラストはどれもとてもきれいで、中には懐かしいキャラクターもいたりして「あぁこのキャラクターいたなぁ」と懐かしい感情を覚えた。また、それぞれキラキラのホログラムが付いたレアカードもあり、コレクター心がくすぐられる。
なおカードは、カードスクラッチ補助券を集めてカードスクラッチを引くか、スタートデッキを購入することで手に入る。カードスクラッチ補助券は「ラインストライク」を対戦することや、被ったカードを交換して手に入れたリサイクルバッヂを集めて交換することで手に入れられる。また、ACでカードスクラッチ補助券を購入することも可能だ。
「ラインストライク」のルールだが、3ライン×3マスの自陣にカードを召喚し、縦3列それぞれの合計値を対戦相手と競うというもの。各列にはそれぞれ拠点があり、自陣のライン上にあるカードの戦力値の合計が、同じライン上にある敵陣のカードの戦力値の合計より高い場合、その列の相手の拠点にダメージを与えることができる。拠点の体力は5点で、0点まで削ると破壊。3ライン中2ラインの敵陣の拠点を破壊できれば勝利だ。
縦のライン上に並んだカードの戦力値の合計値で拠点を攻撃できるか決まるのだが、拠点にどれだけダメージを与えられるかはライン上にあるカードの枚数で決まるようになっている。どれだけ戦力値で勝っていても、ライン上にカード1枚のみであればダメージは1点。2枚配置されていれば2点となる。
ちなみに、自陣と敵陣の戦力値が同数だった場合は双方の拠点へダメージが入るようになっている。
「ラインストライク」のデッキ枚数は15枚。初期手札は5枚だ。手札にしたカードを場に召喚するためにはカードに表示されているコストを消費するのだが、コストは毎ターン3ずつ追加されていく。コストが足りる限り、何枚でもカードを場に出せるし、ターン中に使いきれなかったコストは次のターンに持ち越しだ。なお基本的には、カードに書かれているコストが高いほど攻撃力も高く強いカードとなっている。
さて、実際のゲームの流れだが、「ターン開始」から、「ドローフェイズ」、「カード配置フェイズ」、「効果発動フェイズ」、「戦闘フェイズ」、そしてまた「ターン開始」へと戻る。「ターン開始」で使用できるコストが3追加され、「ドローフェイズ」でカードを1枚引くまでは自動進行だ。ここから「カード配置フェイズ」でプレーヤーの操作がはじまり、コストを消費してカードを配置できる。互いに配置が終わったら、相手のカードも表示され、「効果発動フェイズ」でお互いにそのターンで出したカードの効果が発動される。そして最後の「戦闘フェイズ」でラインごとに戦力値が計算され、どちらかにダメージが入るという工程を繰り返す。
対戦の流れはとてもシンプルでわかりやすく、1回の対戦時間も10分程度とかなり短い。基本的にはカードを使い切る前に勝負がつくので、サクッと楽しめる。しかしながら、後述する特殊なカードの出し方「リライト召喚」や、カード毎の効果が絡み合い、戦略性も感じられるカードゲームになっている。
ちなみに、対戦には実力が同等のプレーヤー同士でレートを奪い合う「レートバトル」、レートを気にすることなく気軽に遊べる「アンレートバトル」、NPCとの対戦を楽しむ「対NPCバトル」、対戦したいプレーヤーを指名して承認されると対戦できる「フリーバトル」がある。今回の体験では「対NPCバトル」のみだったが、レートを掛けて戦う「レートバトル」のひりつき感も味わってみたい。
6種の属性、3種のスキル。カードそれぞれに個性が
カードの効果は「スキル」と呼ばれ、スキルには「支援効果」と「妨害効果」、「パッシブ」の3種類がある。
「支援効果」と「妨害効果」のスキルはカードを配置したときに1度だけ発動する。「対象の味方の戦力値を上げる」や「今のターンのあいだ、対象の敵を行動不能にする」といった即時に効果が発揮されるスキルだ。「支援効果」を持つカードと「妨害効果」を持つカードが同時に出た場合は、お互いの支援効果が発動したあと、次に妨害効果が発動する。
「パッシブ」は、「自分の戦力値が、味方の数だけ上がる」や「自分が敵の拠点を攻撃するとき、1度だけ1点増える」など、配置されているだけで常に効果が発揮しているスキルだ。配置してからターン終了後も効果が継続して発揮される。
また、カードにはそれぞれ「炎」、「氷」、「風」、「雷」、「光」、「闇」という6種類の属性に分かれており、属性によって得意なスキルがある。炎属性は場にいる味方の数に応じて戦力が強化されるので、中盤から後半にかけてより強くなっていく。氷属性は敵の弱体化が得意で敵の戦力を削る。風属性は味方や相手のカードの位置を入れ替えて戦況の変化を与える、雷属性は低コストカードが多く、拠点へのダメージを増加させるカードもあり序盤に強い属性だ。光属性は自拠点へのダメージ軽減や味方の強化を得意としている。そして闇属性は敵のカードを1ターン無力化して戦力値を一時減少させることができる。この6つの属性のカードを組み合わせてデッキを作ることができる。
同じ属性のカード同士であれば、場に出ているカードの上にカードを出す「リライト召喚」という特殊なカードの出し方をすることができる。
このリライト召喚では、出したいカードの必要コストから場に出ているカードの必要コストを引いた差分コストで場にカードを出すことができるようになる。例えば、4コストのカードを召喚したい状態で、場に2コストのカードが出ていれば、4−2=2の2コストだけを支払ってそのカードの上に召喚できる。
ただし、出したいカードが、召喚されているカードよりコストが高いことがリライト召喚の条件だ。低コストで強いカードを場に出せるというメリットもあるが、元々配置されていたカードは使えなくなるため、元のカードの戦力値や付与されていたバフデバフはリセットされる。
デッキを組む際は1つの属性のみで組むことも複数の属性を混ぜて組むこともできる。開発陣によると、デッキを組むコツは2つ程度の属性にとどめてデッキを組むことだそうだ。それぞれの属性の強みも出やすく、リライト召喚もしやすいとのことだった。
デッキはもちろん複数個つくることができるので、自分なりにデッキをつくってみて様々なプレイスタイルを試してみるのもいいだろう。
目まぐるしく変わる戦況と対戦相手との読み合いが楽しい
実際に対戦してみると、ターンごとに戦況が目まぐるしく変わるゲームを楽しめた。1ターン目で場にカードを召喚し、どちらかの拠点もしくは双方の拠点にダメージが入ったあと、次のターンから本格的にどうプレイしていくかを考えていくことになる。例えば、1ターン目に対戦相手がカードを召喚したラインに、対抗するようにカードを召喚してダメージを受けないようにするのか、あえてダメージを負ったラインは放っておき、残りの2つの拠点を確実に攻めていくのかといった決断を迫られる。
ゲームに勝利するには確実に2ラインの戦力値で勝っておかなくてはいけないので、ターンが終わるたびに次はどこを攻めるかどこを守るかを判断する必要がでてくる。対戦相手がどこのラインを攻めてくるか、このため、より対戦にスピード感があるように感じるのかもしれない。
2ターン目以降は、手札やコストの残数を見つつ、相手の動向を予測しながら次のアクションを考える。またコストの残数が少なくても、リライト召喚も候補に入ってくるので、一気に戦況を変えることも可能になる。2ターン3ターン目あたりは場に出ているカードも少ないため戦況を読みやすいが、5ターン6ターンあたりになってくると場にたくさんカードがあるため考えることが増えてくる。そうなってくると対象の敵を行動不能にする効果や、カードの場所を移動させる効果、味方の攻撃力上昇などが効果的に効いてくるので、どのカードを切るか、ひとつひとつの行動が勝負の結果に直結する。
ターンごとに相手のカードが表示される瞬間は自身の判断が間違っていなかったのか、ドキドキする。読みが当たっても外れても次の一手を考えるのが楽しい。
今回の体験では全てのカードが揃った状態でNPCとの対戦だったため、かなり戦いやすい環境だった。手持ちのカード資産が少ないながらも、工夫してデッキを組んで対戦するのはカードゲームの楽しさのひとつ。筆者的にはカードを1から集めていくのがとても楽しみだ。何が出てくるのかわからないワクワク感や、目当てのカードが当たった時の高揚、逆にカードが被った時のちょっとしたがっかり感も楽しみたい。
対戦も有人戦になってくるとまた違った楽しみ方も出てくると思う。レートバトルで上を目指すのも楽しそうだ。対戦時間も10分程度と短めなので、緊急クエストの前の時間でサクッと遊ぶのも良さそうだ。せひ1回プレイしておもしろさを体験してみてほしい。
(C)SEGA



































![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)


![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)
![ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 102期活動記録 ~Ties of Triangle~ (ドラマCD付き)[グッズ]*この商品はDVDではございません 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/510ZUtt4YhL._SL160_.jpg)
![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)












![ソニー・インタラクティブエンタテインメント スティックモジュール(DualSense Edge(TM) ワイヤレスコントローラー用) [CFI-ZSM1G PS5 デュアルセンスエッジ スティックモジュール] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0075/4948872415729.jpg?_ex=128x128)
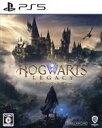

![Mojang Studios 【PS5】Minecraft(マインクラフト) [ELJM-30581 PS5 マインクラフト] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0419/4595057030071.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS5] Stellar Blade(ステラブレイド) ソニー・インタラクティブエンタテインメント (20240426) 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480564.jpg?_ex=128x128)

![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer【2月27日以降出荷分】 [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS5] ドラゴンクエストVII Reimagined(ドラクエ7 リイマジンド) スクウェア・エニックス(20260205) 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/1/cg10481022.jpg?_ex=128x128)







![【中古】【未使用品】カーズ2 MovieNEX [DVDのみ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/issue/cabinet/11599041/11702825/imgrc0098958884.jpg?_ex=128x128)
![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム0083 -ジオンの残光ー【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4715/4934569364715.jpg?_ex=128x128)
![機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(4K ULTRA HD Blu-ray)【4K ULTRA HD】 [ 小野賢章 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0138/4934569800138_1_2.jpg?_ex=128x128)
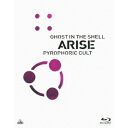

![映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」Blu-ray(通常版)【Blu-ray】 [ EVIL LINE RECORDS ] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4771/4988003894771.jpg?_ex=128x128)
![「多聞くん今どっち!?」1【Blu-ray】 [ 師走ゆき ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4399/4988003894399.jpg?_ex=128x128)
![劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 【完全生産限定版】【Blu-ray】 [ 杉田智和 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0876/4534530070876.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典+他】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.1 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX+他) [ 芥見下々 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4343/2100014774343_1_4.jpg?_ex=128x128)