先行レビュー
古の遊戯王ここに復活! 「遊戯王 アーリーデイズコレクション」先行試遊プレイ
追加機能でバージョンの垣根を超えた最強デッキを構築できる!
2025年2月26日 00:00
- 【遊戯王 アーリーデイズコレクション】
- 2月27日 発売予定
- 価格:6,050円
コナミデジタルエンタテインメントは、ゲームボーイなどで発売された古の「遊戯王」のデジタルゲームタイトルを一挙に楽しめる「遊戯王 アーリーデイズコレクション(以下:アーリーデイズコレクション)」を2月27日に発売する。
本作は1998年に発売されたゲームボーイ用「遊戯王デュエルモンスターズ」から2004年発売のゲームボーイアドバンス用「遊戯王デュエルモンスターズ インターナショナル2」までの期間に生まれた「遊戯王」に関連するゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのタイトル計14本がNintendo SwitchおよびPC(Steam)にて一気にプレイできる作品だ。
現代でも大人気なカードゲーム「遊戯王OCG」のルーツとなった古の“遊戯王カードゲーム”を体験できるだけでなく、各ゲーム作品で独自ルールが適用されたタイトル、カードゲームですら無い遊戯王を楽しめたり等、ファン必見のタイトルが多数用意されている。加えて現代向けに発売されるにあたっての便利機能も多数用意されているため、過去作品の思い出に浸りながらも快適になった新たなゲーム性を楽しめるだろう。
今回はそんな本作を一足早く少しだけ試遊する事ができたので、進化したポイントなどを中心にプレイした所感をお届けしたいと思う。
・遊戯王デュエルモンスターズ(1998年/ゲームボーイ)
・遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記(1999年/ゲームボーイ、ゲームボーイカラー)
・遊戯王モンスターカプセルGB(2000年/ゲームボーイ、ゲームボーイカラー)
・遊戯王デュエルモンスターズⅢ 三聖戦神降臨(2000年/ゲームボーイカラー)
・遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記(2000年/ゲームボーイカラー) ※オンライン対戦に対応予定
・遊戯王ダンジョンダイスモンスターズ(2001年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ5 エキスパート1(2001年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ6 エキスパート2(2001年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ7 決闘都市伝説(2002年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ8 破滅の大邪神(2003年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ インターナショナル -ワールドワイドエディション-(2003年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ エキスパート3(2004年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王 双六のスゴロク(2004年/ゲームボーイアドバンス)
・遊戯王デュエルモンスターズ インターナショナル2(2004年/ゲームボーイアドバンス)
14タイトルを大画面でプレイ。当時の説明書まで収録
ゲームを起動すると、早速本作で遊べる14本のゲームタイトルがズラっとプレーヤーを出迎えてくれる。
各ゲームタイトル毎にそれぞれ日本版か海外版の変更、カラー表示を「ゲームボーイ」か「ゲームボーイカラー」版かの変更といった具合に、細かいバージョンの違いを変更できる。
当時のプレイ環境に合わせたバージョンで遊ぶこともできれば、あえて海外版等をプレイする事で日本版との違いを体験するといった新しい遊び方も可能だろう。
当然、ゲーム画面は当時の環境よりも格段に進化しており、同じ内容でも映像・音楽共に進化を感じられる。大画面でプレイする事で改めてドット絵で表現されたカードデザインに感動できたりもするだろう。
また当時のプレーヤーの懐かしさを刺激する機能として、逆に画質感を当時使用に近づける画面設定の「LCDフィルター」を適用する事も可能だ。
他にも各タイトルの海外版パッケージや当時の取扱説明書を高画質で見る事ができたりなど、シリーズファンとしては資料的価値も高い作品だと言えるだろう。
便利な「追加機能」で最強デッキの構築が可能に!
次に今作ならではの便利機能についても紹介していこう。
まずは各タイトル毎に使用できる「追加機能」だ。各タイトルをプレイする前にメニュー画面から各項目を適用できる機能で、プレイする上での手間を省いたり隠し要素を自由にアンロックする事が可能となっている。
大体のタイトルで共通しているのが「全カードの解放」と「デッキキャパシティの解放」で、今作では最初からカードを全て所持している状態にすることができ、カード収集の時間を大幅にカットできる。全タイトルでカード収集を1から行なうと全タイトルクリアまでにとんでもない時間がかかってしまうので、非常にありがたいシステムと言えるだろう。それに伴い、古の作品では頻繁に目にするデッキ構築の際に発生するコスト制限「デッキキャパシティ」も実質無限にすることが可能なので、ゲーム序盤から好きにデッキ構築が可能だ。
子どもの頃は構築不可能だったパワーカードをタコ盛りしたデッキを簡単に構築する事ができるので、当時とは違う視点で古の遊戯王を楽しむ事ができるだろう。
もちろん当時の難易度で挑みたい場合はこれらの機能をOFFにして収集やキャパシティ稼ぎを楽しむ事もできるため、自由な遊び方が可能となっている。
「追加機能」の中でも特に目を惹くものを紹介しよう。
1つめは「隠しステージ」の自由選択だ。初期のゲームタイトルにはゲームクリア後に特別な相手とデュエルできる「隠しステージ」が存在するのだが、その際の対戦相手はパスワードの入力が必要だったり、中には複数人の中からランダムに選ばれるといった仕様だったりで自由に選べなかったのだ。
今作ではその「隠しステージ」を自由に設定して挑戦できるようになったため、当時は出会えなかった相手とのデュエルが簡単にできるようになったのである。
2つ目は遊戯王ゲームの中でも断トツの売り上げを誇り、色々な意味で今もなお伝説となっている「遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記(以下:DM4)」の追加機能だ。
このタイトルは「遊戯デッキ」、「海馬デッキ」、「城之内デッキ」の3バージョンが同時発売されているタイトルとなり、各バージョンで“使用できるカードが異なる”という特殊な仕様が存在していた。例を挙げると当時最強カードの一角だった「こころがわり」は「城之内デッキ」でしか使用できないといった感じで、選んだバージョンの使用可能カードによってパワー格差が生まれるタイトルだったのだ。
今作はそのバージョン毎の使用カード制限を解除できる「追加機能」を適用できるため、バージョン毎の格差を無くすだけでなく、バージョンの垣根を超えた最強デッキの構築が可能になったのである。
加えて「DM4」に関しては発売直後からオンライン対戦が可能となる予定で、当時とは全く異なる対人戦を楽しむ事もできるのだ。
ゲームのルール自体が既存作品とはかなり異なるタイトルなため慣れは必要だが、逆に現代では味わえない遊戯王を体験できるタイトルなので是非「追加機能」を駆使してこのタイトルを遊んでみて欲しい。
「追加機能」に続くもう1つの便利機能として今作では「巻き戻し」機能が備わっている。
その名の通りプレイ中にゲームを巻き戻せる機能となり、自由にやり直しが可能なシステムとなっている。本作収録のほとんどがカードゲームを遊ぶタイトルな事もあり、負けた試合のやり直しをデメリット無しでできたり、自分がちょっとした操作ミスやプレイミスをした際にやり直しが可能になる。
また、タイトルによってはゲーム難易度を下げられる悪魔的使い方も可能となっていた。例を挙げると「遊戯王モンスターカプセルGB」というタイトルでは、カプセルとダイスの出目を用いたバトルがゲームの根本となるのだが、なんと「巻き戻し」を使用する事でダイスの出目を何度も変更可能となっている。
これにより相手の出目を弱くし、自分の出目が強くなるまで何度もやり直せばどんな敵も突破可能になっているのだ。このタイトルは敵エネミーとのエンカウントもダイスの出目で決まるのでエンカウントしたら「巻き戻し」をする事で1度も敵と遭遇する事無くクリアも可能となっていた。ストーリーを見たい、強敵とのバトルだけを楽しみたい場合等は「巻き戻し」を駆使してサクサクプレイをするのも悪く無いだろう。
逆に同じくダイスを用いたバトルをする「遊戯王ダンジョンダイスモンスターズ(以下:DDM)」では直前の「やり直し」だけではダイスの出目を変える事はできなかったので、各タイトルの仕様毎に「やり直し」する場所をうまく調整する必要がある。ちなみに、「DDM」ではダイスのモンスターやモンスターの順番まで変えれば出目が変化する。
他のタイトルでも上手く使う事で難易度を下げられる方法があるかもしれないので、色々と模索してみるのも面白いだろう。自身のプレイ方針に合わせてどこまでこの機能を使うか試されるシステムとなっているのだ。
イチオシしたい「遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記」&「遊戯王ダンジョンダイスモンスターズ」
今回の試遊では上記でも強く取り上げた「DM4」とカードゲーム以外のタイトルとして「DDM」を中心にプレイしたのだが、どちらも固有の素晴らしさを秘めたタイトルとなっていた。
繰り返しにはなるが「DM4」は「デッキキャパシティの解放」&「バージョン毎の使用カード解除」による恩恵が凄まじく、当時実際にプレイしていた身からすると「全カード解放」でデッキを組んだ時の自由度に感動してしまうほどだった。ゲーム内で強力なカードを多数使える事で“カードゲームとしての面白さ”を手軽にかつ、しっかり感じる事ができ、遊戯王らしい魔法・罠カードで盤面を返しあう攻防をこのタイトルで体験できるのが素晴らしい。
昔は様々な要因でデッキに投入できるカードが少なかったため、消去法的にカードを投入してデッキを組む必要があったが、今作では「追加機能」を使うことで入れたいカードが多すぎて構築に悩むといった経験ができるので、全く違うゲーム体験を味わう事ができた。
オンライン対戦が可能となれば対人戦ならではのメタゲームも発生しそうなので、今作の中でも発売後最も熱いタイトルになり得ると筆者は感じている。
「DDM」に関しては現代ではほぼ遊べない希少性の高いタイトルだったので、大画面でプレイできるだけでも感動レベルだった。
その昔、現実でも遊ぶことが可能なボードゲームの「DDM」は存在していたが、カードと異なり流通数が限られていたこともあってか玩具にもプレミアがつき、本タイトルの元となったGBA版もプレミアがついていた事でそもそも「DDM」をプレイする事が難しい状態だったのだ。
シミュレーション要素+ダイスを用いた本作ならでは攻防は運要素が強めながらも独自の面白さがあり、ルールを理解すれば多くの面白さに気付けるタイトルとなっていた。
また「遊戯王OCG」のモンスターが数多く登場する豪華な仕様、さらには原作マンガのキャラクターが数多く登場するといったファンサービスも相まって、遊戯王ファンにはぜひ1度プレイして欲しいタイトルだった。
今回の試遊で判明した内容は以上となる。古の「遊戯王」のゲームタイトルは癖の強い作品が多いが、本作ならではのシステムで難易度を緩和し、面白さをしっかり味わえる仕様に作り替えた素晴らしい作品となっていた。
当時の懐かしさを感じながらも、新しいゲーム体験も味わえる作品だったので、気になるプレーヤーは是非遊んでみて欲しい。
(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment










































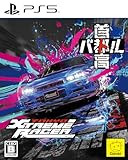










![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)
![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)
![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)
![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)
 [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)

![AZLA FitSense for SWITCH 2(TM) アナログスティックカバー [AZL-FITSENSE-NS2-GR]【送料無料】【ゆうパケット対応】【3月6日発売 発売日以降お届け】 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akiba-eshop/cabinet/item15/8809825495419-5.jpg?_ex=128x128)



![[switch2対応!! 安心の国内メーカー] Switch Switch2 コントローラー 有機ELモデル Lite スイッチ2 スイッチ ワイヤレス プロコン プロコントローラー switchコントローラ プロコンswitch プロコン2 ワイヤレスコントローラー ジョイコン 連射機能 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/habit-onlinestore/cabinet/imgrc0108532336.jpg?_ex=128x128)









![ソニー・インタラクティブエンタテインメント スティックモジュール(DualSense Edge(TM) ワイヤレスコントローラー用) [CFI-ZSM1G PS5 デュアルセンスエッジ スティックモジュール] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0075/4948872415729.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【新品】【PS5】三國志8 REMAKE[PS5版][在庫品] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10790000/10795051.jpg?_ex=128x128)


![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)






![[Switch] イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード (ダウンロード版)※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/6/802252526_p.jpg?_ex=128x128)

![『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』(通常版) 【Blu-ray】 [ サンエックス ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7545/4571614677545.jpg?_ex=128x128)
![銀魂 後祭り2023(仮)【初回仕様限定版】【Blu-ray】 [ 杉田智和 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4409/4534530144409_1_2.jpg?_ex=128x128)
![音楽朗読劇READING HIGH第3回公演 「Chevre Note」~Story from Jeanne d'Arc~【Blu-ray】 [ 中村悠一 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6116/4534530116116.jpg?_ex=128x128)
![ルパン三世 カリオストロの城 【4K ULTRA HD】 [ 山田康雄 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7311/4988021717311_20.jpg?_ex=128x128)
![キミとアイドルプリキュア♪感謝祭(通常版)【Blu-ray】 [ プリキュア ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0758/4535506020758_1_2.jpg?_ex=128x128)
![劇団「忍たま乱太郎」 忍たま長屋物語【Blu-ray】 [ (趣味/教養) ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0611/4550621580611.jpg?_ex=128x128)
![ミュージカル「Fate/Zero」 ~A Hero of Justice~(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ TYPE-MOON ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0782/4534530160782.jpg?_ex=128x128)
![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0051/4934569370051.jpg?_ex=128x128)
