 |
★ PCゲームレビュー★ |
|
RTSとRPGの両立は可能なのか!? 2つのジャンルを秘めた意欲作が登場 Knight Shift 完全日本語版 |
 |
|
RTSにキャラクタの成長要素をはじめとしたRPG要素を盛り込むことは、近年の流行のひとつである。しかし、ひとつのタイトルの中にRTSとRPGの2種類のゲームモードをバランス良く盛り込んだのはレアなケースではないだろうか。「Knight Shift 完全日本語版」は、完全新作でありながらRTSとRPGの両立に挑戦した意欲作である。
■ RTSとRPG。1粒で2度おいしい意欲作
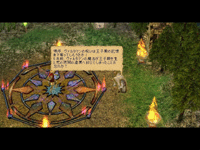 |
| ガリウスによって救出されるプリンス・ジョン |
 |
| 本作のキャンペーンモードは、チュートリアルの役割も兼ねている |
 |
| 登場する多くのモンスターは、HPが少なくなると逃げる |
これらの2ジャンルをどのように両立させてるのかというと、本作のゲームモードを「キャンペーンモード/RPGモード/RTSモード」に切り分けることで可能としている。ちなみにキャンペーンモードとは、ストーリーに沿ってRPG/RTSの両方を織り交ぜた内容となっている。たとえゲームモードを分けてるとはいえ、同一タイトル上で複数のジャンルの実現は可能なのか? この点が本作の最大の注目点といえよう。
ゲームの世界観は王道的なファンタジー世界を基盤としている。ここでメインストーリーを簡単に紹介しておこう。とある国を治めるプリンス・ジョンは、邪悪な魔法使いヴァルタマンの手によって呪いを掛けられてしまった。ジョンの体は虚無へと飛ばされてしまったが、5年が経過した後に善良な魔法使いガリウスが彼の救出に成功する。そしてジョンは国を取り戻すべく、ガリウスや配下と共に冒険に出かける、というのが大まかな流れだ。
グラフィックは全編フル3Dで描かれ、ゲームシステムがある程度共通することもあってか、第一印象はBlizzard Entertainmentの「Warcraft III」に近い。ただ、「Warcraft III」のように硬派なタイトルなのかというとそうでもない。悪役も含む総ての登場キャラクタはどこかしら愛嬌を漂わせており、彼等と交わす会話もコメディの要素がふんだんにあるのだ。
ユニットのグラフィックはリアル系でもデフォルメ系でもなく、丁度その中間といったところだろうか。また、掲載画面を見ればわかるが特に背景はよく描き込まれている。水面に写る景色や風に揺れる木々、そしてそれらが昼夜の時間経過によって切り替わる様はきっと満足できるはずだ。ゲーム中は右クリックでいつでも視点を360度単位に変更できる。本作の難易度は全般的に抑えめに作られているため、ユニット操作等の作業に忙殺されることはあまり無い。プレイ中はこれらの美しい背景を存分に堪能できるだろう。
 |
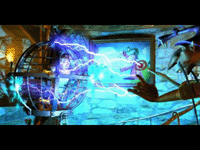 |
| 左が邪悪な魔法使いヴァルタマンで、右が呪いを掛けられたプリンス・ジョン。悪役といえども、どことなくひょうきんな顔立ちだ | |
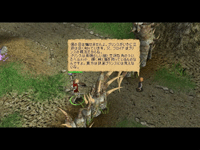 |
 |
| 流石に5年間も国を留守にしているため、民はジョンの存在をなかなか認めてくれない。彼等に正当な王子であることを証明するのが当面の目的となる | RTS及びRPGモードにはチュートリアルといったものはない。まず最初に、キャンペーンモードをある程度行なうことをお勧めする |
 |
 |
| 地下エリアにてスケルトンの大群と激戦の最中。フィールドは複数のエリアで構成されていることが多いため、ミニマップから受ける印象よりもかなり広い | 本作のグラフィックは実に細かい所まで描き込まれている。ゲーム中に時折一時停止して、画面を拡大してじっくり見てみよう |
■ 牛の乳搾りで資源採取を行なうユニークな「RTSモード」
 |
| 本作の最大の注目ユニット「牛様」。これらが草を食べている様子を眺めていると愛着が沸いてきてしまう |
 |
| 牛からミルクを絞ると、画面右下にある樽が徐々に満たされていく。ミルクを絞り出すことで牛は経験を積み、より多くの量を絞り出せるようになる |
RTSタイトルにおける資源採取とは、その後のユニット生産や戦闘に直結する作業である。ゆえにプレーヤーは、資源採取ユニットをどのように動かせば効率が良くなるか? という点に常に気を配っており、ゲーム中はぴりぴりとした空気が張り巡らされるものだ。しかし本作のRTSモードは、ゲーム開始時からしていきなり肩すかしを受けてしまう。牛からミルクを搾り取る周期が約1分という点からも、資源採取作業がどれだけのんびりとしているかが想像できるだろう。
備蓄できるミルクには最大量が定められており、ゲーム開始時ではこれが100。だが建築物「牛小屋」を一棟建てると、これが100上昇し、さらに牛を最大で3頭生産できるようになる。そしてユニットを一体生産するのに必要なミルクは50~400である。つまり、ゲーム開始直後から戦闘ユニットを立て続けに作ることはできない。牛小屋を建てて牛を複数体生産し、そして彼等が草を食べる様子をじっと見守るという展開である。どちらかというと殺伐としたRTSというジャンルであるにも係わらず、ここまでまったりとしたゲーム展開はこれまで見たことがない。むしろ箱庭系のタイトルに近い、独創的な資源採取システムだ。
RTSモードに登場するユニットと建築物は、各12種類と少な目になっている。それぞれの役割は近接攻撃、遠隔攻撃、魔法攻撃、魔法支援、そして建築担当といったように、基本的な役割は一通り押さえられている。ユニットの名称に関しても本作ならではの味が滲み出ており、たとえば戦士タイプは「ウォリヤン」、弓兵タイプは「アーチャン」といった具合。これらの中で性能面で特に面白いのが「ババーン」。なんと敵の建築物の上に臆することなく座り込み、作業を行なえなくしてしまうのだ。
RTSモードで選択できる勢力は1種類のみで、他RTSタイトルにおける種族・文明・民族等といったものは存在しない。よってユニットの編成や戦術の幅広さに関しては、一般的なRTSタイトルと比較すると大幅にシンプルな作りである。本作のRTSモードは、スポーツ系RTSのように戦略・戦術面をじっくりと追求するタイプではなく、集団戦の雰囲気を軽く楽しむことに主眼が置かれているようだ。
実際にRTSモードをプレイした感想としては、ユニットの動作を正方形のマス単位で行なっているためか、大部隊を操る展開において、なかなか自分が思ったようには動いてくれないのが気になった。ユニットの移動が45度単位(=8方向)でしか行えなく、スタックが発生するなど、ぎこちなさを感じてしまうのだ。とはいえ、あくまでもこれは本格的なRTSタイトルと比較した上での話である。RTSモードは本作で遊べる内の一スタイルにしか過ぎないと割り切れば、評価は多少和らぐだろう。
 |
 |
| 川に橋を架け、自陣を拡大している最中。本作ではユニット生産や建築以外にも、橋や街路の敷設なども行なえる | 防御用の柵と砦を築いている。本作のRTSモードは基本的に、敵へ攻め込む側より、迎え撃つ側の方が圧倒的に強い |
 |
 |
| 万全の体制を整えた後に、敵をおびき寄せるようにして戦うとよいだろう。この際は、遠隔攻撃ユニットが重宝するはずだ | ユニット毎に生産数を管理する建築物が異なる点に注意しよう。一般的なRTSタイトルにおける家の概念とは少々異なるのだ |
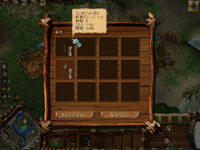 |
 |
| 各建築物ではユニットの能力をアップグレードできる。登場するユニットの種類こそ少ないが、RTSとしての基本は一通り押さえられている | 通常プレイ時は、このようなクォータービューで操作を行なう。右クリックを用いない独特な操作スタイルは、シンプルな反面、RTS経験者にとっては慣れを要する |
■ アクションRPGのエリアを1枚のマップに押し込んだ「RPGモード」
 |
| RPGモードを開始した直後の状態。自分の右にあるのは専用の保管箱で、マップを切り替えても共通して出し入れできる |
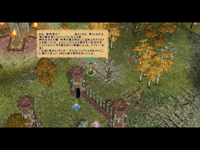 |
| 同じマップに登場するNPCでも、依頼されるクエストはゲーム毎にランダムで切り替わる |
 |
| クエストの本編そのものは、目的地にたどり着けば完了するものが大半。それよりも、道中に出現するモンスターとの戦いに苦心することだろう |
 |
| 倒れているように見えるが、実は休息してHPとMPを回復させている最中 |
RPGモードで選択できるユニットは「アーチャー、ナイト、バーバリアン、スピアマン、プリエステ、ソーサラー、アマゾンメイジ」の全7種類。これらは見た目こそRTSモードのユニットと同じだが、RPGモードでは成長させることできる。具体的にはモンスターを倒すことで経験を積み、レベルアップが可能。またお金を集めてNPCからマジックアイテムを購入といった具合である。
そしてRPGモードのキャラクタデータは、ゲームを終えても保存されるため、何度もダンジョンに潜ってキャラクタを成長し続けられる点にも注目。しかも、マルチプレイではこの育てたキャラクタを用いた冒険ができるのだ。これは「Warcraft III」のUMSでは成し得なかったことである。
ただし、「Diablo 2」に代表される本格的なアクションRPGと比べると、キャラクタの成長時に追求できる個性の幅は大分狭くなっている。レベルが上昇するといっても、基本的には任意のステータス値を上昇させられるだけなのだ。スキルツリー形式で新たな技を習得するわけでもなく、同じキャラクタであれば誰が育てていっても似たような性能になってしまうのは残念である。
RPGモードの基本的な流れとしては、各地に点在するNPCと会話を行なうことでクエストを依頼される。クエストの内容はモンスターの討伐やNPCの護衛といったもので、しかもミニマップ上に目的地がマークされるためわかりやすい。当然ながら目的地までの間にはモンスターが待ちかまえており、これらを倒したりクエストを達成することで少しづつキャラクタが成長するという仕組みだ。
敵を含むキャラクタの進行速度が幾分遅めなのと、モンスターが近づくと自動的に攻撃を行なうため、ゲーム中で求められるアクション性はそれほど高くない。基本戦術はヒット&アウェイのみで、たとえば複数のスキルを交互に繰り出しながら難局を乗り越えるような、「Diablo」的な醍醐味は薄いだろう。イメージとしては、どちらかというと「Diablo」シリーズより「Priston Tale」のような韓国製オンラインRPGに近いかもしれない。
RPGモードにおいて特徴的なのは、通常のマップとは別に、地下エリアが用意されていることである(これはキャンペーンモードも共通)。ゲーム中にTABキーを押すと、ミニマップ上に表示される区域が地上/地下でいつでも切り替えられるのだ。つまり、実際にはミニマップで見る倍の広さがあると考えてよいだろう。キャラクタの移動速度が一般的なアクションRPGに比べて遅めなこともあり、マップ中をくまなく歩き回るのには意外と時間が掛かる。クエストを含めると、小さめのマップを完全に攻略する場合は2~3時間を要するだろう。
RPGモードの感想としては、クエストの種類はランダムで発生するものの大半が似たような展開で、戦闘そのものが単調なのも相まってか、プレイ中は繰り返し作業的な印象が拭えない。RPGモードの評価としては、やはり本格的なアクションRPGタイトルと比較すると、厳しい見方をせざるを得ない。
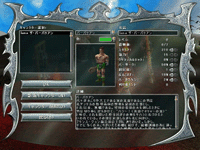 |
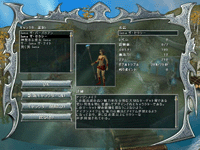 |
| アマゾンメイジの詳細欄を見てほしい。本作が決して硬派寄りではなく、斜に構えた独特のユーモアがあることがわかるだろう。日本語のローカライズはこれらの微妙なニュアンスを忠実に伝えており、そのレベルは全般的に高い | |
 |
 |
| マップの所々には中ボス的なモンスターも登場する。強敵だが、数多くの経験値と金銭を得られるので見逃さないように | NPCから購入できるアイテムの品揃えは、ゲームを作り直す度に変わる。この際も所持金は残ったままなので安心しよう |
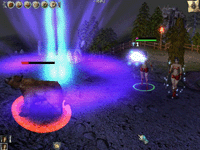 |
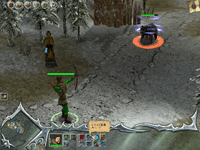 |
| アマゾンメイジは、自分の分身を作り出して一緒に戦わせるアビリティを得意とする。分身は攻撃能力も備えているため、うまく使えば戦闘力は2倍になる | 写真右上にいる熊は、ハンターが設置したトラップにより足止めされている。その間に、弓による遠隔攻撃で確実にダメージを与えるのだ |
■ RTSもしくはRPGの未経験者にとっては敷居の高さを感じさせない作り
 |
| マルチプレイ用のロビーサーバー「Earthnet」が用意されている。自分で育てたRPGモードのキャラクタを、他のプレーヤーと共に遊べるのはありがたい |
 |
| RPGモードは仲間と共にわいわい遊ぶ方が断然面白い。その一方でRTSモードは、あまり殺伐とした対戦には向いていないだろう |
RTSの一キャラクタに操作を専念させ、成長要素を持たせるという着眼点は評価できるが、それは基本となるRTSのゲームシステム面がしっかりしていないと成し得ないことだ。まずはユニットのAIを強化したり種類を増やしたりといったように、RTSとしての完成度を平均水準まで高めるべきだった。このレベルでは、RTSとアクションRPGのどちらのコアユーザーがプレイしても、それぞれ物足りなさを感じてしまうだろう。
しかし、ライトユーザーの視点から見れば話はかわってくる。たとえば、韓国製のオンラインRPGを好むプレーヤーで、RTSタイトルは未経験だったとする。まったく未知のジャンルには手が出しにくい人は多いだろうが、本作であれば最初にRPGモードで慣れてから、同じユニットが登場するRTSモードをプレイするというのは有りだろう。掲載画面を見ればわかるように本作のグラフィックは十分に魅力的で、またローカライズの出来も良いため、各ジャンルの未経験者から見た場合、敷居の高さは感じられないはずだ。
筆者はアクションRPGとRTSの両方のコアユーザーであるため、あえて重箱の隅をつつくような指摘に終始した。だが本作のアピールポイントは、本来はありえないRPGとRTSの2ジャンルを、1本のタイトルで手軽に堪能できる所にある。この点に興味を持った読者は、とりあえずデモ版をプレイしてみてはどうだろうか。
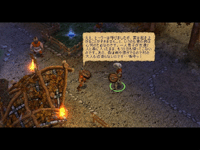 |
 |
| 筆者がプレイした限りでは、ローカライズ作業に関しては非の打ち所がまったくない出来映えだった。今後の同社のPCゲームタイトルにも期待が寄せられる | グラフィックの出来は全般的に高い。RTSやRPGの未経験者が始めてプレイする分には、本作は向いているかも知れない |
Copyright 2004. (c) livedoor Co.,Ltd. Schanz Interactive GmbH.ZUXXEZ Entertainment AG. All rights reserved.
|
□「Knight Shift 完全日本語版」の公式ページ
http://pro-g.livedoor.com/game/ks/
□関連情報
【2004年5月22日】本日到着! DEMO & PATCH 「Knight Shift 日本語版」体験版
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20040622/demo0622.htm
(2004年8月5日)
[Reported by 川崎政一郎]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.