 |
★ PCゲームレビュー★ |
|
北アフリカ戦線をテーマにした3DRTS ロンメル戦車軍団を指揮して砂漠戦を戦い抜け デザートラッツ ~砂漠の鼠VS北アフリカ軍団~ |
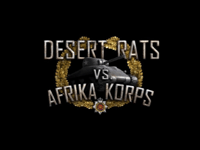 |
|
世界史上最大の戦争であった第2次世界大戦の最中、ロンメル率いるドイツ軍の参入によって勃発した北アフリカ戦線。この歴史的な戦いを再現したRTSが今回紹介する「デザートラッツ ~砂漠の鼠VS北アフリカ軍団~」である。優れた3Dグラフィックエンジンを用いながらも、ゲームシステムを手堅くまとめた、ミリタリーファンなら納得の内容である。
■ ロンメルの足跡を辿るリアルタイムストラテジー
 |
| デザートラッツには、北アフリカ戦線で活躍した戦車が数多く登場する。誰でも迫力のある戦車戦を手軽に味わえるのだ |
 |
| フル3D描画なので、視点切り替えをスムースに行なえる。戦闘が開始すると思わず戦車が格好よく見えるアングルに切り替えてしまう |
この北アフリカ戦線は、同時期に太平洋戦争において真珠湾攻撃が行なわれたこともあり、我々日本人にとっては印象が薄いかもしれない。しかし、枢軸軍の北アフリカ軍団を指揮したのが、「砂漠の狐」ことエルウィン・ロンメルだと聞けば、ピンと来る読者は多いだろう。本作では、北アフリカ戦線におけるロンメルの足跡を実際に辿ることができるのだ。
史実におけるロンメルは、劣勢な状況下で圧倒的な物資量を誇るイギリス軍を敗退させたことと、限られた資源を最大限に活用した大胆不敵な作戦でよく知られている。それらの史実を再現するために、本作は「Sudden Strike」や「Close Combat」と同様、資源採取及びユニット生産の概念が無い。プレーヤーは最前線での戦術に専念できるので、RTS初心者でも比較的プレイしやすくなっている。その分DRのシングルキャンペーンは、当時のロンメルが科せられた、厳しい条件のシナリオがふんだんに用意されているので期待してほしい。
 |
 |
 |
| 市街地に陣取る敵軍を掃討しているところ。史実に沿った多彩なシングルキャンペーンも本作の魅力のひとつだ | プレーヤーは、ロンメルの元で働く士官という設定だ。プレイ前に挿入されるムービーが気分を盛り上げてくれる | ミッションが始まる際は、イベント画面からゲーム画面へとシームレスに移行する。3Dならではの演出効果だ |
■ 3Dグラフィックエンジンによって新たな命を吹き込まれたユニット
 |
| 戦車を最大まで拡大した状態。装甲の上に積もった砂埃や錆までもが感じられるはずだ。これらの戦車が縦横無尽に動き回る様を思い浮かべてほしい |
 |
| 戦車が破壊され、木っ端微塵に吹き飛ぶ。このような立体描写を行わせると、2Dは3Dの足下にも及ばない |
 |
| 戦車だけでなく、歩兵や小道具なども実に細かく描き込まれている。北アフリカ戦線の砂埃の臭いまでが伝わってきそうだ |
目を凝らして戦車を見ると、回転するキャタピラや砲塔部、それに土埃を巻き上げながら走る姿などが見事に表現されていることに気付くだろう。そしてこれらが戦闘によって粉々に吹き飛ぶ様は、圧巻そのもの。もちろん、建築物などのオブジェクトもフル3Dで描画されており、砲撃で破壊される民家や、戦車に踏み倒される樹木などの描写も非常にリアルだ。
これらのずば抜けた表現技術によって描かれたゲーム画面を注視していると、北アフリカ戦線の灼熱の砂漠の風景がじっとりと伝わってくる。また、ゲーム中はいつでもズームイン/アウトや、画面の拡大/縮小及び回転を行なえるのも、2Dタイトルでは行なえなかった芸当である。
DRには合計70以上の軍事ユニットが登場し、その総てが緻密なフル3Dグラフィックで描画されている。北アフリカ戦線のみならず、ミリタリーに傾倒するプレーヤーは、これらのグラフィックを心ゆくまで堪能するだけでも買った元は取れるはずだ。
最近の軍事系RTSタイトルでは「Commandos 3」の屋外背景に代表されるように、2Dの書き込みレベルは限界を通り越し、もはや絵画の域にまで達している。「Commandos 3」のような1ドット単位の職人芸も捨てがたい魅力はあるが、DRの3Dグラフィックを目の当たりにしてしまうと、やはり時代の進化を感じてしまうのが正直なところだ。
DRの3Dグラフィックは、演出面だけでなくゲームシステムにも活用されている。戦車等の車両系ユニットは、いくつかの部位毎に異なる耐久度が定められている。例えば本物の戦車と同様に、敵からの攻撃を受けやすい前面は装甲が厚めに設計されているのだ。さらに、砲塔部やキャタピラといった弱点箇所を「特殊攻撃」のコマンドで集中的に攻撃をすることもできる。その結果、敵戦車の攻撃能力や移動能力だけを喪失させる戦術も可能となっているのだ。
これを利用した作戦例をひとつ紹介しよう。まず、敵戦車部隊が細い路地を進軍してくる状況を思い浮かべてほしい。この際に自軍が真正面から受けて立つと、仮に先頭車両を破壊しても後続が続々と押し寄せてくるのできりがない。そこで、先頭車両のキャタピラに狙いを定め、これを破壊するのだ。すると移動能力を失った戦車のせいで、後続車両は身動きができなくなる。その間に、予め周囲に待機させた味方ユニットを総動員させ、防御力の薄い側面や後方から一斉放火を行なう、というわけだ。
実際にはここまで理想的な展開はそれほど多くないが、車両ユニットの耐久度が部位毎に定められているという点は、覚えておくと役に立つだろう。これをマップ中の地形情報と結びつけ、いかにして側面や後方から敵戦車を叩くかの作戦を考えるところが、DRの醍醐味である。
これまで戦車のリアリティ面ばかりを強調してきたが、歩兵にも重要な役割がある。もっとも大切なのは、車両や固定砲台といった操縦を必要とするユニットは、搭乗させる人数によって強さが変化することである。多くの兵士を搭乗させることで、視界範囲、射程範囲、攻撃速度などの性能が向上し、同じユニットでもより強力になるのだ。また歩兵は建物に篭もることもでき、特に敵の歩兵部隊を待ち伏せする展開では圧倒的な防御力を誇る。
マップ上には無人の戦車や固定砲台、建築物などが多数放置されており、これらを有効利用しない手はない。主力の戦車部隊と共に歩兵を行動させ、利用できるオブジェクトはすかさず奪い取ることは、DRの基本テクニックとなるだろう。強力無比な兵器も、操作する兵士がいてこその強さなのだ。
 |
 |
 |
| この画面内に登場する塔や民家に至るまで、総ての建築物に歩兵は立てこもることができる。待ち伏を行なう際の配置を考えるのが楽しい | 戦車の搭乗数を変化させると、このように判りやすいメッセージが表示される。日本語のフォントは大きくて見やすい | 戦車を操縦する兵士の1人が倒されてしまった。このままでは同じユニットを用いても不利なので、早めに兵士を補充せねばならない |
■ 北アフリカ戦線を常に勝者の立場で追体験できるキャンペーン
 |
 |
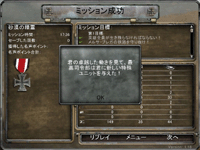 |
| ミッション開始前には、主人公の手記によるブリーフィングが表示される。北アフリカ戦線当時の写真を用いるなど、小道具も芸が細かい |
その後は、イギリス陸軍第7機甲師団のモントゴメリーによる猛反撃が始まる。ライトフット作戦、スーパーチャージ作戦などを成功させ、前半部で北アフリカに奪われた拠点を再度奪回してゆく。ロンメルは本軍に援軍を要請するも却下、そのため思い通りの作戦を遂行できず、最終的にエル・アゲイラまで奪われてしまう。かなり大雑把ではあるが、北アフリカ戦線はこのあたりまでの展開である。
何が言いたいのかというと、北アフリカ戦線の前半部と後半部で勝者が逆転しているのだ。これをDRでどのように再現してるのかというと、なんとキャンペーンの前半部は北アフリカ軍団、後半部はイギリス軍の視点によってシナリオが展開される。途中で主人公が逆転しては感情移入がしづらいのではないか? と普通は思うだろう。この問題については、当初は仲間同士だった2人が、戦争によって引き裂かれて敵軍に所属し、ロンメル及びモントゴメリーの元に仕官するという方法で解決している。
これはいささか強引なストーリーだと思うのだが、勝者が途中で入れ替わる北アフリカ戦線において、主役の気分を手軽に味わうには良い手法だろう。つまりDRの最大の魅力は、北アフリカ戦線を常に勝ち組の立場で追体験できるという所にあるのだ。ちなみに、主役となる2人を始めとした一部の仕官ユニットは、周囲の兵士に支援効果を与える効果を持つ。その代わり、途中で彼等が倒れるとゲームオーバーとなる点には気をつけてほしい。
キャンペーン中の具体的なミッション内容は、敵軍の目をかいくぐっての偵察、市街地での掃討、砂漠要塞の包囲、そしてそこからの脱出など多岐に及んでいる。北アフリカが舞台ということで大半のマップが砂漠なのは致し方ないが、各ミッション毎に目的が大きく異なるのでプレイして飽きない。
ミッションの難易度は一般的なミリタリー系RTSの例に漏れず、全体的に高めに調整されている。史実のロンメルは、圧倒的な数を誇るイギリス軍を翻弄させ続けた。これはDRになっても変わっておらず、ユニットの数で力押しできるのは、最初の2~3ミッションのみである。自軍の戦車ユニットの数は常に少なく、放置されているオブジェクトに限られた兵士をどのように割り振るかに頭を悩ませることだろう。ゲーム中はスペースキーによるポーズと、+/-キーでの速度調整をいつでも行なえる。この機能を頻繁に用いて、少しづつ少しづつミッションを進めてゆくという雰囲気だ。
自軍ユニットの合計数こそ少ないものの、ミッション開始時はある程度自由な部隊編成が可能である。具体的には、MPと呼ばれる部隊編成ポイントを消費して、ユニットを選択するシステムだ。ミッション毎にAIがユニットの割り振り例をアドバイスしてくれるため、基本的にはこれに従って問題はない。ひとつだけアドバイスすると、これに整備車両のユニットを2台前後加えておくとよい。整備車両ユニットさえいれば、仮に戦車のキャタピラや砲塔部が破壊されても戦線復帰できるのだ。DRは全体的に自軍のユニット数が少ないので、これらを大切にすることを心がけよう。
 |
 |
 |
| 一番簡単な難易度を選択しても、セーブとロードを何度も繰り返すことになるだろう。ゲーム中の速度調節とポーズ機能は重宝するはずだ | 画面下にいるのが、修理を行なえる整備車両ユニット。戦車がダメージを受けたら控えユニットと交替させつつ、すかさず修理しようい | キャンペーン中は具体的な目的を細かく指示してくれる。次に何をしたらいいのだろう? と戸惑うことはない |
■ ミリタリーファンにお薦めできる佳作
 |
| 同作のグラフィックスは特筆に値する。このゲームエンジンを用いた他の戦場をテーマにしたRTSもプレイしてみたい |
ミリタリー系のタイトルは史実を題材としているため、ゲームシステムに奇想天外なアイデアを取り入れられないという縛りがある。例えば一騎当千のヒーローユニットをミリタリー系のタイトルに登場させた瞬間、その時点でヒストリカルゲームの枠を超えてしまう。かといって、史実と矛盾せずにゲーム性をも両立させるアイデアはほぼ出尽くしており、どのようにしてプレーヤーに新鮮さを感じさせるか、という所にゲームクリエイターは苦労していることだろう。
そのような現状を踏まえると、DRの優れた3Dグラフィックはそれだけでも賞賛に値する。少なくとも筆者は、もう2DタイプのミリタリーRTSには戻れないと強く感じた。3Dグラフィックを用いながらもゲーム内容を手堅くまとめたDRは、北アフリカ戦線に興味のあるプレーヤーのみならず、ミリタリー全般のファンにお薦めできる佳作である。
DRで唯一残念だった点は、マルチプレイに関するシステムがおざなりになっていることだ。IP直打ち、またはGamespyを用いた2~4人の対戦をサポートしているが、使用マップが3つのみといった有様で、辛うじてマルチプレイができるといった程度にしか過ぎない。Blizzard Entertainmentが運営する「battle.net」のような対戦専用サーバーを設置してくれとまでは言わないが、もう少し何とかしてほしかった。DRはシングルプレイ主体のRTSと考えてよいだろう。
 |
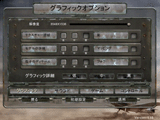 |
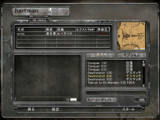 |
| 砂漠の要塞を引いたカメラアングルで撮影。砂漠だけとはいえども、ミッションには様々な舞台が用意されている | 画面描画に関するオプションは、かなり細かく行える。現在入手できる最高級のマシンでも、性能を存分に生かすことができるはずだ | ミリタリー系のRTSは、シングル重視のタイトルが多いように思える。本作もこれでマルチの出来さえよければ、手放しで誉められただけに残念 |
(C)2003 Monte Cristo. Monte Cristo and its logo are registered trademarks of Monte Cristo. All other trademarks and logos are property of their respective owners. Developed by Digital Reality. Orchestral samples included in this recording from the Vienna Symphonic Orchestra
|
□ズーのホームページ
http://www.zoo.co.jp/
□「デザートラッツ」のホームページ
http://desertrats.zoo.co.jp/
(2004年5月11日)
[Reported by 川崎政一郎]
GAME Watchホームページ |
また、弊誌に掲載された写真、文章の無許諾での転載、使用に関しましては一切お断わりいたします
ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved.